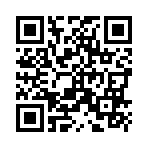2010年04月28日
新しい標準
ヒット商品応援団日記No462(毎週2回更新) 2010.4.28.
先日、東京新宿高島屋に百貨店では最大規模の面積のユニクロが出店した。今年3月には渋谷にも大型店が出店しており、ユニクロの快進撃が報じられた。都心の地価が下がり、賃料も下がり出店しやすくなったということではあるが、何よりも幅広く顧客支持が得られているブランドに成長したということだ。
同じように、既存店の売上を伸ばしている企業の一つがマクドナルドである。共に1990年代後半、「デフレの旗手」と言われたことがあったが、もはやそうした名称とは異なる消費価値のフェーズに到達しているということだ。つまり、「新しい標準」、価格は勿論のこと、品質もデザインも、マクドナルドで言えば味もサービスも、それらの総合価値としての標準である。
この2社を追いかけるように、各業種・業態でも「新しい標準」を目指す動きが見られる。家電量販のヤマダ、家具インテリアのニトリ、靴のABCマート、飲食の餃子の王将も入るかもしれない。少し前になるが、ソフトバンクによる携帯電話の料金設定も同様である。
こうした「新しい標準」とは、企業経営にとって一番重要であるプライスリーダーになるということである。勿論、そのプライスには圧倒的な顧客支持があってのことであるが。このデフレ下、不況下にあって、プライスリーダーとは想定した利益確保が他社と比較し容易になるということだ。
ただこうした標準は市場がグローバル化している時代においては、半導体産業が高機能製造に向かうことによってガラパゴス化してしまったことを教訓としなければならない。特に、工業製品において、例えばPCや携帯電話、あるいは薄型TVといった市場は多機能=高価格、単機能=低価格という2極化しているが、日本国内市場も低価格のグローバル市場へと準じ始めていることを忘れてはならないということである。グローバル市場とは、日本の場合特に中国と不可分にあり、その標準的価値を視野に入れなければならないということだ。いわゆる新興国市場は膨大であり、その潜在市場の成長への入り口では単機能=低価格戦略が不可欠となっている。
ところで新しい標準へと向かう潮流を整理すると以下のようになる。
○多機能(=高価格)から単機能(=低価格)へ
○プロサービス(=高価格)からセルフサービス(=低価格)へ
○独自・固有(=高価格)から一般・共通(=低価格)へ
以上のような潮流が新しい標準としてのマス市場を形成しつつあるということである。前回のブログの延長線上でいうと、個性から成熟へということとなる。そして、2極化とはこうした潮流のどちらかを選択肢としてもつということである。勿論、経済的裏付けもあるが、例えば携帯は単機能で十分だが、ファッションだけは少々高くても好きなブランドを選びたい。あるいは日頃の食事はつましく倹約するが、年1回の家族旅行には足を伸ばして海外で楽しみたい。つまり、選択肢の幅が広がり、その広がる幅が大きくなったことを2極化と呼んでいる。昔10人10色と言われてきたが、今や1人10色の時代になったということだ。そして、1人のなかにある色は総じて個性色が減り、普通色が増え、低価格色が増えてきたということである。これが不況下のデフレ心理である。
勿論、新しい標準にもの足らなさを感じるマーケットもある。例えば、東京に成城石井という輸入ワインやチーズといった高級食材を扱う食品スーパーがある。数年前ミニバブルにのって急速に多店舗展開し、成長ではなく膨張であったことから経営に行き詰り、新しい経営陣によって再建したスーパーである。他のスーパーと較べ、こだわり、違いを求めた少し高い価格帯の商品MDである。その内容であるが、例えば自家製パンなどでは朝用の詰め合わせパンには「国産ほうれん草ロール」が入っていたり、午後のティータイムロールにはマンゴーロールを入れる。新体制によるこうした丁寧な時間帯MDは小売業にとっては基本であり、個性色を求める顧客にしっかり応えれば成長しえる良き事例である。
何回も繰り返すが、「誰を顧客とするのか」、「その顧客は何色なのか」、その見極めが全てを決めるといっても過言ではない。新しい標準としてマス市場が形成されつつあるが、その標準もいつまで標準足りえるのか分からない時代である。(続く)
先日、東京新宿高島屋に百貨店では最大規模の面積のユニクロが出店した。今年3月には渋谷にも大型店が出店しており、ユニクロの快進撃が報じられた。都心の地価が下がり、賃料も下がり出店しやすくなったということではあるが、何よりも幅広く顧客支持が得られているブランドに成長したということだ。
同じように、既存店の売上を伸ばしている企業の一つがマクドナルドである。共に1990年代後半、「デフレの旗手」と言われたことがあったが、もはやそうした名称とは異なる消費価値のフェーズに到達しているということだ。つまり、「新しい標準」、価格は勿論のこと、品質もデザインも、マクドナルドで言えば味もサービスも、それらの総合価値としての標準である。
この2社を追いかけるように、各業種・業態でも「新しい標準」を目指す動きが見られる。家電量販のヤマダ、家具インテリアのニトリ、靴のABCマート、飲食の餃子の王将も入るかもしれない。少し前になるが、ソフトバンクによる携帯電話の料金設定も同様である。
こうした「新しい標準」とは、企業経営にとって一番重要であるプライスリーダーになるということである。勿論、そのプライスには圧倒的な顧客支持があってのことであるが。このデフレ下、不況下にあって、プライスリーダーとは想定した利益確保が他社と比較し容易になるということだ。
ただこうした標準は市場がグローバル化している時代においては、半導体産業が高機能製造に向かうことによってガラパゴス化してしまったことを教訓としなければならない。特に、工業製品において、例えばPCや携帯電話、あるいは薄型TVといった市場は多機能=高価格、単機能=低価格という2極化しているが、日本国内市場も低価格のグローバル市場へと準じ始めていることを忘れてはならないということである。グローバル市場とは、日本の場合特に中国と不可分にあり、その標準的価値を視野に入れなければならないということだ。いわゆる新興国市場は膨大であり、その潜在市場の成長への入り口では単機能=低価格戦略が不可欠となっている。
ところで新しい標準へと向かう潮流を整理すると以下のようになる。
○多機能(=高価格)から単機能(=低価格)へ
○プロサービス(=高価格)からセルフサービス(=低価格)へ
○独自・固有(=高価格)から一般・共通(=低価格)へ
以上のような潮流が新しい標準としてのマス市場を形成しつつあるということである。前回のブログの延長線上でいうと、個性から成熟へということとなる。そして、2極化とはこうした潮流のどちらかを選択肢としてもつということである。勿論、経済的裏付けもあるが、例えば携帯は単機能で十分だが、ファッションだけは少々高くても好きなブランドを選びたい。あるいは日頃の食事はつましく倹約するが、年1回の家族旅行には足を伸ばして海外で楽しみたい。つまり、選択肢の幅が広がり、その広がる幅が大きくなったことを2極化と呼んでいる。昔10人10色と言われてきたが、今や1人10色の時代になったということだ。そして、1人のなかにある色は総じて個性色が減り、普通色が増え、低価格色が増えてきたということである。これが不況下のデフレ心理である。
勿論、新しい標準にもの足らなさを感じるマーケットもある。例えば、東京に成城石井という輸入ワインやチーズといった高級食材を扱う食品スーパーがある。数年前ミニバブルにのって急速に多店舗展開し、成長ではなく膨張であったことから経営に行き詰り、新しい経営陣によって再建したスーパーである。他のスーパーと較べ、こだわり、違いを求めた少し高い価格帯の商品MDである。その内容であるが、例えば自家製パンなどでは朝用の詰め合わせパンには「国産ほうれん草ロール」が入っていたり、午後のティータイムロールにはマンゴーロールを入れる。新体制によるこうした丁寧な時間帯MDは小売業にとっては基本であり、個性色を求める顧客にしっかり応えれば成長しえる良き事例である。
何回も繰り返すが、「誰を顧客とするのか」、「その顧客は何色なのか」、その見極めが全てを決めるといっても過言ではない。新しい標準としてマス市場が形成されつつあるが、その標準もいつまで標準足りえるのか分からない時代である。(続く)
2010年04月25日
個性と成熟
ヒット商品応援団日記No461(毎週2回更新) 2010.4.25.
個性、自分らしさ、こうしたキーワードが聞こえてこなくなって久しい。マーケティングという需要を創造していく際、必ず向き合わなければならなかったテーマの一つである。何故、こうしたキーワードがビジネス現場から隠れてしまったか、その訳を知るためにいつ頃生まれたのかを考えている。
私の理解では、1980年代初め、当時の若い世代が丸井などに行列して買い求めたDC(デザイナーズ&キャラクター)ブランドが個性という「違い」をマーケティングした最初であったと思う。その代表的ブランドはコムデギャルソンやY's、ビギグループのブランドであったが、そうした「違い」を身にまとうことによって、他との違いを表現する欲望が市場として創られた最初であった。つまり、生きていく上で必要な必需消費ではない、個性という選択的消費、新たな消費概念が生まれたということでもある。
それまでの「違い」の概念は「高級」であった。私のような団塊世代が若い頃、サラリーマンになりたての薄給の時代にはサントリーレッドを飲み、給与が増え役職につける年代になるに従って、角やオールド、更には輸入ウイスキーがあった。つまり、収入と各種商品のクラス・価格がパラレルな関係にあった。車も排気量ごとのクラスに分かれ、価格もそれに準じていた。働き、給与が上がり、次のクラスのモノ(商品)を生活に取り入れることに最大の価値を置いていた。
こうした収入の増加と共にモノを生活へと取り入れてきた団塊世代と比較し、DCブランドブームの中心であったポスト団塊世代にとって、モノへの欠乏感はない。あるとすれば精神的充足感が個性という違いを追い求めたのだと思う。
こうした精神的充足感は新しい市場創造へと向かっていく。その最大のものがサブカルチャーである。コミック、アニメ、キャラクターといった今で言うところのクールジャパンの芽が奔出した時期である。更に言えば、前代未聞のメガヒット商品であるビックリマンチョコが生まれ、東京ディズニーランドもオープンする。
精神的充足はモノから物語へ、記号的価値へと急速に発展していく。消費においても、仮想としての物語、虚構としての物語が日常、現実へと向かっていく。この時、市場を牽引創造したのが真性おたく(オタクではない)であった。個性、自分らしさを追い求めた先が、仮想、虚構の世界であった。仮想、虚構とは無限空間のことであり、その過剰さはいつしか臨界点を向かえる。その象徴が、あのエヴァンゲリオンであった。面白いことに、1990年代半ば真性おたくがエヴァンゲリオンと共に市場から離れていく後を引き継ぐように、おたくはオタクとしてマスプロダクト化していく。
1990年代後半、IT技術の進歩によって少量生産少量販売が可能となり、個性という名のマスプロダクト化が低価格で市場へと浸透していく。当時デフレの旗手と言われたユニクロがその代表的企業である。このブログにおいても何回も書いてきたので省略するが、1998年以降収入は減り続け10年で年間100万円弱減少した。途中ミニバブル的様相はあったものの底流として低価格潮流、デフレの潮流があった、と私は理解している。そして、サブプライムローン問題が出始めた2007年夏以降東京都心の地価は下がり始め、翌年のリーマンショックによって一挙にデフレが加速する。
仮想から現実、虚構から日常へと消費の目が移行していく。個性、自分らしさというキーワードがカギの機能を果たせず、そのカギはわけあり商品に代表される低価格、あるいは何々したつもりといった代替消費へと変わった。これが巣ごもり消費時代の潮流である。
さて、個性、自分らしさはどこへいったのだろうか。代表的なDCブランドであるコムデギャルソンやビギグループのブランドは規模を縮小しビジネスを行っているが、Y'sは周知のように昨年破綻した。そもそも自分らしさとは他者との違いを前提としており、異なる商品を自分の周りに埋め尽くすことである。消費は収入の関数であり、そんな経済的余裕はない、という側面は勿論ある。以前、「キョロキョロ消費」というキーワードを使ったことがあった。周りを気にしてモノを買う、ランキング情報を気にして商品選択するのと同じ消費構造である。ある意味、「みんなと一緒」、KY語の世界と同じである。個性的、自分らしさの追求とは「空気が読めていない」人となる。
2月バンクーバーで行われた冬期オリンピックで、男子ハーフパイプの国母選手の服装問題はこのことを象徴するものであった。総じて、公式の場でのマナーや礼儀を指摘する議論が多かったようであるが、私に言わせれば国母選手は公式という「空気が読めていない」一人であったということだ。
本質的な問題として指摘をすれば、経済も、社会も、教育も戦後一貫して行ってきた根底には「個人」があり、共同して生きる、生活する、そうした価値観は無かった。いや、団塊世代ぐらいはあったと思うが、ポスト団塊世代以降は無かった。一言でいえば、あらゆる意味で個人化を進行させてきた。消費においても個人単位が基礎となってきた。当然、そこには家族はなく、コミュニティもなく、共同して何かをすることもなく、あるのは一種の私生活主義であった。しかし、その行き過ぎた反動として、一人鍋は家族鍋に変わり、村起こし町起こしといったコミュニティ再生の動きは全国各地で起こり、ルームシェアー、カーシェアーといった共有する価値観も生まれてきた。その背景には経済・社会の閉塞感と向き合うことに、一人ではなく共同して向き合う、一種防衛的にならざるを得ない情況にあるということだ。
こうしたなか、消費の2極化が指摘され始めている。収入と各種商品のクラス・価格がパラレルな消費関係に向かうということである。こうした消費傾向になっていくと思うが、少し前ブログに書いたように「好きの復活」ではないが、「違い」を求めるだけでなく、互いに「違い」を認め合う「大人の消費」、つまり各人が多様な「好き」を纏う方向へと向かっていく。別な言葉を使うとすれば「成熟した消費」である。ある意味、物語消費、記号的価値から最も離れた消費ということだ。多様な個人、多様な家族、多様なコミュニティが生まれ、小さなヒット商品が多様な消費シーンを創っていく。(続く)
個性、自分らしさ、こうしたキーワードが聞こえてこなくなって久しい。マーケティングという需要を創造していく際、必ず向き合わなければならなかったテーマの一つである。何故、こうしたキーワードがビジネス現場から隠れてしまったか、その訳を知るためにいつ頃生まれたのかを考えている。
私の理解では、1980年代初め、当時の若い世代が丸井などに行列して買い求めたDC(デザイナーズ&キャラクター)ブランドが個性という「違い」をマーケティングした最初であったと思う。その代表的ブランドはコムデギャルソンやY's、ビギグループのブランドであったが、そうした「違い」を身にまとうことによって、他との違いを表現する欲望が市場として創られた最初であった。つまり、生きていく上で必要な必需消費ではない、個性という選択的消費、新たな消費概念が生まれたということでもある。
それまでの「違い」の概念は「高級」であった。私のような団塊世代が若い頃、サラリーマンになりたての薄給の時代にはサントリーレッドを飲み、給与が増え役職につける年代になるに従って、角やオールド、更には輸入ウイスキーがあった。つまり、収入と各種商品のクラス・価格がパラレルな関係にあった。車も排気量ごとのクラスに分かれ、価格もそれに準じていた。働き、給与が上がり、次のクラスのモノ(商品)を生活に取り入れることに最大の価値を置いていた。
こうした収入の増加と共にモノを生活へと取り入れてきた団塊世代と比較し、DCブランドブームの中心であったポスト団塊世代にとって、モノへの欠乏感はない。あるとすれば精神的充足感が個性という違いを追い求めたのだと思う。
こうした精神的充足感は新しい市場創造へと向かっていく。その最大のものがサブカルチャーである。コミック、アニメ、キャラクターといった今で言うところのクールジャパンの芽が奔出した時期である。更に言えば、前代未聞のメガヒット商品であるビックリマンチョコが生まれ、東京ディズニーランドもオープンする。
精神的充足はモノから物語へ、記号的価値へと急速に発展していく。消費においても、仮想としての物語、虚構としての物語が日常、現実へと向かっていく。この時、市場を牽引創造したのが真性おたく(オタクではない)であった。個性、自分らしさを追い求めた先が、仮想、虚構の世界であった。仮想、虚構とは無限空間のことであり、その過剰さはいつしか臨界点を向かえる。その象徴が、あのエヴァンゲリオンであった。面白いことに、1990年代半ば真性おたくがエヴァンゲリオンと共に市場から離れていく後を引き継ぐように、おたくはオタクとしてマスプロダクト化していく。
1990年代後半、IT技術の進歩によって少量生産少量販売が可能となり、個性という名のマスプロダクト化が低価格で市場へと浸透していく。当時デフレの旗手と言われたユニクロがその代表的企業である。このブログにおいても何回も書いてきたので省略するが、1998年以降収入は減り続け10年で年間100万円弱減少した。途中ミニバブル的様相はあったものの底流として低価格潮流、デフレの潮流があった、と私は理解している。そして、サブプライムローン問題が出始めた2007年夏以降東京都心の地価は下がり始め、翌年のリーマンショックによって一挙にデフレが加速する。
仮想から現実、虚構から日常へと消費の目が移行していく。個性、自分らしさというキーワードがカギの機能を果たせず、そのカギはわけあり商品に代表される低価格、あるいは何々したつもりといった代替消費へと変わった。これが巣ごもり消費時代の潮流である。
さて、個性、自分らしさはどこへいったのだろうか。代表的なDCブランドであるコムデギャルソンやビギグループのブランドは規模を縮小しビジネスを行っているが、Y'sは周知のように昨年破綻した。そもそも自分らしさとは他者との違いを前提としており、異なる商品を自分の周りに埋め尽くすことである。消費は収入の関数であり、そんな経済的余裕はない、という側面は勿論ある。以前、「キョロキョロ消費」というキーワードを使ったことがあった。周りを気にしてモノを買う、ランキング情報を気にして商品選択するのと同じ消費構造である。ある意味、「みんなと一緒」、KY語の世界と同じである。個性的、自分らしさの追求とは「空気が読めていない」人となる。
2月バンクーバーで行われた冬期オリンピックで、男子ハーフパイプの国母選手の服装問題はこのことを象徴するものであった。総じて、公式の場でのマナーや礼儀を指摘する議論が多かったようであるが、私に言わせれば国母選手は公式という「空気が読めていない」一人であったということだ。
本質的な問題として指摘をすれば、経済も、社会も、教育も戦後一貫して行ってきた根底には「個人」があり、共同して生きる、生活する、そうした価値観は無かった。いや、団塊世代ぐらいはあったと思うが、ポスト団塊世代以降は無かった。一言でいえば、あらゆる意味で個人化を進行させてきた。消費においても個人単位が基礎となってきた。当然、そこには家族はなく、コミュニティもなく、共同して何かをすることもなく、あるのは一種の私生活主義であった。しかし、その行き過ぎた反動として、一人鍋は家族鍋に変わり、村起こし町起こしといったコミュニティ再生の動きは全国各地で起こり、ルームシェアー、カーシェアーといった共有する価値観も生まれてきた。その背景には経済・社会の閉塞感と向き合うことに、一人ではなく共同して向き合う、一種防衛的にならざるを得ない情況にあるということだ。
こうしたなか、消費の2極化が指摘され始めている。収入と各種商品のクラス・価格がパラレルな消費関係に向かうということである。こうした消費傾向になっていくと思うが、少し前ブログに書いたように「好きの復活」ではないが、「違い」を求めるだけでなく、互いに「違い」を認め合う「大人の消費」、つまり各人が多様な「好き」を纏う方向へと向かっていく。別な言葉を使うとすれば「成熟した消費」である。ある意味、物語消費、記号的価値から最も離れた消費ということだ。多様な個人、多様な家族、多様なコミュニティが生まれ、小さなヒット商品が多様な消費シーンを創っていく。(続く)
2010年04月21日
つぶやき効果
ヒット商品応援団日記No460(毎週2回更新) 2010.4.21.
ここ2回ほどツイッターに関するテーマについて書いたが、そのキーワードである「つぶやき効果」について、日経MJが「1−3月のヒット商品」について触れている。個人の体験などを踏まえたブログやツイッターの「つぶやき」が消費を促進させる良きコミュニケーションになっているとの指摘である。その代表的商品として桃屋の「ラー油」やSBの「おかずラー油」を取り上げていた。
ラー油と言えば、数年前から石垣島ぺんぎん食堂の「石垣島ラー油」が一部の好事家のお取り寄せ商品として話題になっていたが、こうしたつぶやきコミュニケーションがマス市場への広がりにかなりの効果を上げてきていることが分かる。
1ヶ月ほど前から従来の巣ごもり消費から少し活性化し始めてきたと指摘してきたが、その打開策の一つが消費体験の人づてコミュニケーションということだ。裏返せば、いかに多くの情報偽装を体験してきたかということである。既成マスメディアに対する不信とまでは言わないが、信用出来る情報は消費体験を持った生活者の「つぶやき」、「思わず出た言葉」、つまり「本音」ということだ。ブームとしての「わけあり商品」は終わったが、その火付け役である東京圏の地域スーパー「OKストア」のMDコンセプトであるオネスト、正直さ、を思い起こさせる。正直に安い訳を店頭に表示する、という方法が生活者の支持を得たということであった。
過剰な情報が行き交う真っただ中にあって、一生活者の小さな「つぶやき」が信頼出来る社会とは皮肉でもなんでもなく、全ての主体が生活者・個人に移行したということである。そして、無縁社会にあって、ひとときのつながり、ゆるい関係を結ぶメディア、特にツイッターへの関心は至極当然と言えよう。更に言えば、ツイッターの持つ「同時性」、今ここで何かを共有しているという感覚は、小さな単位ではあるが「時代共有感覚」といっても良いかもしれない。「つぶやき」で言えば、「あああの人も同じように感じているんだ」という時間感覚の共有である。
恐らく、マスメディアは桃屋のラー油の消費者を指して、「桃ラー」などと取り上げるかもしれない。大仰に言えば、個人が情報源・発信者になり、時代感覚をもたないマスメディアはその後を追う時代になったということだ。
この1−3月のヒット商品については、マクドナルドの「ビッグアメリカ」シリーズや旧エコ基準品の薄型TVについては既に取り上げてきたのでここでは取り上げない。また、2月にバンダイから「ハイパーーヨーヨー」が売り出されたが、販売は好調とのこと。これも10年ぶりに復活した玩具である。昨年の現代版ベーゴマ「ベイブレード」と同じ過去に遡った商品である。今月24日にはオタクの聖地秋葉原に「ガンダムカフェ」を併設したバンダイのキャラクターを集積したショップがオープンする。これにも多くのオタク、フアンが集まるであろう。つまり、昨年からのヒット商品の延長線上に全てある商品である。
以前から、当分の間「大型のヒット商品」は生まれないと指摘をしてきた。逆に、「つぶやき」が届く範囲内のヒット商品、小さなヒット商品は生まれる、という時代になったということでもあった。その「つぶやき」が一つの普遍性、普遍的な価値が見出せた時、「つぶやき」は「つぶやき」にリンクし、大きなヒット商品へと孵化していくと思う。ある意味、身体の多くは巣ごもりしているが、頭だけ外へ出し、時代の空気感を感じ取っている情況だと思う。そんな空気感のなか、つぶやくように歌うシンガーソングライター植村花菜さんの「トイレの神様」が静かにヒットしている。(続く)
ここ2回ほどツイッターに関するテーマについて書いたが、そのキーワードである「つぶやき効果」について、日経MJが「1−3月のヒット商品」について触れている。個人の体験などを踏まえたブログやツイッターの「つぶやき」が消費を促進させる良きコミュニケーションになっているとの指摘である。その代表的商品として桃屋の「ラー油」やSBの「おかずラー油」を取り上げていた。
ラー油と言えば、数年前から石垣島ぺんぎん食堂の「石垣島ラー油」が一部の好事家のお取り寄せ商品として話題になっていたが、こうしたつぶやきコミュニケーションがマス市場への広がりにかなりの効果を上げてきていることが分かる。
1ヶ月ほど前から従来の巣ごもり消費から少し活性化し始めてきたと指摘してきたが、その打開策の一つが消費体験の人づてコミュニケーションということだ。裏返せば、いかに多くの情報偽装を体験してきたかということである。既成マスメディアに対する不信とまでは言わないが、信用出来る情報は消費体験を持った生活者の「つぶやき」、「思わず出た言葉」、つまり「本音」ということだ。ブームとしての「わけあり商品」は終わったが、その火付け役である東京圏の地域スーパー「OKストア」のMDコンセプトであるオネスト、正直さ、を思い起こさせる。正直に安い訳を店頭に表示する、という方法が生活者の支持を得たということであった。
過剰な情報が行き交う真っただ中にあって、一生活者の小さな「つぶやき」が信頼出来る社会とは皮肉でもなんでもなく、全ての主体が生活者・個人に移行したということである。そして、無縁社会にあって、ひとときのつながり、ゆるい関係を結ぶメディア、特にツイッターへの関心は至極当然と言えよう。更に言えば、ツイッターの持つ「同時性」、今ここで何かを共有しているという感覚は、小さな単位ではあるが「時代共有感覚」といっても良いかもしれない。「つぶやき」で言えば、「あああの人も同じように感じているんだ」という時間感覚の共有である。
恐らく、マスメディアは桃屋のラー油の消費者を指して、「桃ラー」などと取り上げるかもしれない。大仰に言えば、個人が情報源・発信者になり、時代感覚をもたないマスメディアはその後を追う時代になったということだ。
この1−3月のヒット商品については、マクドナルドの「ビッグアメリカ」シリーズや旧エコ基準品の薄型TVについては既に取り上げてきたのでここでは取り上げない。また、2月にバンダイから「ハイパーーヨーヨー」が売り出されたが、販売は好調とのこと。これも10年ぶりに復活した玩具である。昨年の現代版ベーゴマ「ベイブレード」と同じ過去に遡った商品である。今月24日にはオタクの聖地秋葉原に「ガンダムカフェ」を併設したバンダイのキャラクターを集積したショップがオープンする。これにも多くのオタク、フアンが集まるであろう。つまり、昨年からのヒット商品の延長線上に全てある商品である。
以前から、当分の間「大型のヒット商品」は生まれないと指摘をしてきた。逆に、「つぶやき」が届く範囲内のヒット商品、小さなヒット商品は生まれる、という時代になったということでもあった。その「つぶやき」が一つの普遍性、普遍的な価値が見出せた時、「つぶやき」は「つぶやき」にリンクし、大きなヒット商品へと孵化していくと思う。ある意味、身体の多くは巣ごもりしているが、頭だけ外へ出し、時代の空気感を感じ取っている情況だと思う。そんな空気感のなか、つぶやくように歌うシンガーソングライター植村花菜さんの「トイレの神様」が静かにヒットしている。(続く)
2010年04月18日
無縁空間の通過儀礼
ヒット商品応援団日記No459(毎週2回更新) 2010.4.18.
前回、ツイッターというメディアを通じ、無縁社会であればこその新しい可能性について少しブログに書いた。その意図は少し理屈っぽくなるが、無縁と有縁とがぶつかり合う一種の境界の中に、何か次なる新しい人と人との関係性、コミュニティが生まれてくるのではないかということであった。
元々、無縁という言葉を一つのキーワードとして私が受け止めたのは、異端の歴史学者である網野善彦さんの「日本とは何か」(講談社刊)と出会ったからであった。今まで、中世日本について、四方を海に囲まれた島国という地形、荘園、封建制、こうした閉鎖された国というイメージを歴史教科書などで刷り込まれてきた。しかし、網野さんは、そうではないと民俗学の手法を使って庶民の生き生きとした歴史を明らかにしてくれた。島国という四方を海に囲まれていることとは、逆に自由に朝鮮半島や中国、更には南米ペルーにまで日本人が行き来していたという事実をもって、私たちを目うろこさせてくれた方である。
その網野さんであるが、歴史資料に出て来る「百姓」が、実は農民だけでなく、商人、金融業者、手工業者、船持といった多様な非農民が含まれていたことに着目し、中世日本の社会が農業社会、封建社会であったとする常識を覆した。その非農民的民、全国を流浪する非定住の民を「無縁の民」と呼んで光を当てた。無縁とは、どこにも帰属しない、今風に言えば血縁、地縁、職縁にとらわれない地理的にも精神的にも自由な民という意味である。
網野さんの著書に「海辺の百姓」という記述がある。物と物との交換経済から貨幣経済という信用経済が全国へと浸透していくのだが、その経済活動の中心として各地の産物を流通させていたのが海上交通を行っていた海辺の百姓であった。例えば、福井若狭湾の集落には漁労、製塩、廻船交易を営む「海人」といわれた人達も百姓と言われていた。当たり前のことであるが、四方を海に囲まれている日本であり、海人(うみんちゅ〜)は沖縄だけではないということだ。
ところで、海人も百姓であり、山中も平地も同様百姓である。こうした全国を動き回る無縁の民が集まり交易する場が市場(=市庭)であった。
既に鎌倉時代には無数の市庭があり交易交流していた。米や魚から絹、布、塩、壷、多くの生活に必要な物品が交換取引されていて、見知らぬ無縁の人々が市庭に集まった。その市が建つ場所であるが、荘園(共同体)と荘園との境界に寺社と共につくられ、網野さんの言葉に依れば無縁空間としてあった。何故無縁かと言うと、荘園内は定住農民による有縁の共同体があり、見知らぬ人同士が血縁や地縁にとらわれずに物を交換する特別な場所が必要であった。そこでは血縁、地縁といった有縁から離れた自立した個人として存在し、ある意味で自由空間であり、今で言う「自由貿易地域」「自由都市」のようなものであった。既に、この時代から市場原理の芽が出てきていたということだ。勿論、この時代にあっても、自由を良いことに「不善の輩」による「泥棒市」のようなものもあったようだ。
この市庭のルールであるが、地域差を超えた共通ルールが2つあったと言われている。1つは老若という年齢によるもので、集団という組織の秩序を老若で決めていったという点である。もう一つが、平等原則であったという。この平等原則は親子兄弟という縁を離れ、ある意味身分を超越した個人によって市場が運営されていくという点にあったという。
勿論、既成の歴史家が取り上げなかった無縁の民は、決して多数を占めていた訳ではない。中世日本は定住民である農民を中心にした自給自足的農耕経済、封建的社会であったと思う。しかし、そうした経済、社会が次へと進んでいくためには無縁の民が必要であったことだけは事実である。いずれにせよ、こうした無縁の民によって経済が活性・成長し、近世日本へと向かうのである。つまり、時代のエンジン役を果たしていたということだ。
ところで1月31日のNHKスペシャル「無縁社会〜”無縁死”3万2千人の衝撃」、更に第二弾である「『無縁社会』の衝撃」について私も番組を見た一人である。第二弾では情報縁としてのツイッターの可能性について詳しくは議論されていなかったのが残念ではあった。血縁、地縁、職縁を持たない人がこれからも増え続けていくと思う。しかし、単純に昔からある伝統的な共同体、コミュニティに戻れば良いということではない。私の場合、地理的にも精神的にも自由なWebの世界に、自由に行き来する中世日本の無縁の民を見たのである。
ウェッブ進化の方向について、梅田望夫氏は、「ネットのあちら側」の「信頼できる」空間がWeb2.0であると指摘をしてくれた。その方向にSNSもあり、ツイッターもあると思う。Webの世界と中世日本の市庭とを「無縁空間」として短絡的に重ねてしまってはいけないが、ツイッターなどの小さな単位での会話はどこか井戸端会議の雰囲気を感じる。実際にはリアルな顔を見ることは無いが、多様な価値観を互いに認め合う信頼関係が私には見て取れた。
既に、身じかで小さな困りごとなどでは、ミニNPO、ミニボランティアのような活動も行われている。そうした活動はリアルな現実とツイッターとを行ったり来たりしていると思う。あるいはママ友間で行われていたバザールなども、ツイッターの掲示板を介し、もう少し広がっていくと思う。勿論、こうした理想とする情報縁による新コミュニティばかりではない。インターネットの公空間には真偽、清濁、善悪、それらが玉石混淆・混沌としてある。しかし、こうしたことはインターネット上だけでなく、現実世界においても同様にある。数年前、情報偽装は多数存在し経験もしてきた。ツイッター上においても詐欺や「やらせ」といった詐欺まがいのこともこれから起きると思う。しかし、中世日本の市庭にも「不善の輩」が存在していたように、情報の時代に生きる私たちにとって、不可避な通過儀礼ということだ。結果、信頼できるWeb2.0を目指し、どんなルールが参加者によって作られていくか注目したい。そして、次の時代を切り拓くエンジンの一つとしてSNSやツイッターはある。いや、そう使って行かなければならないということだ。(続く)
前回、ツイッターというメディアを通じ、無縁社会であればこその新しい可能性について少しブログに書いた。その意図は少し理屈っぽくなるが、無縁と有縁とがぶつかり合う一種の境界の中に、何か次なる新しい人と人との関係性、コミュニティが生まれてくるのではないかということであった。
元々、無縁という言葉を一つのキーワードとして私が受け止めたのは、異端の歴史学者である網野善彦さんの「日本とは何か」(講談社刊)と出会ったからであった。今まで、中世日本について、四方を海に囲まれた島国という地形、荘園、封建制、こうした閉鎖された国というイメージを歴史教科書などで刷り込まれてきた。しかし、網野さんは、そうではないと民俗学の手法を使って庶民の生き生きとした歴史を明らかにしてくれた。島国という四方を海に囲まれていることとは、逆に自由に朝鮮半島や中国、更には南米ペルーにまで日本人が行き来していたという事実をもって、私たちを目うろこさせてくれた方である。
その網野さんであるが、歴史資料に出て来る「百姓」が、実は農民だけでなく、商人、金融業者、手工業者、船持といった多様な非農民が含まれていたことに着目し、中世日本の社会が農業社会、封建社会であったとする常識を覆した。その非農民的民、全国を流浪する非定住の民を「無縁の民」と呼んで光を当てた。無縁とは、どこにも帰属しない、今風に言えば血縁、地縁、職縁にとらわれない地理的にも精神的にも自由な民という意味である。
網野さんの著書に「海辺の百姓」という記述がある。物と物との交換経済から貨幣経済という信用経済が全国へと浸透していくのだが、その経済活動の中心として各地の産物を流通させていたのが海上交通を行っていた海辺の百姓であった。例えば、福井若狭湾の集落には漁労、製塩、廻船交易を営む「海人」といわれた人達も百姓と言われていた。当たり前のことであるが、四方を海に囲まれている日本であり、海人(うみんちゅ〜)は沖縄だけではないということだ。
ところで、海人も百姓であり、山中も平地も同様百姓である。こうした全国を動き回る無縁の民が集まり交易する場が市場(=市庭)であった。
既に鎌倉時代には無数の市庭があり交易交流していた。米や魚から絹、布、塩、壷、多くの生活に必要な物品が交換取引されていて、見知らぬ無縁の人々が市庭に集まった。その市が建つ場所であるが、荘園(共同体)と荘園との境界に寺社と共につくられ、網野さんの言葉に依れば無縁空間としてあった。何故無縁かと言うと、荘園内は定住農民による有縁の共同体があり、見知らぬ人同士が血縁や地縁にとらわれずに物を交換する特別な場所が必要であった。そこでは血縁、地縁といった有縁から離れた自立した個人として存在し、ある意味で自由空間であり、今で言う「自由貿易地域」「自由都市」のようなものであった。既に、この時代から市場原理の芽が出てきていたということだ。勿論、この時代にあっても、自由を良いことに「不善の輩」による「泥棒市」のようなものもあったようだ。
この市庭のルールであるが、地域差を超えた共通ルールが2つあったと言われている。1つは老若という年齢によるもので、集団という組織の秩序を老若で決めていったという点である。もう一つが、平等原則であったという。この平等原則は親子兄弟という縁を離れ、ある意味身分を超越した個人によって市場が運営されていくという点にあったという。
勿論、既成の歴史家が取り上げなかった無縁の民は、決して多数を占めていた訳ではない。中世日本は定住民である農民を中心にした自給自足的農耕経済、封建的社会であったと思う。しかし、そうした経済、社会が次へと進んでいくためには無縁の民が必要であったことだけは事実である。いずれにせよ、こうした無縁の民によって経済が活性・成長し、近世日本へと向かうのである。つまり、時代のエンジン役を果たしていたということだ。
ところで1月31日のNHKスペシャル「無縁社会〜”無縁死”3万2千人の衝撃」、更に第二弾である「『無縁社会』の衝撃」について私も番組を見た一人である。第二弾では情報縁としてのツイッターの可能性について詳しくは議論されていなかったのが残念ではあった。血縁、地縁、職縁を持たない人がこれからも増え続けていくと思う。しかし、単純に昔からある伝統的な共同体、コミュニティに戻れば良いということではない。私の場合、地理的にも精神的にも自由なWebの世界に、自由に行き来する中世日本の無縁の民を見たのである。
ウェッブ進化の方向について、梅田望夫氏は、「ネットのあちら側」の「信頼できる」空間がWeb2.0であると指摘をしてくれた。その方向にSNSもあり、ツイッターもあると思う。Webの世界と中世日本の市庭とを「無縁空間」として短絡的に重ねてしまってはいけないが、ツイッターなどの小さな単位での会話はどこか井戸端会議の雰囲気を感じる。実際にはリアルな顔を見ることは無いが、多様な価値観を互いに認め合う信頼関係が私には見て取れた。
既に、身じかで小さな困りごとなどでは、ミニNPO、ミニボランティアのような活動も行われている。そうした活動はリアルな現実とツイッターとを行ったり来たりしていると思う。あるいはママ友間で行われていたバザールなども、ツイッターの掲示板を介し、もう少し広がっていくと思う。勿論、こうした理想とする情報縁による新コミュニティばかりではない。インターネットの公空間には真偽、清濁、善悪、それらが玉石混淆・混沌としてある。しかし、こうしたことはインターネット上だけでなく、現実世界においても同様にある。数年前、情報偽装は多数存在し経験もしてきた。ツイッター上においても詐欺や「やらせ」といった詐欺まがいのこともこれから起きると思う。しかし、中世日本の市庭にも「不善の輩」が存在していたように、情報の時代に生きる私たちにとって、不可避な通過儀礼ということだ。結果、信頼できるWeb2.0を目指し、どんなルールが参加者によって作られていくか注目したい。そして、次の時代を切り拓くエンジンの一つとしてSNSやツイッターはある。いや、そう使って行かなければならないということだ。(続く)
2010年04月14日
無縁社会とツイッター
ヒット商品応援団日記No458(毎週2回更新) 2010.4.14.
昨年のヒット商品の一つであったツイッターが更に広がりを見せているようだ。日経MJによれば昨年は月間利用者が250万人に及んでいると報じていたが、政治家を始め、企業の新製品の試食会やモニターリングなど多様な使われ方が表へと出てきた。当初は140文字以内のつぶやくミニブログであったが、その双方向コミュニケーションのスピード、即時性によって、新しい会話メディアとして定着し始めたということであろう。
そもそもプログの発展は、誕生した米国では主にビジネス用として使われていたが、日本に導入されるや「子育て情報」の交換・交流メディアとして、更には自分のペットを舞台へと上げるメディアとして成長してきた。日本の場合は、「話し相手・つながりを求めて」という動機であったということだ。その裏返しであるが、いかに話し相手がいないか、個人化社会の進化と共に生まれてきたメディアと言えよう。
団塊世代以上のシニアにとって、血縁、地縁、職縁というつながりは今なお残ってはいる。しかし、1990年代に起こった多くの神話崩壊、特に終身雇用・年功序列といった会社=第二のコミュニティ神話の崩壊、更には大企業神話、金融企業神話がもろくも崩れるさまを見てきた。今の若い世代にとって職縁というつながりは極めて薄く無縁へと向かってきた。更には、都市を漂流するティーン達、援助交際や薬物汚染に象徴されるような第一の神話であった家庭の崩壊、学校の崩壊。バラバラとなった社会、そうした予兆が明確になったのがツイッターの前身である2ちゃんねるの掲示板への書き込みであろう。2000年代初期、多い日には1日300万件もの書き込みがあった2ちゃんねるであるが、書き込むという行為でそれなりの満足を得ていた時代であった。
こうしたつながりを求めたコミュニケーションはSNSやツイッターへと発展していく。既成のマスメディアが送り手として物語や世界観を一方的に送るコミュニケーションであるのに対し、インターネット上のコミュニケーションはプラットフォームさえ整備できればメディアとして大きく成長できることを証明した。
おもしろいことに、こうした双方向のコミュニケーションから生まれたのが、あの「電車男」である。2004年に出版され、映画化されたものであるが、送り手=作家を持たない新しい物語である。2004年3月〜5月まで、2ちゃんねるの掲示板に書き込まれた匿名の人達によるコミュニケーションである。つまり、匿名が物語の作者であり、主人公ということだ。
ところでこのツイッターであるが、多様な会話メディアとして活用されている。その冴えたるものがラジオ番組であり、いわば匿名レポーターとして番組内で紹介されるといった具合である。どこそこの桜は今は5分咲きであるとか、この地域で一番美味しいラーメン屋さんはどこそこといったように。テーマ次第ではあるが、コミュニティの相互補完メディアとしても機能している。
少し前に、「仮想と現実、行ったり来たり」というテーマでデジタル社会とアナログ社会について書いたことがあったが、インターネットの側から、特にツイッターにおいては、現実、アナログ社会へとその境界を越えてきたということであろう。これは未だ仮説ではあるが、初期の2ちゃんねるにおいては「電車男」のような副産物として新しい物語が生まれたが、ツイッターではより現実的な「出会い物語」が生まれて来ると思う。勿論、こうした新しい出会いを求め、促しているのが無縁社会ということであり、一方的にコンテンツを送るマスメディアへの違和感であろう。
ツイッター的リアリズム、という言葉はまだどこにも無いが、血縁、地縁、職縁といった動かし難い大きな観念から離れた、小さな軽い縁、ゆるい縁結びということだと思う。別な表現をすれば、小さなコミュニティの小さな物語創出メディアということになる。これは私の夢想かもしれないが、ツイッターからヒット商品が生まれて来ると予感している。それは企業がツイッターを通じて行うモニタリングやテスティングといった方法によってではない。2ちゃんねるから電車男が生まれたように、小さな軽い縁から生まれた「何か」が、急速に広がりヒット商品になるという意味である。小さな縁が小さな縁にリンクし、その「何か」を縁とすることに満足を得る。単なる話し相手でもなく、売り手・買い手といった関係でもない、そんな関係をツイッター的リアリズムと呼んでみたい。(続く)
昨年のヒット商品の一つであったツイッターが更に広がりを見せているようだ。日経MJによれば昨年は月間利用者が250万人に及んでいると報じていたが、政治家を始め、企業の新製品の試食会やモニターリングなど多様な使われ方が表へと出てきた。当初は140文字以内のつぶやくミニブログであったが、その双方向コミュニケーションのスピード、即時性によって、新しい会話メディアとして定着し始めたということであろう。
そもそもプログの発展は、誕生した米国では主にビジネス用として使われていたが、日本に導入されるや「子育て情報」の交換・交流メディアとして、更には自分のペットを舞台へと上げるメディアとして成長してきた。日本の場合は、「話し相手・つながりを求めて」という動機であったということだ。その裏返しであるが、いかに話し相手がいないか、個人化社会の進化と共に生まれてきたメディアと言えよう。
団塊世代以上のシニアにとって、血縁、地縁、職縁というつながりは今なお残ってはいる。しかし、1990年代に起こった多くの神話崩壊、特に終身雇用・年功序列といった会社=第二のコミュニティ神話の崩壊、更には大企業神話、金融企業神話がもろくも崩れるさまを見てきた。今の若い世代にとって職縁というつながりは極めて薄く無縁へと向かってきた。更には、都市を漂流するティーン達、援助交際や薬物汚染に象徴されるような第一の神話であった家庭の崩壊、学校の崩壊。バラバラとなった社会、そうした予兆が明確になったのがツイッターの前身である2ちゃんねるの掲示板への書き込みであろう。2000年代初期、多い日には1日300万件もの書き込みがあった2ちゃんねるであるが、書き込むという行為でそれなりの満足を得ていた時代であった。
こうしたつながりを求めたコミュニケーションはSNSやツイッターへと発展していく。既成のマスメディアが送り手として物語や世界観を一方的に送るコミュニケーションであるのに対し、インターネット上のコミュニケーションはプラットフォームさえ整備できればメディアとして大きく成長できることを証明した。
おもしろいことに、こうした双方向のコミュニケーションから生まれたのが、あの「電車男」である。2004年に出版され、映画化されたものであるが、送り手=作家を持たない新しい物語である。2004年3月〜5月まで、2ちゃんねるの掲示板に書き込まれた匿名の人達によるコミュニケーションである。つまり、匿名が物語の作者であり、主人公ということだ。
ところでこのツイッターであるが、多様な会話メディアとして活用されている。その冴えたるものがラジオ番組であり、いわば匿名レポーターとして番組内で紹介されるといった具合である。どこそこの桜は今は5分咲きであるとか、この地域で一番美味しいラーメン屋さんはどこそこといったように。テーマ次第ではあるが、コミュニティの相互補完メディアとしても機能している。
少し前に、「仮想と現実、行ったり来たり」というテーマでデジタル社会とアナログ社会について書いたことがあったが、インターネットの側から、特にツイッターにおいては、現実、アナログ社会へとその境界を越えてきたということであろう。これは未だ仮説ではあるが、初期の2ちゃんねるにおいては「電車男」のような副産物として新しい物語が生まれたが、ツイッターではより現実的な「出会い物語」が生まれて来ると思う。勿論、こうした新しい出会いを求め、促しているのが無縁社会ということであり、一方的にコンテンツを送るマスメディアへの違和感であろう。
ツイッター的リアリズム、という言葉はまだどこにも無いが、血縁、地縁、職縁といった動かし難い大きな観念から離れた、小さな軽い縁、ゆるい縁結びということだと思う。別な表現をすれば、小さなコミュニティの小さな物語創出メディアということになる。これは私の夢想かもしれないが、ツイッターからヒット商品が生まれて来ると予感している。それは企業がツイッターを通じて行うモニタリングやテスティングといった方法によってではない。2ちゃんねるから電車男が生まれたように、小さな軽い縁から生まれた「何か」が、急速に広がりヒット商品になるという意味である。小さな縁が小さな縁にリンクし、その「何か」を縁とすることに満足を得る。単なる話し相手でもなく、売り手・買い手といった関係でもない、そんな関係をツイッター的リアリズムと呼んでみたい。(続く)
2010年04月11日
「好き」の復活
ヒット商品応援団日記No457(毎週2回更新) 2010.4.11.
ここ数週間、寒暖の差の激しい不順な天気であったが、少しづつ本来の季節に戻りつつあるようだ。景気、消費はと言えば、ここ数回ブログにも書いたが、回復の兆しが見えてきた。というのも先日、ユニクロを展開するファーストリテイリングが、2010年八月期連結決算予想を上方修正すると発表した。勿論、増収増益であるが、この発表のなかで、柳井会長から、国内既存店の3月の売上・客数が共にマイナスに転じ、低価格の潮流はこれからも続くが以前と同じように一斉に集中することはなくなるであろうとのコメントがあった。私流の言葉にかえれば、低価格ブームは終わったということである。わけあり低価格は終焉に向かったということだ。勿論、過剰なわけあり価格競争という意味である。
つまり、急激に所得が増えたり、新たな雇用が生まれたという理由からではない。節約疲れ、我慢疲れからひとときハレの日の時間を持ちたいということである。ケの日、日常はやはり巣ごもり生活ではあるが、ハレの日ぐらいはチョット贅沢という消費感覚である。5月のゴールデンウイークもこの2年間の安近短と比較し、少し遠くへ、少し日数を伸ばし、使う金額も少し多めという消費が予測されている。
課題はハレの日にどんな消費行動の変化となってくるかということである。特に、6月からは子ども手当が支給され、更には高速道の料金が改定される。観光地のホテルや旅館、旅行代理店、旅客輸送各社、更には高速道のSA、あるいは町起こしなどのイベントなど、一斉に企画を実行し始めたと思う。一方、都心ではファミリー向けの企画も準備されていると思う。一種の地域間競争が生まれる訳であるが、昨年の1000円高速に集中し大渋滞した移動とは少し異なる世界も生まれて来る。東京でいうと、昨年は渋滞先が軽井沢や御殿場のアウトレットであったが、その異なる世界とはハレの日の「チョット贅沢」、この時位はいつもと違って、という消費行動である。
ハレの日とは季節歳時もあるが、記念日でもある。個人化した時代、無縁社会と呼ばれる時代にあって、人と人との関係を確認し合う記念日は重要なハレの日となった。誕生日から始まり、結婚、出産、といった人生の節目もさることながら、極めて個人的な思いの日もまた記念日となる。以前、「ミーギフト」、頑張った自分にご褒美、というキーワードが流行ったことがあったが、若い独身女性にとってはこうした消費も復活するであろう。いわゆる小さな幸福感を求めてである。
大仰な構えた消費ではない。いつもとチョット違った気分転換を促してくれる、そんな商品やサービスということとなる。例えば、旅行でいうと、最近では食泊分離が選択できる旅館も増えてきた。いつもと違って風情ある老舗高級旅館に泊まるが、食事は街中にある安いがその土地ならではの郷土料理を楽しむ、といった具合である。他は我慢しても、これだけは少し贅沢してみたい、そんな消費心理である。
それではどんな贅沢かと言うと、今ではほとんど忘れ去られてしまった本格、本物、上質、クオリティ感、老舗、匠、といった独自・固有な商品やサービス。あるいはここ数年我慢して購入を抑えてきたお気に入り、好き、といった商品群。そうした意味でブランド復活への芽も出てきたということである。足が遠のいていた百貨店、敷居がチョット高かった老舗旅館、趣味の世界においても上級を目指す機種や道具も少しづつ活性化されていくであろう。ある意味、「好きの復活」である。
こうした好きの復活は、わけあり商品や低価格商品といった巣ごもり体験が一巡したということでもある。今度は過剰になったわけあり商品や低価格商品を削ぎ落とす時を迎えたということだ。
つまり、低価格商品の量を追いかけることから上質や好きがハレの日を飾るということである。例えば、食で言えば、いつもは鳥や豚肉がテーブルにのるが、この時位は量は少ないがA5ランクの牛肉のステーキを食べる、といったことである。減選から厳選へと再び転換し始めた。1990年代の消費傾向と同じように見えるが、そこには確かな合理性、費用対効果(満足感)という新しい価値観も見えて来る。ヒット商品となったLED電球ではないが、長く使える、愛着が湧く、結果お得になる、といった合理性である。デフレ基調は変わらないが、わけあり商品(=価格力)というベストセラーの時代が終わり、ロングセラーという商品力の時代へと転換し始めた。(続く)
ここ数週間、寒暖の差の激しい不順な天気であったが、少しづつ本来の季節に戻りつつあるようだ。景気、消費はと言えば、ここ数回ブログにも書いたが、回復の兆しが見えてきた。というのも先日、ユニクロを展開するファーストリテイリングが、2010年八月期連結決算予想を上方修正すると発表した。勿論、増収増益であるが、この発表のなかで、柳井会長から、国内既存店の3月の売上・客数が共にマイナスに転じ、低価格の潮流はこれからも続くが以前と同じように一斉に集中することはなくなるであろうとのコメントがあった。私流の言葉にかえれば、低価格ブームは終わったということである。わけあり低価格は終焉に向かったということだ。勿論、過剰なわけあり価格競争という意味である。
つまり、急激に所得が増えたり、新たな雇用が生まれたという理由からではない。節約疲れ、我慢疲れからひとときハレの日の時間を持ちたいということである。ケの日、日常はやはり巣ごもり生活ではあるが、ハレの日ぐらいはチョット贅沢という消費感覚である。5月のゴールデンウイークもこの2年間の安近短と比較し、少し遠くへ、少し日数を伸ばし、使う金額も少し多めという消費が予測されている。
課題はハレの日にどんな消費行動の変化となってくるかということである。特に、6月からは子ども手当が支給され、更には高速道の料金が改定される。観光地のホテルや旅館、旅行代理店、旅客輸送各社、更には高速道のSA、あるいは町起こしなどのイベントなど、一斉に企画を実行し始めたと思う。一方、都心ではファミリー向けの企画も準備されていると思う。一種の地域間競争が生まれる訳であるが、昨年の1000円高速に集中し大渋滞した移動とは少し異なる世界も生まれて来る。東京でいうと、昨年は渋滞先が軽井沢や御殿場のアウトレットであったが、その異なる世界とはハレの日の「チョット贅沢」、この時位はいつもと違って、という消費行動である。
ハレの日とは季節歳時もあるが、記念日でもある。個人化した時代、無縁社会と呼ばれる時代にあって、人と人との関係を確認し合う記念日は重要なハレの日となった。誕生日から始まり、結婚、出産、といった人生の節目もさることながら、極めて個人的な思いの日もまた記念日となる。以前、「ミーギフト」、頑張った自分にご褒美、というキーワードが流行ったことがあったが、若い独身女性にとってはこうした消費も復活するであろう。いわゆる小さな幸福感を求めてである。
大仰な構えた消費ではない。いつもとチョット違った気分転換を促してくれる、そんな商品やサービスということとなる。例えば、旅行でいうと、最近では食泊分離が選択できる旅館も増えてきた。いつもと違って風情ある老舗高級旅館に泊まるが、食事は街中にある安いがその土地ならではの郷土料理を楽しむ、といった具合である。他は我慢しても、これだけは少し贅沢してみたい、そんな消費心理である。
それではどんな贅沢かと言うと、今ではほとんど忘れ去られてしまった本格、本物、上質、クオリティ感、老舗、匠、といった独自・固有な商品やサービス。あるいはここ数年我慢して購入を抑えてきたお気に入り、好き、といった商品群。そうした意味でブランド復活への芽も出てきたということである。足が遠のいていた百貨店、敷居がチョット高かった老舗旅館、趣味の世界においても上級を目指す機種や道具も少しづつ活性化されていくであろう。ある意味、「好きの復活」である。
こうした好きの復活は、わけあり商品や低価格商品といった巣ごもり体験が一巡したということでもある。今度は過剰になったわけあり商品や低価格商品を削ぎ落とす時を迎えたということだ。
つまり、低価格商品の量を追いかけることから上質や好きがハレの日を飾るということである。例えば、食で言えば、いつもは鳥や豚肉がテーブルにのるが、この時位は量は少ないがA5ランクの牛肉のステーキを食べる、といったことである。減選から厳選へと再び転換し始めた。1990年代の消費傾向と同じように見えるが、そこには確かな合理性、費用対効果(満足感)という新しい価値観も見えて来る。ヒット商品となったLED電球ではないが、長く使える、愛着が湧く、結果お得になる、といった合理性である。デフレ基調は変わらないが、わけあり商品(=価格力)というベストセラーの時代が終わり、ロングセラーという商品力の時代へと転換し始めた。(続く)
2010年04月07日
無料経済と興味の深化
ヒット商品応援団日記No456(毎週2回更新) 2010.4.7.
ここ10数年、インターネットが普及し、そのデジタル化の進行と共に無料経済の世界が広がってきた。勿論、全てが無料になるという訳ではないが、商品やメニューがデジタル化できれば、「無料」が価格設定の一つとなった。そうした無料化のなかで注目されてきたのが、「フリーミアム」というビジネスモデルである。一部の有料顧客が他の顧客の無料分を負担するモデルで、フリーとプレミアムを合わせた造語とのこと。良く知られているのが、GREEが行っている携帯魚釣りゲーム「釣りスタ」で、そのほとんどの人が無料でゲームを楽しむが、ゲームへの興味が深くなるにつれて、特殊な竿や餌(有料)が欲しくなり、その有料分で全体コストが賄われているというビジネスである。
こうしたマーケティング手法はデジタル世界だけではなく、アナログの世界においても既に行われている。その良き事例であるが、東京虎ノ門の「播磨屋」ではお茶やおかき、煎餅が無料となっており、人気の店となっている。普通であれば、お茶もしくは煎餅のどちらかを有料にしそうなものだが、この播磨屋は全て無料である。勿論、製造工程で割れてしまったような「わけあり商品」ではない。TVにおいても紹介されており、広告費を必要としないと同時に、カフェ利用顧客には好きな商品を購入する顧客、有料顧客も多いと聞いている。一種のお試しマーケティングであるが、無料が与える心理的インパクトは○○offといったものとは全く異なる強さを持っている。
つまり、デジタル世界、アナログ世界の如何を問わず、無料を入り口にした価格戦略・マーケティング戦略が本格化してきたということだ。
以前、「仮想と現実、行ったり来たり」というテーマでブログを書いたことがあったが、仮想世界も現実世界も同様に、顧客の興味・関心がどれだけ深くなるかがマーケティングのポイントとなる。蕎麦好きが高じて、自ら道具を揃え家族や親しい人にふるまっていた人が、最終的には蕎麦屋を開店させてしまう現代版道楽に似ている。こうした「興味」から「好き」へと促す従来型のマーケティングと共に、「無料」を入り口としたマーケティングの場合もアップグレードした世界を目指す有料プログラムが用意されている。つまり、アップグレードに価値を見出し、有料でかまわないと思ってもらうことである。「FREE」(NHK出版刊)を書いたクリス・アンダーソンによれば、無料顧客95%、有料顧客5%が「フリーミアム」というビジネスモデルの定説であると言う。一方、播磨屋の場合はどうであろうか。おかきや煎餅のメーカーであることから、店舗単位での収支ではなく、多分にPR経費として計上していると思う。但し、播磨屋本店のHPを見ても分かるが、「無料お試しセット」を始め「じっくり味わい楽しむコース」など4コースが用意されている。これも興味を入り口とした体験による深化、アップグレードを期待したメニュープログラムになっている。
また、従来からある需給バランスに基づいた価格設定も更にきめ細かく進化してきている。例えば、この4月から全日空の料金の仕組みが変わった。従来は早く席を埋めるために早割や特割といった価格戦略を採っていたが、この4月からは需要の多い時間帯の便は高く、需要の低い時間帯の便は安く設定されており、現在は幹線だけではあるが、最小単位である席の稼働率を上げる工夫がなされてきた。同じように「生もの」と言われてきたホテルや旅館も同様である。利用者にとっては多様な選択肢が用意されることで価格への満足度は高まるが、インターネット上を中心とした無料経済と共にデフレを促進していることは間違いない。
古いマーケティングの話で恐縮であるが、20−80の法則という経営モデルがある。20%のリピーター顧客が80%の売上を占めるという一つの経営指標のことである。初めてビジネスを行う時、顧客は全て新規開拓顧客である。その新規顧客をいかにフアンになってもらい、リピーターという安定した継続顧客を創造していくか、このことはデジタル世界でも同じである。ただロングテールのように、デジタル世界の市場規模は途方もなく大きく、ほんのわずかな%の有料顧客を生み出せれば経営が成り立つ。そのわずかな顧客も無料を入り口に興味を深化させ、有料へと向かわせられるかがこの時代の経営である。デジタル世界も、アナログ世界も同様に、無料というキーワードが広く市場へと侵蝕し始めた。(続く)
ここ10数年、インターネットが普及し、そのデジタル化の進行と共に無料経済の世界が広がってきた。勿論、全てが無料になるという訳ではないが、商品やメニューがデジタル化できれば、「無料」が価格設定の一つとなった。そうした無料化のなかで注目されてきたのが、「フリーミアム」というビジネスモデルである。一部の有料顧客が他の顧客の無料分を負担するモデルで、フリーとプレミアムを合わせた造語とのこと。良く知られているのが、GREEが行っている携帯魚釣りゲーム「釣りスタ」で、そのほとんどの人が無料でゲームを楽しむが、ゲームへの興味が深くなるにつれて、特殊な竿や餌(有料)が欲しくなり、その有料分で全体コストが賄われているというビジネスである。
こうしたマーケティング手法はデジタル世界だけではなく、アナログの世界においても既に行われている。その良き事例であるが、東京虎ノ門の「播磨屋」ではお茶やおかき、煎餅が無料となっており、人気の店となっている。普通であれば、お茶もしくは煎餅のどちらかを有料にしそうなものだが、この播磨屋は全て無料である。勿論、製造工程で割れてしまったような「わけあり商品」ではない。TVにおいても紹介されており、広告費を必要としないと同時に、カフェ利用顧客には好きな商品を購入する顧客、有料顧客も多いと聞いている。一種のお試しマーケティングであるが、無料が与える心理的インパクトは○○offといったものとは全く異なる強さを持っている。
つまり、デジタル世界、アナログ世界の如何を問わず、無料を入り口にした価格戦略・マーケティング戦略が本格化してきたということだ。
以前、「仮想と現実、行ったり来たり」というテーマでブログを書いたことがあったが、仮想世界も現実世界も同様に、顧客の興味・関心がどれだけ深くなるかがマーケティングのポイントとなる。蕎麦好きが高じて、自ら道具を揃え家族や親しい人にふるまっていた人が、最終的には蕎麦屋を開店させてしまう現代版道楽に似ている。こうした「興味」から「好き」へと促す従来型のマーケティングと共に、「無料」を入り口としたマーケティングの場合もアップグレードした世界を目指す有料プログラムが用意されている。つまり、アップグレードに価値を見出し、有料でかまわないと思ってもらうことである。「FREE」(NHK出版刊)を書いたクリス・アンダーソンによれば、無料顧客95%、有料顧客5%が「フリーミアム」というビジネスモデルの定説であると言う。一方、播磨屋の場合はどうであろうか。おかきや煎餅のメーカーであることから、店舗単位での収支ではなく、多分にPR経費として計上していると思う。但し、播磨屋本店のHPを見ても分かるが、「無料お試しセット」を始め「じっくり味わい楽しむコース」など4コースが用意されている。これも興味を入り口とした体験による深化、アップグレードを期待したメニュープログラムになっている。
また、従来からある需給バランスに基づいた価格設定も更にきめ細かく進化してきている。例えば、この4月から全日空の料金の仕組みが変わった。従来は早く席を埋めるために早割や特割といった価格戦略を採っていたが、この4月からは需要の多い時間帯の便は高く、需要の低い時間帯の便は安く設定されており、現在は幹線だけではあるが、最小単位である席の稼働率を上げる工夫がなされてきた。同じように「生もの」と言われてきたホテルや旅館も同様である。利用者にとっては多様な選択肢が用意されることで価格への満足度は高まるが、インターネット上を中心とした無料経済と共にデフレを促進していることは間違いない。
古いマーケティングの話で恐縮であるが、20−80の法則という経営モデルがある。20%のリピーター顧客が80%の売上を占めるという一つの経営指標のことである。初めてビジネスを行う時、顧客は全て新規開拓顧客である。その新規顧客をいかにフアンになってもらい、リピーターという安定した継続顧客を創造していくか、このことはデジタル世界でも同じである。ただロングテールのように、デジタル世界の市場規模は途方もなく大きく、ほんのわずかな%の有料顧客を生み出せれば経営が成り立つ。そのわずかな顧客も無料を入り口に興味を深化させ、有料へと向かわせられるかがこの時代の経営である。デジタル世界も、アナログ世界も同様に、無料というキーワードが広く市場へと侵蝕し始めた。(続く)
2010年04月04日
Reという発想の転換
ヒット商品応援団日記No455(毎週2回更新) 2010.4.4.
ここ数ヶ月、私のブログにアクセスするキーワードで一番多いのが「未来予測」についてである。未来はわからないということの証左であるが、前回書いた「シニア市場/再び、シニア市場に着眼」についても同様で、わからなかったら原則・基本に立ち帰ることだ。5〜6年ほど前、団塊世代の第二の人生市場について多くのマーケッターが語っており、私も何回かブログに書いてきた。当時論議されていたように、シニア市場は健在である。
先日、はとバスが企画した「昭和の懐メロツアー」に人気が集まり、30分でチケットが完売したと報じられた。過去回帰、歴史回帰は大きな潮流となっていることはこのブログでも指摘してきたが、今昭和歌謡がカラオケを始めシニア世代で大きなブームとなっている。この企画は1日限定であったが、顧客からの強い要請で定期メニューとなった。このはとバスは1990年代後半債務超過で破綻寸前であった会社である。この窮地を救ったのが以前ブログにも書いた宮端社長であったが、この時行ったのが、顧客の本音を聞くということであった。この昭和の懐メロツアーが定期メニューとなったことは、この顧客に聞くという「企業文化」が根付き、継承されているということだ。
話が横道にそれてしまったが、数年前も今もシニア市場だけは元気である。マスコミは注目しないが、このことが基本であることは言うまでもないことだ。
さてその顧客の消費であるが、私が一つの指標としてきた東京ディズニーリゾートの2009年度の来場者数の発表があった。25周年記念を行った2008年度と比較し5.2%減とのこと。しかし、これは昨年度に次ぐ二番目に高い来場者数であり、この巣ごもり消費という不況下しかも新型インフルエンザの流行にも関わらず、りリピーターは足を運んだということだ。
また、この発表に続きJTBからゴールデンウイーク期間の旅行動向の予測が発表された。海外旅行は2009年と比較し4.3%増の50.8万人。そして、欧州方面は6.3%増、上海万博もあって中国方面は12.%増。国内旅行は0.9%増の2150万人の見通しであると発表があった。ここ2年ほどの安近短という旅行傾向から少しづつ以前の旅行へと復調し始めたということだ。
深刻な状態を続けてきた百貨店売上も2月度は前年比5.4%減と昨年11月までの二桁減少から持ち直しつつあるようだ。資産デフレ、消費デフレは相変わらず続いており、消費氷河期的状態から完全に抜け切れたとは言えないが、6月からの子ども手当や高校授業料無料化の実施を考えると少し明るさが戻ってきたと言えよう。
但し、ヒルズ族やセレブといったキーワードが流行った2004年〜2006年頃のミニバブル的消費に戻るということではない。急速に資産デフレから脱却し、新たな雇用も生まれ、賃金も上がるといった劇的な回復に向かうとは誰も考えてはいない。2007年からの3年間、消費も含めて学習し、その上での消費の活性である。
その中で最も顕著に出てきた価値観はキーワード的にいうとReであろう。既にあるものを、再び、生かし切る、復活、復元、再生、再使用、勿体ない、といった価値観である。確か1992年頃であったと記憶しているが、中古車販売台数が新車販売台数を超えて以降、家も家の中にある生活道具も、バッグやアクセサリーに至まで多くのモノが「下取り」や「レンタル」、あるいは「アウトレット」や「わけあり商品」といった方法で生かされてきた。リ・ユース、リ・フォーム、リ・デザイン、リ・バイバル、リ・デュース、勿論リ・サイクルもであるが、このReの世界に多くの知恵やアイディアが創造されてきた。
過疎地の廃校となった小学校をオフィスに転用するといった発想以外に、生ハム製造工場や魚の養殖にも活用されている。都市周辺の工場跡地には野菜工場が作られたり、商店街の空き店舗は保育園になったりしているが、全てのアイディアの根底にはReがある。つまり、Reとは発想の転換ということだ。
こうしたスペース・場以外にも時間という過去・歴史を遡ればリ・バイバルとなり、昨年のヒット商品を見ればいかに多くの商品がヒットしているか分かると思う。はとバスの「昭和の懐メロツアー」もそうであるし、映画「Always三丁目の夕日」以降、大きな潮流となっている。こうした既にある過去や歴史もさることながら、やはり一番Reすべきものは自然である。東京ではこの4月から条例によりCO2削減の義務化と共に、以前ブログにも書いたように排出量取引制度が実施されている。つまり、地方にある自然エネルギーを東京の企業が買うということである。こうした動きに併行し、いわゆるグリーンビジネスが至る所で活性化されてきている。恐らく1年後には屋上緑化、壁面緑化といったことが至る所で見られることであろう。そして、既にある自然を使ったネイチャーウオーキングのような新しい楽しみ方も生まれてくる。
昨年末、2010年を「エコライフ元年」になると予測した。いや予測というより、断言したと言った方が正確であった。エコロジーとは生活そのものであり、そのエコライフの根底には新技術と共にReがある。そして、生活者の視点に立てば、Reを楽しむ時代を迎えたということだ。(続く)
ここ数ヶ月、私のブログにアクセスするキーワードで一番多いのが「未来予測」についてである。未来はわからないということの証左であるが、前回書いた「シニア市場/再び、シニア市場に着眼」についても同様で、わからなかったら原則・基本に立ち帰ることだ。5〜6年ほど前、団塊世代の第二の人生市場について多くのマーケッターが語っており、私も何回かブログに書いてきた。当時論議されていたように、シニア市場は健在である。
先日、はとバスが企画した「昭和の懐メロツアー」に人気が集まり、30分でチケットが完売したと報じられた。過去回帰、歴史回帰は大きな潮流となっていることはこのブログでも指摘してきたが、今昭和歌謡がカラオケを始めシニア世代で大きなブームとなっている。この企画は1日限定であったが、顧客からの強い要請で定期メニューとなった。このはとバスは1990年代後半債務超過で破綻寸前であった会社である。この窮地を救ったのが以前ブログにも書いた宮端社長であったが、この時行ったのが、顧客の本音を聞くということであった。この昭和の懐メロツアーが定期メニューとなったことは、この顧客に聞くという「企業文化」が根付き、継承されているということだ。
話が横道にそれてしまったが、数年前も今もシニア市場だけは元気である。マスコミは注目しないが、このことが基本であることは言うまでもないことだ。
さてその顧客の消費であるが、私が一つの指標としてきた東京ディズニーリゾートの2009年度の来場者数の発表があった。25周年記念を行った2008年度と比較し5.2%減とのこと。しかし、これは昨年度に次ぐ二番目に高い来場者数であり、この巣ごもり消費という不況下しかも新型インフルエンザの流行にも関わらず、りリピーターは足を運んだということだ。
また、この発表に続きJTBからゴールデンウイーク期間の旅行動向の予測が発表された。海外旅行は2009年と比較し4.3%増の50.8万人。そして、欧州方面は6.3%増、上海万博もあって中国方面は12.%増。国内旅行は0.9%増の2150万人の見通しであると発表があった。ここ2年ほどの安近短という旅行傾向から少しづつ以前の旅行へと復調し始めたということだ。
深刻な状態を続けてきた百貨店売上も2月度は前年比5.4%減と昨年11月までの二桁減少から持ち直しつつあるようだ。資産デフレ、消費デフレは相変わらず続いており、消費氷河期的状態から完全に抜け切れたとは言えないが、6月からの子ども手当や高校授業料無料化の実施を考えると少し明るさが戻ってきたと言えよう。
但し、ヒルズ族やセレブといったキーワードが流行った2004年〜2006年頃のミニバブル的消費に戻るということではない。急速に資産デフレから脱却し、新たな雇用も生まれ、賃金も上がるといった劇的な回復に向かうとは誰も考えてはいない。2007年からの3年間、消費も含めて学習し、その上での消費の活性である。
その中で最も顕著に出てきた価値観はキーワード的にいうとReであろう。既にあるものを、再び、生かし切る、復活、復元、再生、再使用、勿体ない、といった価値観である。確か1992年頃であったと記憶しているが、中古車販売台数が新車販売台数を超えて以降、家も家の中にある生活道具も、バッグやアクセサリーに至まで多くのモノが「下取り」や「レンタル」、あるいは「アウトレット」や「わけあり商品」といった方法で生かされてきた。リ・ユース、リ・フォーム、リ・デザイン、リ・バイバル、リ・デュース、勿論リ・サイクルもであるが、このReの世界に多くの知恵やアイディアが創造されてきた。
過疎地の廃校となった小学校をオフィスに転用するといった発想以外に、生ハム製造工場や魚の養殖にも活用されている。都市周辺の工場跡地には野菜工場が作られたり、商店街の空き店舗は保育園になったりしているが、全てのアイディアの根底にはReがある。つまり、Reとは発想の転換ということだ。
こうしたスペース・場以外にも時間という過去・歴史を遡ればリ・バイバルとなり、昨年のヒット商品を見ればいかに多くの商品がヒットしているか分かると思う。はとバスの「昭和の懐メロツアー」もそうであるし、映画「Always三丁目の夕日」以降、大きな潮流となっている。こうした既にある過去や歴史もさることながら、やはり一番Reすべきものは自然である。東京ではこの4月から条例によりCO2削減の義務化と共に、以前ブログにも書いたように排出量取引制度が実施されている。つまり、地方にある自然エネルギーを東京の企業が買うということである。こうした動きに併行し、いわゆるグリーンビジネスが至る所で活性化されてきている。恐らく1年後には屋上緑化、壁面緑化といったことが至る所で見られることであろう。そして、既にある自然を使ったネイチャーウオーキングのような新しい楽しみ方も生まれてくる。
昨年末、2010年を「エコライフ元年」になると予測した。いや予測というより、断言したと言った方が正確であった。エコロジーとは生活そのものであり、そのエコライフの根底には新技術と共にReがある。そして、生活者の視点に立てば、Reを楽しむ時代を迎えたということだ。(続く)