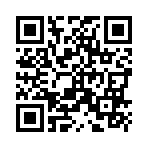2024年04月07日
マーケティングノート(2)後半
ヒット商品応援団日記No820(毎週更新) 2024.4,7.

街と共にある駅、その商業施設
「街と共にある駅」とは至極当たり前のことのように考えてしまうが、街の未来を生活者住民、商業者も行政も多くの力を借りて共に取り組んでいくということでもある。大船ルミネウイングも東口の再開発の中から生まれリニューアルしたように未来へ向けた変化の中心にはその多くに「駅」がある。
今都心の千代田区議会で秋葉原の再開発が議論されているが、秋葉原、いやアキバはその街の歴史・生業をものの見事に映し出した街である。現在のJR秋葉原北口一帯はその昔は神田青果市場であった。また、駅西口南側には「電気街」という表示が示すように戦後ラジオなどの電気部品などを販売する商店が雑居する街でもあった。
神田青果市場の歴史は古く江戸時代からの神田須田町にあった市場であったが、、1928年に秋葉原北口一帯に移転したが、更には1991年には現在の北口一帯の高層ビル群へと再開発によって変貌する。そして周知のように神田青果市場は大田区へと移転する。
こうした再開発は2001年秋葉原北口の神田青果市場の跡地を中心とした東京都によるITをテーマとした再開発事業が始まる。事業の正式名称は「AKIHABARA CROSSFIELD(アキハバラ クロスフィールド)」。名称の由来について、「様々な専門領域の人や情報が集うとともに、これらがクロスして切磋琢磨することで、ITを活用した次世代のビジネスを創造する場になることを目指した」と説明している。
JR秋葉原駅駅北口の超高層ビルUDXビルである。先端IT企業の誘致にふさわしく日本の大手企業であるNTTグループや新日鐵住金グルーパや日立グループといった企業が多数入居している。ところで、秋葉原は千代田区の中心となるエリアであるが、昼間人口・就業者数は約72.5万人、夜間人口はわずか4.7万人といういわばオフィスと商業街という「昼の街」である。
こうした再開発から外れた場所も駅周辺にはある。再開発が持つ一つの特徴であるが、まさに秋葉原駅北側の近代的な高層ビル群とは正反対の猥雑な街並が駅西側及び南側に広がっている。周知の電子部品や電気製品のパーツ、半導体、こうした電機関連商品を販売している専門店街。あるいはオタクの聖地と呼ばれるように、コミック、アニメ、フィギュアといった小さな専門店。数年前話題となったメイド喫茶も、こうしたごみごみとした一種猥雑な街並に溶け込んでいる。まるで地下都市であるかのように、ロースタイルと言ったら怒られるが定番のリュックサックを背負ったオタクやマニア、あるいは学生が行き交う街である。一方、駅北側の超高層ビルの1階にはオシャレなオープンカフェのあるキレイな街並が作られている。そんな異なる2つのエリアを比較してみると以下のように整理することができる。
駅北口エリア 駅西側エリア
○超高層ビル群/地球都市 ●アンダーグランド/地下都市
○IT先端企業、ソフト開発企業 ●電子部品、電気製品パーツ、半導体
○大型家電量販店/ヨドバシ ●電子部品販売中小零細街
○エリートサラリーマン・OL ●オタク、学生・フリーター・マニア
○オープンカフェ/風景 ●メイド喫茶/風俗
○最先端技術/デジタル世界 ●漫画、アニメ、フィギュア/アナログ世界
○エスニック料理 ●おでん缶詰の自販機
秋葉原の駅北側の再開発街とそれを囲むように広がる南西の旧電気街を、地球都市と地下都市という表現を使って対比させてみた。更に言うと、表と裏、昼と夜、あるいはビジネスマンとオタク、風景(オープンカフェ)と風俗(メイド喫茶)、デジタル世界(最先端技術)とアナログ世界(コミック、アニメ)、更にはカルチャーとサブカルチャーと言ってもかまわないし、あるいは表通り観光都市と路地裏観光都市といってもかまわない。こうした相反する、いや都市、人間が本来的に持つ2つの異質な欲望が交差する街、実はそれが秋葉原の魅力である。

こうした異空間が交差する街は再開発によって起こる現象であり、例えば新宿西口の開発されたビル群との間JR硬貨横の思い出横町、吉祥寺駅北口の商業施設街とハモニカ横町、・・・・・こうした「今」と「昭和」が交差する場所は東京では当たり前の光景となっている。面白いのは「今」という再開発から外れた場所はどんな生き方があるのか、その典型的な場所が谷根千(谷中、千田き、根津)という戦災を免れた上野裏の地域で「昭和レトロ」をコンセプトにした観光地化である。

ところでこうした先端技術を駆使したIT関連企業と共に、戦後間もない頃のITと言えば、それはラジオであった。同じ電気製品といっても前者をデジタルとすれば後者はアナログである。JR秋葉原駅の西側高架下は電気街口となっており、今なおそうしたパーツなどのアナログ製品が所狭しと販売されている。
しかし、昨年11月末そうした部品商店街の一つである「秋葉原ラジオストアー」が閉館した。JR秋葉原駅に隣接し、電機パーツ・機器ショップが多く入居する秋葉原の顔の1つであったが、「1つの時代の役割を終える事にいたしました」と64年の歴史に幕を下ろした。その役割を終えたとは、日本の家電メーカーの衰退と共に、そうした電気パーツなどはネット通販で購入することが多くなり、皮肉にも同じIT技術によって幕が引かれたということである。それでもなお、秋葉原電気街はマニアックな技術系オタクの聖地であることには変わりはない。
秋葉原がアキバと呼ばれオタクの街として発展したもう一つの「出来事」がある。2005年アキバオタクから生まれたのがAKB48であった。秋葉原北口から数分歩いたところにある雑居ビルのドンキ・ホーテが入る8階に専用劇場を設け、「会いにいけるアイドル」というコンセプトをもってスタートする。アイドルはあこがれの存在で遠くで応援するのが従来のフアンであった。こうした「既成」とは異なるところからスタートするのだが、最初の公演の観客はわずか72人でその内ほとんどが関係者であったと言われている。結果、2008年頃まではアキバオタクのアイドルと冷笑され、そのフアンスタイルの特異性や過剰さばかりがマスメディアを通じて報道されていた。
秋葉原、アキバにはサブカルチャーを生み出す街、オタクにとってその過激なこだわりを満足させる「何か」が存在していた。そのオタクの街を大きく転換させたのがAKB48であった。
数年前まで誰も見向きもしなかった、冷笑すらされたAKB48は次第にブレークしていく。卒業した前田敦子を見てもわかるが、「会いに行けるアイドル」という、どこにでも居そうな身近でかわいい少女はオタク達が創った日常リアルなアイドル物語と言えよう。そして、日本ばかりでなく世界各国にAKB48同様のチームが誕生している。
バブル崩壊は純文学といった既成文化の崩壊を進めたが、アニメや漫画といったサブカルチャーはアキバの地でオタクたちによって育てられ今や一大産業となった。コロナ禍を終え訪日観光客が85%まで回復したと言われているが、観光先が地方や横町露地歌の日本交友の生活文化体験へと変化して入るが、サブカルチャーの聖地である秋葉原を訪れるアニメオタクは多い。
十数年前までは日本の食文化の代表的なものは寿司やすき焼きであったが、勿論今なお訪日外国人にとって人気はあるが、今やラーメンが中心となり、コンビニのおにぎりに至る日常食が抗日外国人の目的の一つとなっている。こうした広がりはアニメや漫画のサブカルと同じようにクールジャパン、クールフーズとなっている。それは訪日観光客の変化、回数化が進み日本の生活文化、日常生活への興味関心が進化し、当然その傾向は地方へと広がる。その広がり進化を促進させているのがいうまでもなくSNSによるものである。
「失われた30年」と言われるが、確かに失ったものは多くあるが、残ったもの、いや新たに生まれたものもあった。日本アニメ、漫画、AKB48それら全て「サブ」であり、極々一部、の指示された世界、それは「既成」から外れたもの、一見非合理に見えるもの、「オタク」によって生み出されたものだ。
以前ブログにバブル崩壊の時代の「消費」について、次のように書いたことがあった。
『1980年代を「特異な時代」としたのは、その後の消費における新しい、面白い、珍しい商品やサービスが数多く市場に誕生してきたことにある。江戸時代との比較でいうと、江戸っ子の心を掴むキーワードは「珍」「奇」「怪」で、珍しい、奇をてらった、秘密めいた怪しげなものに惹かれた。例えば、天ぷらであれば上方では魚のすり身を揚げていたが、江戸では切り身に衣をつけて揚げる。寿司で言えば、時間のかかる押し寿司ではなく、酢飯にネタを握って素早く食べるように。似て非なるものを創ったのである。
江戸の場合は上方をモデルに「珍」「奇」「怪」という工夫・アイディアを付与し創造したのに対し、バブル期は欧米のメニュー業態をモデルに日本的な業態に変えていったということである。例えば、日本マクドナルドの成長についても日本版マクドナルドであり、1980年代半ばマクドナルドのハンバーガーにはミミズが入っているという「噂」を根本から否定するために、それまでの米国レシピから「100%ビーフ」に変更した。日本マクドナルドというより創業者の意向が強く反映した「藤田マクドナルド」であった。 あるいはダスキンが行なっているミスタードーナツの場合も、米国との契約上レシピ変更は不可であったが、確か1980年代契約を変更し、日本独自のメニューが可能となった。その本格的な独自メニューが1992年の新商品「飲茶」で、後に大ヒットとなるポン・デ・リングに繋がる。 つまり、ある意味今までの既成メニューとは全く異なる「商品」が生まれたという点にある。こうした例は米国生まれのコンビニ・セブンイレブンも同様で、米国のメニューや業態とは全く異なる日本独自の小売業を確立したのも1980年~1990年代であった。江戸時代から続いてきた異なる地域・文化の取り入れ方の工夫ではなく、全く発想の異なる今まで無かった「新」が生まれた点にある。
その理由は何であったか、それはあらゆる面で「自由」であったということである。過去にとらわれない「自由」、冒険ができる「自由」、とことん面白がれる「自由」、目標という前もった成果からの「自由」、サントリーの創業精神「やってみなはれ」もそうした自由な企業風土から生まれたものだ。そうした風土に触発されて「自由」を自覚することもあるが、その基本は多くの「しがらみ」を自ら解き放つことによって得られる実感である。勿論、そのことによって生まれる困難さや失敗を含めてであるが。 一方、受け手である生活者・消費者においては、壁を作らない「自由」、性別・年齢という壁を超えた「自由」、価格からの「自由」(安くても好きであればいいじゃないか)、こうした自由な選択肢があった時代である。今や当たり前となったセレクトショップも団塊ジュニアが作ったものだが、中国製でも気に入ればそれでいいじゃないかという「自由」が生まれていた。
バブルから学ぶこと・・・・・・「自由」であった時代
1980年代を「特異な時代」としたのは、その後の消費における新しい、面白い、珍しい商品やサービスが数多く市場に誕生してきたことにある。江戸時代との比較でいうと、江戸っ子の心を掴むキーワードは「珍」「奇」「怪」で、珍しい、奇をてらった、秘密めいた怪しげなものに惹かれた。例えば、天ぷらであれば上方では魚のすり身を揚げていたが、江戸では切り身に衣をつけて揚げる。寿司で言えば、時間のかかる押し寿司ではなく、酢飯にネタを握って素早く食べるように。似て非なるものを創ったのである。
江戸の場合は上方をモデルに「珍」「奇」「怪」という工夫・アイディアを付与し創造したのに対し、バブル期は欧米のメニュー業態をモデルに日本的な業態に変えていったということである。例えば、日本マクドナルドの成長についても日本版マクドナルドであり、1980年代半ばマクドナルドのハンバーガーにはミミズが入っているという「噂」を根本から否定するために、それまでの米国レシピから「100%ビーフ」に変更した。日本マクドナルドというより創業者の意向が強く反映した「藤田マクドナルド」であった。 あるいはダスキンが行なっているミスタードーナツの場合も、米国との契約上レシピ変更は不可であったが、確か1980年代契約を変更し、日本独自のメニューが可能となった。その本格的な独自メニューが1992年の新商品「飲茶」で、後に大ヒットとなるポン・デ・リングに繋がる。 つまり、ある意味今までの既成メニューとは全く異なる「商品」が生まれたという点にある。こうした例は米国生まれのコンビニ・セブンイレブンも同様で、米国のメニューや業態とは全く異なる日本独自の小売業を確立したのも1980年~1990年代であった。江戸時代から続いてきた異なる地域・文化の取り入れ方の工夫ではなく、全く発想の異なる今まで無かった「新」が生まれた点にある。
その理由は何であったか、それはあらゆる面で「自由」であったということである。過去にとらわれない「自由」、冒険ができる「自由」、とことん面白がれる「自由」、目標という前もった成果からの「自由」、サントリーの創業精神「やってみなはれ」もそうした自由な企業風土から生まれたものだ。そうした風土に触発されて「自由」を自覚することもあるが、その基本は多くの「しがらみ」を自ら解き放つことによって得られる実感である。勿論、そのことによって生まれる困難さや失敗を含めてであるが。 一方、受け手である生活者・消費者においては、壁を作らない「自由」、性別・年齢という壁を超えた「自由」、価格からの「自由」(安くても好きであればいいじゃないか)、こうした自由な選択肢があった時代である。今や当たり前となったセレクトショップも団塊ジュニアが作ったものだが、中国製でも気に入ればそれでいいじゃないかという「自由」が生まれていた。
「自由」を面白がる時代へ
こうした「自由さ」は戦前の価値観からの解放と共に、映画「Always三丁目の夕日」に描かれていたように「豊かではなかったが、そこには夢や希望があった」、そんな夢や希望を持ち得たのが昭和という時代であった。そこには夢や希望を追いかける「自由」が横溢していた時代のことでもあった。企業も個人も、何事かを生み出す「創業」時代であったということだ。平成の時代になり、特に2000年代になり盛んにベンチャーが叫ばれてきたが、ほとんど結果は得られてはいない。数年前から、ベンチャーキャピタルのいくつかのフアンドによる試みが始まっているが、社会を動かす潮流には程遠い。 ところで「自由」というと勝手気儘なことのように思いがちであるが、実は真逆の世界である。結果は誰でもない自分自身に返ってくるもので、だから面白いと思える人によってのみ「自由」はある。 江戸元禄の世を「浮世」と呼んでいるが、実は自己責任は明確にあった。平和な江戸時代には五街道が整備され、一定の制限はあるもののお伊勢参りのように旅行が盛んであった。その際必要となったのが通行手形で居住する大家(町役人・村役人)に申請し発行してもらう仕組みであった。今日のパスポートと同じようなものだが、手形に書いてあるのが「旅先で死んでもあり合わせのところに埋めてください」「亡骸は送り戻す必要はありません」といった主旨の一文が記載されていた。つまり、生きるも死ぬも自分の判断、他人のせいにしない」ということが理解されていた社会であった。
こうした自由を面白がれるには、周囲も、社会も、時代も「前」「未来」に向いていることが必要であった。しかし、バブル崩壊後の30数年、多くの神話崩壊と共に企業・個人にのしかかる「不安」、広く社会に広がる「不安」を前に「自由」になれる環境には程遠かった。一言で言えば、繰り返し言われていることだが「将来不安」ということになる。消費を含めた心が向かう先は「内側」ということになる。しかも、「過去」へと遡る傾向を強めていく心理市場については過去何度となく書いているのでここでは省略する。
また、このブログでも繰り返し書いてきている家計調査報告を踏まえると、勤労者世帯収入が増えないばかりか、リーマンショック以降社会保険料が増え、手取り給与(可処分所得)は減るだけでなく、企業側も半分負担していることからその負担も大きい。「自由」を面白がる環境条件が更に満たされなくなってきている。これが将来不安に直接繋がり、雇用形態も非正規雇用が4割を超えた。
ただ昨年夏以降、ユニクロ柳井社長の言葉ではないが、「デフレもまた良いものではないか」という発言に見られるように、企業も、生活者も自ら「デフレ的なるもの」の世界観からは既に脱却している。そうしたことを踏まえデフレは日常化し、死語になったとブログにも書いた。バブル崩壊によって生まれた個々の「不安」は勿論残ってはいるものの、昭和と平成の世代比較において考えるならば、バブル崩壊という「不安」視座から「消費」を見れば、昭和世代は崩壊経験もあり「リアルなものとしての不安」であり、平成世代のそれは「漠とした不安」である。昭和世代にとっての不安は具体的であり解決もまた可能である。しかし、平成世代の方が不確かであるが故に問題は深刻であるということだ。 ただ、「自由」という視座を持って考えるとすれば、国や社会といった大きな単位における制度や環境作りではなく、もっと小さな単位、家庭やコミュニティ、あるいは企業の部署単位や団体単位で「自由」に取り組むことは可能である。
既成から「自由」である企業がどんな成果を上げてきたか、例えば非常識経営と言われた岐阜にある電気設備資材メーカーである未来工業があり、最近ではブログにも取り上げた24時間営業の立ち食いそば「富士そば」もある。両社共に「人」を大切に考えた経営者による企業であり、従業員もそれに応えた企業である。未来工業においては社員から様々なアイディアを募集し商品開発や作業改善に役立てている。富士そばにおいても店独自のメニュー開発を促進し、一味違う店作りを行なっている。どちらも社員の自由な創意工夫が経営に大きく貢献し、勿論その成果配分は言うまでもない。そんな経営の仕組みを持った企業である。
今回はバブルのマイナス面ばかりが指摘されてきた20数年であったことに対し。敢えて「バブル期に生まれた<新しさ>」の背景に「自由」があったということに着眼した。「失われた30年」という言葉で、ビジネスもマーケティングにおいても全てを切り捨ててきたが、1980年という特異な時代を読み解いていくと、そこにこれから「先」の着眼も見えてきたように思える。発想を変えてコトに向かう、これもまた「自由」のなせる技である。
世代論は好きではないが、多くの専門家は指摘するようにその消費のユニークさからZ世代に注目が集まっている。それはバブル崩壊の「意味」から離れたところに生活しているからに他ならない。新しいデジタル機器を使いこなし、団塊世代が育った時代社会、つまり昭和レトロに興味を持ち、その新しさをいとも簡単位取り入れる軽やか消費など、その上の世代が「離れ世代」と呼ばれた現象とは正反対である。
本年度のアカデミー賞で、日本の作品として初めて視覚効果賞を受賞した「ゴジラ-1.0」。受賞した山崎貴監督(白組)はあの「Always三丁目の夕日」のCGを監督した人物で、今回の「ゴジラ-1.0」はZ世代が中心となって制作したように、この世代が消費のみならずビジネスにおいても表舞台へと出てきた。規制から「自由」な世代として期待される意味がよくわかる気がする。過剰な情報時代にも「倍速」という方法で乗り越える軽やか世代で有る。(続く)

街と共にある駅、その商業施設
「街と共にある駅」とは至極当たり前のことのように考えてしまうが、街の未来を生活者住民、商業者も行政も多くの力を借りて共に取り組んでいくということでもある。大船ルミネウイングも東口の再開発の中から生まれリニューアルしたように未来へ向けた変化の中心にはその多くに「駅」がある。
今都心の千代田区議会で秋葉原の再開発が議論されているが、秋葉原、いやアキバはその街の歴史・生業をものの見事に映し出した街である。現在のJR秋葉原北口一帯はその昔は神田青果市場であった。また、駅西口南側には「電気街」という表示が示すように戦後ラジオなどの電気部品などを販売する商店が雑居する街でもあった。
神田青果市場の歴史は古く江戸時代からの神田須田町にあった市場であったが、、1928年に秋葉原北口一帯に移転したが、更には1991年には現在の北口一帯の高層ビル群へと再開発によって変貌する。そして周知のように神田青果市場は大田区へと移転する。
こうした再開発は2001年秋葉原北口の神田青果市場の跡地を中心とした東京都によるITをテーマとした再開発事業が始まる。事業の正式名称は「AKIHABARA CROSSFIELD(アキハバラ クロスフィールド)」。名称の由来について、「様々な専門領域の人や情報が集うとともに、これらがクロスして切磋琢磨することで、ITを活用した次世代のビジネスを創造する場になることを目指した」と説明している。
JR秋葉原駅駅北口の超高層ビルUDXビルである。先端IT企業の誘致にふさわしく日本の大手企業であるNTTグループや新日鐵住金グルーパや日立グループといった企業が多数入居している。ところで、秋葉原は千代田区の中心となるエリアであるが、昼間人口・就業者数は約72.5万人、夜間人口はわずか4.7万人といういわばオフィスと商業街という「昼の街」である。
こうした再開発から外れた場所も駅周辺にはある。再開発が持つ一つの特徴であるが、まさに秋葉原駅北側の近代的な高層ビル群とは正反対の猥雑な街並が駅西側及び南側に広がっている。周知の電子部品や電気製品のパーツ、半導体、こうした電機関連商品を販売している専門店街。あるいはオタクの聖地と呼ばれるように、コミック、アニメ、フィギュアといった小さな専門店。数年前話題となったメイド喫茶も、こうしたごみごみとした一種猥雑な街並に溶け込んでいる。まるで地下都市であるかのように、ロースタイルと言ったら怒られるが定番のリュックサックを背負ったオタクやマニア、あるいは学生が行き交う街である。一方、駅北側の超高層ビルの1階にはオシャレなオープンカフェのあるキレイな街並が作られている。そんな異なる2つのエリアを比較してみると以下のように整理することができる。
駅北口エリア 駅西側エリア
○超高層ビル群/地球都市 ●アンダーグランド/地下都市
○IT先端企業、ソフト開発企業 ●電子部品、電気製品パーツ、半導体
○大型家電量販店/ヨドバシ ●電子部品販売中小零細街
○エリートサラリーマン・OL ●オタク、学生・フリーター・マニア
○オープンカフェ/風景 ●メイド喫茶/風俗
○最先端技術/デジタル世界 ●漫画、アニメ、フィギュア/アナログ世界
○エスニック料理 ●おでん缶詰の自販機
秋葉原の駅北側の再開発街とそれを囲むように広がる南西の旧電気街を、地球都市と地下都市という表現を使って対比させてみた。更に言うと、表と裏、昼と夜、あるいはビジネスマンとオタク、風景(オープンカフェ)と風俗(メイド喫茶)、デジタル世界(最先端技術)とアナログ世界(コミック、アニメ)、更にはカルチャーとサブカルチャーと言ってもかまわないし、あるいは表通り観光都市と路地裏観光都市といってもかまわない。こうした相反する、いや都市、人間が本来的に持つ2つの異質な欲望が交差する街、実はそれが秋葉原の魅力である。

こうした異空間が交差する街は再開発によって起こる現象であり、例えば新宿西口の開発されたビル群との間JR硬貨横の思い出横町、吉祥寺駅北口の商業施設街とハモニカ横町、・・・・・こうした「今」と「昭和」が交差する場所は東京では当たり前の光景となっている。面白いのは「今」という再開発から外れた場所はどんな生き方があるのか、その典型的な場所が谷根千(谷中、千田き、根津)という戦災を免れた上野裏の地域で「昭和レトロ」をコンセプトにした観光地化である。

ところでこうした先端技術を駆使したIT関連企業と共に、戦後間もない頃のITと言えば、それはラジオであった。同じ電気製品といっても前者をデジタルとすれば後者はアナログである。JR秋葉原駅の西側高架下は電気街口となっており、今なおそうしたパーツなどのアナログ製品が所狭しと販売されている。
しかし、昨年11月末そうした部品商店街の一つである「秋葉原ラジオストアー」が閉館した。JR秋葉原駅に隣接し、電機パーツ・機器ショップが多く入居する秋葉原の顔の1つであったが、「1つの時代の役割を終える事にいたしました」と64年の歴史に幕を下ろした。その役割を終えたとは、日本の家電メーカーの衰退と共に、そうした電気パーツなどはネット通販で購入することが多くなり、皮肉にも同じIT技術によって幕が引かれたということである。それでもなお、秋葉原電気街はマニアックな技術系オタクの聖地であることには変わりはない。
秋葉原がアキバと呼ばれオタクの街として発展したもう一つの「出来事」がある。2005年アキバオタクから生まれたのがAKB48であった。秋葉原北口から数分歩いたところにある雑居ビルのドンキ・ホーテが入る8階に専用劇場を設け、「会いにいけるアイドル」というコンセプトをもってスタートする。アイドルはあこがれの存在で遠くで応援するのが従来のフアンであった。こうした「既成」とは異なるところからスタートするのだが、最初の公演の観客はわずか72人でその内ほとんどが関係者であったと言われている。結果、2008年頃まではアキバオタクのアイドルと冷笑され、そのフアンスタイルの特異性や過剰さばかりがマスメディアを通じて報道されていた。
秋葉原、アキバにはサブカルチャーを生み出す街、オタクにとってその過激なこだわりを満足させる「何か」が存在していた。そのオタクの街を大きく転換させたのがAKB48であった。
数年前まで誰も見向きもしなかった、冷笑すらされたAKB48は次第にブレークしていく。卒業した前田敦子を見てもわかるが、「会いに行けるアイドル」という、どこにでも居そうな身近でかわいい少女はオタク達が創った日常リアルなアイドル物語と言えよう。そして、日本ばかりでなく世界各国にAKB48同様のチームが誕生している。
バブル崩壊は純文学といった既成文化の崩壊を進めたが、アニメや漫画といったサブカルチャーはアキバの地でオタクたちによって育てられ今や一大産業となった。コロナ禍を終え訪日観光客が85%まで回復したと言われているが、観光先が地方や横町露地歌の日本交友の生活文化体験へと変化して入るが、サブカルチャーの聖地である秋葉原を訪れるアニメオタクは多い。
十数年前までは日本の食文化の代表的なものは寿司やすき焼きであったが、勿論今なお訪日外国人にとって人気はあるが、今やラーメンが中心となり、コンビニのおにぎりに至る日常食が抗日外国人の目的の一つとなっている。こうした広がりはアニメや漫画のサブカルと同じようにクールジャパン、クールフーズとなっている。それは訪日観光客の変化、回数化が進み日本の生活文化、日常生活への興味関心が進化し、当然その傾向は地方へと広がる。その広がり進化を促進させているのがいうまでもなくSNSによるものである。
「失われた30年」と言われるが、確かに失ったものは多くあるが、残ったもの、いや新たに生まれたものもあった。日本アニメ、漫画、AKB48それら全て「サブ」であり、極々一部、の指示された世界、それは「既成」から外れたもの、一見非合理に見えるもの、「オタク」によって生み出されたものだ。
以前ブログにバブル崩壊の時代の「消費」について、次のように書いたことがあった。
『1980年代を「特異な時代」としたのは、その後の消費における新しい、面白い、珍しい商品やサービスが数多く市場に誕生してきたことにある。江戸時代との比較でいうと、江戸っ子の心を掴むキーワードは「珍」「奇」「怪」で、珍しい、奇をてらった、秘密めいた怪しげなものに惹かれた。例えば、天ぷらであれば上方では魚のすり身を揚げていたが、江戸では切り身に衣をつけて揚げる。寿司で言えば、時間のかかる押し寿司ではなく、酢飯にネタを握って素早く食べるように。似て非なるものを創ったのである。
江戸の場合は上方をモデルに「珍」「奇」「怪」という工夫・アイディアを付与し創造したのに対し、バブル期は欧米のメニュー業態をモデルに日本的な業態に変えていったということである。例えば、日本マクドナルドの成長についても日本版マクドナルドであり、1980年代半ばマクドナルドのハンバーガーにはミミズが入っているという「噂」を根本から否定するために、それまでの米国レシピから「100%ビーフ」に変更した。日本マクドナルドというより創業者の意向が強く反映した「藤田マクドナルド」であった。 あるいはダスキンが行なっているミスタードーナツの場合も、米国との契約上レシピ変更は不可であったが、確か1980年代契約を変更し、日本独自のメニューが可能となった。その本格的な独自メニューが1992年の新商品「飲茶」で、後に大ヒットとなるポン・デ・リングに繋がる。 つまり、ある意味今までの既成メニューとは全く異なる「商品」が生まれたという点にある。こうした例は米国生まれのコンビニ・セブンイレブンも同様で、米国のメニューや業態とは全く異なる日本独自の小売業を確立したのも1980年~1990年代であった。江戸時代から続いてきた異なる地域・文化の取り入れ方の工夫ではなく、全く発想の異なる今まで無かった「新」が生まれた点にある。
その理由は何であったか、それはあらゆる面で「自由」であったということである。過去にとらわれない「自由」、冒険ができる「自由」、とことん面白がれる「自由」、目標という前もった成果からの「自由」、サントリーの創業精神「やってみなはれ」もそうした自由な企業風土から生まれたものだ。そうした風土に触発されて「自由」を自覚することもあるが、その基本は多くの「しがらみ」を自ら解き放つことによって得られる実感である。勿論、そのことによって生まれる困難さや失敗を含めてであるが。 一方、受け手である生活者・消費者においては、壁を作らない「自由」、性別・年齢という壁を超えた「自由」、価格からの「自由」(安くても好きであればいいじゃないか)、こうした自由な選択肢があった時代である。今や当たり前となったセレクトショップも団塊ジュニアが作ったものだが、中国製でも気に入ればそれでいいじゃないかという「自由」が生まれていた。
バブルから学ぶこと・・・・・・「自由」であった時代
1980年代を「特異な時代」としたのは、その後の消費における新しい、面白い、珍しい商品やサービスが数多く市場に誕生してきたことにある。江戸時代との比較でいうと、江戸っ子の心を掴むキーワードは「珍」「奇」「怪」で、珍しい、奇をてらった、秘密めいた怪しげなものに惹かれた。例えば、天ぷらであれば上方では魚のすり身を揚げていたが、江戸では切り身に衣をつけて揚げる。寿司で言えば、時間のかかる押し寿司ではなく、酢飯にネタを握って素早く食べるように。似て非なるものを創ったのである。
江戸の場合は上方をモデルに「珍」「奇」「怪」という工夫・アイディアを付与し創造したのに対し、バブル期は欧米のメニュー業態をモデルに日本的な業態に変えていったということである。例えば、日本マクドナルドの成長についても日本版マクドナルドであり、1980年代半ばマクドナルドのハンバーガーにはミミズが入っているという「噂」を根本から否定するために、それまでの米国レシピから「100%ビーフ」に変更した。日本マクドナルドというより創業者の意向が強く反映した「藤田マクドナルド」であった。 あるいはダスキンが行なっているミスタードーナツの場合も、米国との契約上レシピ変更は不可であったが、確か1980年代契約を変更し、日本独自のメニューが可能となった。その本格的な独自メニューが1992年の新商品「飲茶」で、後に大ヒットとなるポン・デ・リングに繋がる。 つまり、ある意味今までの既成メニューとは全く異なる「商品」が生まれたという点にある。こうした例は米国生まれのコンビニ・セブンイレブンも同様で、米国のメニューや業態とは全く異なる日本独自の小売業を確立したのも1980年~1990年代であった。江戸時代から続いてきた異なる地域・文化の取り入れ方の工夫ではなく、全く発想の異なる今まで無かった「新」が生まれた点にある。
その理由は何であったか、それはあらゆる面で「自由」であったということである。過去にとらわれない「自由」、冒険ができる「自由」、とことん面白がれる「自由」、目標という前もった成果からの「自由」、サントリーの創業精神「やってみなはれ」もそうした自由な企業風土から生まれたものだ。そうした風土に触発されて「自由」を自覚することもあるが、その基本は多くの「しがらみ」を自ら解き放つことによって得られる実感である。勿論、そのことによって生まれる困難さや失敗を含めてであるが。 一方、受け手である生活者・消費者においては、壁を作らない「自由」、性別・年齢という壁を超えた「自由」、価格からの「自由」(安くても好きであればいいじゃないか)、こうした自由な選択肢があった時代である。今や当たり前となったセレクトショップも団塊ジュニアが作ったものだが、中国製でも気に入ればそれでいいじゃないかという「自由」が生まれていた。
「自由」を面白がる時代へ
こうした「自由さ」は戦前の価値観からの解放と共に、映画「Always三丁目の夕日」に描かれていたように「豊かではなかったが、そこには夢や希望があった」、そんな夢や希望を持ち得たのが昭和という時代であった。そこには夢や希望を追いかける「自由」が横溢していた時代のことでもあった。企業も個人も、何事かを生み出す「創業」時代であったということだ。平成の時代になり、特に2000年代になり盛んにベンチャーが叫ばれてきたが、ほとんど結果は得られてはいない。数年前から、ベンチャーキャピタルのいくつかのフアンドによる試みが始まっているが、社会を動かす潮流には程遠い。 ところで「自由」というと勝手気儘なことのように思いがちであるが、実は真逆の世界である。結果は誰でもない自分自身に返ってくるもので、だから面白いと思える人によってのみ「自由」はある。 江戸元禄の世を「浮世」と呼んでいるが、実は自己責任は明確にあった。平和な江戸時代には五街道が整備され、一定の制限はあるもののお伊勢参りのように旅行が盛んであった。その際必要となったのが通行手形で居住する大家(町役人・村役人)に申請し発行してもらう仕組みであった。今日のパスポートと同じようなものだが、手形に書いてあるのが「旅先で死んでもあり合わせのところに埋めてください」「亡骸は送り戻す必要はありません」といった主旨の一文が記載されていた。つまり、生きるも死ぬも自分の判断、他人のせいにしない」ということが理解されていた社会であった。
こうした自由を面白がれるには、周囲も、社会も、時代も「前」「未来」に向いていることが必要であった。しかし、バブル崩壊後の30数年、多くの神話崩壊と共に企業・個人にのしかかる「不安」、広く社会に広がる「不安」を前に「自由」になれる環境には程遠かった。一言で言えば、繰り返し言われていることだが「将来不安」ということになる。消費を含めた心が向かう先は「内側」ということになる。しかも、「過去」へと遡る傾向を強めていく心理市場については過去何度となく書いているのでここでは省略する。
また、このブログでも繰り返し書いてきている家計調査報告を踏まえると、勤労者世帯収入が増えないばかりか、リーマンショック以降社会保険料が増え、手取り給与(可処分所得)は減るだけでなく、企業側も半分負担していることからその負担も大きい。「自由」を面白がる環境条件が更に満たされなくなってきている。これが将来不安に直接繋がり、雇用形態も非正規雇用が4割を超えた。
ただ昨年夏以降、ユニクロ柳井社長の言葉ではないが、「デフレもまた良いものではないか」という発言に見られるように、企業も、生活者も自ら「デフレ的なるもの」の世界観からは既に脱却している。そうしたことを踏まえデフレは日常化し、死語になったとブログにも書いた。バブル崩壊によって生まれた個々の「不安」は勿論残ってはいるものの、昭和と平成の世代比較において考えるならば、バブル崩壊という「不安」視座から「消費」を見れば、昭和世代は崩壊経験もあり「リアルなものとしての不安」であり、平成世代のそれは「漠とした不安」である。昭和世代にとっての不安は具体的であり解決もまた可能である。しかし、平成世代の方が不確かであるが故に問題は深刻であるということだ。 ただ、「自由」という視座を持って考えるとすれば、国や社会といった大きな単位における制度や環境作りではなく、もっと小さな単位、家庭やコミュニティ、あるいは企業の部署単位や団体単位で「自由」に取り組むことは可能である。
既成から「自由」である企業がどんな成果を上げてきたか、例えば非常識経営と言われた岐阜にある電気設備資材メーカーである未来工業があり、最近ではブログにも取り上げた24時間営業の立ち食いそば「富士そば」もある。両社共に「人」を大切に考えた経営者による企業であり、従業員もそれに応えた企業である。未来工業においては社員から様々なアイディアを募集し商品開発や作業改善に役立てている。富士そばにおいても店独自のメニュー開発を促進し、一味違う店作りを行なっている。どちらも社員の自由な創意工夫が経営に大きく貢献し、勿論その成果配分は言うまでもない。そんな経営の仕組みを持った企業である。
今回はバブルのマイナス面ばかりが指摘されてきた20数年であったことに対し。敢えて「バブル期に生まれた<新しさ>」の背景に「自由」があったということに着眼した。「失われた30年」という言葉で、ビジネスもマーケティングにおいても全てを切り捨ててきたが、1980年という特異な時代を読み解いていくと、そこにこれから「先」の着眼も見えてきたように思える。発想を変えてコトに向かう、これもまた「自由」のなせる技である。
世代論は好きではないが、多くの専門家は指摘するようにその消費のユニークさからZ世代に注目が集まっている。それはバブル崩壊の「意味」から離れたところに生活しているからに他ならない。新しいデジタル機器を使いこなし、団塊世代が育った時代社会、つまり昭和レトロに興味を持ち、その新しさをいとも簡単位取り入れる軽やか消費など、その上の世代が「離れ世代」と呼ばれた現象とは正反対である。
本年度のアカデミー賞で、日本の作品として初めて視覚効果賞を受賞した「ゴジラ-1.0」。受賞した山崎貴監督(白組)はあの「Always三丁目の夕日」のCGを監督した人物で、今回の「ゴジラ-1.0」はZ世代が中心となって制作したように、この世代が消費のみならずビジネスにおいても表舞台へと出てきた。規制から「自由」な世代として期待される意味がよくわかる気がする。過剰な情報時代にも「倍速」という方法で乗り越える軽やか世代で有る。(続く)
タグ :マーケティング
2024年04月03日
マーケティングノート(2)
今日の停滞する経済のスタートがバブル崩壊であり、その精算、見直しが中途半端な形で今日に至っているというのが私のバブル認識である。私のマーケティング課題の認識も当然変わり、新たなテーマに取り組んだことは言うまでない。
ところで今回のブログのタイトルとして「マーケティングの旅」としたが、「過去」に遡っての体験だけでなく、その当時の認識と「今」という時代認識を重ね合わせたブログでもあり、そうした意味を含め旅ではなく、ノート「マーケティング・ノート」とした。その変化体験の前に「バブル経済」とは何か、「何」が崩壊したのかを確認しておくこととする。

ヒット商品応援団日記No820(毎週更新) 2024.4,1.
「激変の時代へ」
バブルとその崩壊
流通に現れた消費変化、
元禄と昭和その成熟消費文化
過剰からデフレへ、失われた30年へ
崩壊への歴史的経過
バブル崩壊は1991年の大蔵省による「土地関連融資の抑制について」(総量規制)に加えて、日本銀行による金融引き締めに端を発する信用崩壊であった。こうした政府・日銀のバブル潰し=加熱した投機マネーの変化は少し前からその兆候を見せていた。株式市場においては1989年の大納会(12月29日)に終値の最高値38,915円87銭を付けたのをピークに暴落に転じ、湾岸危機と原油高や公定歩合の急激な引き上げが起こった後の1990年10月1日には一時20,000円割れと、わずか9か月あまりの間に半値近い水準にまで暴落した。こうした状況に追い討ちをかけたのが総量規制であった。
1980年代後半「過剰さ」はオタクだけでなく、狭い国土の日本では土地価格は上がっても下がることはない、そんな不動産神話は企業ばかりか個人にまで広く行き渡り、銀行も個人融資を積極的に行った時代であった。そして、バブル経済が崩壊した結果、日本全体の土地資産額は、1990-2002年で1000兆円減少。バブル崩壊で日本の失われた資産は、土地・株だけで約1400兆円とされている。
実はバブル崩壊の影響が企業における経済活動だけであれば、その復活もまた可能かもしれない。しかし、当たり前のことであるが、生活者個々の生活に直接・間接にわたる影響は、極論ではあるが「今尚続いている」と考えている。住宅ローン破綻など数値に現れている影響についてはわかりやすいが、心理的なものについてはほとんで分析されたことがない。そこでバブル前後の社会現象を比較すると以下となる
<着目すべきバブル期の主な社会現象>
1981年 映画「機動戦士ガンダム」 田中康夫「なんとなく、クリスタル」 川久保玲、山本耀司パリコレ進出 1982年 西武百貨店「おいしい生活」キャンペーン 1983年 東京ディズニーランド開園 「無印良品」青山1号店オープン 1984年 「チケットぴあ」営業開始 マハラジャ 麻布十番」オープン 1985年 「ゆうやけニャンニャン」放送開始 「8時だよ! 全員集合」放送終了 「ビックリマンチョコ」販売開始 「男女雇用機会均等法」施行 1986年 「岡田有希子」自殺、後追い自殺多発 1987年 「ビックリマンチョコ」大ブーム 1988年 「Hanako」創刊、「平凡パンチ」休刊 1989年 「株価3万八千円超え」 *消費税3%導入 1991年 バブル崩壊
<着目すべきバブル崩壊後10年の主な社会現象>
1992年 残業がなくなり「父帰る」が話題
就職氷河期が始まる
1993年以降 流通の売り上げに影響が出てくる
1994年には一世を風靡したジュリアナ東京も閉店
1995年以降 「デフレ」というキーワードと共に
吉野家、マクドナルド、ユニクロ(御三家)が注目
1997年拓銀が経営破綻
山一証券破綻
*消費税5%導入 以降デフレが加速する
なおバブル崩壊が庶民に与えた影響を描いた著書である 「ホームレス中学生」が225万部を売り上げる。
デフレにはバブル崩壊が今なお底流している
一言で言うならばそれまでの「豊かさ」の意味合いを再度考える時間が続いている。それは「投機」に対する考え方に現れており、極論ではあるがバブル期お金がお金を過剰に産む投機経験をしてきたことによる。一定の投資に対するリターンではなく、何倍何十倍にも変換できる「投機」は是としないということである。これは欧米のような保有資産を株式で持つのではなく、いわゆるリターンの少ない貯金のままであるのはこうした理由からである。0金利時代にあっても預貯金比率が高いのはこうした理由からである。いくら政府日銀が株価を高くし個人投資家の投資を期待しても活況を見せないのもこうした背景からである。バブル崩壊という経験は単なる世界経済の変動、例えば2008年のリーマンショックが与えた影響どころではない。「単なる」という形容詞をつけたのも、バブル崩壊は多くの生活者の「生活・経済」を変えただけでなく、ある意味「人生」を変えた転換であったということだ。つまり、人生観をも変えたということである。
神話とは「こころ」のなせるものである。情緒的な表現になるが、神話崩壊とは「こころ」が壊れてしまったということだ。この崩壊を直接経験したのがバブル世代・新人類を中心に団塊世代という消費の中心世代であった。更にいうならば、団塊ジュニアは1990年代初頭の第一次就職氷河期を経験し、新人類の子供達の一部は家庭崩壊に陥り、更に子供の一部は都市漂流民となった。1980年代新人類の結婚観を「成田離婚」とネーミングされ話題となったが、実はこの世代以降離婚率が増加する。つまり、シングルマザーが増加するということである。こうした社会現象が生まれた背景の一つ、いや中心にバブル崩壊があり、それは消費においても「デフレマインド形成」へとつながっている。 団塊世代が多くの金融資産を持ちながら、子供や孫にはお金を使ってもそれ以上は使わない。新人類世代も高齢社会の只中にいて、両親の介護に没頭し、1980年代の頃のような「自由な行動」「自由な消費」に向かうことができない状況だ。 彼ら世代の子供達もまた、間接的にバブル崩壊を経験しており、その価値観の根底には「冒険」より「安定」、「消費」より「貯蓄」、といった内向き傾向となり、デフレマインドに繋がっていく。
1993年消費に大きな変化が出始める
1990年代に入り主な仕事の一つが「流通」に関するものであった。担当していたクライアントであるSC(ショッピングセンター)の売り上げが激減する。その現象は数%ではなく、その多くは二桁、20数%のSCも出てきた。出店するテナント・専門店の経営もさることながらデベロッパーの賃料経営も厳しくなる。そのデベロッパーの依頼からであるが、その売り上げを分析してわかったことは消費価値観が変わったということであった。単なる景気の良し悪しといったことではなく、何が売れ、何が売れないか、その業種や価格帯に共通した「変化」が現れていた。そうした分析結果をまとめたのがt次の図である。

生活は継続が基本であり、しかし取り入れやすい方向、より小さく、より日常消費へと向っていく。小さなことの第一は小さな価格であり、デフレへとストレートにつながる。また、日常に向かうとはカジュアルで構えない消費、となる。こうしたデフレ消費の代表として吉野家、マクドナルド、ユニクロが挙げられた。
それまでの興味あを入り口とした断絶する昭和マーケットと平成マーケット
バブル崩壊とは直接影響を受けない平成世代による消費市場はどうかと言えば、数年前のキーワード「草食男子・肉食女子」という構図が如実に表している。かなり前のブログになるが、この世代について次のようにブログに書いたことがあった。 『本来であれば欲望むき出しのアニマル世代(under30)は草食世代と呼ばれ、肉食女子、女子会という消費牽引役の女性達も、境目を軽々と超えてしまう「オヤジギャル」の迫力には遠く及ばない。私が以前ネーミングしたのが「20歳の老人」であったが、達観、諦観、という言葉が似合う世代である。消費の現象面では「離れ世代」と呼べるであろう。TV離れ、車離れ、オシャレ離れ、海外旅行離れ、恋愛離れ、結婚離れ、・・・・・・執着する「何か」を持たない、欲望を喪失しているかのように見える世代である。唯一離さないのが携帯をはじめとした「コミュニケーションツールや場」である。「新語・流行語大賞」のTOP10に入った「~なう」というツイッター用語に見られる常時接続世界もこの世代の特徴であるが、これも深い関係を結ぶための接続ではなく、私が「だよね世代」と名付けたように軽い相づちを打つようなそんな関係である。例えば、居酒屋にも行くが、酔うためではなく、人との関係を結ぶ軽いつきあいとしてである。だから、今や居酒屋のドリンクメニューの中心はノンアルコールドリンクになろうとしている。』
あまり世代論に偏ってはいけないが、バブル期、バブル崩壊に直接間接関わった世代における価値観とは根底から異なることが分かるであろう。「デフレ」という言葉はデフレ経済のそれであって、今や多様な使われ方をしているが、新人類を始めバブル(崩壊)経験世代にとってはデフレマインドは消費心理の底流としてあるが、このunder30(確か10年ほど前に日経新聞が特集を組みネーミングした)はデフレとは無縁なマーケットとしてある。私は「欲望喪失世代」との表現をしたが、それは団塊世代や新人類との比較においてであって、under30にとってはこれが普通の消費感覚となっている。つまり、全く異なる価値観のマーケットが存在しているということである。こうした一般論としてバブルを語ることができないZ世代と同じである。
1997年11月
バブル崩壊後その崩壊の象徴とも呼べる企業破綻が11月に起きた。周知の山一証券の破綻・廃業である。不動産神話の崩壊に続く破綻することはないとした金融神話の崩壊である。実はちょうど同じ時期に北海道拓殖銀行も破綻する。バブル崩壊への対策として「顧客満足」というキーワードに沿って札幌の専門店さん(札専塾)と勉強会を行っていた。勤務先ジャパンライフデザインシシテムズの代表であった谷口氏と共に11月17日午後札幌市内の会議室で勉強会を行い、その後破綻発表のあった拓銀の定山渓にあった保養所で食事をした。参加された専門店の多くはメインバンクが拓銀で今後どんな取引となるか話題は破綻の話ばかりであった。いつもならば満室となある保養所は私たち札専塾のメンバーだけで広い館内は閑散としていたことを鮮明に覚えている。
リニューアルの時代を迎える
バブル崩壊は個人の消費変化に応えるように企業もまた変わっていくことが急務となった。1900年代半ば以降バブル崩壊による急激な売り上げ減少への対応、いわゆる「りニューアル」である。まずは私自信の実体験からのリニューアルを取り上げてみたいが、その最初に取り組んだのが大船ルミネウイングであった。ウイングという名前がついているのは大船駅東口の再開発に京浜急行も参加していることによる。
東京郊外の神奈川の駅ビルであるがJR東海道本線、JR湘南新宿ライン、JR横須賀線、JR根岸線、湘南モノレールが直結する商業施設である。シニア世代にとっては松竹大船撮影所のある駅である。『男はつらいよ』シリーズなど多くの作品が制作されたが、現在は閉館されており、公園となっている。
過不足調査から始める
その調査は大きくは「売り上げ分析」と駅東側にある商業施設の分析によってリニューアルのコンセプトを探った。バブル崩壊が消費を大きく落としたのは全体としては客数減少に現れていた。
そうした減少を踏まえ、個々の専門店の売り上げ分析として次のとうな特徴が、見られた

・例えばユニクロの落ち込みは小さかったが、若い世代のファッションブランドであるセシルマクビーは大きく売り上げを落としていた。周知のように渋谷109を代表する人気ブランドであったが、後に退店することとなる。宝飾品など高価格帯の専門店は売り上げを落としていたが、ユニクロなどを除き落ち込みは客数減少によるものであった。また、大船駅利用者には周知のことであるが、湘南モノレール到着ホームからJR線のホームへは館内を通っていくのだが、その導線上の通路には小さな食品専門店があり、客数減による大きな落ち込むはなかった。
・もう一つの過不足調査は大船ルミネウイングを中心とした市場調査である。大きくは西口のバスターミナルにはほとんど松魚施設はなく東口にイトーヨーカドーを中心に昔ながらのいわゆる商店が密集し近隣の生活者はこの東口にある商品で買い物がなされていた。湘南モノレールや西口バスターミナル利用者はこの東口商店街を利用することは極めて少なかった。生鮮三品を始め日常使用の商品については業種としては充足してはいたが、生活を彩る新しさ、珍しさ、楽しさはほとんどなく、横浜や都心の商業施設で買い求めるといった消費行動が多く見られた。つまり、デフレの騎手と呼ばれるユニクロですら売り上げを落とし、東口にある青果を扱う市場の賑わいもバブル前と比較して少ないいということは単なる景気悪化対応では無いということだ。勿論、東口の商店街歩きをする中で、地元顧客に愛されている商店もある。その代表であるとおもうが、駅から数分のところにある鎌倉食堂なんかはその代表であろう、食堂の定番であるアジフライ定食を思い出す。こうした事例もあrったが、新しいコンセプトによるリニューアルが必要であるというのが過不足調査の結論であった。
新たな取り組み
こうした売り上げや市場から見ることができる消費の「過不足」と共に大船ルミネウイングの長年の課題の一つに東側地下350坪の活用があった。当時はデッドスペースとしてゲームセンターにしており、ゲーム好きの中高生の利用でしかなかった。駅東口の階段下の横からしか入れない構造となっており、その活用が待たれていた。
そこで上記過不足調査の結果を踏まえたリニューアルプランを立てることとなった。350坪という面積は一つの「ライフスタイル」を提供できるものであり、横浜や都心の商業施設を利用しなくても地元、大船でも利用できるプランとして。勿論、ライフスタイルを実感できるものの第一は「食」であり、都市がもつ新しさ、珍しさ、面白さのある賑わいである。そのためには湘南モノレールの2FホームからB1Fの350坪までの新たな銅線をエスカレーターによって作る、そんな着眼であった。そのためにはどれだけ魅力あるライフスタイルをMDとして編集できるかであった。当時所属していた会社にはテナントリーシングの機能を持たなかったので、コンセプトプランとして提案した。その概要として以下のとおりであった。
■ 「食」の中心として例えば「ザ・ガーデン」や「クイーンズ伊勢丹」を置き、生鮮3品については例えば鮮魚であれば「魚力」 さらには惣菜を充実させるためにRF1や柿安ダイニングなどを組み合わせる。勿論、デベロッパーの方針からあテナント誘致が行われrのだが、この「食」の充実戦略は変わってはいない。
■既に書いたようにいわゆるブランド専門店ではなく、日常利用ではあるが小洒落たリーズナブルはあ専門店を誘致し、傾向として生活雑貨的なMD専門店が多く編集された。
結果、リニューアル前と比較しどんな変化を創出できたかと言えば、
<それまでのブランド専門店を集めたファッションビルから、日常生活の中心となる食品や生活雑貨を中心とした新しいライフスタイルを集積したSCへの転換であり、業種別の売り上げ構成を大きく変えたリニューアル。と言えよう。勿論、日常利用、来館頻度が増え消費額が増えたことは言うまでもない。>
こうしたリニューアル計画は近隣のJRによSCへとつながっており、茅ヶ崎ルミネや浜松メイワン、京急上大岡ウイングへとリニューアルは広がった。更にはヒルトップガーデン(現目黒アトレ)も駅に隣接した隣のビルを借り受けることが可能となったことからリニューアルの原型の一つが出来上がったと言えよう。その目黒のリニューアル担当者は「今までのリニューアルにおけるMDは全てファッション専門店の組み合わせ編集であったが、食品を中心としたライフスタイルMDによる提案はほとんどなかった」と話していたことを思い出す。勿論リニューアっる前の売り上げに対し30%のアップであった。
こうした転換の背景には「ルミネ」は「パルコ」という先進的な商業施設を一つのモデルとしていたこともあり、新しさや珍しさ、面白さがファッションという文化価値に偏りすぎていたことからの脱却であったと言えよう。
ところで今回のブログのタイトルとして「マーケティングの旅」としたが、「過去」に遡っての体験だけでなく、その当時の認識と「今」という時代認識を重ね合わせたブログでもあり、そうした意味を含め旅ではなく、ノート「マーケティング・ノート」とした。その変化体験の前に「バブル経済」とは何か、「何」が崩壊したのかを確認しておくこととする。

ヒット商品応援団日記No820(毎週更新) 2024.4,1.
「激変の時代へ」
バブルとその崩壊
流通に現れた消費変化、
元禄と昭和その成熟消費文化
過剰からデフレへ、失われた30年へ
崩壊への歴史的経過
バブル崩壊は1991年の大蔵省による「土地関連融資の抑制について」(総量規制)に加えて、日本銀行による金融引き締めに端を発する信用崩壊であった。こうした政府・日銀のバブル潰し=加熱した投機マネーの変化は少し前からその兆候を見せていた。株式市場においては1989年の大納会(12月29日)に終値の最高値38,915円87銭を付けたのをピークに暴落に転じ、湾岸危機と原油高や公定歩合の急激な引き上げが起こった後の1990年10月1日には一時20,000円割れと、わずか9か月あまりの間に半値近い水準にまで暴落した。こうした状況に追い討ちをかけたのが総量規制であった。
1980年代後半「過剰さ」はオタクだけでなく、狭い国土の日本では土地価格は上がっても下がることはない、そんな不動産神話は企業ばかりか個人にまで広く行き渡り、銀行も個人融資を積極的に行った時代であった。そして、バブル経済が崩壊した結果、日本全体の土地資産額は、1990-2002年で1000兆円減少。バブル崩壊で日本の失われた資産は、土地・株だけで約1400兆円とされている。
実はバブル崩壊の影響が企業における経済活動だけであれば、その復活もまた可能かもしれない。しかし、当たり前のことであるが、生活者個々の生活に直接・間接にわたる影響は、極論ではあるが「今尚続いている」と考えている。住宅ローン破綻など数値に現れている影響についてはわかりやすいが、心理的なものについてはほとんで分析されたことがない。そこでバブル前後の社会現象を比較すると以下となる
<着目すべきバブル期の主な社会現象>
1981年 映画「機動戦士ガンダム」 田中康夫「なんとなく、クリスタル」 川久保玲、山本耀司パリコレ進出 1982年 西武百貨店「おいしい生活」キャンペーン 1983年 東京ディズニーランド開園 「無印良品」青山1号店オープン 1984年 「チケットぴあ」営業開始 マハラジャ 麻布十番」オープン 1985年 「ゆうやけニャンニャン」放送開始 「8時だよ! 全員集合」放送終了 「ビックリマンチョコ」販売開始 「男女雇用機会均等法」施行 1986年 「岡田有希子」自殺、後追い自殺多発 1987年 「ビックリマンチョコ」大ブーム 1988年 「Hanako」創刊、「平凡パンチ」休刊 1989年 「株価3万八千円超え」 *消費税3%導入 1991年 バブル崩壊
<着目すべきバブル崩壊後10年の主な社会現象>
1992年 残業がなくなり「父帰る」が話題
就職氷河期が始まる
1993年以降 流通の売り上げに影響が出てくる
1994年には一世を風靡したジュリアナ東京も閉店
1995年以降 「デフレ」というキーワードと共に
吉野家、マクドナルド、ユニクロ(御三家)が注目
1997年拓銀が経営破綻
山一証券破綻
*消費税5%導入 以降デフレが加速する
なおバブル崩壊が庶民に与えた影響を描いた著書である 「ホームレス中学生」が225万部を売り上げる。
デフレにはバブル崩壊が今なお底流している
一言で言うならばそれまでの「豊かさ」の意味合いを再度考える時間が続いている。それは「投機」に対する考え方に現れており、極論ではあるがバブル期お金がお金を過剰に産む投機経験をしてきたことによる。一定の投資に対するリターンではなく、何倍何十倍にも変換できる「投機」は是としないということである。これは欧米のような保有資産を株式で持つのではなく、いわゆるリターンの少ない貯金のままであるのはこうした理由からである。0金利時代にあっても預貯金比率が高いのはこうした理由からである。いくら政府日銀が株価を高くし個人投資家の投資を期待しても活況を見せないのもこうした背景からである。バブル崩壊という経験は単なる世界経済の変動、例えば2008年のリーマンショックが与えた影響どころではない。「単なる」という形容詞をつけたのも、バブル崩壊は多くの生活者の「生活・経済」を変えただけでなく、ある意味「人生」を変えた転換であったということだ。つまり、人生観をも変えたということである。
神話とは「こころ」のなせるものである。情緒的な表現になるが、神話崩壊とは「こころ」が壊れてしまったということだ。この崩壊を直接経験したのがバブル世代・新人類を中心に団塊世代という消費の中心世代であった。更にいうならば、団塊ジュニアは1990年代初頭の第一次就職氷河期を経験し、新人類の子供達の一部は家庭崩壊に陥り、更に子供の一部は都市漂流民となった。1980年代新人類の結婚観を「成田離婚」とネーミングされ話題となったが、実はこの世代以降離婚率が増加する。つまり、シングルマザーが増加するということである。こうした社会現象が生まれた背景の一つ、いや中心にバブル崩壊があり、それは消費においても「デフレマインド形成」へとつながっている。 団塊世代が多くの金融資産を持ちながら、子供や孫にはお金を使ってもそれ以上は使わない。新人類世代も高齢社会の只中にいて、両親の介護に没頭し、1980年代の頃のような「自由な行動」「自由な消費」に向かうことができない状況だ。 彼ら世代の子供達もまた、間接的にバブル崩壊を経験しており、その価値観の根底には「冒険」より「安定」、「消費」より「貯蓄」、といった内向き傾向となり、デフレマインドに繋がっていく。
1993年消費に大きな変化が出始める
1990年代に入り主な仕事の一つが「流通」に関するものであった。担当していたクライアントであるSC(ショッピングセンター)の売り上げが激減する。その現象は数%ではなく、その多くは二桁、20数%のSCも出てきた。出店するテナント・専門店の経営もさることながらデベロッパーの賃料経営も厳しくなる。そのデベロッパーの依頼からであるが、その売り上げを分析してわかったことは消費価値観が変わったということであった。単なる景気の良し悪しといったことではなく、何が売れ、何が売れないか、その業種や価格帯に共通した「変化」が現れていた。そうした分析結果をまとめたのがt次の図である。

生活は継続が基本であり、しかし取り入れやすい方向、より小さく、より日常消費へと向っていく。小さなことの第一は小さな価格であり、デフレへとストレートにつながる。また、日常に向かうとはカジュアルで構えない消費、となる。こうしたデフレ消費の代表として吉野家、マクドナルド、ユニクロが挙げられた。
それまでの興味あを入り口とした断絶する昭和マーケットと平成マーケット
バブル崩壊とは直接影響を受けない平成世代による消費市場はどうかと言えば、数年前のキーワード「草食男子・肉食女子」という構図が如実に表している。かなり前のブログになるが、この世代について次のようにブログに書いたことがあった。 『本来であれば欲望むき出しのアニマル世代(under30)は草食世代と呼ばれ、肉食女子、女子会という消費牽引役の女性達も、境目を軽々と超えてしまう「オヤジギャル」の迫力には遠く及ばない。私が以前ネーミングしたのが「20歳の老人」であったが、達観、諦観、という言葉が似合う世代である。消費の現象面では「離れ世代」と呼べるであろう。TV離れ、車離れ、オシャレ離れ、海外旅行離れ、恋愛離れ、結婚離れ、・・・・・・執着する「何か」を持たない、欲望を喪失しているかのように見える世代である。唯一離さないのが携帯をはじめとした「コミュニケーションツールや場」である。「新語・流行語大賞」のTOP10に入った「~なう」というツイッター用語に見られる常時接続世界もこの世代の特徴であるが、これも深い関係を結ぶための接続ではなく、私が「だよね世代」と名付けたように軽い相づちを打つようなそんな関係である。例えば、居酒屋にも行くが、酔うためではなく、人との関係を結ぶ軽いつきあいとしてである。だから、今や居酒屋のドリンクメニューの中心はノンアルコールドリンクになろうとしている。』
あまり世代論に偏ってはいけないが、バブル期、バブル崩壊に直接間接関わった世代における価値観とは根底から異なることが分かるであろう。「デフレ」という言葉はデフレ経済のそれであって、今や多様な使われ方をしているが、新人類を始めバブル(崩壊)経験世代にとってはデフレマインドは消費心理の底流としてあるが、このunder30(確か10年ほど前に日経新聞が特集を組みネーミングした)はデフレとは無縁なマーケットとしてある。私は「欲望喪失世代」との表現をしたが、それは団塊世代や新人類との比較においてであって、under30にとってはこれが普通の消費感覚となっている。つまり、全く異なる価値観のマーケットが存在しているということである。こうした一般論としてバブルを語ることができないZ世代と同じである。
1997年11月
バブル崩壊後その崩壊の象徴とも呼べる企業破綻が11月に起きた。周知の山一証券の破綻・廃業である。不動産神話の崩壊に続く破綻することはないとした金融神話の崩壊である。実はちょうど同じ時期に北海道拓殖銀行も破綻する。バブル崩壊への対策として「顧客満足」というキーワードに沿って札幌の専門店さん(札専塾)と勉強会を行っていた。勤務先ジャパンライフデザインシシテムズの代表であった谷口氏と共に11月17日午後札幌市内の会議室で勉強会を行い、その後破綻発表のあった拓銀の定山渓にあった保養所で食事をした。参加された専門店の多くはメインバンクが拓銀で今後どんな取引となるか話題は破綻の話ばかりであった。いつもならば満室となある保養所は私たち札専塾のメンバーだけで広い館内は閑散としていたことを鮮明に覚えている。
リニューアルの時代を迎える
バブル崩壊は個人の消費変化に応えるように企業もまた変わっていくことが急務となった。1900年代半ば以降バブル崩壊による急激な売り上げ減少への対応、いわゆる「りニューアル」である。まずは私自信の実体験からのリニューアルを取り上げてみたいが、その最初に取り組んだのが大船ルミネウイングであった。ウイングという名前がついているのは大船駅東口の再開発に京浜急行も参加していることによる。
東京郊外の神奈川の駅ビルであるがJR東海道本線、JR湘南新宿ライン、JR横須賀線、JR根岸線、湘南モノレールが直結する商業施設である。シニア世代にとっては松竹大船撮影所のある駅である。『男はつらいよ』シリーズなど多くの作品が制作されたが、現在は閉館されており、公園となっている。
過不足調査から始める
その調査は大きくは「売り上げ分析」と駅東側にある商業施設の分析によってリニューアルのコンセプトを探った。バブル崩壊が消費を大きく落としたのは全体としては客数減少に現れていた。
そうした減少を踏まえ、個々の専門店の売り上げ分析として次のとうな特徴が、見られた

・例えばユニクロの落ち込みは小さかったが、若い世代のファッションブランドであるセシルマクビーは大きく売り上げを落としていた。周知のように渋谷109を代表する人気ブランドであったが、後に退店することとなる。宝飾品など高価格帯の専門店は売り上げを落としていたが、ユニクロなどを除き落ち込みは客数減少によるものであった。また、大船駅利用者には周知のことであるが、湘南モノレール到着ホームからJR線のホームへは館内を通っていくのだが、その導線上の通路には小さな食品専門店があり、客数減による大きな落ち込むはなかった。
・もう一つの過不足調査は大船ルミネウイングを中心とした市場調査である。大きくは西口のバスターミナルにはほとんど松魚施設はなく東口にイトーヨーカドーを中心に昔ながらのいわゆる商店が密集し近隣の生活者はこの東口にある商品で買い物がなされていた。湘南モノレールや西口バスターミナル利用者はこの東口商店街を利用することは極めて少なかった。生鮮三品を始め日常使用の商品については業種としては充足してはいたが、生活を彩る新しさ、珍しさ、楽しさはほとんどなく、横浜や都心の商業施設で買い求めるといった消費行動が多く見られた。つまり、デフレの騎手と呼ばれるユニクロですら売り上げを落とし、東口にある青果を扱う市場の賑わいもバブル前と比較して少ないいということは単なる景気悪化対応では無いということだ。勿論、東口の商店街歩きをする中で、地元顧客に愛されている商店もある。その代表であるとおもうが、駅から数分のところにある鎌倉食堂なんかはその代表であろう、食堂の定番であるアジフライ定食を思い出す。こうした事例もあrったが、新しいコンセプトによるリニューアルが必要であるというのが過不足調査の結論であった。
新たな取り組み
こうした売り上げや市場から見ることができる消費の「過不足」と共に大船ルミネウイングの長年の課題の一つに東側地下350坪の活用があった。当時はデッドスペースとしてゲームセンターにしており、ゲーム好きの中高生の利用でしかなかった。駅東口の階段下の横からしか入れない構造となっており、その活用が待たれていた。
そこで上記過不足調査の結果を踏まえたリニューアルプランを立てることとなった。350坪という面積は一つの「ライフスタイル」を提供できるものであり、横浜や都心の商業施設を利用しなくても地元、大船でも利用できるプランとして。勿論、ライフスタイルを実感できるものの第一は「食」であり、都市がもつ新しさ、珍しさ、面白さのある賑わいである。そのためには湘南モノレールの2FホームからB1Fの350坪までの新たな銅線をエスカレーターによって作る、そんな着眼であった。そのためにはどれだけ魅力あるライフスタイルをMDとして編集できるかであった。当時所属していた会社にはテナントリーシングの機能を持たなかったので、コンセプトプランとして提案した。その概要として以下のとおりであった。
■ 「食」の中心として例えば「ザ・ガーデン」や「クイーンズ伊勢丹」を置き、生鮮3品については例えば鮮魚であれば「魚力」 さらには惣菜を充実させるためにRF1や柿安ダイニングなどを組み合わせる。勿論、デベロッパーの方針からあテナント誘致が行われrのだが、この「食」の充実戦略は変わってはいない。
■既に書いたようにいわゆるブランド専門店ではなく、日常利用ではあるが小洒落たリーズナブルはあ専門店を誘致し、傾向として生活雑貨的なMD専門店が多く編集された。
結果、リニューアル前と比較しどんな変化を創出できたかと言えば、
<それまでのブランド専門店を集めたファッションビルから、日常生活の中心となる食品や生活雑貨を中心とした新しいライフスタイルを集積したSCへの転換であり、業種別の売り上げ構成を大きく変えたリニューアル。と言えよう。勿論、日常利用、来館頻度が増え消費額が増えたことは言うまでもない。>
こうしたリニューアル計画は近隣のJRによSCへとつながっており、茅ヶ崎ルミネや浜松メイワン、京急上大岡ウイングへとリニューアルは広がった。更にはヒルトップガーデン(現目黒アトレ)も駅に隣接した隣のビルを借り受けることが可能となったことからリニューアルの原型の一つが出来上がったと言えよう。その目黒のリニューアル担当者は「今までのリニューアルにおけるMDは全てファッション専門店の組み合わせ編集であったが、食品を中心としたライフスタイルMDによる提案はほとんどなかった」と話していたことを思い出す。勿論リニューアっる前の売り上げに対し30%のアップであった。
こうした転換の背景には「ルミネ」は「パルコ」という先進的な商業施設を一つのモデルとしていたこともあり、新しさや珍しさ、面白さがファッションという文化価値に偏りすぎていたことからの脱却であったと言えよう。