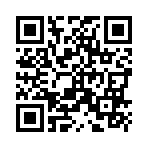2016年10月18日
創業者から見えてくること
ヒット商品応援団日記No662(毎週更新) 2016.10.18.
ユニクロの決算会見のニュース及びその内容を新聞などで読みながら、ああ柳井会長も根っからの創業者なんだなと強く思った。「根っからの」とは超ワンマン経営であり、超現場経営であることをまざまざと感じ入ったからである。実は私はダスキンの創業者である鈴木清一社長と亡くなるまで直接マーケティングの仕事をさせていただいたことと、同じ会社の隣のチームは日本マクドナルドを担当し、これも創業者である藤田田社長の経営や人となりについて多くのことを見聞きしていたからである。
何故今創業者が注目されるのか、創業から何を学べば良いのか、多くの企業がその原点に戻りつつあるからである。1999年にAIBOを世に出し、2006年にロボット事業から撤退したソニーが、同分野に再参入する。撤退から10年周回遅れのソニーは大丈夫なのかと危惧される声もあるが、そのことよりAIBOの先にあるAI(人工知能)の無限の可能性を睨んでいた創業者の理念に戻ろうということの方が大きい。その創業精神とは「他人がやらないことをやれ」という不可能への挑戦で、「他社に真似されるものを作りなさい」という未来を期待させるものであった。しかし、ことごとくアップル社に先を越されてしまった先端技術のソニーを取り戻すことである。勿論、そのまま10年前の過去に戻ることではない。むしろ、過去の創業者から学び、ある意味で創業がそうであったように再び「一つの革新」を起こすためであると理解すべきである。
実は創業期には理想とするビジネスの原型、ある意味完成形に近いものがある。ビジネスは成長と共に次第に多数の事業がからみあい複雑になり、グローバル化し、視座も視野も視点もごちゃ混ぜになり、大切なことを見失ってしまう時代にいる。創業回帰とは、今一度「大切なこと」を明確にして、未来を目指すということである。
そのユニクロの記者発表であるが、上半期の決算でも業績の下方修正に触れて「値上げに失敗した点」にあると、更には大企業病にもかかっていると、その原因を認めていた。今回の年度決算に於いても同じことを発表していたが、今回は更に加えて「賃金が上がらない以上、デフレは消費者にとってそれほど悪いことだとは思わない。」と、デフレを認め、その上での価格戦略、値上げの間違いを認めていた点にある。
その見直しを踏まえた転換へのスタートが「Life Wear」というコンセプトである。「人はなぜ服を着るのだろうか」というCMを見る限り、表現としてこなしきれていないためおそらく視聴者の評価は低いものと思う。私の受け止め方は、ある意味原点に戻って今一度「服」について考え直しますという意味の宣言だと思っている。ユニクロという社名にあるように「ユニーククロージング」を次々と発売してきた。最初があの「フリース」である。GAPの物真似であると揶揄されながらも、GAPのコンセプトのように、男女の差も年齢の差も超えた服として利用され大きな顧客支持を得た。以降、英国進出の失敗などあったが、新素材開発に力を入れた「ヒートテック」、ソフトな履き心地の「UNIQLO JEANS」、「ブラトップ」・・・・・・・・ある意味社名にある「ユニーク」な商品をどこよりも早く開発し発売してきた。こうした「ユニーク」商品の「軸」となるのが今回の「Life Wear」というコンセプトである。
そのユニクロの柳井会長の超ワンマンぶりは「折り込みチラシの微妙な表現にまで介入する」と言われている。そんなことは現場経営では至極当たり前のことで、ほとんどの創業経営者はそうであった。ダスキンの創業者鈴木清一社長も私たちが作った制作物をとことん睨め付けるように見ていた。そして、FCビジネスであることから、現場の加盟店の動向については地域の担当者以上に熟知していた。
また、日本マクドナルドの藤田社長もファストフーズの命とも言える店内厨房のレイアウトなど幹部社員より熟知しており、誰よりも多く各店舗を回っていた。
周知の日本マクドナルドの1号店は銀座三越の1階であった。銀座というメディア性の高い立地もあって順調に出店も加速し、銀座店はいわばフラッグショップとしての役割を果たしていた。米国マクドナルドからはその成功ノウハウとしてシステマティックな各種マニュアル類がもたらされていた。時期は忘れてしまったが、藤田社長から「覆面顧客による調査」の依頼を受けたのを覚えている。マニュアルだけでは解決できないことが現場にはあるというのがその理由であった。そこでマニュアルに書かれていない顧客要望を「覆面顧客」として店舗で行い、その時の現場対応をレポートしてほしいというものであった。私の同僚の担当者は店舗スタッフから顔を覚えられているので私にその役割が回ってきたという次第であった。ところでその要望であるが、「ビッグマック」にマスタードを塗ってほしいというものであった。結果どうであったか、カウンターの若いスタッフは少々混乱気味に「店長~」と呼びに行ったことを覚えている。こうした顧客要望は新たなマニュアルへと追加していったことは言うまでもない。
どんな企業でも曲がり角はある。消費の変化はもとより業界のみならず大きくは時代そのものの変化要請である。そうした「変化」を誰よりも早く知覚し手を打つことが特に創業者には求められている。ダスキンで言うならば、売り上げが毎年30~50%という高い成長を見せていた時、敢えて新しいチャレンジのためのリニューアル計画を立てた時があった。右肩上がりのこの時に何故という声が上がったが、この時しかできないと決断した。それは屋台骨となる既存事業の再生であったが、役員を始め幹部社員を全て外し、地方の部長クラスを責任者に置き、中心メンバーも地方の現場担当者クラスを本社に呼び寄せたことがあった。そして、創業者自らが本部長になり、新しい改革を行った。ユニクロの柳井社長が一時期経営陣から離れたことがあったが、社長を解任し再度社長兼会長職に戻ったことがあった。これもダスキンの場合と同じである。そして、こうした行動が取れるのも創業者オーナーであればこそである。
ところで日本マクドナルドの最初の危機は1980年代半ばにあった。「あのマクドナルドのハンバーガーの肉はミミズである」という根拠のない風説による都市伝説が流行ったことがあった。勿論、根拠のないマクドナルドにとって迷惑な風評であるが、マクドナルドは実はビーフ(牛肉)以外にも他の肉を使い、消費者に知らせていなかった事実があった。確かNHKが調査を行い指摘したと記憶しているが、その指摘を受けて1985年にマクドナルドは「100%ビーフ」として再スタートしV字回復した経緯がある。これを指揮したのが、藤田田社長であった。よく「ピンチをチャンスに変える」と言われるが、仕入れや製造工程、現場のオペレーションを変えていく決断と実行は、これも創業者オーナーであればこそ可能となる。2004年7月に発覚した消費期限切れの鶏肉使用問題以降の対応策とを比較すると、その覚悟の違いと結果は歴然としている。
創業期の精神を忘れないために多くの企業は創業記念日を設定している。ユニクロも11月20日の創業記念日には感謝祭として「牛乳とあんぱん」を来店顧客に無料で配布している。これはユニクロが1号店をオープンさせた時に、朝早くから並んでくださったお客様に、朝食代わりとしてあんぱんと牛乳を配布したことに由来したものである。これも「初心」に立ち返る意味があり、周年記念や新規店オープンにも必ず「牛乳とあんぱん」が用意されていると聞いている。ダスキンの場合も11月16日が創業記念日となっており、お掃除会社らしく全国各地でご近所のお掃除をする托鉢が組まれている。
何故、初心に帰る、創業の理念や志を再度学び直す、こうしたことが必要となっているのかについては拙著「人力経営」を一読いただきたいが、創業時には「理想とするビジネスの完成形」があるということに尽きる。これは大企業であれ、町のラーメン店であれ、事業者にとって創業は必ずある。後継者がいないまま店を閉めるラーメン屋さんも多いが、それでもフアンの中から手を上げて再開する店もある。思い起こさなければならないのはその「思い」と共に、「ビジネスの完成形」はなんであったかを思い起こすことにある。ラーメン屋さんの理想形とは、他には無い「独自な味」ということになるかと思う。
今回は一定の情報と経験のある2社、ダスキンと日本マクドナルドを選んだが、創業者亡き後はいわゆるサラリーマン経営者となり、悪く言えば「普通の会社」になってしまったということである。普通であれば、至極簡単に言えば自然に業績を下げることへと向かっていくものである。多くの専門家はリーダーシップの欠如を指摘するが、オーナー創業者であればこそ、決断ができることがある。独断的・専制的に外目には見えるが、「普通」であったら成長などできないことを一番よく知っているのが創業者である。普通ではなかったからこそ「今日」があることを嫌という程骨身にしみているのが創業者ということだ。これは勝手な推測ではあるが、ユニクロに求められているのは第二の創業、もっと明確に言えば第二の「柳井正」が次から次へと登場することが待たれているということだ。勿論、次なる「ビジネスの理想形」を構想でき、しかも胆力のある人物ということになる。(続く)
<お知らせ>
「人力経営」 ヒットの裏側、人づくり経営を聞く 756円
ユニクロの決算会見のニュース及びその内容を新聞などで読みながら、ああ柳井会長も根っからの創業者なんだなと強く思った。「根っからの」とは超ワンマン経営であり、超現場経営であることをまざまざと感じ入ったからである。実は私はダスキンの創業者である鈴木清一社長と亡くなるまで直接マーケティングの仕事をさせていただいたことと、同じ会社の隣のチームは日本マクドナルドを担当し、これも創業者である藤田田社長の経営や人となりについて多くのことを見聞きしていたからである。
何故今創業者が注目されるのか、創業から何を学べば良いのか、多くの企業がその原点に戻りつつあるからである。1999年にAIBOを世に出し、2006年にロボット事業から撤退したソニーが、同分野に再参入する。撤退から10年周回遅れのソニーは大丈夫なのかと危惧される声もあるが、そのことよりAIBOの先にあるAI(人工知能)の無限の可能性を睨んでいた創業者の理念に戻ろうということの方が大きい。その創業精神とは「他人がやらないことをやれ」という不可能への挑戦で、「他社に真似されるものを作りなさい」という未来を期待させるものであった。しかし、ことごとくアップル社に先を越されてしまった先端技術のソニーを取り戻すことである。勿論、そのまま10年前の過去に戻ることではない。むしろ、過去の創業者から学び、ある意味で創業がそうであったように再び「一つの革新」を起こすためであると理解すべきである。
実は創業期には理想とするビジネスの原型、ある意味完成形に近いものがある。ビジネスは成長と共に次第に多数の事業がからみあい複雑になり、グローバル化し、視座も視野も視点もごちゃ混ぜになり、大切なことを見失ってしまう時代にいる。創業回帰とは、今一度「大切なこと」を明確にして、未来を目指すということである。
そのユニクロの記者発表であるが、上半期の決算でも業績の下方修正に触れて「値上げに失敗した点」にあると、更には大企業病にもかかっていると、その原因を認めていた。今回の年度決算に於いても同じことを発表していたが、今回は更に加えて「賃金が上がらない以上、デフレは消費者にとってそれほど悪いことだとは思わない。」と、デフレを認め、その上での価格戦略、値上げの間違いを認めていた点にある。
その見直しを踏まえた転換へのスタートが「Life Wear」というコンセプトである。「人はなぜ服を着るのだろうか」というCMを見る限り、表現としてこなしきれていないためおそらく視聴者の評価は低いものと思う。私の受け止め方は、ある意味原点に戻って今一度「服」について考え直しますという意味の宣言だと思っている。ユニクロという社名にあるように「ユニーククロージング」を次々と発売してきた。最初があの「フリース」である。GAPの物真似であると揶揄されながらも、GAPのコンセプトのように、男女の差も年齢の差も超えた服として利用され大きな顧客支持を得た。以降、英国進出の失敗などあったが、新素材開発に力を入れた「ヒートテック」、ソフトな履き心地の「UNIQLO JEANS」、「ブラトップ」・・・・・・・・ある意味社名にある「ユニーク」な商品をどこよりも早く開発し発売してきた。こうした「ユニーク」商品の「軸」となるのが今回の「Life Wear」というコンセプトである。
そのユニクロの柳井会長の超ワンマンぶりは「折り込みチラシの微妙な表現にまで介入する」と言われている。そんなことは現場経営では至極当たり前のことで、ほとんどの創業経営者はそうであった。ダスキンの創業者鈴木清一社長も私たちが作った制作物をとことん睨め付けるように見ていた。そして、FCビジネスであることから、現場の加盟店の動向については地域の担当者以上に熟知していた。
また、日本マクドナルドの藤田社長もファストフーズの命とも言える店内厨房のレイアウトなど幹部社員より熟知しており、誰よりも多く各店舗を回っていた。
周知の日本マクドナルドの1号店は銀座三越の1階であった。銀座というメディア性の高い立地もあって順調に出店も加速し、銀座店はいわばフラッグショップとしての役割を果たしていた。米国マクドナルドからはその成功ノウハウとしてシステマティックな各種マニュアル類がもたらされていた。時期は忘れてしまったが、藤田社長から「覆面顧客による調査」の依頼を受けたのを覚えている。マニュアルだけでは解決できないことが現場にはあるというのがその理由であった。そこでマニュアルに書かれていない顧客要望を「覆面顧客」として店舗で行い、その時の現場対応をレポートしてほしいというものであった。私の同僚の担当者は店舗スタッフから顔を覚えられているので私にその役割が回ってきたという次第であった。ところでその要望であるが、「ビッグマック」にマスタードを塗ってほしいというものであった。結果どうであったか、カウンターの若いスタッフは少々混乱気味に「店長~」と呼びに行ったことを覚えている。こうした顧客要望は新たなマニュアルへと追加していったことは言うまでもない。
どんな企業でも曲がり角はある。消費の変化はもとより業界のみならず大きくは時代そのものの変化要請である。そうした「変化」を誰よりも早く知覚し手を打つことが特に創業者には求められている。ダスキンで言うならば、売り上げが毎年30~50%という高い成長を見せていた時、敢えて新しいチャレンジのためのリニューアル計画を立てた時があった。右肩上がりのこの時に何故という声が上がったが、この時しかできないと決断した。それは屋台骨となる既存事業の再生であったが、役員を始め幹部社員を全て外し、地方の部長クラスを責任者に置き、中心メンバーも地方の現場担当者クラスを本社に呼び寄せたことがあった。そして、創業者自らが本部長になり、新しい改革を行った。ユニクロの柳井社長が一時期経営陣から離れたことがあったが、社長を解任し再度社長兼会長職に戻ったことがあった。これもダスキンの場合と同じである。そして、こうした行動が取れるのも創業者オーナーであればこそである。
ところで日本マクドナルドの最初の危機は1980年代半ばにあった。「あのマクドナルドのハンバーガーの肉はミミズである」という根拠のない風説による都市伝説が流行ったことがあった。勿論、根拠のないマクドナルドにとって迷惑な風評であるが、マクドナルドは実はビーフ(牛肉)以外にも他の肉を使い、消費者に知らせていなかった事実があった。確かNHKが調査を行い指摘したと記憶しているが、その指摘を受けて1985年にマクドナルドは「100%ビーフ」として再スタートしV字回復した経緯がある。これを指揮したのが、藤田田社長であった。よく「ピンチをチャンスに変える」と言われるが、仕入れや製造工程、現場のオペレーションを変えていく決断と実行は、これも創業者オーナーであればこそ可能となる。2004年7月に発覚した消費期限切れの鶏肉使用問題以降の対応策とを比較すると、その覚悟の違いと結果は歴然としている。
創業期の精神を忘れないために多くの企業は創業記念日を設定している。ユニクロも11月20日の創業記念日には感謝祭として「牛乳とあんぱん」を来店顧客に無料で配布している。これはユニクロが1号店をオープンさせた時に、朝早くから並んでくださったお客様に、朝食代わりとしてあんぱんと牛乳を配布したことに由来したものである。これも「初心」に立ち返る意味があり、周年記念や新規店オープンにも必ず「牛乳とあんぱん」が用意されていると聞いている。ダスキンの場合も11月16日が創業記念日となっており、お掃除会社らしく全国各地でご近所のお掃除をする托鉢が組まれている。
何故、初心に帰る、創業の理念や志を再度学び直す、こうしたことが必要となっているのかについては拙著「人力経営」を一読いただきたいが、創業時には「理想とするビジネスの完成形」があるということに尽きる。これは大企業であれ、町のラーメン店であれ、事業者にとって創業は必ずある。後継者がいないまま店を閉めるラーメン屋さんも多いが、それでもフアンの中から手を上げて再開する店もある。思い起こさなければならないのはその「思い」と共に、「ビジネスの完成形」はなんであったかを思い起こすことにある。ラーメン屋さんの理想形とは、他には無い「独自な味」ということになるかと思う。
今回は一定の情報と経験のある2社、ダスキンと日本マクドナルドを選んだが、創業者亡き後はいわゆるサラリーマン経営者となり、悪く言えば「普通の会社」になってしまったということである。普通であれば、至極簡単に言えば自然に業績を下げることへと向かっていくものである。多くの専門家はリーダーシップの欠如を指摘するが、オーナー創業者であればこそ、決断ができることがある。独断的・専制的に外目には見えるが、「普通」であったら成長などできないことを一番よく知っているのが創業者である。普通ではなかったからこそ「今日」があることを嫌という程骨身にしみているのが創業者ということだ。これは勝手な推測ではあるが、ユニクロに求められているのは第二の創業、もっと明確に言えば第二の「柳井正」が次から次へと登場することが待たれているということだ。勿論、次なる「ビジネスの理想形」を構想でき、しかも胆力のある人物ということになる。(続く)
<お知らせ>
「人力経営」 ヒットの裏側、人づくり経営を聞く 756円
2016年10月15日
インバウンドビジネスの今
ヒット商品応援団日記No661(毎週更新) 2016.10.15.
先日大阪・ミナミの寿司店で訪日外国人に対し、過剰なまでのわさびを入れ「外国客への嫌がらせ」といった差別批判がネット上に書き込まれTVにも取り上げられ話題となった。更に、南海電鉄の難波発関西空港行き空港急行の車内アナウンスで「本日は外国人のお客さまが多く乗車し、ご不便をお掛けしております」としたことから、外国人への差別ではないかと、これまた話題となった。関西、特に大阪はインバウンドビジネスには力を入れており、訪日外国人が急増していることもあって、こうした訪日外国人への理解の無さが表へとやっと出てきたということだろう。
既に1年ほど前から訪日外国人の日本への興味、更にはその消費は大きく変わってきていると指摘をしてきた。訪日外国人とひとくくりにはできないが、その共通していることは日本人のライフスタイルへの興味で、普通の日常の生活、食事、住まい方、おしゃれ、娯楽や趣味、・・・・・・・・・私たちにとっては至極「普通」「当たり前」であることへの興味関心で、特にそのディテールについてである。
その象徴が「わさび」で、韓国人や中国人ばかりでなく、欧米人にとっても関心が高い香辛料である。ましてや寿司店で使われるすりおろしの生わさびなどは香りも良く、わさびを多く入れて欲しいと注文するのは至極当たり前のこととしてある。こうした「好み」はリピーターになればなるほどより強く出てくる。そうした「好み」はわさびだけでなく、和がらしや山椒、七味もそうであり、日本人の使い方とは少し異なる使い方になる。結果、リピーターの日本土産は何になるのか、こうしたチュウブ入りのわさびや和からしになるということである。つまり、何回か日本に来て、街を歩き、食べたり飲んだり、日本人と会話したり、そうした経験の中から「これはいいな」「自分に合っているな」・・・・・・そうした「好み」が鮮明になって来たということである。生魚をご飯にのせて食べるなどと敬遠して来た握り寿司も、ここまで進化して来たと理解すべきである。
南海電鉄の「差別アナウンス発言」も同じようなことで、悪意あってのことではないと思う。東京では成田エクスプレスには荷物用のスペースが用意され、羽田行きのモノレールも同様である。訪日外国人の団体旅行の場合はどうしても仲間だけで行動するため騒がしくもなり、外見には傍若無人に見えるだけである。日本人が海外旅行した最初の頃を思い出せばわかるはずである。
しかし、あまりの訪日観光客の多さに少々辟易する日本人も出て来たことは事実である。京都の友人から京都観光の「今」を伝えてくれている。京都市が行なった調査によれば、日本人客の満足度が低下しており、その最大要因は「混雑」にあると。「人が多い、混雑」13.8%、「交通状況」11.4%、ゆっくり観光できないという理由である。結果京都観光全体に占める日本人客と外国人客の内訳はわからないが、宿泊客に限れば2015年は外国人客は133万人増えた一方、日本人客は112万人減ったことが明らかになったと。京都下鴨神社や東京浅草寺も必ず訪れる観光地であり、まあ仕方のない観光地であると理解すれば良いのだ。訪日外国人観光客のリピーターが進化しているように、日本人観光客も進化したら良い。東京観光に来た友人や知人を案内する場合は、例えば浅草案内であれな横丁路地裏ではないが、六区界隈は昼間も空いているし、更に夜の浅草もまた味わい深いものである。
つまり、中国の国慶節も爆買いもあまり話題になることもなく、インバウンドビジネスも今やっと真正面から見つめる入り口に来たということである。その良き事例が東京谷根千にある旅館「澤の屋」であろう。1982年に日本旅館としていち早く外国人の受け入れを開始し、今や宿泊客の約9割が外国人という「澤の屋旅館」であるが、都内の中小旅館と同様ビジネスホテルへと顧客は移り苦境に陥った時期があった。その澤の屋がいかにして訪日外国人客の高い評価を得たかである。訪日外国人受け入れ転換時は大分苦労されたようだ。英語も都心のホテルスタッフのようにはうまくない、たどたどしい会話であったが、それを救ってくれたのが家族でもてなす下町人情サービスであった。そして、重要なことは澤の屋だけでなく谷根千という地域全体が訪日外国人をもてなすという点にある。土産物店や飲食店だけでなく、日本固有の銭湯もである。グローバル経済の中の観光、それは日本ならではの固有な文化ビジネスであると理解しなければならないということだ。
つまり、インバウンドビジネスにも文化ビジネスであることをより鮮明にするような外国人客の観光行動が出て来ている。それは書道や武道といったいわゆる伝統的な日本文化だけでなく、日本の生活文化の理解を得るための観光行動の一つに「市場巡り」がある。日本人は何をどう食べているか、その集積場所である市場で実感したいという観光である。それは東京であれば築地市場巡りであり、京都であれば錦市場である。京都新聞では「越境する食と人」というテーマで”錦市場、飛び交う外国語”と書き、今や京の台所は日本人客より外国人客の方が多い、そんな状況であると伝えている。日本の理解、日本文化の理解はまずは「食」から、その集積されている市場を巡れば理解が深まるということである。
一方、そうした訪日外国客の「好み」をどう把握するのか、市場の側も模索していると報じている。例えば、豆菓子店では「中国客は黒豆をヘイトうと呼び、米国客はそら豆」を好み、鮮魚店では「中国客はうなぎを好み、欧米人は鱧」を好むといったようにその背景を模索している。また鰹節は日本固有の出汁をとる調味料であり、ほとんどの外国客は驚くという。また、日本人客も外国客も一様に好むのが「わらび餅」であるとも。
このように消費現場ではより明確な外国客の「好み」の解明が進んでいるようだ。まだ外国客へのアンテナを張っており様子を見ている段階と思うが、こうしたインバウンド市場とは異なるのではと思いがちであるファストフードビジネスでも同様な動きも始まっているようだ。例えば、ラーメンから日本そばへと外国人客の好みの広がりを見せてはいるが、うどんまではと多くの人は考えている。しかし、讃岐うどんの丸亀製麺は少し前にうどんのトッピングにタルタルソースの「とり天」導入に外国人モデルに使った TVCMをオンエアしていた。その後の売り上げ成功度合いはわからないが、一つのアプローチであろう。これも外国人客の「好み」の進化がどの方向に広がり、深まっているかを見極める段階へと移っている。訪日した最初は渋谷のスクランブル交差点や自販機に驚いたが、やがて渋谷の街に好みのラーメン店を探し、食べ放題も体験。今や日本人の日常にまで入り込んで来たという段階である。(続く)
先日大阪・ミナミの寿司店で訪日外国人に対し、過剰なまでのわさびを入れ「外国客への嫌がらせ」といった差別批判がネット上に書き込まれTVにも取り上げられ話題となった。更に、南海電鉄の難波発関西空港行き空港急行の車内アナウンスで「本日は外国人のお客さまが多く乗車し、ご不便をお掛けしております」としたことから、外国人への差別ではないかと、これまた話題となった。関西、特に大阪はインバウンドビジネスには力を入れており、訪日外国人が急増していることもあって、こうした訪日外国人への理解の無さが表へとやっと出てきたということだろう。
既に1年ほど前から訪日外国人の日本への興味、更にはその消費は大きく変わってきていると指摘をしてきた。訪日外国人とひとくくりにはできないが、その共通していることは日本人のライフスタイルへの興味で、普通の日常の生活、食事、住まい方、おしゃれ、娯楽や趣味、・・・・・・・・・私たちにとっては至極「普通」「当たり前」であることへの興味関心で、特にそのディテールについてである。
その象徴が「わさび」で、韓国人や中国人ばかりでなく、欧米人にとっても関心が高い香辛料である。ましてや寿司店で使われるすりおろしの生わさびなどは香りも良く、わさびを多く入れて欲しいと注文するのは至極当たり前のこととしてある。こうした「好み」はリピーターになればなるほどより強く出てくる。そうした「好み」はわさびだけでなく、和がらしや山椒、七味もそうであり、日本人の使い方とは少し異なる使い方になる。結果、リピーターの日本土産は何になるのか、こうしたチュウブ入りのわさびや和からしになるということである。つまり、何回か日本に来て、街を歩き、食べたり飲んだり、日本人と会話したり、そうした経験の中から「これはいいな」「自分に合っているな」・・・・・・そうした「好み」が鮮明になって来たということである。生魚をご飯にのせて食べるなどと敬遠して来た握り寿司も、ここまで進化して来たと理解すべきである。
南海電鉄の「差別アナウンス発言」も同じようなことで、悪意あってのことではないと思う。東京では成田エクスプレスには荷物用のスペースが用意され、羽田行きのモノレールも同様である。訪日外国人の団体旅行の場合はどうしても仲間だけで行動するため騒がしくもなり、外見には傍若無人に見えるだけである。日本人が海外旅行した最初の頃を思い出せばわかるはずである。
しかし、あまりの訪日観光客の多さに少々辟易する日本人も出て来たことは事実である。京都の友人から京都観光の「今」を伝えてくれている。京都市が行なった調査によれば、日本人客の満足度が低下しており、その最大要因は「混雑」にあると。「人が多い、混雑」13.8%、「交通状況」11.4%、ゆっくり観光できないという理由である。結果京都観光全体に占める日本人客と外国人客の内訳はわからないが、宿泊客に限れば2015年は外国人客は133万人増えた一方、日本人客は112万人減ったことが明らかになったと。京都下鴨神社や東京浅草寺も必ず訪れる観光地であり、まあ仕方のない観光地であると理解すれば良いのだ。訪日外国人観光客のリピーターが進化しているように、日本人観光客も進化したら良い。東京観光に来た友人や知人を案内する場合は、例えば浅草案内であれな横丁路地裏ではないが、六区界隈は昼間も空いているし、更に夜の浅草もまた味わい深いものである。
つまり、中国の国慶節も爆買いもあまり話題になることもなく、インバウンドビジネスも今やっと真正面から見つめる入り口に来たということである。その良き事例が東京谷根千にある旅館「澤の屋」であろう。1982年に日本旅館としていち早く外国人の受け入れを開始し、今や宿泊客の約9割が外国人という「澤の屋旅館」であるが、都内の中小旅館と同様ビジネスホテルへと顧客は移り苦境に陥った時期があった。その澤の屋がいかにして訪日外国人客の高い評価を得たかである。訪日外国人受け入れ転換時は大分苦労されたようだ。英語も都心のホテルスタッフのようにはうまくない、たどたどしい会話であったが、それを救ってくれたのが家族でもてなす下町人情サービスであった。そして、重要なことは澤の屋だけでなく谷根千という地域全体が訪日外国人をもてなすという点にある。土産物店や飲食店だけでなく、日本固有の銭湯もである。グローバル経済の中の観光、それは日本ならではの固有な文化ビジネスであると理解しなければならないということだ。
つまり、インバウンドビジネスにも文化ビジネスであることをより鮮明にするような外国人客の観光行動が出て来ている。それは書道や武道といったいわゆる伝統的な日本文化だけでなく、日本の生活文化の理解を得るための観光行動の一つに「市場巡り」がある。日本人は何をどう食べているか、その集積場所である市場で実感したいという観光である。それは東京であれば築地市場巡りであり、京都であれば錦市場である。京都新聞では「越境する食と人」というテーマで”錦市場、飛び交う外国語”と書き、今や京の台所は日本人客より外国人客の方が多い、そんな状況であると伝えている。日本の理解、日本文化の理解はまずは「食」から、その集積されている市場を巡れば理解が深まるということである。
一方、そうした訪日外国客の「好み」をどう把握するのか、市場の側も模索していると報じている。例えば、豆菓子店では「中国客は黒豆をヘイトうと呼び、米国客はそら豆」を好み、鮮魚店では「中国客はうなぎを好み、欧米人は鱧」を好むといったようにその背景を模索している。また鰹節は日本固有の出汁をとる調味料であり、ほとんどの外国客は驚くという。また、日本人客も外国客も一様に好むのが「わらび餅」であるとも。
このように消費現場ではより明確な外国客の「好み」の解明が進んでいるようだ。まだ外国客へのアンテナを張っており様子を見ている段階と思うが、こうしたインバウンド市場とは異なるのではと思いがちであるファストフードビジネスでも同様な動きも始まっているようだ。例えば、ラーメンから日本そばへと外国人客の好みの広がりを見せてはいるが、うどんまではと多くの人は考えている。しかし、讃岐うどんの丸亀製麺は少し前にうどんのトッピングにタルタルソースの「とり天」導入に外国人モデルに使った TVCMをオンエアしていた。その後の売り上げ成功度合いはわからないが、一つのアプローチであろう。これも外国人客の「好み」の進化がどの方向に広がり、深まっているかを見極める段階へと移っている。訪日した最初は渋谷のスクランブル交差点や自販機に驚いたが、やがて渋谷の街に好みのラーメン店を探し、食べ放題も体験。今や日本人の日常にまで入り込んで来たという段階である。(続く)
2016年10月09日
果たして、豊洲ブランドは成立するであろうか?
ヒット商品応援団日記No660(毎週更新) 2016.10.9.
東京中央卸売市場の築地から豊洲への移転計画において、築地ブランドという言葉と共に、豊洲ブランドという言葉が使われ始めている。ブランド価値、無形の資産ブランドという考えがビジネスに導入されてきた背景には、例えば同じ便益・機能を持つ商品がA社では100なのに、何故B社では120と評価されるのかという、誰もが持っている心理的価値に着眼してきたことによる。その心理的価値とは何かであるが、結論から言えば「人は皆、記憶の生産者である」ということが根底にある。多忙な日常の中で記憶はある時何かに触発され、商品やサービスを使い、満足を得て、そして「思い出すこと」によって記憶は深く刻まれる。その繰り返しがブランド価値を更に強めたり弱めたりしていく。そうした期待と満足が時間をかけて創られるのがブランドである。つまり、ブランドは顧客によって創られるものであり、長い時間にわたって育てられた文化価値のことである。
ブランドという言葉以前に日本には老舗・暖簾という言葉がある。実は日本ほど老舗企業が今なお活動している国はない。創業200年以上の老舗企業ではだんとつ日本が1位で約3000社、2位がドイツで約800社、3位はオランドの約200社、米国は4位でわずか14社しかない。何故、日本だけが今なお生き残り活動しえているのであろうか。出口の見えない失われた20年と言われてきたが、グローバリズムの波、激烈な価格競争、そうした市場に生き残るためのヒントがここにある。その象徴とも言える世界最古の会社である金剛組について以前ブログに次のように書いたことがあった。創業1400年以上、聖徳太子の招聘で朝鮮半島の百済から来た3人の工匠の一人が創業したと言われ、日本書紀にも書かれている宮大工の会社である。何故、1400年以上も生き残ってきたのかである。その苦難の歴史は別の機会とし、金剛組の仕事にその秘密はある。
『宮大工という仕事はその出来上がった外形面からはできの善し悪しは分からない。200年後、300年後に建物を解体した時、初めてその技がわかるというものだ。見えない技、これが伝統と言えるのかも知れないが、見えないものであることを信じられる社会・風土、顧客が日本にあればこそ、世界最古の会社の存続を可能にしたと思う。
しかし、今日の情況はと言えば、「見える化」というキーワードが流行るように、膨大な情報のなかで、これでもかとパフォーマンスを高めることに注力しなければならない時代となっている。物やサービスの評価の前に情報競争に勝たなければ先に進むことが出来ないからだ。』
実は築地市場にはこの「見えない技」が代々継承されてきた。よく「こだわり」と言うが、宮大工の世界まではいかなくても、「見えない」世界に執着することがこだわりである。その執着を今まで私たちは修行と呼んできた。例えば、料理で言えば、基本の出汁は言うまでもないが、隠し味、隠し包丁、見えない工夫に執着することこそこだわりであろう。ファッションであれば、外面デザインだけでなく、素材や縫製更には裏地やボタン一つということになる。こうした「見えない技」を築地では「目利き」と呼ぶプロの人たちが卸売市場を形成してきた。
こうした食のプロ達が日常食べる店がいわゆる場外市場と呼ばれている場所である。この場外には数年前から多くの人がその食を求めて行列する、そんな観光地にもなってきた。プロの料理人が食べる賄い飯を素人である生活者が求める構図は、隠れ家食堂のようなものである。
もう一つの「見えない努力」は食の安全に対する日々の努力であろう。最近築地には行ってはいないが、若いころ銀座で働いていた頃はよく歩いて場外の寿司店など利用していた。当時から建物は老朽化し、決して綺麗とは言えない場内外であったが、ここ数十年食中毒など一度も聞いたことがなかった。これも衛生という見えない世界に対する伝統であろう。そして、この見えない世界という伝統を育ててきたのも築地から食材を仕入れきた鮮魚店や青果店、あるいは飲食店であり、その向こうには膨大な安全安心を求める消費者がいるということである。
さてこうした築地が創ってきたブランド価値、有形無形の文化価値は豊洲でも創っていけるであろうかということである。今、豊洲市場の建物の地下空間に盛り土がなされておらず、その安全性に対する疑義が噴出している。土壌や地下水の汚染等の専門家ではないので科学的な安全性についてはコメントできる立場にばない。しかし、東京都議会が始まり、専門家会議や技術会議といった安全を担保する人たちの提言とは異なる建築物になっており、既に「風評」という二次被害は始まっている。その風評とは市場の第一次顧客である鮮魚店や青果店、あるいは飲食店が移転しても大丈夫なのかという「不安」となって現れている。
こうした風評被害の構図は5年半前の東日本大震災による福島の原発事故を思い起こさせる。当時の一番大きな問題は事故後1週間ほどの初動メッセージであった。「メルトダウンは起きてはいません。既に原子炉は止まっており心配はいりません」、そう繰り返し発表されてきた。しかし、その後水素爆発が連続して起こり、無惨な建屋が映像として現れる。そして、その建屋は原発事故の象徴記号として今なお記憶に残っている。
こうした虚偽のメッセージこそが「不安」を生むことにつながっている。今回の建物の地下空間に盛り土がなされていなかったことを隠したり、地下にたまった水を地下水にもかかわらず雨水であると言ったり、こうしたメッセージを出せば出すほど不安は増幅し、より具体的な被害へと向かっていくのだ。不安を作っているのは東京都自身であるということである。
そして、卸売市場を取り巻く商環境であるが、鮮魚や青果は大手流通の場合は「一船買い」あるいは「一畑買い」が行われており、一定量を継続確保するためのいわば補足的な仕入れへと向かっている。大手飲食店の場合も直接漁港の市馬などから仕入れる、あるいは生産者と交渉して仕入れる、こうした卸売市場を介在させない方向に向かっている。これが現状である。
またこうした中間事業者を通さない流通は「個人」においても産直として行われ、互いに「顔の見える関係」として商品の売買がなされ、この傾向も増える傾向にある。
東京都は都内にある市場事業の個別市馬の売り上げ等詳細を発表していないので移転の是非についてはコメントできないが、「移転&再開発」については秋葉原の場合はJR東日本の協力もあって、ユニークな街づくり、オタクと最先端ITとが交差する他にはない街へと変化・進化させてきた。そして、1989年には神田青果市場は大田市場へと移転し、これも順調にいっていると聞いている。
ところで豊洲は市場として成立するのであろうか、という疑問が起きてくる。勿論、築地という銀座に隣り合わせた超一等地の売却が前提である。移転先の豊洲にこれまで6000億円近く投資しているが、これも売却が前提であるが、「安全」が科学的にも十分担保できた場合であっても、果たして豊洲市場の大家さんである東京都はビジネスとしてやっていけるのか疑問が残る。それは「安全」は科学的に担保されても、「安心」にはつながらない状況に至りつつあるからである。安全=安心ではないということである。築地で営々と培ってきた信用に基づく安心を再びどう豊洲で創っていけば良いのかという問題である。
そして、豊洲市場のスペースに新たな観光拠点として「千客万来施設」を誘致する予定であったが、運営会社に、整備設計の一時中止を要請したことが分かった。敷地の地下を駐車場にする設計だったが、既に施工済みの盛り土を除去する必要があり、地下水への影響など安全性の検証が不可欠と判断したとの事。この計画は簡単に言ってしまうと、「築地場外市場」と温浴施設を中心に置いた170~280店が入居可能な飲食店街の「商業ゾーン」の構成となっている。この計画を中断するというものである。元々周知の大和ハウス工業がこうしたデベロッパー役としてオーガナイズする予定であったが、理由はわからないが撤退した経緯がある。その役割を温浴施設である万葉倶楽部が運営することになっていた。こうした経緯を見てきた私にとって、東京都は困って観光施設などという卸売市場とは全く異なる集客装置に手を出さざるを得なくなったと推測していた。まあ、これもビジネスではやむを得ないことだとは思っていたが、コンセプトづくりを長年やってきた私にとっては「卸売市場」を観光化するのであれば、集客のための温浴施設は必要はないと考えていた。
いずれにせよ、観光もあらゆる意味での「安全」が不可欠となる。
その安全であるが、ITを駆使した汚染による「0リスク」を目指す試案もある。その一つであるが、全ての個々の食材はコストがかかりすぎて難しいが、水産であれば「漁船や漁港単位」、農作物であれば「畑や生産者単位」の安全確認のための履歴の追跡、いわゆるトレーサビリティの仕組みを提案する専門家もいる。しかし、トレースして「汚染のリスク」があったらどうするのか、という問題は依然として残る。こうした「0リスク」を確率論として処理することは可能だが、それでブランドとして成立できるであろうか。つまり、一度は買っても二度と買うことはないというのが答えである。こうした理屈とは異なるのが消費における心理である。
顧客が主人公の時代とは、安全と安心との間には大きな谷間があることをまず認識することから始めなければならない。既に現在は風評等負のスパイラルへと向かっている。それは東京都の縦割り行政や無責任体制といったガバナンスの欠如によってそのスパイラルを加速させている。ブランドを創るのは最終顧客であると私は書いたが、例えば評判の前では風評は消滅する時代のことでもある。何故なら、誰もがリアルな体験をこそ信じているからである。自分が食べてみて、これは本当に身体にも良いとみんなそう思いたがっているということだ。勿論、デマ好き、愉快犯的人間もいる。それは風評ではない。皆、風評を打ち消してくれる、不安を打ち消してくれる「何か」を欲しがっているということだ。もし、豊洲への移転を小池都知事が政治決断したとするならば、その「何か」は今なお築地にはあるということである。築地の誕生、いわば創業の精神に立ち帰る、その生きざまを「豊洲」に重ねてみることだ。重ねても重ねても難しいということになるのであれば、移転は断念し、現在の築地市場を再度段階的にリニューアルする計画二することだ。こうした顧客の期待に応えることから始めるということである。そのためには言うまでもなく、まずは徹底した「情報公開」からであろう。(続く)
東京中央卸売市場の築地から豊洲への移転計画において、築地ブランドという言葉と共に、豊洲ブランドという言葉が使われ始めている。ブランド価値、無形の資産ブランドという考えがビジネスに導入されてきた背景には、例えば同じ便益・機能を持つ商品がA社では100なのに、何故B社では120と評価されるのかという、誰もが持っている心理的価値に着眼してきたことによる。その心理的価値とは何かであるが、結論から言えば「人は皆、記憶の生産者である」ということが根底にある。多忙な日常の中で記憶はある時何かに触発され、商品やサービスを使い、満足を得て、そして「思い出すこと」によって記憶は深く刻まれる。その繰り返しがブランド価値を更に強めたり弱めたりしていく。そうした期待と満足が時間をかけて創られるのがブランドである。つまり、ブランドは顧客によって創られるものであり、長い時間にわたって育てられた文化価値のことである。
ブランドという言葉以前に日本には老舗・暖簾という言葉がある。実は日本ほど老舗企業が今なお活動している国はない。創業200年以上の老舗企業ではだんとつ日本が1位で約3000社、2位がドイツで約800社、3位はオランドの約200社、米国は4位でわずか14社しかない。何故、日本だけが今なお生き残り活動しえているのであろうか。出口の見えない失われた20年と言われてきたが、グローバリズムの波、激烈な価格競争、そうした市場に生き残るためのヒントがここにある。その象徴とも言える世界最古の会社である金剛組について以前ブログに次のように書いたことがあった。創業1400年以上、聖徳太子の招聘で朝鮮半島の百済から来た3人の工匠の一人が創業したと言われ、日本書紀にも書かれている宮大工の会社である。何故、1400年以上も生き残ってきたのかである。その苦難の歴史は別の機会とし、金剛組の仕事にその秘密はある。
『宮大工という仕事はその出来上がった外形面からはできの善し悪しは分からない。200年後、300年後に建物を解体した時、初めてその技がわかるというものだ。見えない技、これが伝統と言えるのかも知れないが、見えないものであることを信じられる社会・風土、顧客が日本にあればこそ、世界最古の会社の存続を可能にしたと思う。
しかし、今日の情況はと言えば、「見える化」というキーワードが流行るように、膨大な情報のなかで、これでもかとパフォーマンスを高めることに注力しなければならない時代となっている。物やサービスの評価の前に情報競争に勝たなければ先に進むことが出来ないからだ。』
実は築地市場にはこの「見えない技」が代々継承されてきた。よく「こだわり」と言うが、宮大工の世界まではいかなくても、「見えない」世界に執着することがこだわりである。その執着を今まで私たちは修行と呼んできた。例えば、料理で言えば、基本の出汁は言うまでもないが、隠し味、隠し包丁、見えない工夫に執着することこそこだわりであろう。ファッションであれば、外面デザインだけでなく、素材や縫製更には裏地やボタン一つということになる。こうした「見えない技」を築地では「目利き」と呼ぶプロの人たちが卸売市場を形成してきた。
こうした食のプロ達が日常食べる店がいわゆる場外市場と呼ばれている場所である。この場外には数年前から多くの人がその食を求めて行列する、そんな観光地にもなってきた。プロの料理人が食べる賄い飯を素人である生活者が求める構図は、隠れ家食堂のようなものである。
もう一つの「見えない努力」は食の安全に対する日々の努力であろう。最近築地には行ってはいないが、若いころ銀座で働いていた頃はよく歩いて場外の寿司店など利用していた。当時から建物は老朽化し、決して綺麗とは言えない場内外であったが、ここ数十年食中毒など一度も聞いたことがなかった。これも衛生という見えない世界に対する伝統であろう。そして、この見えない世界という伝統を育ててきたのも築地から食材を仕入れきた鮮魚店や青果店、あるいは飲食店であり、その向こうには膨大な安全安心を求める消費者がいるということである。
さてこうした築地が創ってきたブランド価値、有形無形の文化価値は豊洲でも創っていけるであろうかということである。今、豊洲市場の建物の地下空間に盛り土がなされておらず、その安全性に対する疑義が噴出している。土壌や地下水の汚染等の専門家ではないので科学的な安全性についてはコメントできる立場にばない。しかし、東京都議会が始まり、専門家会議や技術会議といった安全を担保する人たちの提言とは異なる建築物になっており、既に「風評」という二次被害は始まっている。その風評とは市場の第一次顧客である鮮魚店や青果店、あるいは飲食店が移転しても大丈夫なのかという「不安」となって現れている。
こうした風評被害の構図は5年半前の東日本大震災による福島の原発事故を思い起こさせる。当時の一番大きな問題は事故後1週間ほどの初動メッセージであった。「メルトダウンは起きてはいません。既に原子炉は止まっており心配はいりません」、そう繰り返し発表されてきた。しかし、その後水素爆発が連続して起こり、無惨な建屋が映像として現れる。そして、その建屋は原発事故の象徴記号として今なお記憶に残っている。
こうした虚偽のメッセージこそが「不安」を生むことにつながっている。今回の建物の地下空間に盛り土がなされていなかったことを隠したり、地下にたまった水を地下水にもかかわらず雨水であると言ったり、こうしたメッセージを出せば出すほど不安は増幅し、より具体的な被害へと向かっていくのだ。不安を作っているのは東京都自身であるということである。
そして、卸売市場を取り巻く商環境であるが、鮮魚や青果は大手流通の場合は「一船買い」あるいは「一畑買い」が行われており、一定量を継続確保するためのいわば補足的な仕入れへと向かっている。大手飲食店の場合も直接漁港の市馬などから仕入れる、あるいは生産者と交渉して仕入れる、こうした卸売市場を介在させない方向に向かっている。これが現状である。
またこうした中間事業者を通さない流通は「個人」においても産直として行われ、互いに「顔の見える関係」として商品の売買がなされ、この傾向も増える傾向にある。
東京都は都内にある市場事業の個別市馬の売り上げ等詳細を発表していないので移転の是非についてはコメントできないが、「移転&再開発」については秋葉原の場合はJR東日本の協力もあって、ユニークな街づくり、オタクと最先端ITとが交差する他にはない街へと変化・進化させてきた。そして、1989年には神田青果市場は大田市場へと移転し、これも順調にいっていると聞いている。
ところで豊洲は市場として成立するのであろうか、という疑問が起きてくる。勿論、築地という銀座に隣り合わせた超一等地の売却が前提である。移転先の豊洲にこれまで6000億円近く投資しているが、これも売却が前提であるが、「安全」が科学的にも十分担保できた場合であっても、果たして豊洲市場の大家さんである東京都はビジネスとしてやっていけるのか疑問が残る。それは「安全」は科学的に担保されても、「安心」にはつながらない状況に至りつつあるからである。安全=安心ではないということである。築地で営々と培ってきた信用に基づく安心を再びどう豊洲で創っていけば良いのかという問題である。
そして、豊洲市場のスペースに新たな観光拠点として「千客万来施設」を誘致する予定であったが、運営会社に、整備設計の一時中止を要請したことが分かった。敷地の地下を駐車場にする設計だったが、既に施工済みの盛り土を除去する必要があり、地下水への影響など安全性の検証が不可欠と判断したとの事。この計画は簡単に言ってしまうと、「築地場外市場」と温浴施設を中心に置いた170~280店が入居可能な飲食店街の「商業ゾーン」の構成となっている。この計画を中断するというものである。元々周知の大和ハウス工業がこうしたデベロッパー役としてオーガナイズする予定であったが、理由はわからないが撤退した経緯がある。その役割を温浴施設である万葉倶楽部が運営することになっていた。こうした経緯を見てきた私にとって、東京都は困って観光施設などという卸売市場とは全く異なる集客装置に手を出さざるを得なくなったと推測していた。まあ、これもビジネスではやむを得ないことだとは思っていたが、コンセプトづくりを長年やってきた私にとっては「卸売市場」を観光化するのであれば、集客のための温浴施設は必要はないと考えていた。
いずれにせよ、観光もあらゆる意味での「安全」が不可欠となる。
その安全であるが、ITを駆使した汚染による「0リスク」を目指す試案もある。その一つであるが、全ての個々の食材はコストがかかりすぎて難しいが、水産であれば「漁船や漁港単位」、農作物であれば「畑や生産者単位」の安全確認のための履歴の追跡、いわゆるトレーサビリティの仕組みを提案する専門家もいる。しかし、トレースして「汚染のリスク」があったらどうするのか、という問題は依然として残る。こうした「0リスク」を確率論として処理することは可能だが、それでブランドとして成立できるであろうか。つまり、一度は買っても二度と買うことはないというのが答えである。こうした理屈とは異なるのが消費における心理である。
顧客が主人公の時代とは、安全と安心との間には大きな谷間があることをまず認識することから始めなければならない。既に現在は風評等負のスパイラルへと向かっている。それは東京都の縦割り行政や無責任体制といったガバナンスの欠如によってそのスパイラルを加速させている。ブランドを創るのは最終顧客であると私は書いたが、例えば評判の前では風評は消滅する時代のことでもある。何故なら、誰もがリアルな体験をこそ信じているからである。自分が食べてみて、これは本当に身体にも良いとみんなそう思いたがっているということだ。勿論、デマ好き、愉快犯的人間もいる。それは風評ではない。皆、風評を打ち消してくれる、不安を打ち消してくれる「何か」を欲しがっているということだ。もし、豊洲への移転を小池都知事が政治決断したとするならば、その「何か」は今なお築地にはあるということである。築地の誕生、いわば創業の精神に立ち帰る、その生きざまを「豊洲」に重ねてみることだ。重ねても重ねても難しいということになるのであれば、移転は断念し、現在の築地市場を再度段階的にリニューアルする計画二することだ。こうした顧客の期待に応えることから始めるということである。そのためには言うまでもなく、まずは徹底した「情報公開」からであろう。(続く)
2016年10月07日
未来塾(25)「パラダイム転換から学ぶ」 健康時代の未来 (後半)
ヒット商品応援団日記No659(毎週更新) 2016.10.7.

戦後の物不足・欠乏の時代を終え、1980年代以降生きるための食から健康のための食へと大きくパラダイムの転換が起きてきた。そして、その質的変化を表したのが表紙のカロリー摂取量のグラフで、終戦後間もない頃と比較し、経済的豊かさにも関わらず、新たな豊かさを象徴するかのようにカロリー摂取量は減少する。そして、スーパーの食品売り場には、糖質0、カロリーオフ、トクホ(特定保健用食品 )といった表示商品が棚に並んでいる。過剰な情報時代というが、「健康」もまた過剰な時代となり、どんな「健康」を選択したら良いのかわからない時代を迎えている。
一方、物の豊かさの陰には新たな問題も生まれている。肥満による成人病という現代病から始まり、過食や拒食といった摂食障害という病も10~20代の女性の間で出てきている。ストレス社会ならではの病であるが、その発症のきっかけがダイエットであると専門家は指摘する。あるいは無菌社会と呼ぶ専門家もいるが、アトピーやアレルギーといった免疫疾患も生まれてきている。免疫力の低下とは、身体の持つ自然力・生命力の低下でもある。このパラダイムは今後どんな方向へと向かうのか、仮説を含め考えてみたい。
江戸時代にもあった飽食の是正
前回の未来塾「江戸と京」では、その江戸という町の都市化の構造を京との関係の中で考えてみた。そして、江戸時代における生活は1日の食事が2回から3回になり、屋台のような外食産業が栄え、しかも24時間化も進展していた。元禄時代をバブル期と呼ぶ専門家もいるが、今日の「健康・からだ・食」を彷彿とさせるような現象も起きていた。
 例えば、当時は既に大食いコンテストも行われ、江戸の豊かさの象徴として「江戸に行けば銀シャリが食べられる」と言われ、幕府の人返し令にもかかわらず、多くの人が地方から江戸へと向かった。当時は1日の食事量としては白米5合ほど食べられていたと言われている。しかも、豆腐や野菜、魚も食べられていたが、その量は極めて少なく、一汁一菜と言われているように、主食の白米がほとんどであった。結果、江戸の武士階級を中心に「脚気患者」が増加する。ビタミンB1の欠乏症による末梢神経障害であるが、「江戸わずらい」と呼ばれていた。
例えば、当時は既に大食いコンテストも行われ、江戸の豊かさの象徴として「江戸に行けば銀シャリが食べられる」と言われ、幕府の人返し令にもかかわらず、多くの人が地方から江戸へと向かった。当時は1日の食事量としては白米5合ほど食べられていたと言われている。しかも、豆腐や野菜、魚も食べられていたが、その量は極めて少なく、一汁一菜と言われているように、主食の白米がほとんどであった。結果、江戸の武士階級を中心に「脚気患者」が増加する。ビタミンB1の欠乏症による末梢神経障害であるが、「江戸わずらい」と呼ばれていた。
ある意味現代における飽食生活と同じで、「健康・からだ・食」に対し警鐘を鳴らし啓蒙活動を行ったのが『養生訓』を書いた儒学者の貝原益軒であった。長寿を全うするための身体の養生だけでなく、精神の養生も説いているところに特徴があり、今日の振子消費のように揺れ動く心理状況にも的確な示唆をしてくれている。貝原益軒は内なる4つの欲望を抑え、我慢することによって長寿が得られると説いている。その4つであるが、ウイキペディアによれば
1、あれこれ食べてみたい食欲
2、色欲
3、むやみに眠りたがる欲
4、徒らに喋りたがる欲
江戸時代は乳幼児の死亡率が高く、今日の平均寿命と単純比較はできないが、一般的には50歳程度と言われている。しかし、実際には30~40歳ほどではないかという説もある。ちなみに、自ら「養生訓」を実践した貝原益軒は85歳で亡くなったと言われている。
沖縄料理から学ぶ;「ルーツに遡る」
戦後米軍統治下にあって、SPAMに代表される加工肉を日常的に食べてきた沖縄の人たち、特に男性については肥満度全国No1という事実によって「健康・からだ・食」という問題の所在は明らかになっている。そうした事実を踏まえ、県も盛んに是正策、長野県などをモデルに幾つかの施策、職場健診などを行っているようだ。
実は沖縄の食文化を調べていくと分かるが、一時期までの長寿の島である所以はその歴史、伝統料理に残されている。”美味しゅうございます”という決めセリフで知られている料理ジャーナリストである故岸朝子さんは沖縄生まれであった。その岸さんは沖縄の中でも一番の長寿村であるやんばるの森に囲まれた大宜味村の元村長との対談の中で、「私の子供の頃は食べるものも少なく, 生活が大変だった。飽食しない,食べ過ぎないのがいいということでしょう」と。まさに養生訓の言葉通りである。
沖縄には命草(ぬちぐさ)という言葉がある。語の意味そのもので命を支え育む草のことで、沖縄にはどこにでもある野草のことである。その代表植物が長命草で、沖縄ではよく知られたセリ科の植物である。
そして、その沖縄の歴史であるが、琉球王朝は,中国から来た冊封使を接待するために福建省へ料理人を派遣して,中国料理を勉強させたと言われている。更には島津藩の支配が始まると,日本の役人を接待するために,鹿児島へ料理人を派遣して,日本料理を勉強させる。 中国や日本の料理は,始めは接待料理であったが,次第に庶民の間に広がって,沖縄料理にバリエーションが増えていく。
 沖縄という島の地政学上からであると思うが、実はインドネシアからは,「ゴーヤーチャンプルー」で有名なチャンプルー(混ぜ合わせる)料理も伝わって来ている。沖縄にはよく食べる家庭料理の一つにヒラヤーチーがあるが、これも韓国のチヂミが源流だと考えられている。
沖縄という島の地政学上からであると思うが、実はインドネシアからは,「ゴーヤーチャンプルー」で有名なチャンプルー(混ぜ合わせる)料理も伝わって来ている。沖縄にはよく食べる家庭料理の一つにヒラヤーチーがあるが、これも韓国のチヂミが源流だと考えられている。
このように沖縄の料理は,昔から伝えられていた郷土料理に中国,日本,朝鮮,東南アジアのいろいろな国の料理が融合して 成立した、これが沖縄料理の歴史である。
私は日本文化を東京渋谷のスクランブル交差点のようだと指摘をしたが、そうした東京以外の沖縄もまさに東アジア~東南アジアの海道の交差点となっている。「ルーツに遡る」ならばチャンプルー(融合)こそが健康長寿の源であるということである。
岸朝子さんが整理した沖縄長寿食の特徴は以下となっている。
(1)良質のタンパク質
(2)長寿を支える緑黄色野菜
(3)サツマイモでバランスのとれた食生活
(4)ミネラル豊富な海藻類
(5)塩分を抑える調理法
(6)生き甲斐のある暮らし
上記の特徴は沖縄料理のどんなところにその工夫があるのか、いくらでも書けるがこのブログは料理レシピのブログではないので割愛する。実はこうした特徴は長野県をはじめ地方の郷土食の多くが有している特徴である。全国の学校給食においても地産地消・食育を含め郷土食を取り入れ始めている。更には、京野菜や加賀野菜だけでなく、地方に埋もれた伝統野菜の復活も始まっている。こうした地方に埋もれた、あるいは忘れられ過去となってしまった郷土料理の復活こそが待たれている。但し、過去をそのまま復活させることではなく、「今」を味わうことのできる郷土料理であることは言うまでもない。地方の生活に今なお残されている伝統料理、京都で言うならば「おばんざい料理」に次なる可能性の芽があるということである。
健康におけるグローバリズムとローカリズム
2016年世界保健機関(WHO)が発表した世界保健統計2016によると、世界一の長寿国は前年同様日本で男女平均が83.7歳だった。長寿大国ということはある意味裾野の広い食を中心とした健康産業大国ということである。サブカルチャーのクールジャパンと共に、長寿の国のライフスタイルはこれからの輸出産業の中心となりえる。その第1番目が「日本食」である。ある意味日本型LOHASを世界へと輸出するということだ。
少子高齢化をマイナス面でしかとらえられない発想の貧困さには辟易してしまうが、ポジティブに見ていく視座を持てば宝の山となる。日本の場合、ips細胞といった先端再生医療から食生活まで、世界における固有な健康資源を保有している。今までは若い世代を中心に海外セレブの健康法などトレンドとして取り入れてきた。しかし、例えば従来からの発想であるアンチエイジング=若返りという発想から、老いる=成熟という美しさへの発想へと、実はシニア生活の転換が始まっている。勿論、若い世代において若返り・美容についてはこれからもトレンドとして取り入れていくと思うが、老年を迎える団塊世代にとっても健美同源、つまり年相応の健康である美しさへと価値観は変わっていく。そんな事例ではないが、私の住む世田谷砧には大きな公園があり、老若男女がジョギングしている。遠くから見る限り年齢は全く識別できない。それはファッションもさることながら、走るスピードやスタイルによっても識別できないということである。いかに元気な若々しいシニアが多いかである。
独居老人の孤独死といった負の側面もあるが、長寿の国のライフスタイルを輸出していくといった発想、欧米諸国が既に認識している日本食を健康ダイエット食として売っていく、そうした試みが必要な時を迎えているということだ。
台湾には台湾素食という菜食主義料理がある。日本における精進料理に近いもので「もどき料理」もあるようだ。日本ではあまり注目はされていないが、着目すべきは「素」にある。素という、そのまま、自然体であること、そんなライフスタイルこそが健康の源である。そして、その素はまずは郷土料理に残されている。そんなローカルフードこそグローバル市場を開拓する新たな戦略ツールとなり得る。
ところで以前「消費都市TOKYO」というテーマで、市場の特性について考えたことがあった。結論からいうと、東京はグローバルなTOKYOという市場と地球市場から見ればローカルな東京という市場の2つの市場から成り立っている「グローカル市場」だ。つまり、TOKYOという市場を狙うことはそのままグローバル市場につながっている。また、国内市場という視点に立つと東京という都市市場の2つの側面、前回は江戸と京についてその構図を明らかにしたが、まさに混在したスクランブル交差点市場となっている。どんな市場を狙うのか、誰を顧客とするのかが最も重要なテーマとなっている。東京は一つの地球都市国家として見ていくことが必要で、そこには都市と地方が混在しているということだ。別の視点で見れば、グローバル市場への玄関口でもあり、世界へ向けた一大実験市場、テストの場でもある。例えば、ヒット商品という視点に立てば、一昔前にはルイヴィトンがパリ観光のお土産であったように、東京でのお土産あるいは記念品といったことが大きなビジネスチャンスとなるであろう。
訪日外国人、特に中国人観光客の家電製品に見られた爆買いは終わり、ドラッグストアに化粧品や目薬などを買い求める訪日外国人が増えている。そして、富士山観光は一巡し、富士山登山や花見や花火に興味関心は移ってきている。食についてもラーメンと共に、しゃぶしゃぶの食べ放題といった日本人の実生活にどんどん入り込んできた。つまり、日本人のライフスタイルそのものに興味関心は移っているということである。ビジネスチャンスが変化していることに気づかないのが日本人ということだ。
過剰情報の時代にあって
過剰な情報の時代にあって、どう取捨選択したら良いのか誰もが考えざるをえない時代にいる。2008年の直木賞に天童荒太の「悼む人」が選ばれた。読まれた方も多いと思うが、マスメディアから流される過剰な情報の中で「何」が自分にとって必要で、大切な情報なのか、その疑念から「悼む人」が書かれたという。亡くなった人を訪ね、その死の扱われ方を聞くことによって自身の心変わりをテーマとした小説である。生前どのように生き切っていたかを探し求めた小説であるが、情報の持つ意味合いを考えさせる小説である。マスメディアから流される情報、いや流されない情報の裏側で「何」が起こっていたのかを気づかせてくれた小説であるが、実は生活者がこうした裏にある事実へと気づき手に入れ始めた時代と言えよう。裏にある何か、それは自らの想像力によってであるが、今や過剰な情報が行き交う時代であるが故に、情報の裏にある何かへと想像に向かわさせる。
どんな人が、どんな場所で、いつどのように作られているのか、こうした産地見学や自ら無農薬による菜園作りが進んでいるのもこうした想像の故である。圧倒的に足りないのは実体験、追体験、そのリアリティの時代にいるという事実である。
同様にダイエットにおいても、ライザップ(RIZAP)のように「結果にコミットした徹底サポート」と言った特徴に人気が集まった。如何に「結果」の得られないダイエットが多かったかである。実績として2016年現在、2ヶ月という短期間で99%のお客様がライザップでダイエットに成功していると。ただし、リアルな結果を得るには、入会金は5万円、コース料金で29万8千円とかなり高額である。
商品に対し、サービスに対し、更には企業に対し、顧客が想像力を働かせる時、つまりどれだけリアルな結果を提供できるか、実質を約束出来るか、それを可能とする本当のプロ、専門家しか生き残ることはできないということである。既に情報だけのイメージだけの競争は終わっているということである。私たちがそのことに思い至らなければ、消費の輪郭は明らかにはならないということである。
自己解決型健康法の時代へ
ひと頃ブームとなっていたプチ整形の韓国旅行、南のリゾート地でのエステ三昧、こうしたメニューが話題に上ることは少なくなった。収入が増えないデフレマインドが充満した時代であると言えばそうであるが、健康も、美容も、過剰であったことを削ぎ落とし、「ルーツに遡る」つまり普通に戻ったということだ。
 かなり前になるが日経MJに「フットパス」の記事が載っていた。森や田園、古い街並を散策する英国発祥のリフレッシュ法で愛好家が増えているとある。10年ほど前にベストセラーとなった「えんぴつで奥の細道」の、その書を担当された大迫閑歩さんの言葉を思い出す。”紀行文を読む行為が闊歩することだとしたら、書くとは路傍の花を見ながら道草を食うようなもの”という言葉である。大迫閑歩さん風にいうなら、フットパスは心と身体の道草、お金のかからない健康法であろう。
かなり前になるが日経MJに「フットパス」の記事が載っていた。森や田園、古い街並を散策する英国発祥のリフレッシュ法で愛好家が増えているとある。10年ほど前にベストセラーとなった「えんぴつで奥の細道」の、その書を担当された大迫閑歩さんの言葉を思い出す。”紀行文を読む行為が闊歩することだとしたら、書くとは路傍の花を見ながら道草を食うようなもの”という言葉である。大迫閑歩さん風にいうなら、フットパスは心と身体の道草、お金のかからない健康法であろう。
あるいは、私の友人もそうであるが、日常の健康法として、通勤時一駅分を歩くビジネスマンが増加しており、「一駅族」と呼ばれている。10数年前にシニアのハイキングブームからウオーキングへ、最近ではフットパスや一駅族まで、自分で歩く健康法はお金をかけない方法である。その根底にある価値観は、激変する環境への自己防衛、自活、自助、自己解決へと向かっている潮流の中にあるということだ。
冒頭の摂取カロリーのグラフではないが、日常の食事をバランスよく摂取カロリーを控える食事メニューの提供に注目が集まったのがタニタ食堂であった。1回の食事はほぼ500kcalに抑えられている。東京丸の内のビルの地下にある食堂である。価格もリーズナルブルで近隣のビジネスマンに好評で、以降他の地域にも同様のタニタ食堂が出店している。
また、鹿児島にある鹿屋体育大学は、皇居をジョギングするアスリート向けの食堂を東京竹橋に作ったのだが、これもアスリートだけでなく近隣のビジネスマンの人気となり、いかに日々のカロリー管理を含めた健康メニューが大切であると認識されているかがわかる。
その日々の食事メニューを提供しているcookpadではライザップではないが、「ただしく食べて痩せる」をポリシーに専属のパーソナル・ダイエットトレーナーによる有料カウンセリングが行われている。
そして、自己解決型健康に欠かせないのが「今」という時代ならではのインターネットを活用した「モバイルヘルスケア」であろう。今や万歩計のような記録だけでなく、摂取した食べ物のカロリーなど。そうした記録をもとに健康維持に役立つトレーニングメニューの提供と管理などそのアプリは多岐にわたっている。モバイルアプリというとゲームを思い浮かべるが、実は数年先には世界の市場規模としては350億ドルを超えると言われている。アプリのプラットフォームはアップルのiOSとグーグルのandroidでそのシェアは75%。そのビジネスモデルは現在の有料アプリからインターネットサイトと同じように広告によって収益を上げる無料化へと進展していくと推測されている。但し、「ポケモンGO!」によってゲームアプリが注目されているが、ここ数年こうしたゲームアプリの供給が過剰になり、ダウンロード数は横ばい状況となっている。こうした中、健康アプリはまだまだ成長の可能性が見込まれる。健康長寿大国である日本こそ独自なアプリ開発に集中すべきであろう。
また自己解決法としてブームとなっているのが糖質ダイエットである。痩せるという結果が出るからといって糖質ダイエットに傾倒する若い女性が多くなっている。炭水化物を極端に取らない自己流は危険であると多くの医師が警鐘を鳴らしている。痩せるという見た目の結果からはわからない隠れメタボ、中性脂肪は逆に増えてしまう。あるいは脳の働きが悪くなり、更にだるい体調の日が続く、とも言われている。命を育む体は、ファッションのようにブームが終われば着なくて済むわけにはいかない。自己解決法にも落とし穴があるということだ。
成熟時代の新たな概念、ライフデザイン
一定の物質的豊かさを手に入れたが、精神的豊かさはどうかという課題もあるが、それは個人化社会における自立した「個」が未だ成長段階にあることから、一概に結論には至らない。これから先も常に成長段階ということになるかと思うが、成熟社会の入り口に来ていることだけは間違いない。しかし、成熟とは何か、100人に聞けば100通りの答えがあるので、誰もこれだと決めつけることはできない。
そうした大仰に構えた考えとしての「成熟」ではなく、もう少し狭い消費生活という視座に立てば、人間の持つ欲望を自らコントロールできる時代に向かっている。
ところでライフスタイルという言葉がある。私もよく使う言葉であるが、生活の様式・営み方を指し示すことだが、実はその裏側には多様な価値観が潜んでおり、時として「消費行動」を左右する。。その多様な価値観の中でも生命観や人生観といった個人の生き方が生活に占めることが年々大きくなった感がしてならない。食であれば、生きるために必要な食から楽しむ食への転換が良き事例である。その「楽しむ」という欲をはじめ、もう少し意志的な考えに基づいた欲もある。豊かさとはこうした欲の変化の多様性が叶う時代になったということであろう。
ライフスタイルという概念だけでなく、多様な「欲」、1980年代以降社会の表舞台に出てきた「欲」を包含した概念が必要となっている。私はその概念を「ライフデザイン」と呼び、次のような図解で表現してきた。
次の図解は生活全般についてであるが、今までの生活・ライフスタイルは「人生観」と「生命観」によって再編集されるという仮説である。この仮説の背景には市場が心理によって動く時代を迎えていることが最大の要因となっている。逆の言い方をするならば、心理が働くほど「豊かに」なったということである。
前述の「フットパス」などはシニア世代に人気となっているが、これもここまで生きてきたという道草人生観が強く出てきた行動である。また、シニア世代のジョギングもブームになっているが、そのスポーツウエアはカラフルというより派手な柄のウエアでこれも少女の如き衣装となっている。いつまでも若く少女でありたい、そんな心理がウエアにも表れているということである。こうした生活生命化市場と呼ぶにふさわしい市場、「生きていること」を感じさせてくれるような市場はこれからますます拡大していくであろう。
あるいは「パワーリング」というキーワードで言うとすれば、沖縄の長命草などを使った野草料理などはまさに生命活性食、元気食、パワーフーズと言えよう。今や若い女性の間では神社巡りなどのパワースポットブームとなっているが、沖縄の野草料理は一部ハーブとして使われているだけで、主菜として美味しく食べさせる工夫や店舗がほとんど無い。お手本とすべきはアリス・ウオータースの食育菜園のように、素材だけでなくメニューとしてレストランとしてやっていくような運動が必要であろう。こうした芽の一つが日本の場合は農家レストランであるが、まだまだ田舎料理レベルが多く、もう少しコンセプト的なメニュー業態、しかも日常業態を目指すべきである。

心理市場を解く鍵、ライフデザイン
こうしたことは沖縄以外の地方に埋もれている食材・料理も同様である。東京には多くの地方のアンテナショップがあり、中にはレストランを併設させている店もある。しかし、アリスのようなコンセプト&テーマを持って運営しているアンテナショップは聞いたことがない。
私もアンテナショップをつくるプロジェクトに携わったことがあるが、現在のアンテナショップは単なる食材のPRやお土産的物産販売にとどまっている。これからは上記の図解にならって言うとすれば、生活の文化化、つまりその土地ならではの文化食を特徴とするようなコンセプトとなる。アンテナショップも個々の地域文化を楽しめるような場所への進化が必要な時期に来ている。
ところで上記図解に人生観とあるが、例えば前回の未来塾「回帰から見える未来」で書いたようにシニア世代では懐かしさもあって給食メニューを食べたいと思うことがある。しかし、こうした懐かしさは若い世代にとっても同様に持っている。そんな商品の一つが揚げパンでコンビニのヒット商品になったこともある。どちらも「思い出消費」であり、思い出時間の長短はあっても、当時を思い起こさせる人生観に裏付けされた心理市場のことである。
そして、ここでは生命観、人生観を新たな価値軸としたが、他にもシニア世代になれば終活としての死生観も生活編集の鍵となる。また、独身男女が30歳前後になれば恋愛観・結婚観も当然出てくる。こうした価値観が大きく消費生活をも変えていく。これが心理市場を構成する新たな生活編集の鍵となる。
今回は生きるための食から、楽しむ食へ、更には「健康・からだ・食」という多様な食へと大きくパラダイムの転換が進み、そうした豊かさから見える未来を考えてみた。市場は心理化してきたと言われてから10数年経つ。それまでは顧客心理は広告はじめとした情報によって動かすことができると考えられてきたが、生活者は多くの体験学習により一定の方向に向かっていることがわかってきた。ある意味、従来の欲望とは異なる欲望消費に向かっていることだけは確かである。例えば、環境に優しいエコライフもそうであるし、物をできる限り持たない断捨離という暮らし方もそうした新たな欲望の一つである。過剰なまでの「健康」に囲まれながら、こころはどこへ向かうか、それを見極めることこそがビジネスの鍵となる時代だ。(続く)
注) 「アリス・ウオータース」:世界にスローフードを普及させ、アメリカで最も予約が取れないと言われるレストラン「 シェ・パニース」のオーナーでもある。

パラダイム転換から学ぶ
戦後の物不足・欠乏の時代を終え、1980年代以降生きるための食から健康のための食へと大きくパラダイムの転換が起きてきた。そして、その質的変化を表したのが表紙のカロリー摂取量のグラフで、終戦後間もない頃と比較し、経済的豊かさにも関わらず、新たな豊かさを象徴するかのようにカロリー摂取量は減少する。そして、スーパーの食品売り場には、糖質0、カロリーオフ、トクホ(特定保健用食品 )といった表示商品が棚に並んでいる。過剰な情報時代というが、「健康」もまた過剰な時代となり、どんな「健康」を選択したら良いのかわからない時代を迎えている。
一方、物の豊かさの陰には新たな問題も生まれている。肥満による成人病という現代病から始まり、過食や拒食といった摂食障害という病も10~20代の女性の間で出てきている。ストレス社会ならではの病であるが、その発症のきっかけがダイエットであると専門家は指摘する。あるいは無菌社会と呼ぶ専門家もいるが、アトピーやアレルギーといった免疫疾患も生まれてきている。免疫力の低下とは、身体の持つ自然力・生命力の低下でもある。このパラダイムは今後どんな方向へと向かうのか、仮説を含め考えてみたい。
江戸時代にもあった飽食の是正
前回の未来塾「江戸と京」では、その江戸という町の都市化の構造を京との関係の中で考えてみた。そして、江戸時代における生活は1日の食事が2回から3回になり、屋台のような外食産業が栄え、しかも24時間化も進展していた。元禄時代をバブル期と呼ぶ専門家もいるが、今日の「健康・からだ・食」を彷彿とさせるような現象も起きていた。
 例えば、当時は既に大食いコンテストも行われ、江戸の豊かさの象徴として「江戸に行けば銀シャリが食べられる」と言われ、幕府の人返し令にもかかわらず、多くの人が地方から江戸へと向かった。当時は1日の食事量としては白米5合ほど食べられていたと言われている。しかも、豆腐や野菜、魚も食べられていたが、その量は極めて少なく、一汁一菜と言われているように、主食の白米がほとんどであった。結果、江戸の武士階級を中心に「脚気患者」が増加する。ビタミンB1の欠乏症による末梢神経障害であるが、「江戸わずらい」と呼ばれていた。
例えば、当時は既に大食いコンテストも行われ、江戸の豊かさの象徴として「江戸に行けば銀シャリが食べられる」と言われ、幕府の人返し令にもかかわらず、多くの人が地方から江戸へと向かった。当時は1日の食事量としては白米5合ほど食べられていたと言われている。しかも、豆腐や野菜、魚も食べられていたが、その量は極めて少なく、一汁一菜と言われているように、主食の白米がほとんどであった。結果、江戸の武士階級を中心に「脚気患者」が増加する。ビタミンB1の欠乏症による末梢神経障害であるが、「江戸わずらい」と呼ばれていた。ある意味現代における飽食生活と同じで、「健康・からだ・食」に対し警鐘を鳴らし啓蒙活動を行ったのが『養生訓』を書いた儒学者の貝原益軒であった。長寿を全うするための身体の養生だけでなく、精神の養生も説いているところに特徴があり、今日の振子消費のように揺れ動く心理状況にも的確な示唆をしてくれている。貝原益軒は内なる4つの欲望を抑え、我慢することによって長寿が得られると説いている。その4つであるが、ウイキペディアによれば
1、あれこれ食べてみたい食欲
2、色欲
3、むやみに眠りたがる欲
4、徒らに喋りたがる欲
江戸時代は乳幼児の死亡率が高く、今日の平均寿命と単純比較はできないが、一般的には50歳程度と言われている。しかし、実際には30~40歳ほどではないかという説もある。ちなみに、自ら「養生訓」を実践した貝原益軒は85歳で亡くなったと言われている。
沖縄料理から学ぶ;「ルーツに遡る」
戦後米軍統治下にあって、SPAMに代表される加工肉を日常的に食べてきた沖縄の人たち、特に男性については肥満度全国No1という事実によって「健康・からだ・食」という問題の所在は明らかになっている。そうした事実を踏まえ、県も盛んに是正策、長野県などをモデルに幾つかの施策、職場健診などを行っているようだ。
実は沖縄の食文化を調べていくと分かるが、一時期までの長寿の島である所以はその歴史、伝統料理に残されている。”美味しゅうございます”という決めセリフで知られている料理ジャーナリストである故岸朝子さんは沖縄生まれであった。その岸さんは沖縄の中でも一番の長寿村であるやんばるの森に囲まれた大宜味村の元村長との対談の中で、「私の子供の頃は食べるものも少なく, 生活が大変だった。飽食しない,食べ過ぎないのがいいということでしょう」と。まさに養生訓の言葉通りである。
沖縄には命草(ぬちぐさ)という言葉がある。語の意味そのもので命を支え育む草のことで、沖縄にはどこにでもある野草のことである。その代表植物が長命草で、沖縄ではよく知られたセリ科の植物である。
そして、その沖縄の歴史であるが、琉球王朝は,中国から来た冊封使を接待するために福建省へ料理人を派遣して,中国料理を勉強させたと言われている。更には島津藩の支配が始まると,日本の役人を接待するために,鹿児島へ料理人を派遣して,日本料理を勉強させる。 中国や日本の料理は,始めは接待料理であったが,次第に庶民の間に広がって,沖縄料理にバリエーションが増えていく。
 沖縄という島の地政学上からであると思うが、実はインドネシアからは,「ゴーヤーチャンプルー」で有名なチャンプルー(混ぜ合わせる)料理も伝わって来ている。沖縄にはよく食べる家庭料理の一つにヒラヤーチーがあるが、これも韓国のチヂミが源流だと考えられている。
沖縄という島の地政学上からであると思うが、実はインドネシアからは,「ゴーヤーチャンプルー」で有名なチャンプルー(混ぜ合わせる)料理も伝わって来ている。沖縄にはよく食べる家庭料理の一つにヒラヤーチーがあるが、これも韓国のチヂミが源流だと考えられている。このように沖縄の料理は,昔から伝えられていた郷土料理に中国,日本,朝鮮,東南アジアのいろいろな国の料理が融合して 成立した、これが沖縄料理の歴史である。
私は日本文化を東京渋谷のスクランブル交差点のようだと指摘をしたが、そうした東京以外の沖縄もまさに東アジア~東南アジアの海道の交差点となっている。「ルーツに遡る」ならばチャンプルー(融合)こそが健康長寿の源であるということである。
岸朝子さんが整理した沖縄長寿食の特徴は以下となっている。
(1)良質のタンパク質
(2)長寿を支える緑黄色野菜
(3)サツマイモでバランスのとれた食生活
(4)ミネラル豊富な海藻類
(5)塩分を抑える調理法
(6)生き甲斐のある暮らし
上記の特徴は沖縄料理のどんなところにその工夫があるのか、いくらでも書けるがこのブログは料理レシピのブログではないので割愛する。実はこうした特徴は長野県をはじめ地方の郷土食の多くが有している特徴である。全国の学校給食においても地産地消・食育を含め郷土食を取り入れ始めている。更には、京野菜や加賀野菜だけでなく、地方に埋もれた伝統野菜の復活も始まっている。こうした地方に埋もれた、あるいは忘れられ過去となってしまった郷土料理の復活こそが待たれている。但し、過去をそのまま復活させることではなく、「今」を味わうことのできる郷土料理であることは言うまでもない。地方の生活に今なお残されている伝統料理、京都で言うならば「おばんざい料理」に次なる可能性の芽があるということである。
健康におけるグローバリズムとローカリズム
2016年世界保健機関(WHO)が発表した世界保健統計2016によると、世界一の長寿国は前年同様日本で男女平均が83.7歳だった。長寿大国ということはある意味裾野の広い食を中心とした健康産業大国ということである。サブカルチャーのクールジャパンと共に、長寿の国のライフスタイルはこれからの輸出産業の中心となりえる。その第1番目が「日本食」である。ある意味日本型LOHASを世界へと輸出するということだ。
少子高齢化をマイナス面でしかとらえられない発想の貧困さには辟易してしまうが、ポジティブに見ていく視座を持てば宝の山となる。日本の場合、ips細胞といった先端再生医療から食生活まで、世界における固有な健康資源を保有している。今までは若い世代を中心に海外セレブの健康法などトレンドとして取り入れてきた。しかし、例えば従来からの発想であるアンチエイジング=若返りという発想から、老いる=成熟という美しさへの発想へと、実はシニア生活の転換が始まっている。勿論、若い世代において若返り・美容についてはこれからもトレンドとして取り入れていくと思うが、老年を迎える団塊世代にとっても健美同源、つまり年相応の健康である美しさへと価値観は変わっていく。そんな事例ではないが、私の住む世田谷砧には大きな公園があり、老若男女がジョギングしている。遠くから見る限り年齢は全く識別できない。それはファッションもさることながら、走るスピードやスタイルによっても識別できないということである。いかに元気な若々しいシニアが多いかである。
独居老人の孤独死といった負の側面もあるが、長寿の国のライフスタイルを輸出していくといった発想、欧米諸国が既に認識している日本食を健康ダイエット食として売っていく、そうした試みが必要な時を迎えているということだ。
台湾には台湾素食という菜食主義料理がある。日本における精進料理に近いもので「もどき料理」もあるようだ。日本ではあまり注目はされていないが、着目すべきは「素」にある。素という、そのまま、自然体であること、そんなライフスタイルこそが健康の源である。そして、その素はまずは郷土料理に残されている。そんなローカルフードこそグローバル市場を開拓する新たな戦略ツールとなり得る。
ところで以前「消費都市TOKYO」というテーマで、市場の特性について考えたことがあった。結論からいうと、東京はグローバルなTOKYOという市場と地球市場から見ればローカルな東京という市場の2つの市場から成り立っている「グローカル市場」だ。つまり、TOKYOという市場を狙うことはそのままグローバル市場につながっている。また、国内市場という視点に立つと東京という都市市場の2つの側面、前回は江戸と京についてその構図を明らかにしたが、まさに混在したスクランブル交差点市場となっている。どんな市場を狙うのか、誰を顧客とするのかが最も重要なテーマとなっている。東京は一つの地球都市国家として見ていくことが必要で、そこには都市と地方が混在しているということだ。別の視点で見れば、グローバル市場への玄関口でもあり、世界へ向けた一大実験市場、テストの場でもある。例えば、ヒット商品という視点に立てば、一昔前にはルイヴィトンがパリ観光のお土産であったように、東京でのお土産あるいは記念品といったことが大きなビジネスチャンスとなるであろう。
訪日外国人、特に中国人観光客の家電製品に見られた爆買いは終わり、ドラッグストアに化粧品や目薬などを買い求める訪日外国人が増えている。そして、富士山観光は一巡し、富士山登山や花見や花火に興味関心は移ってきている。食についてもラーメンと共に、しゃぶしゃぶの食べ放題といった日本人の実生活にどんどん入り込んできた。つまり、日本人のライフスタイルそのものに興味関心は移っているということである。ビジネスチャンスが変化していることに気づかないのが日本人ということだ。
過剰情報の時代にあって
過剰な情報の時代にあって、どう取捨選択したら良いのか誰もが考えざるをえない時代にいる。2008年の直木賞に天童荒太の「悼む人」が選ばれた。読まれた方も多いと思うが、マスメディアから流される過剰な情報の中で「何」が自分にとって必要で、大切な情報なのか、その疑念から「悼む人」が書かれたという。亡くなった人を訪ね、その死の扱われ方を聞くことによって自身の心変わりをテーマとした小説である。生前どのように生き切っていたかを探し求めた小説であるが、情報の持つ意味合いを考えさせる小説である。マスメディアから流される情報、いや流されない情報の裏側で「何」が起こっていたのかを気づかせてくれた小説であるが、実は生活者がこうした裏にある事実へと気づき手に入れ始めた時代と言えよう。裏にある何か、それは自らの想像力によってであるが、今や過剰な情報が行き交う時代であるが故に、情報の裏にある何かへと想像に向かわさせる。
どんな人が、どんな場所で、いつどのように作られているのか、こうした産地見学や自ら無農薬による菜園作りが進んでいるのもこうした想像の故である。圧倒的に足りないのは実体験、追体験、そのリアリティの時代にいるという事実である。
同様にダイエットにおいても、ライザップ(RIZAP)のように「結果にコミットした徹底サポート」と言った特徴に人気が集まった。如何に「結果」の得られないダイエットが多かったかである。実績として2016年現在、2ヶ月という短期間で99%のお客様がライザップでダイエットに成功していると。ただし、リアルな結果を得るには、入会金は5万円、コース料金で29万8千円とかなり高額である。
商品に対し、サービスに対し、更には企業に対し、顧客が想像力を働かせる時、つまりどれだけリアルな結果を提供できるか、実質を約束出来るか、それを可能とする本当のプロ、専門家しか生き残ることはできないということである。既に情報だけのイメージだけの競争は終わっているということである。私たちがそのことに思い至らなければ、消費の輪郭は明らかにはならないということである。
自己解決型健康法の時代へ
ひと頃ブームとなっていたプチ整形の韓国旅行、南のリゾート地でのエステ三昧、こうしたメニューが話題に上ることは少なくなった。収入が増えないデフレマインドが充満した時代であると言えばそうであるが、健康も、美容も、過剰であったことを削ぎ落とし、「ルーツに遡る」つまり普通に戻ったということだ。
 かなり前になるが日経MJに「フットパス」の記事が載っていた。森や田園、古い街並を散策する英国発祥のリフレッシュ法で愛好家が増えているとある。10年ほど前にベストセラーとなった「えんぴつで奥の細道」の、その書を担当された大迫閑歩さんの言葉を思い出す。”紀行文を読む行為が闊歩することだとしたら、書くとは路傍の花を見ながら道草を食うようなもの”という言葉である。大迫閑歩さん風にいうなら、フットパスは心と身体の道草、お金のかからない健康法であろう。
かなり前になるが日経MJに「フットパス」の記事が載っていた。森や田園、古い街並を散策する英国発祥のリフレッシュ法で愛好家が増えているとある。10年ほど前にベストセラーとなった「えんぴつで奥の細道」の、その書を担当された大迫閑歩さんの言葉を思い出す。”紀行文を読む行為が闊歩することだとしたら、書くとは路傍の花を見ながら道草を食うようなもの”という言葉である。大迫閑歩さん風にいうなら、フットパスは心と身体の道草、お金のかからない健康法であろう。あるいは、私の友人もそうであるが、日常の健康法として、通勤時一駅分を歩くビジネスマンが増加しており、「一駅族」と呼ばれている。10数年前にシニアのハイキングブームからウオーキングへ、最近ではフットパスや一駅族まで、自分で歩く健康法はお金をかけない方法である。その根底にある価値観は、激変する環境への自己防衛、自活、自助、自己解決へと向かっている潮流の中にあるということだ。
冒頭の摂取カロリーのグラフではないが、日常の食事をバランスよく摂取カロリーを控える食事メニューの提供に注目が集まったのがタニタ食堂であった。1回の食事はほぼ500kcalに抑えられている。東京丸の内のビルの地下にある食堂である。価格もリーズナルブルで近隣のビジネスマンに好評で、以降他の地域にも同様のタニタ食堂が出店している。
また、鹿児島にある鹿屋体育大学は、皇居をジョギングするアスリート向けの食堂を東京竹橋に作ったのだが、これもアスリートだけでなく近隣のビジネスマンの人気となり、いかに日々のカロリー管理を含めた健康メニューが大切であると認識されているかがわかる。
その日々の食事メニューを提供しているcookpadではライザップではないが、「ただしく食べて痩せる」をポリシーに専属のパーソナル・ダイエットトレーナーによる有料カウンセリングが行われている。
そして、自己解決型健康に欠かせないのが「今」という時代ならではのインターネットを活用した「モバイルヘルスケア」であろう。今や万歩計のような記録だけでなく、摂取した食べ物のカロリーなど。そうした記録をもとに健康維持に役立つトレーニングメニューの提供と管理などそのアプリは多岐にわたっている。モバイルアプリというとゲームを思い浮かべるが、実は数年先には世界の市場規模としては350億ドルを超えると言われている。アプリのプラットフォームはアップルのiOSとグーグルのandroidでそのシェアは75%。そのビジネスモデルは現在の有料アプリからインターネットサイトと同じように広告によって収益を上げる無料化へと進展していくと推測されている。但し、「ポケモンGO!」によってゲームアプリが注目されているが、ここ数年こうしたゲームアプリの供給が過剰になり、ダウンロード数は横ばい状況となっている。こうした中、健康アプリはまだまだ成長の可能性が見込まれる。健康長寿大国である日本こそ独自なアプリ開発に集中すべきであろう。
また自己解決法としてブームとなっているのが糖質ダイエットである。痩せるという結果が出るからといって糖質ダイエットに傾倒する若い女性が多くなっている。炭水化物を極端に取らない自己流は危険であると多くの医師が警鐘を鳴らしている。痩せるという見た目の結果からはわからない隠れメタボ、中性脂肪は逆に増えてしまう。あるいは脳の働きが悪くなり、更にだるい体調の日が続く、とも言われている。命を育む体は、ファッションのようにブームが終われば着なくて済むわけにはいかない。自己解決法にも落とし穴があるということだ。
成熟時代の新たな概念、ライフデザイン
一定の物質的豊かさを手に入れたが、精神的豊かさはどうかという課題もあるが、それは個人化社会における自立した「個」が未だ成長段階にあることから、一概に結論には至らない。これから先も常に成長段階ということになるかと思うが、成熟社会の入り口に来ていることだけは間違いない。しかし、成熟とは何か、100人に聞けば100通りの答えがあるので、誰もこれだと決めつけることはできない。
そうした大仰に構えた考えとしての「成熟」ではなく、もう少し狭い消費生活という視座に立てば、人間の持つ欲望を自らコントロールできる時代に向かっている。
ところでライフスタイルという言葉がある。私もよく使う言葉であるが、生活の様式・営み方を指し示すことだが、実はその裏側には多様な価値観が潜んでおり、時として「消費行動」を左右する。。その多様な価値観の中でも生命観や人生観といった個人の生き方が生活に占めることが年々大きくなった感がしてならない。食であれば、生きるために必要な食から楽しむ食への転換が良き事例である。その「楽しむ」という欲をはじめ、もう少し意志的な考えに基づいた欲もある。豊かさとはこうした欲の変化の多様性が叶う時代になったということであろう。
ライフスタイルという概念だけでなく、多様な「欲」、1980年代以降社会の表舞台に出てきた「欲」を包含した概念が必要となっている。私はその概念を「ライフデザイン」と呼び、次のような図解で表現してきた。
次の図解は生活全般についてであるが、今までの生活・ライフスタイルは「人生観」と「生命観」によって再編集されるという仮説である。この仮説の背景には市場が心理によって動く時代を迎えていることが最大の要因となっている。逆の言い方をするならば、心理が働くほど「豊かに」なったということである。
前述の「フットパス」などはシニア世代に人気となっているが、これもここまで生きてきたという道草人生観が強く出てきた行動である。また、シニア世代のジョギングもブームになっているが、そのスポーツウエアはカラフルというより派手な柄のウエアでこれも少女の如き衣装となっている。いつまでも若く少女でありたい、そんな心理がウエアにも表れているということである。こうした生活生命化市場と呼ぶにふさわしい市場、「生きていること」を感じさせてくれるような市場はこれからますます拡大していくであろう。
あるいは「パワーリング」というキーワードで言うとすれば、沖縄の長命草などを使った野草料理などはまさに生命活性食、元気食、パワーフーズと言えよう。今や若い女性の間では神社巡りなどのパワースポットブームとなっているが、沖縄の野草料理は一部ハーブとして使われているだけで、主菜として美味しく食べさせる工夫や店舗がほとんど無い。お手本とすべきはアリス・ウオータースの食育菜園のように、素材だけでなくメニューとしてレストランとしてやっていくような運動が必要であろう。こうした芽の一つが日本の場合は農家レストランであるが、まだまだ田舎料理レベルが多く、もう少しコンセプト的なメニュー業態、しかも日常業態を目指すべきである。

心理市場を解く鍵、ライフデザイン
こうしたことは沖縄以外の地方に埋もれている食材・料理も同様である。東京には多くの地方のアンテナショップがあり、中にはレストランを併設させている店もある。しかし、アリスのようなコンセプト&テーマを持って運営しているアンテナショップは聞いたことがない。
私もアンテナショップをつくるプロジェクトに携わったことがあるが、現在のアンテナショップは単なる食材のPRやお土産的物産販売にとどまっている。これからは上記の図解にならって言うとすれば、生活の文化化、つまりその土地ならではの文化食を特徴とするようなコンセプトとなる。アンテナショップも個々の地域文化を楽しめるような場所への進化が必要な時期に来ている。
ところで上記図解に人生観とあるが、例えば前回の未来塾「回帰から見える未来」で書いたようにシニア世代では懐かしさもあって給食メニューを食べたいと思うことがある。しかし、こうした懐かしさは若い世代にとっても同様に持っている。そんな商品の一つが揚げパンでコンビニのヒット商品になったこともある。どちらも「思い出消費」であり、思い出時間の長短はあっても、当時を思い起こさせる人生観に裏付けされた心理市場のことである。
そして、ここでは生命観、人生観を新たな価値軸としたが、他にもシニア世代になれば終活としての死生観も生活編集の鍵となる。また、独身男女が30歳前後になれば恋愛観・結婚観も当然出てくる。こうした価値観が大きく消費生活をも変えていく。これが心理市場を構成する新たな生活編集の鍵となる。
今回は生きるための食から、楽しむ食へ、更には「健康・からだ・食」という多様な食へと大きくパラダイムの転換が進み、そうした豊かさから見える未来を考えてみた。市場は心理化してきたと言われてから10数年経つ。それまでは顧客心理は広告はじめとした情報によって動かすことができると考えられてきたが、生活者は多くの体験学習により一定の方向に向かっていることがわかってきた。ある意味、従来の欲望とは異なる欲望消費に向かっていることだけは確かである。例えば、環境に優しいエコライフもそうであるし、物をできる限り持たない断捨離という暮らし方もそうした新たな欲望の一つである。過剰なまでの「健康」に囲まれながら、こころはどこへ向かうか、それを見極めることこそがビジネスの鍵となる時代だ。(続く)
注) 「アリス・ウオータース」:世界にスローフードを普及させ、アメリカで最も予約が取れないと言われるレストラン「 シェ・パニース」のオーナーでもある。
2016年10月03日
未来塾(25)「パラダイム転換から学ぶ」 健康時代の未来 (前半)
ヒット商品応援団日記No659(毎週更新) 2016.10.3.
今回の「パラダイム転換から学ぶ」では、戦後昭和から今日に至る中で一番変化が大きかった「食」を通じた価値観の変化を取り上げることとする。「食」は日常であり、経済的豊かさにあって変化が最も出やすい世界である。そして、ほとんどの人が実感できるものである。そうした価値観変化はいつ頃からどのような変化として現れてきたか、そしてこれからどのような変化が生まれてくるであろうか、そうした推測を含め、その劇的変化について学ぶこととする。

このグラフは日本人の1日あたりのカロリー摂取量の推移グラフである。戦後直後の物資のない窮乏時代のカロリー摂取量はわずか1903Calであった。その後経済成長と共に所得も増え生活の豊かさが進み摂取Calも増えたが、1980年代に入り急激に摂取量は減少へと向かう。そして、既に摂取Calはその戦後直後を大きく下回るレベルへと進み数年前に話題となった。この摂取Calの内容の違いに生活価値観の劇的な変化が現れている。戦後71年物質的豊かさはどのように変化し、どこに向かっているのか、その変化はライフスタイルの根底を成している日常の「食」に明確に現れている。今回はこの大きな転換、豊かさの意味について「食」を通じて学んでみることとする。
カロリー不足・栄養不足を補う給食
カロリー摂取量の多くは日常の食生活によるものだが、戦後昭和の時代の学校給食の歴史を見ていくとカロリー不足、栄養不足をいかに給食で補っていたかがわかる。
全国学校給食会連合会(全給連によれば、学校給食の始まりは明治22年(1889年)、山形県鶴岡町(現鶴岡市)の私立忠愛小学校だといわれているが、まずは戦後の学校給食を見ていくこととする。昭和21年(1946年)に、文部・厚生・農林三省から「学校給食実施の普及奨励について」が出され、12月24日、東京・神奈川・千葉で学校給食が開始される。当時は全国都市の児童約300万人に対し学校給食がはじまり、米国から無償で与えられた脱脂粉乳が使われる。
そして、昭和25年(1950年)、米国からの小麦粉を使い、8大都市の 小学生児童対象の完全給食がおこなわれルようになる。(以下の写真は千葉県学校給食会による。)
 写真は昭和29年(1954年)の学校給食で、その当時の代表的な給食メニューである。団塊世代にとっては懐かしい鯨肉の竜田揚げが入っており、平成世代にとっては食べたことのないメニューである。そして、現在のコッペパンとは比べようがないほどパサパサのパンで、ミルクといっても脱脂粉乳によるミルクでとても美味しいとは言い難いメニューであった。つまり、生きるために必要なカロリー、栄養を取り入れることが目的の給食生活であった。
写真は昭和29年(1954年)の学校給食で、その当時の代表的な給食メニューである。団塊世代にとっては懐かしい鯨肉の竜田揚げが入っており、平成世代にとっては食べたことのないメニューである。そして、現在のコッペパンとは比べようがないほどパサパサのパンで、ミルクといっても脱脂粉乳によるミルクでとても美味しいとは言い難いメニューであった。つまり、生きるために必要なカロリー、栄養を取り入れることが目的の給食生活であった。
こうしたいわゆるパン食が主流であった給食は 昭和51年(1976年)以降米飯給食が開始される。そして、コッペパンの時代と比べてメニューの種類が増え、勿論味の面でもよくなる。そして、カレーライスのように今日のメニューに近いものが提供されるようになる。
 そして、平成の時代の給食はどうかというと栄養バランスもよく考えられた、おいしい給食が出されるようになり、戦後間もない頃の給食と比べ一段と豪華になったと言える。ちなみに下記のメニューには手巻きずしなどが入っており、ある意味家庭ではあまり作られない半歩先のメニューも出されるようになる。おふくろの味は給食によって作られてきたと言っても過言ではない。
そして、平成の時代の給食はどうかというと栄養バランスもよく考えられた、おいしい給食が出されるようになり、戦後間もない頃の給食と比べ一段と豪華になったと言える。ちなみに下記のメニューには手巻きずしなどが入っており、ある意味家庭ではあまり作られない半歩先のメニューも出されるようになる。おふくろの味は給食によって作られてきたと言っても過言ではない。
 ところでネット上で紹介されている親世代と現代っ子の人気メニューランキングは、ほぼ以下となっている。
ところでネット上で紹介されている親世代と現代っ子の人気メニューランキングは、ほぼ以下となっている。
●親世代の給食人気ランキング
第1位「揚げパン」(53.9%)
第2位「カレーライス」(52.3%)
第3位「ソフト麺」(47.1%)
第4位「炊き込みご飯」(27.6%)
第5位「わかめご飯」(26.2%)
●現代っ子の給食人気ランキング
第1位「鶏のから揚げ」(74.3%)
第2位「ハンバーグ」(71.6%)
第3位「カレーライス」(67.3%)
第4位「オムライス」(57.4%)
第5位「スパゲティ」(56%)
米飯の工夫もあるが、やはり食の洋風化とその多様なメニュー、そして健康を考えたバランスの良い食育メニューが用意され、戦後の生きるための「食」から大きく転換したことがわかる。
摂取食品の変化
ところで生活費に占める食費の比率をエンゲル係数と呼び、1970年代までは一つの豊かさのレベルの指標として使われてきた。いつからエンゲル係数が死語となったか定かではないが、カロリー摂取量が下がり始める1980年代と推測される。
この1980年代の変化は1日あたりの食品の摂取量(g)の変化となって表れている。以下のグラフを見ればわかるが、主食である米飯の摂取量は昭和30年代の半分以下となっている。(途中から米飯の単位が変わっているので下記の注を参照のこと)また、一番伸びが大きいのが乳類と肉類で、洋風化を摂取食品群からも見ることができる。

注)平成 13 年から米類については調理を加味した値(g)に変更している。つまり平成 12 年 の値は、炊く前のコメの量、平成 17 年は炊いた後のご飯の量で示している 。そのようにグラフを見れば米の摂取量は同じような右肩下がりとなり、既に言われているように昭和30年代の半分以下となっていることがわかる。
高度経済成長期からバブル期へ
1955年から1973年まで、日本の実質経済成長率は年平均10%を超え、欧米の2~4倍にもなった。朝鮮特需から始まり、神武景気( 31ヵ月 )、岩戸景気( 42ヵ月 )、東京オリンピック景気24ヵ月 )、いざなぎ景気( 57ヵ月 )、いわゆる高度経済成長期は1973年の第一次石油ショックで終わる。この高度経済成長期に流行った言葉に3C・3種の神器(車、クーラー、カラーテレビ)がある。こうした新商品をどんどん生活のなかに取り入れてきた時代で、まだまだ物不足、物を満たすために働いていた時代であった。
 その後も安定成長を続け、所得も増え、一億総中流時代と呼ばれる時代となる。
その後も安定成長を続け、所得も増え、一億総中流時代と呼ばれる時代となる。
そして、食におけるパラダイム変化の第一弾はこの1980年代からスタートしている。戦後の生きるための食からの変化であるが、1980年代はバブルへと向かう時期であり、その方向はやはりバブル崩壊後の平成時代にはより鮮明に現れてくる。大きく言うならば、「食」においても昭和と平成の価値観が大きく変わってきているということだ。豊かさを多くの人が実感し始めた時代であった。
生きるための食から、楽しむ食、遊ぶ食へ
冒頭のカロリー摂取量のグラフに見られるように、1980年代からカロリー摂取量が極端に減少へと向かっている。この傾向は米飯の消費量の減少、乳類・肉類の増加と多様化、こうした変化と軌を一にしていることがわかる。生きるための食から、楽しむ食への転換である。1980年代に入ると、その経済的豊かさの発露として、消費の主役は団塊世代からポスト団塊世代へと移行する。特に若い女性の海外旅行が盛んになり、輸入チーズに代表されるように洋風化、多様化が更に進行する。
そして、このバブル期の食の特徴の一つが食生活における女性の変化である。当時の時代の在り方を見事に表していたのが中尊寺ゆっこが描いた漫画「オヤジギャル」であった。従来男の牙城であった居酒屋、競馬場、パチンコ屋にOLが乗り込むといった女性の本音を描いたもので多くの女性の共感を得たマンガである。女性が居酒屋でチューハイを飲む、という姿はこの頃現れ、また第一次ワインブーム、とりわけ「世界一早いボージョレヌーボー」ブームはその楽しむ食の象徴でもあった。
もう一つの特徴が物価値から情報価値への転換が始まった時期である。その代表例がロッテが発売したビックリマンチョコであった。シール集めが主目的で、チョコレートを食べずにゴミ箱に捨てて社会問題化した事件である。つまりチョコレートという物価値ではなく、シール集めという情報価値が買われていったということである。しかも、一番売れた「悪魔VS天使」は月間1300万個も売れたというメガヒット商品である。楽しむ食というより、遊ぶ食、今日のエンターテイメントフーズにつながる芽がこの頃から始まっている。
こうした豊かさは次の時代、バブル崩壊後の食を予感させるような芽が更に表れている。その代表例が二谷百合枝による「愛される理由」が75万部という1989年のベストセラーになっている。物質的には満たされたお嬢様である二谷百合枝が郷ひろみとの出会いから結婚までを描いたものだが、物は充足するが何か心は満たされていない、そんなテーマの本であった。豊かさが次の段階、精神的な豊かさ、あるいは本質的な事への回帰、健康という原点回帰へと向かう萌芽である。
そして、もう一つ着目しなければならないのが、物質的豊かさの中から、子供のアトピー、あるいはアレルギーが初めて社会問題となった時代である。
また、「ダイエット」という言葉が多くのメディアで使われるようになったのはこの時期からであった。
昭和から平成への転換

実は上記グラフを見ていただくとわかるが、バブル崩壊後も世帯収入は増え続けていた。グラフの数字は主婦のパート収入を含めた実収入の数値であり、夫婦共稼ぎが一般化し始めた時代である。また、1993年には新聞紙上に「父帰る」というタイトルと共に、当時の家庭状況が紹介されていた。残業が無くなり、主人が早く帰宅し、味噌や醤油の売れ行きが復活したことがニュースになった時代である。
そして、1997年をピークに世帯収入は急激な右肩下がりとなる。思い起こせば「デフレ」の芽が出始めた年でもある。ユニクロは本格的なSPAを始めるために社内改革をした時期であり、楽天市場がネット上で仮想商店街をつくり注目されはじめたのも1997~1998年頃であった。
前回の「パラダイム転換から学ぶ」 ”回帰から見える未来”にも書いたことだが、回帰現象という大きな現象の背景にはバブル崩壊後の「失われたものの回復」がある。そして、その中の一つが「自然・健康」の回復であると。そのメガトレンドである自然・健康生活とは食における自然の回復=取り入れであり、その先には身体の自然化でもある。まず現れたのが無農薬や減農薬の農作物であり、自然の持つ生命力が一番盛んである旬のものの取り入れが再認識される。
そして、1990年代に入ると主に次のような健康関連商品のブームが起きる。
1992年;魚に含まれるDHAが注目される
1993年:杜仲茶の血圧低減効果が知られブームとなる
1997年:赤ワインに含まれるポリフェノールの抗酸化作用に注目が集まりブームとなる
1999年:ビタミン類などの低価格サプリメントがコンビニでも発売され、市場は大きく伸びる
2000年:ザクロが更年期障害を抑える効果があると話題になる
2004年:コエンザイムQ10ブームが起きる
こうしたサプリメント市場の拡大は働く女性の増加に伴い家庭内調理が少なくなり、そうした栄養バランスを補助するものとして急成長していく。ちょうどデパ地下の中食が成長・一般化した時期と符合している。こうしたサプリメントさえ摂取すれば健康になれるといった間違ったサプリメント信仰は、2006年以降厚労省によるアガリスク製品の一部に発がん性のリスクがあると指摘され、安全性への懸念から市場は一挙に冷え込む。
更に、健康食品の効能効果に疑問が起こり始める。その代表例が関西テレビの「発掘!あるある大辞典」で、2007年1月7日放映の『納豆ダイエット問題』を皮切りに科学的根拠のない実験を行い、更にはデータの捏造すらされていたことがわかり、番組は中止となる。実はこの「発掘!あるある大辞典」のスタートは1996年10月で、この健康ブームに乗って高視聴率を上げた番組であった。「健康・からだ・食」のテーマが多く、「○○の食材が痩せる!」などと放映すれば、翌日にはその食材がスーパーなどで飛ぶように売れるという社会現象が生まれるほどであった。
こうした背景から2005年には1兆2850億円(健康産業新聞調べ)あった健康食品市場は翌年以降マイナス成長となる。(但し、2010年以降は回復し、プラス成長に向かっている。)
そして、「健康・からだ・食」という最大関心事に衝撃的な事件が起きる。2007年12月から08年1月にかけ、中国の天洋食品の冷凍ギョーザを食べた千葉、兵庫両県の計10人が下痢などの中毒症状を訴え、そのギョーザから殺虫剤メタミドホスが検出された事件である。安全という最も基本的なことを思い起こさせる契機となった事件である。
以降、食の安全性や表示偽装など内部告発を含め、社会事件として取り上げられる。
2007年:ミートホープ社による牛肉ミンチの品質表示偽装事件
2007年:老舗船場吉兆による賞味期限切れや産地偽装問題
2008年:三笠フーズによる事故米(汚染米)不正転売事件
 こうした事件が明るみに出たことにより、安全を安心へと変えるために食の「見える化」は流通を中心に広がることとなる。いわゆる「ご安心ください、私が作りました」という生産者表示や食品履歴がトレースできるような仕組みの導入など。
こうした事件が明るみに出たことにより、安全を安心へと変えるために食の「見える化」は流通を中心に広がることとなる。いわゆる「ご安心ください、私が作りました」という生産者表示や食品履歴がトレースできるような仕組みの導入など。
また、食料の自給率が40%前後の日本の場合、その多くは輸入に頼っている。つまり、見えないところで作られる食品の見える化が進むが、その対策を講じなかったのがあの日本マクドナルドであった。2014年中国で製造されたチキンナゲットの鶏肉が期限切れであったことを契機に小さな子を持つファミリーを中心に客離れが起こり、その後わずか数年の間に900数十店舗の店を閉店するという事態に至ったことは周知の通りである。
健康長寿から肥満ワースト県への変貌
本格的な人口減少時代を迎え、衰退する都市や町についてスタディした拙著「未来の消滅都市論」にも書いたことだが、周知のように「日本一長寿の県」といえば、既に沖縄県ではなく長野県である。少し古いが2013年に発表されたデータを見ても、男性が80.88歳で1位、女性が87.18歳で1位と、名実ともに全国一の長寿県となっている。この長寿の秘訣として食生活を挙げる専門家が多く、確かに塩分の多い野沢菜などを食しているが、そうした塩分を排出する野菜の摂取量が極めて多くバランスがとれた食生活を送っている。そして、かなり前から佐久病院をはじめ、予防医療が導入されてきたことも大きい。もう10年以上前になるが、「予防は治療に勝る」という「長野モデル」が提唱されていた。そして、平成2年から20年 まで1人当たりの老人医療費は全国最低額だった。つま り、長野では老人が病気にかかることなく、元気で働い ている、とも言えるだろう。社会保障費の増大が問題視されているが、抑える方法の一つは既に長野において実証されている。
ところで問題なのは長野県が長寿NO1になる迄沖縄県が長寿県であった。厚生労働省による平成22年国民健康・栄養調査では、沖縄県が全国で肥満率第1位という結果が発表され悪い意味で話題となった。平均寿命も男女ともに長年トップクラス出会ったにも関わらず2000年頃から大きく順位を下げ、今や男性は30位まで転落。女性に関しては1位から3位へ落ちたものの、健康・長寿はなんとか保ってはいる。ただし肥満率はやはり女性も全国トップである。
何故、こうした非健康な県になったのかと言えば、その最大要因は食生活にあると言われている。米国の占領下となった沖縄では、食においてもアメリカの影響を強く受けるようになる。米軍の軍用食料から供出されたポークランチョンミートやコンビーフハッシュ(コンビーフとじゃがいもを合わせたもの)など加工肉が一般に普及し、大量に消費されるようになる。若い世代では昔ながらの沖縄料理を食べる機会はどんどん減り、戦後生まれの世代は子供の頃からこのような食環境であった。沖縄県の調べでは、県民の3人に2人が脂質を過剰摂取していると。もう一つの要因としては運動をしない車社会にあると専門家から指摘されている。表現は悪いが、ある意味「健康・からだ・食」の社会実験結果の如くである。
 私は沖縄の生活文化や琉球文化に興味があり、今まで60回ほど沖縄に行っているが、沖縄の人たちが日常食べている「食堂」をよく利用している。多くの人は沖縄観光=リゾートライフ=ホテルライフ、そして、美ら海水族館をはじめとした観光地を巡り、お土産となると那覇の国際通りとなる。こうしたパターンは本島だけでなく、離島も同様である。
私は沖縄の生活文化や琉球文化に興味があり、今まで60回ほど沖縄に行っているが、沖縄の人たちが日常食べている「食堂」をよく利用している。多くの人は沖縄観光=リゾートライフ=ホテルライフ、そして、美ら海水族館をはじめとした観光地を巡り、お土産となると那覇の国際通りとなる。こうしたパターンは本島だけでなく、離島も同様である。
1990年代後半から長寿の島の代表的な食として那覇の安里にある沖縄第一ホテルの朝食が雑誌などでよく紹介されていた。勿論、私も一度だけだが食べに行ったが、野草に近い島野菜中心の30種ほどある朝食でこうした食生活であれば長寿の島になるなと納得したことを覚えている。現在は安里から中心部の牧志に移転しており、メニューも大分進化しているようだ。今風な言い方をするならば、「地産地消」の伝統的な沖縄料理である。医食同源という言葉があるが、沖縄の人たちの言葉ではこうした伝統料理を「ぬちぐすい」(ぬち=命、ぐすい=薬)と呼んでいるが、これもほとんど死語になっているようだ。
しかし、こうした食をつくれる後継者が少ないこともあって、沖縄の主要な食である豚肉がそうであるように最後まで食べきるといった調理がどんどん廃れていっている感がしてならない。沖縄も豊かになって、その豊かさは伝統的な食から米国の高脂質、加工肉中心の食へと変化し、結果こうした非健康県になった。そして、庶民の食を支えている食堂の多くは、そのメニューのボリューム・量のすごさである。沖縄の普通盛りは東京ではデカ盛りであることも肥満県の要因の一つであろう。
両極に振れる振子消費
実はこうした「健康・からだ・食」という意識が底流する中で、2007年ごろから沖縄のみならず全国的にデカ盛り、メガ盛りといったガツン系の食、高カロリーメニューが人気となる。その代表的な商品としては日本マクドナルドのダブルクオーターパウンド(828kcal)であった。こうした食の裾野には学生や若いビジネスマン以外にも、ファミリーでの食べ放題やブッフェスタイルがあることは言うまでもない。そして、特徴的なのは日経MJの2007年度ヒット商品番付の関脇にガツン系を始めとした「デカ盛りフード」がある一方、「カロリー・ゼロ・コーラ」に人気が集まる。また、日本古来の自然食であり、ローカロリー・高タンパクの豆腐が再認識される。
そして、ダイエットでは、周知のかなりハードな「ビリーズブートキャンプ」がブームになった一方、楽して痩せる「ぷるぷるフィットネス」の手軽さが人気となる。こうした価値観の反対軸にあるような商品が売れる市場の情況を当時私は「振り子消費」と呼んでいた。行ったり来たり振り子のように揺れる時代の心理市場であるが、この振り幅は以降年々小さくなって来ている。例えば10数年前にダイエット&美容のためにサプリメント依存症が問題となるような過剰さはなくなり、今ではコラーゲンのようなものへとトレンドは移行してきているということである。
こうした両極に振れる振子消費とは一線を画したものが、実は軽登山あるいはウオーキングである。今や東京の近郊にある高尾山は老若男女ばかりでなく、最近では外国人にも人気の軽登山コースとなっているが、既に20年ほど前からシニアの間では人気のコースとなっており、待ち合わせスポットになっている八王子には週末の早朝にはシニアが集まり、ちょっとしたニュースにもなっていた。
また、若い世代をはじめとしたジョギングブームが10年ほど前から起こる。そして、2015年には全国で行われるマラソン大会は197大会にも及び健康ブームの先導役を引き受けている。軽いジョギングからフルマラソンを走る人まで、そのランニング人口は1000万人を超えていると推定される。ある意味、情報によって振り子のように振れるトレンド型健康市場にあって、「健康・からだ・食」その中核を占めていると言える。
健康テーマの中心点を探る
 大きな潮流である健康というテーマではどのような振り子となっていたか、ここ数年の動きを見ていくと分かる。寒天ブームはいつ始まりいつ終わったのであろうか。コエンザイムQ10はどうであったか。デドックスブームは岩盤浴と共に終わったが、ホットヨガと共に復活してきたが、果たして継続したダイエットたりえるだろうか。そして、楽して痩せるダイエットから、ビリーズブートキャンプのようにハードなダイエットへと振れて来た。以前、ファッションブランドエゴイストの社長である鬼頭一弥さんとブームについて話をしたことがあった。「山あり谷ありではなく、煙突のように急激に伸び、あっという間に売れなくなる」と情報の時代の商品のライフサイクルを話してくれたが、振り子は大きく振れれば振れるほど、またあっという間に逆に振れるということだ。
大きな潮流である健康というテーマではどのような振り子となっていたか、ここ数年の動きを見ていくと分かる。寒天ブームはいつ始まりいつ終わったのであろうか。コエンザイムQ10はどうであったか。デドックスブームは岩盤浴と共に終わったが、ホットヨガと共に復活してきたが、果たして継続したダイエットたりえるだろうか。そして、楽して痩せるダイエットから、ビリーズブートキャンプのようにハードなダイエットへと振れて来た。以前、ファッションブランドエゴイストの社長である鬼頭一弥さんとブームについて話をしたことがあった。「山あり谷ありではなく、煙突のように急激に伸び、あっという間に売れなくなる」と情報の時代の商品のライフサイクルを話してくれたが、振り子は大きく振れれば振れるほど、またあっという間に逆に振れるということだ。
こうした情報の時代にあって、商品やサービスの安定した成長を誰もが願っている。誰もがベストセラーではなく、ロングセラーを目標とするのだが、この成長の中心点を見出すことの難しさに直面している。ブランドづくりとは、この中心点を探り、見出し、その一点にビジネス努力を集中させることである。
この中心点とは何かということであるが、一つは「ルーツに遡る」ということである。モノや出来事、あるいは企業もそうであるが、創造された「最初」が最も完成形・理想型に近いということだ。「今」は多くのものを取り入れ複雑になり、ある意味偽物になってしまっているということでもある。だから、ルーツへと遡るということが最も重要となる。
見晴らしの良い場所に
その中心点とは「振り子消費」からの脱却と言える。永く使えるもの、住まいであれば永住とまではいかないにせよ永く生活できる住居、衣服であれば10年20年着続けたいもの、食であれば食べ続けていても飽きないもの、こうした「継続価値」という中心点へと収斂していくと思う。勿論、健康というテーマにおいてもトレンドという刺激消費が無くなる訳ではない。ただ過去10年間のような大きな振り子にはならないということだ。継続した文化を味わう、どこかしっくりと馴染む、一見保守的にも見える消費が中心点となる。
今日まで続いていることは、中心化と分散化が錯綜しているということだ。情報の時代は、普通と過剰、 0と∞、とを行ったり来たりする。健康・美容ブームの中心にあった寒天、コエンザイムQ10、今はコラーゲンの吸収率競争となっている。若い女性の間でホットヨガが注目されているが、それまでのデドックスとどう違うのか、これからどの程度まで浸透していくのか。マーケッターはどこに健康の中心化が進み、どこは分散・衰退が進んでいくかを見極めることが主要な仕事となっている。そのためには「見晴らしの良い場所」に立つことが必要である。そうした意味で、東京というあらゆるものが一極集中する世界は見晴らしの良い場所、俯瞰できる場所であると言えよう。
10数年前にマーケッターの間でそうした俯瞰できる場所での定点観測という方法が採られたことがあった。今、必要なことはそうした変化の「定点実感」であると言える。(後半に続く)
今回の「パラダイム転換から学ぶ」では、戦後昭和から今日に至る中で一番変化が大きかった「食」を通じた価値観の変化を取り上げることとする。「食」は日常であり、経済的豊かさにあって変化が最も出やすい世界である。そして、ほとんどの人が実感できるものである。そうした価値観変化はいつ頃からどのような変化として現れてきたか、そしてこれからどのような変化が生まれてくるであろうか、そうした推測を含め、その劇的変化について学ぶこととする。

「パラダイム転換から学ぶ」
モノ不足から健康時代へ
豊かさから見える「未来」
このグラフは日本人の1日あたりのカロリー摂取量の推移グラフである。戦後直後の物資のない窮乏時代のカロリー摂取量はわずか1903Calであった。その後経済成長と共に所得も増え生活の豊かさが進み摂取Calも増えたが、1980年代に入り急激に摂取量は減少へと向かう。そして、既に摂取Calはその戦後直後を大きく下回るレベルへと進み数年前に話題となった。この摂取Calの内容の違いに生活価値観の劇的な変化が現れている。戦後71年物質的豊かさはどのように変化し、どこに向かっているのか、その変化はライフスタイルの根底を成している日常の「食」に明確に現れている。今回はこの大きな転換、豊かさの意味について「食」を通じて学んでみることとする。
カロリー不足・栄養不足を補う給食
カロリー摂取量の多くは日常の食生活によるものだが、戦後昭和の時代の学校給食の歴史を見ていくとカロリー不足、栄養不足をいかに給食で補っていたかがわかる。
全国学校給食会連合会(全給連によれば、学校給食の始まりは明治22年(1889年)、山形県鶴岡町(現鶴岡市)の私立忠愛小学校だといわれているが、まずは戦後の学校給食を見ていくこととする。昭和21年(1946年)に、文部・厚生・農林三省から「学校給食実施の普及奨励について」が出され、12月24日、東京・神奈川・千葉で学校給食が開始される。当時は全国都市の児童約300万人に対し学校給食がはじまり、米国から無償で与えられた脱脂粉乳が使われる。
そして、昭和25年(1950年)、米国からの小麦粉を使い、8大都市の 小学生児童対象の完全給食がおこなわれルようになる。(以下の写真は千葉県学校給食会による。)
 写真は昭和29年(1954年)の学校給食で、その当時の代表的な給食メニューである。団塊世代にとっては懐かしい鯨肉の竜田揚げが入っており、平成世代にとっては食べたことのないメニューである。そして、現在のコッペパンとは比べようがないほどパサパサのパンで、ミルクといっても脱脂粉乳によるミルクでとても美味しいとは言い難いメニューであった。つまり、生きるために必要なカロリー、栄養を取り入れることが目的の給食生活であった。
写真は昭和29年(1954年)の学校給食で、その当時の代表的な給食メニューである。団塊世代にとっては懐かしい鯨肉の竜田揚げが入っており、平成世代にとっては食べたことのないメニューである。そして、現在のコッペパンとは比べようがないほどパサパサのパンで、ミルクといっても脱脂粉乳によるミルクでとても美味しいとは言い難いメニューであった。つまり、生きるために必要なカロリー、栄養を取り入れることが目的の給食生活であった。こうしたいわゆるパン食が主流であった給食は 昭和51年(1976年)以降米飯給食が開始される。そして、コッペパンの時代と比べてメニューの種類が増え、勿論味の面でもよくなる。そして、カレーライスのように今日のメニューに近いものが提供されるようになる。
 そして、平成の時代の給食はどうかというと栄養バランスもよく考えられた、おいしい給食が出されるようになり、戦後間もない頃の給食と比べ一段と豪華になったと言える。ちなみに下記のメニューには手巻きずしなどが入っており、ある意味家庭ではあまり作られない半歩先のメニューも出されるようになる。おふくろの味は給食によって作られてきたと言っても過言ではない。
そして、平成の時代の給食はどうかというと栄養バランスもよく考えられた、おいしい給食が出されるようになり、戦後間もない頃の給食と比べ一段と豪華になったと言える。ちなみに下記のメニューには手巻きずしなどが入っており、ある意味家庭ではあまり作られない半歩先のメニューも出されるようになる。おふくろの味は給食によって作られてきたと言っても過言ではない。 ところでネット上で紹介されている親世代と現代っ子の人気メニューランキングは、ほぼ以下となっている。
ところでネット上で紹介されている親世代と現代っ子の人気メニューランキングは、ほぼ以下となっている。●親世代の給食人気ランキング
第1位「揚げパン」(53.9%)
第2位「カレーライス」(52.3%)
第3位「ソフト麺」(47.1%)
第4位「炊き込みご飯」(27.6%)
第5位「わかめご飯」(26.2%)
●現代っ子の給食人気ランキング
第1位「鶏のから揚げ」(74.3%)
第2位「ハンバーグ」(71.6%)
第3位「カレーライス」(67.3%)
第4位「オムライス」(57.4%)
第5位「スパゲティ」(56%)
米飯の工夫もあるが、やはり食の洋風化とその多様なメニュー、そして健康を考えたバランスの良い食育メニューが用意され、戦後の生きるための「食」から大きく転換したことがわかる。
摂取食品の変化
ところで生活費に占める食費の比率をエンゲル係数と呼び、1970年代までは一つの豊かさのレベルの指標として使われてきた。いつからエンゲル係数が死語となったか定かではないが、カロリー摂取量が下がり始める1980年代と推測される。
この1980年代の変化は1日あたりの食品の摂取量(g)の変化となって表れている。以下のグラフを見ればわかるが、主食である米飯の摂取量は昭和30年代の半分以下となっている。(途中から米飯の単位が変わっているので下記の注を参照のこと)また、一番伸びが大きいのが乳類と肉類で、洋風化を摂取食品群からも見ることができる。

注)平成 13 年から米類については調理を加味した値(g)に変更している。つまり平成 12 年 の値は、炊く前のコメの量、平成 17 年は炊いた後のご飯の量で示している 。そのようにグラフを見れば米の摂取量は同じような右肩下がりとなり、既に言われているように昭和30年代の半分以下となっていることがわかる。
高度経済成長期からバブル期へ
1955年から1973年まで、日本の実質経済成長率は年平均10%を超え、欧米の2~4倍にもなった。朝鮮特需から始まり、神武景気( 31ヵ月 )、岩戸景気( 42ヵ月 )、東京オリンピック景気24ヵ月 )、いざなぎ景気( 57ヵ月 )、いわゆる高度経済成長期は1973年の第一次石油ショックで終わる。この高度経済成長期に流行った言葉に3C・3種の神器(車、クーラー、カラーテレビ)がある。こうした新商品をどんどん生活のなかに取り入れてきた時代で、まだまだ物不足、物を満たすために働いていた時代であった。
 その後も安定成長を続け、所得も増え、一億総中流時代と呼ばれる時代となる。
その後も安定成長を続け、所得も増え、一億総中流時代と呼ばれる時代となる。そして、食におけるパラダイム変化の第一弾はこの1980年代からスタートしている。戦後の生きるための食からの変化であるが、1980年代はバブルへと向かう時期であり、その方向はやはりバブル崩壊後の平成時代にはより鮮明に現れてくる。大きく言うならば、「食」においても昭和と平成の価値観が大きく変わってきているということだ。豊かさを多くの人が実感し始めた時代であった。
生きるための食から、楽しむ食、遊ぶ食へ
冒頭のカロリー摂取量のグラフに見られるように、1980年代からカロリー摂取量が極端に減少へと向かっている。この傾向は米飯の消費量の減少、乳類・肉類の増加と多様化、こうした変化と軌を一にしていることがわかる。生きるための食から、楽しむ食への転換である。1980年代に入ると、その経済的豊かさの発露として、消費の主役は団塊世代からポスト団塊世代へと移行する。特に若い女性の海外旅行が盛んになり、輸入チーズに代表されるように洋風化、多様化が更に進行する。
そして、このバブル期の食の特徴の一つが食生活における女性の変化である。当時の時代の在り方を見事に表していたのが中尊寺ゆっこが描いた漫画「オヤジギャル」であった。従来男の牙城であった居酒屋、競馬場、パチンコ屋にOLが乗り込むといった女性の本音を描いたもので多くの女性の共感を得たマンガである。女性が居酒屋でチューハイを飲む、という姿はこの頃現れ、また第一次ワインブーム、とりわけ「世界一早いボージョレヌーボー」ブームはその楽しむ食の象徴でもあった。
もう一つの特徴が物価値から情報価値への転換が始まった時期である。その代表例がロッテが発売したビックリマンチョコであった。シール集めが主目的で、チョコレートを食べずにゴミ箱に捨てて社会問題化した事件である。つまりチョコレートという物価値ではなく、シール集めという情報価値が買われていったということである。しかも、一番売れた「悪魔VS天使」は月間1300万個も売れたというメガヒット商品である。楽しむ食というより、遊ぶ食、今日のエンターテイメントフーズにつながる芽がこの頃から始まっている。
こうした豊かさは次の時代、バブル崩壊後の食を予感させるような芽が更に表れている。その代表例が二谷百合枝による「愛される理由」が75万部という1989年のベストセラーになっている。物質的には満たされたお嬢様である二谷百合枝が郷ひろみとの出会いから結婚までを描いたものだが、物は充足するが何か心は満たされていない、そんなテーマの本であった。豊かさが次の段階、精神的な豊かさ、あるいは本質的な事への回帰、健康という原点回帰へと向かう萌芽である。
そして、もう一つ着目しなければならないのが、物質的豊かさの中から、子供のアトピー、あるいはアレルギーが初めて社会問題となった時代である。
また、「ダイエット」という言葉が多くのメディアで使われるようになったのはこの時期からであった。
昭和から平成への転換

実は上記グラフを見ていただくとわかるが、バブル崩壊後も世帯収入は増え続けていた。グラフの数字は主婦のパート収入を含めた実収入の数値であり、夫婦共稼ぎが一般化し始めた時代である。また、1993年には新聞紙上に「父帰る」というタイトルと共に、当時の家庭状況が紹介されていた。残業が無くなり、主人が早く帰宅し、味噌や醤油の売れ行きが復活したことがニュースになった時代である。
そして、1997年をピークに世帯収入は急激な右肩下がりとなる。思い起こせば「デフレ」の芽が出始めた年でもある。ユニクロは本格的なSPAを始めるために社内改革をした時期であり、楽天市場がネット上で仮想商店街をつくり注目されはじめたのも1997~1998年頃であった。
前回の「パラダイム転換から学ぶ」 ”回帰から見える未来”にも書いたことだが、回帰現象という大きな現象の背景にはバブル崩壊後の「失われたものの回復」がある。そして、その中の一つが「自然・健康」の回復であると。そのメガトレンドである自然・健康生活とは食における自然の回復=取り入れであり、その先には身体の自然化でもある。まず現れたのが無農薬や減農薬の農作物であり、自然の持つ生命力が一番盛んである旬のものの取り入れが再認識される。
そして、1990年代に入ると主に次のような健康関連商品のブームが起きる。
1992年;魚に含まれるDHAが注目される
1993年:杜仲茶の血圧低減効果が知られブームとなる
1997年:赤ワインに含まれるポリフェノールの抗酸化作用に注目が集まりブームとなる
1999年:ビタミン類などの低価格サプリメントがコンビニでも発売され、市場は大きく伸びる
2000年:ザクロが更年期障害を抑える効果があると話題になる
2004年:コエンザイムQ10ブームが起きる
こうしたサプリメント市場の拡大は働く女性の増加に伴い家庭内調理が少なくなり、そうした栄養バランスを補助するものとして急成長していく。ちょうどデパ地下の中食が成長・一般化した時期と符合している。こうしたサプリメントさえ摂取すれば健康になれるといった間違ったサプリメント信仰は、2006年以降厚労省によるアガリスク製品の一部に発がん性のリスクがあると指摘され、安全性への懸念から市場は一挙に冷え込む。
更に、健康食品の効能効果に疑問が起こり始める。その代表例が関西テレビの「発掘!あるある大辞典」で、2007年1月7日放映の『納豆ダイエット問題』を皮切りに科学的根拠のない実験を行い、更にはデータの捏造すらされていたことがわかり、番組は中止となる。実はこの「発掘!あるある大辞典」のスタートは1996年10月で、この健康ブームに乗って高視聴率を上げた番組であった。「健康・からだ・食」のテーマが多く、「○○の食材が痩せる!」などと放映すれば、翌日にはその食材がスーパーなどで飛ぶように売れるという社会現象が生まれるほどであった。
こうした背景から2005年には1兆2850億円(健康産業新聞調べ)あった健康食品市場は翌年以降マイナス成長となる。(但し、2010年以降は回復し、プラス成長に向かっている。)
そして、「健康・からだ・食」という最大関心事に衝撃的な事件が起きる。2007年12月から08年1月にかけ、中国の天洋食品の冷凍ギョーザを食べた千葉、兵庫両県の計10人が下痢などの中毒症状を訴え、そのギョーザから殺虫剤メタミドホスが検出された事件である。安全という最も基本的なことを思い起こさせる契機となった事件である。
以降、食の安全性や表示偽装など内部告発を含め、社会事件として取り上げられる。
2007年:ミートホープ社による牛肉ミンチの品質表示偽装事件
2007年:老舗船場吉兆による賞味期限切れや産地偽装問題
2008年:三笠フーズによる事故米(汚染米)不正転売事件
 こうした事件が明るみに出たことにより、安全を安心へと変えるために食の「見える化」は流通を中心に広がることとなる。いわゆる「ご安心ください、私が作りました」という生産者表示や食品履歴がトレースできるような仕組みの導入など。
こうした事件が明るみに出たことにより、安全を安心へと変えるために食の「見える化」は流通を中心に広がることとなる。いわゆる「ご安心ください、私が作りました」という生産者表示や食品履歴がトレースできるような仕組みの導入など。また、食料の自給率が40%前後の日本の場合、その多くは輸入に頼っている。つまり、見えないところで作られる食品の見える化が進むが、その対策を講じなかったのがあの日本マクドナルドであった。2014年中国で製造されたチキンナゲットの鶏肉が期限切れであったことを契機に小さな子を持つファミリーを中心に客離れが起こり、その後わずか数年の間に900数十店舗の店を閉店するという事態に至ったことは周知の通りである。
健康長寿から肥満ワースト県への変貌
本格的な人口減少時代を迎え、衰退する都市や町についてスタディした拙著「未来の消滅都市論」にも書いたことだが、周知のように「日本一長寿の県」といえば、既に沖縄県ではなく長野県である。少し古いが2013年に発表されたデータを見ても、男性が80.88歳で1位、女性が87.18歳で1位と、名実ともに全国一の長寿県となっている。この長寿の秘訣として食生活を挙げる専門家が多く、確かに塩分の多い野沢菜などを食しているが、そうした塩分を排出する野菜の摂取量が極めて多くバランスがとれた食生活を送っている。そして、かなり前から佐久病院をはじめ、予防医療が導入されてきたことも大きい。もう10年以上前になるが、「予防は治療に勝る」という「長野モデル」が提唱されていた。そして、平成2年から20年 まで1人当たりの老人医療費は全国最低額だった。つま り、長野では老人が病気にかかることなく、元気で働い ている、とも言えるだろう。社会保障費の増大が問題視されているが、抑える方法の一つは既に長野において実証されている。
ところで問題なのは長野県が長寿NO1になる迄沖縄県が長寿県であった。厚生労働省による平成22年国民健康・栄養調査では、沖縄県が全国で肥満率第1位という結果が発表され悪い意味で話題となった。平均寿命も男女ともに長年トップクラス出会ったにも関わらず2000年頃から大きく順位を下げ、今や男性は30位まで転落。女性に関しては1位から3位へ落ちたものの、健康・長寿はなんとか保ってはいる。ただし肥満率はやはり女性も全国トップである。
何故、こうした非健康な県になったのかと言えば、その最大要因は食生活にあると言われている。米国の占領下となった沖縄では、食においてもアメリカの影響を強く受けるようになる。米軍の軍用食料から供出されたポークランチョンミートやコンビーフハッシュ(コンビーフとじゃがいもを合わせたもの)など加工肉が一般に普及し、大量に消費されるようになる。若い世代では昔ながらの沖縄料理を食べる機会はどんどん減り、戦後生まれの世代は子供の頃からこのような食環境であった。沖縄県の調べでは、県民の3人に2人が脂質を過剰摂取していると。もう一つの要因としては運動をしない車社会にあると専門家から指摘されている。表現は悪いが、ある意味「健康・からだ・食」の社会実験結果の如くである。
 私は沖縄の生活文化や琉球文化に興味があり、今まで60回ほど沖縄に行っているが、沖縄の人たちが日常食べている「食堂」をよく利用している。多くの人は沖縄観光=リゾートライフ=ホテルライフ、そして、美ら海水族館をはじめとした観光地を巡り、お土産となると那覇の国際通りとなる。こうしたパターンは本島だけでなく、離島も同様である。
私は沖縄の生活文化や琉球文化に興味があり、今まで60回ほど沖縄に行っているが、沖縄の人たちが日常食べている「食堂」をよく利用している。多くの人は沖縄観光=リゾートライフ=ホテルライフ、そして、美ら海水族館をはじめとした観光地を巡り、お土産となると那覇の国際通りとなる。こうしたパターンは本島だけでなく、離島も同様である。1990年代後半から長寿の島の代表的な食として那覇の安里にある沖縄第一ホテルの朝食が雑誌などでよく紹介されていた。勿論、私も一度だけだが食べに行ったが、野草に近い島野菜中心の30種ほどある朝食でこうした食生活であれば長寿の島になるなと納得したことを覚えている。現在は安里から中心部の牧志に移転しており、メニューも大分進化しているようだ。今風な言い方をするならば、「地産地消」の伝統的な沖縄料理である。医食同源という言葉があるが、沖縄の人たちの言葉ではこうした伝統料理を「ぬちぐすい」(ぬち=命、ぐすい=薬)と呼んでいるが、これもほとんど死語になっているようだ。
しかし、こうした食をつくれる後継者が少ないこともあって、沖縄の主要な食である豚肉がそうであるように最後まで食べきるといった調理がどんどん廃れていっている感がしてならない。沖縄も豊かになって、その豊かさは伝統的な食から米国の高脂質、加工肉中心の食へと変化し、結果こうした非健康県になった。そして、庶民の食を支えている食堂の多くは、そのメニューのボリューム・量のすごさである。沖縄の普通盛りは東京ではデカ盛りであることも肥満県の要因の一つであろう。
両極に振れる振子消費
実はこうした「健康・からだ・食」という意識が底流する中で、2007年ごろから沖縄のみならず全国的にデカ盛り、メガ盛りといったガツン系の食、高カロリーメニューが人気となる。その代表的な商品としては日本マクドナルドのダブルクオーターパウンド(828kcal)であった。こうした食の裾野には学生や若いビジネスマン以外にも、ファミリーでの食べ放題やブッフェスタイルがあることは言うまでもない。そして、特徴的なのは日経MJの2007年度ヒット商品番付の関脇にガツン系を始めとした「デカ盛りフード」がある一方、「カロリー・ゼロ・コーラ」に人気が集まる。また、日本古来の自然食であり、ローカロリー・高タンパクの豆腐が再認識される。
そして、ダイエットでは、周知のかなりハードな「ビリーズブートキャンプ」がブームになった一方、楽して痩せる「ぷるぷるフィットネス」の手軽さが人気となる。こうした価値観の反対軸にあるような商品が売れる市場の情況を当時私は「振り子消費」と呼んでいた。行ったり来たり振り子のように揺れる時代の心理市場であるが、この振り幅は以降年々小さくなって来ている。例えば10数年前にダイエット&美容のためにサプリメント依存症が問題となるような過剰さはなくなり、今ではコラーゲンのようなものへとトレンドは移行してきているということである。
こうした両極に振れる振子消費とは一線を画したものが、実は軽登山あるいはウオーキングである。今や東京の近郊にある高尾山は老若男女ばかりでなく、最近では外国人にも人気の軽登山コースとなっているが、既に20年ほど前からシニアの間では人気のコースとなっており、待ち合わせスポットになっている八王子には週末の早朝にはシニアが集まり、ちょっとしたニュースにもなっていた。
また、若い世代をはじめとしたジョギングブームが10年ほど前から起こる。そして、2015年には全国で行われるマラソン大会は197大会にも及び健康ブームの先導役を引き受けている。軽いジョギングからフルマラソンを走る人まで、そのランニング人口は1000万人を超えていると推定される。ある意味、情報によって振り子のように振れるトレンド型健康市場にあって、「健康・からだ・食」その中核を占めていると言える。
健康テーマの中心点を探る
 大きな潮流である健康というテーマではどのような振り子となっていたか、ここ数年の動きを見ていくと分かる。寒天ブームはいつ始まりいつ終わったのであろうか。コエンザイムQ10はどうであったか。デドックスブームは岩盤浴と共に終わったが、ホットヨガと共に復活してきたが、果たして継続したダイエットたりえるだろうか。そして、楽して痩せるダイエットから、ビリーズブートキャンプのようにハードなダイエットへと振れて来た。以前、ファッションブランドエゴイストの社長である鬼頭一弥さんとブームについて話をしたことがあった。「山あり谷ありではなく、煙突のように急激に伸び、あっという間に売れなくなる」と情報の時代の商品のライフサイクルを話してくれたが、振り子は大きく振れれば振れるほど、またあっという間に逆に振れるということだ。
大きな潮流である健康というテーマではどのような振り子となっていたか、ここ数年の動きを見ていくと分かる。寒天ブームはいつ始まりいつ終わったのであろうか。コエンザイムQ10はどうであったか。デドックスブームは岩盤浴と共に終わったが、ホットヨガと共に復活してきたが、果たして継続したダイエットたりえるだろうか。そして、楽して痩せるダイエットから、ビリーズブートキャンプのようにハードなダイエットへと振れて来た。以前、ファッションブランドエゴイストの社長である鬼頭一弥さんとブームについて話をしたことがあった。「山あり谷ありではなく、煙突のように急激に伸び、あっという間に売れなくなる」と情報の時代の商品のライフサイクルを話してくれたが、振り子は大きく振れれば振れるほど、またあっという間に逆に振れるということだ。こうした情報の時代にあって、商品やサービスの安定した成長を誰もが願っている。誰もがベストセラーではなく、ロングセラーを目標とするのだが、この成長の中心点を見出すことの難しさに直面している。ブランドづくりとは、この中心点を探り、見出し、その一点にビジネス努力を集中させることである。
この中心点とは何かということであるが、一つは「ルーツに遡る」ということである。モノや出来事、あるいは企業もそうであるが、創造された「最初」が最も完成形・理想型に近いということだ。「今」は多くのものを取り入れ複雑になり、ある意味偽物になってしまっているということでもある。だから、ルーツへと遡るということが最も重要となる。
見晴らしの良い場所に
その中心点とは「振り子消費」からの脱却と言える。永く使えるもの、住まいであれば永住とまではいかないにせよ永く生活できる住居、衣服であれば10年20年着続けたいもの、食であれば食べ続けていても飽きないもの、こうした「継続価値」という中心点へと収斂していくと思う。勿論、健康というテーマにおいてもトレンドという刺激消費が無くなる訳ではない。ただ過去10年間のような大きな振り子にはならないということだ。継続した文化を味わう、どこかしっくりと馴染む、一見保守的にも見える消費が中心点となる。
今日まで続いていることは、中心化と分散化が錯綜しているということだ。情報の時代は、普通と過剰、 0と∞、とを行ったり来たりする。健康・美容ブームの中心にあった寒天、コエンザイムQ10、今はコラーゲンの吸収率競争となっている。若い女性の間でホットヨガが注目されているが、それまでのデドックスとどう違うのか、これからどの程度まで浸透していくのか。マーケッターはどこに健康の中心化が進み、どこは分散・衰退が進んでいくかを見極めることが主要な仕事となっている。そのためには「見晴らしの良い場所」に立つことが必要である。そうした意味で、東京というあらゆるものが一極集中する世界は見晴らしの良い場所、俯瞰できる場所であると言えよう。
10数年前にマーケッターの間でそうした俯瞰できる場所での定点観測という方法が採られたことがあった。今、必要なことはそうした変化の「定点実感」であると言える。(後半に続く)