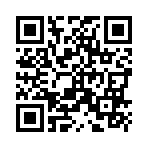2014年08月31日
売り切る力
ヒット商品応援団日記No591(毎週更新) 2014.8.31.
ここ数ヶ月未来塾のテーマを学習することもあって、首都圏の街や商店街を見て回ってきた。勿論、消費増税の影響がどのようなところに表れ、あるいはその壁を超えるためにどんな売り方をしているか、小売り現場を見ることであった。4月ー6月のGDPや家計支出を見ながら、大きな買い物である住宅や自動車、あるいは家電製品の売れ行きを見てきた。その結果、「暑い夏に寒い消費」というタイトルでブログを書いて、まだ2週間しか経たないが、景気が好転する情報は全く無い。逆に、7月度の家計支出が総務省から発表され前年同月比マイナス5.9%と更に悪化し、物価の上昇と相まって更に消費を萎縮させ、いや寒い消費どころか氷河期に向かいかねない状況にある。何度となく新聞紙上に載っているが一応家計支出の2014年度月別推移は以下となっている。
1月+1.1% 2月-2.5% 3月+7.2% 4月-4.6% 5月-8.0% 6月-3.0% 7月-5.9%
ところで1997年の5%増税後はどうであったか、金融危機関連の事象は脇に置くとすれば、増税後の消費の回復は早かったものの、翌年の1998年度には急激に倒産件数が増え年間18988件にまで及んだ。地方企業で、中小企業を中心に、建設・流通といった業種が中心であった。多くの企業、特に大手流通企業の多くはその轍を踏まないように、売り上げが落ちても継続していけるように商品のPB化や自前のMDといった利益性の高い体質へと向かい準備をしてきた。
そして、消費増税後の予測として、百貨店の多くは7月以降はプラスへの転換がはかれるとその意気込みを語っていた。ところが7月はマイナス2.5%であった。そのなかで唯一高島屋だけがこのマイナスはこれからも続くと発表したが、表向きのアナウンスとは別に大手流通企業のほとんどはこうした2~3%のマイナス成長を前提として経営していくものと考えられる。
肌感覚で分かる景気の指標の一つが食品の売れ行き動向であるが、天候不順による野菜類の高騰もあって、ヨーカドー、イオン、西友、地域中堅スーパーはかなりの勢いで直接値引きによるプロモーションを始めている。良く言われることであるが、生鮮三品の売り上げが落ちた時、本格的な不況に入る。
さて大手ではない地方企業、輸出といった円安の恩恵を受けない企業、2~3%のマイナスをこれからも続けられる体力のない企業はどうすべきかである。未来塾のテーマとして町の商店街である江東区の「砂町銀座商店街」、品川区の「戸越銀座商店街」、そして横浜の「洪福寺松原商店街」をスタディしてきた。戸越銀座商店街はいわゆるどこにでもある一般的平均的な商店街で反面教師として取り上げその問題点を指摘してきた。問題点を指摘しても「次」に向かい結果を出すにはなかなか難しい。周りを大型商業施設に囲まれ、価格競争下にあって、更に立地も決して良くないが顧客を引きつける「砂町銀座商店街」と「洪福寺松原商店街」には共通したものがある。それは一言で言うならば、「売り切る力」を発揮している、ある意味商店の原点そのものに根ざした商売を続けているということにつきる。
砂町銀座商店街や洪福寺松原商店街で感じたことの一つがどの店も「売り切る」ための「わけあり」といったアイディアや工夫、精一杯の顧客サービス努力をしていることであった。そして、「売り切る力」はあの仙台にある「主婦の店さいち」を思い起こさせ、次のように書いた。
『「全てをその日で売り切る」、つまりロス率は0(ゼロ)となる。顧客もそうしたことを分かって何十年もつきあってきた。つまり、「安さ」はこうした商売の結果であることを売る側も買う側も良く理解しているということである。「売り切る力」こそが「安さ」の源であるということだ。「安さ」の理由を大量仕入れによるものであると「訳あり商品」をアピールする流通や専門店が多いなか、小さな商圏=仕入れ量も限られる砂町銀座のような中小零細商店にとっては「売り切ること」が経営を維持し持続させていく唯一の方法となっている。』
「ハマのアメ横」と呼ばれる洪福寺松原商店街でも同じであった。確かに商店街全体として「安い」商品ばかりである。しかし、その安さは単に大量仕入れ大量販売によって作られたものではない。顧客と相対し、コミュニケーションをはかりながら販売する。そして、売り切ることによって「安さ」も生まれ、経営も継続することが可能となる。そして、次のようにも書いた。
『町の商店街は必要なのかと流通専門家の間においてもそのように議論されている。スマホに「○○したいのだが」、あるいは「○○を買いたいのだが」と検索すれば、マップ上にいくつかの選択肢が即座に提供される。そんな便利な時代にあって、そうしたスマホ程度の便利さであれば町の商店街はいらない。もし、商店街が存在する理由、顧客に”あって欲しい”と望まれるには、そうした情報では得られない「相対」ならではのリアルな情報となる。こうした相互のコミュニケーションを無くした商店街は、勿論消滅し、シャッター通りとなる。』
今、まさにそうした時を迎えつつある。ここ半年で「名物商品」を作ることができるか、顧客の人気を集める「看板娘」を誕生させることができるか。新たな仕入れ先から顧客が喜ぶであろう「わけあり商品」を店頭に並べることが可能であろうか。いずれもNoである。出来ることは商売をスタートさせた時、創業の時どんな売り方をしてきたかを思い起こすことだ。お金も、経験も、勿論顧客も何も無いなか、あるのは夢と情熱だけで、とにかく売り切ることだけであった筈である。そして、「今」がある。つまり、再創業の時を迎えているということだ。(続く)
ここ数ヶ月未来塾のテーマを学習することもあって、首都圏の街や商店街を見て回ってきた。勿論、消費増税の影響がどのようなところに表れ、あるいはその壁を超えるためにどんな売り方をしているか、小売り現場を見ることであった。4月ー6月のGDPや家計支出を見ながら、大きな買い物である住宅や自動車、あるいは家電製品の売れ行きを見てきた。その結果、「暑い夏に寒い消費」というタイトルでブログを書いて、まだ2週間しか経たないが、景気が好転する情報は全く無い。逆に、7月度の家計支出が総務省から発表され前年同月比マイナス5.9%と更に悪化し、物価の上昇と相まって更に消費を萎縮させ、いや寒い消費どころか氷河期に向かいかねない状況にある。何度となく新聞紙上に載っているが一応家計支出の2014年度月別推移は以下となっている。
1月+1.1% 2月-2.5% 3月+7.2% 4月-4.6% 5月-8.0% 6月-3.0% 7月-5.9%
ところで1997年の5%増税後はどうであったか、金融危機関連の事象は脇に置くとすれば、増税後の消費の回復は早かったものの、翌年の1998年度には急激に倒産件数が増え年間18988件にまで及んだ。地方企業で、中小企業を中心に、建設・流通といった業種が中心であった。多くの企業、特に大手流通企業の多くはその轍を踏まないように、売り上げが落ちても継続していけるように商品のPB化や自前のMDといった利益性の高い体質へと向かい準備をしてきた。
そして、消費増税後の予測として、百貨店の多くは7月以降はプラスへの転換がはかれるとその意気込みを語っていた。ところが7月はマイナス2.5%であった。そのなかで唯一高島屋だけがこのマイナスはこれからも続くと発表したが、表向きのアナウンスとは別に大手流通企業のほとんどはこうした2~3%のマイナス成長を前提として経営していくものと考えられる。
肌感覚で分かる景気の指標の一つが食品の売れ行き動向であるが、天候不順による野菜類の高騰もあって、ヨーカドー、イオン、西友、地域中堅スーパーはかなりの勢いで直接値引きによるプロモーションを始めている。良く言われることであるが、生鮮三品の売り上げが落ちた時、本格的な不況に入る。
さて大手ではない地方企業、輸出といった円安の恩恵を受けない企業、2~3%のマイナスをこれからも続けられる体力のない企業はどうすべきかである。未来塾のテーマとして町の商店街である江東区の「砂町銀座商店街」、品川区の「戸越銀座商店街」、そして横浜の「洪福寺松原商店街」をスタディしてきた。戸越銀座商店街はいわゆるどこにでもある一般的平均的な商店街で反面教師として取り上げその問題点を指摘してきた。問題点を指摘しても「次」に向かい結果を出すにはなかなか難しい。周りを大型商業施設に囲まれ、価格競争下にあって、更に立地も決して良くないが顧客を引きつける「砂町銀座商店街」と「洪福寺松原商店街」には共通したものがある。それは一言で言うならば、「売り切る力」を発揮している、ある意味商店の原点そのものに根ざした商売を続けているということにつきる。
砂町銀座商店街や洪福寺松原商店街で感じたことの一つがどの店も「売り切る」ための「わけあり」といったアイディアや工夫、精一杯の顧客サービス努力をしていることであった。そして、「売り切る力」はあの仙台にある「主婦の店さいち」を思い起こさせ、次のように書いた。
『「全てをその日で売り切る」、つまりロス率は0(ゼロ)となる。顧客もそうしたことを分かって何十年もつきあってきた。つまり、「安さ」はこうした商売の結果であることを売る側も買う側も良く理解しているということである。「売り切る力」こそが「安さ」の源であるということだ。「安さ」の理由を大量仕入れによるものであると「訳あり商品」をアピールする流通や専門店が多いなか、小さな商圏=仕入れ量も限られる砂町銀座のような中小零細商店にとっては「売り切ること」が経営を維持し持続させていく唯一の方法となっている。』
「ハマのアメ横」と呼ばれる洪福寺松原商店街でも同じであった。確かに商店街全体として「安い」商品ばかりである。しかし、その安さは単に大量仕入れ大量販売によって作られたものではない。顧客と相対し、コミュニケーションをはかりながら販売する。そして、売り切ることによって「安さ」も生まれ、経営も継続することが可能となる。そして、次のようにも書いた。
『町の商店街は必要なのかと流通専門家の間においてもそのように議論されている。スマホに「○○したいのだが」、あるいは「○○を買いたいのだが」と検索すれば、マップ上にいくつかの選択肢が即座に提供される。そんな便利な時代にあって、そうしたスマホ程度の便利さであれば町の商店街はいらない。もし、商店街が存在する理由、顧客に”あって欲しい”と望まれるには、そうした情報では得られない「相対」ならではのリアルな情報となる。こうした相互のコミュニケーションを無くした商店街は、勿論消滅し、シャッター通りとなる。』
今、まさにそうした時を迎えつつある。ここ半年で「名物商品」を作ることができるか、顧客の人気を集める「看板娘」を誕生させることができるか。新たな仕入れ先から顧客が喜ぶであろう「わけあり商品」を店頭に並べることが可能であろうか。いずれもNoである。出来ることは商売をスタートさせた時、創業の時どんな売り方をしてきたかを思い起こすことだ。お金も、経験も、勿論顧客も何も無いなか、あるのは夢と情熱だけで、とにかく売り切ることだけであった筈である。そして、「今」がある。つまり、再創業の時を迎えているということだ。(続く)
2014年08月28日
未来塾(9)「商店街から学ぶ」洪福寺松原商店街(後半)
ヒット商品応援団日記No590(毎週更新) 2014.8.28.
「商店街から学ぶ」洪福寺松原商店街(後半)を公開いたします。「ハマのアメ横」と呼ばれる安さの奥に、小売りの原点・原則がしっかりと実践されている。今、商店街にこそこの原則が求められており、松原商店街に学びます。
商店構成も顧客によって創られている

砂町銀座商店街の場合もそうであったが、年数を経ることによって、結果今日の商店構成へと至る。松原商店街の場合、結構業種的にはバランスのとれた構成となっている。生鮮三品を始め、パン、総菜、豆腐、練り製品、乾物、焼き鳥、和菓子、婦人服や用品店、ドラッグに眼鏡、生活雑貨や美容室まで一通りの商店が軒を連ねている。こうした専門店だけでなく、生鮮三品を始めとした地域スーパーもある。
恐らく、店舗としては少ないなと感じたのは飲食店である。吉祥寺や戸越銀座商店街もそうであったが、必ずあるのがラーメン専門店である。松原商店街にも光家という横浜家系の専門店があり、昼時にはいつも行列ができる人気店となっている。

商店街に飲食店が少ないのは駅から5分ほど歩き、周辺にはオフィスビルの少ない住宅地であるからで、写真のように天王町駅前商店街には多くの飲食店がある。昼時には周辺のビジネスマンやOLが利用している。光家のようにどうしても食べてみたいと広域集客できる飲食店以外は商売として成立しないということである。
また、ラーメン専門店とともに人気なのが焼き鳥である。ここ松原商店街にも露店タイプの焼き鳥店があり、なぜか市場という光景になじんだものとなっている。
そして、80店舗弱という小さな松原商店街にあって、結構目立つのが喫茶店や甘味処である。シニア世代向きではあるが、店の中を覗いてみるとファミリーで楽しんでおり、これまた特徴の一つとなっている。
行政が企画推進する商店街ツアー
砂町銀座でよく目にしたのが「食べ歩きツアー」であった。焼き鳥を食べながら、おでんをつまみながら、昭和の商店街を歩くという自然発生的に生まれたものであるが、松原商店街の場合は神奈川県が積極的に商店街を取り上げ、PRを兼ねてツアーを組んでいる。そのなかの一つが松原商店街である。そのツアーの概要であるが、大手旅行会社(近畿日本ツーリストグループ)とタイアップし、神奈川ならではの魅力ある旅行商品の開発と、全国規模での観光PRを行う初めての事業に取り組むとのことである。
 ツアー例:横浜・横須賀下町商店街&横須賀軍港めぐり!(日帰り)
ツアー例:横浜・横須賀下町商店街&横須賀軍港めぐり!(日帰り)
横浜駅-洪福寺松原商店街-横浜橋通商店街-三笠公園-ヴェルニー公園-軍港めぐりクルーズ-ヴェルニー公園-どぶ板通り商店街-横浜駅
*ツアーの実施は平成26年7月23日から平成27年1月31日までとなっており、既にスタートしている。
このツアー例以外にも人気の横浜赤レンガ倉庫やカップヌードルミュージアムなどを回るいくつかツアーがある。
立地商売を超えるテーマ競争力
松原商店街周辺には他の商店街同様商業施設があり、激しい競争が行われている。相鉄線天王町駅から松原商店街に向かう道筋は商店街となっており、近くにはイオン天王町店やマルエツ天王町店もある。砂町銀座商店街も大型商業施設に囲まれたそんな市場と同じ構造を持っている。砂町銀座商店街について小さな商店街であるとブログに書いたが、松原商店街は更に小さな商店街である。しかも、駅前ではなく、徒歩5分という歩かないと行けないどちらかと言えば立地としては中途半端な商店街である。砂町銀座商店街は長さ670メートル、店舗数約180、松原商店街は東西240メートル、南北200メートル、店舗数約80弱。
 こうした小さな商店街が勝ち残るにはどうすれば良いのか、その答えの一つが松原商店街にある。どの店も「安さ」へと向かい、仕入れの工夫やアイディア、売り切る努力、ローコスト経営・・・・ほとんどの店が同じ方向を向いて商売しているということである。この「安さ」というテーマ集積力こそが競争軸となっている。この小さな商店街に平日2万人、休日2.5万人、年末には1日10万人以上という賑わいはこのテーマ集積にある。
こうした小さな商店街が勝ち残るにはどうすれば良いのか、その答えの一つが松原商店街にある。どの店も「安さ」へと向かい、仕入れの工夫やアイディア、売り切る努力、ローコスト経営・・・・ほとんどの店が同じ方向を向いて商売しているということである。この「安さ」というテーマ集積力こそが競争軸となっている。この小さな商店街に平日2万人、休日2.5万人、年末には1日10万人以上という賑わいはこのテーマ集積にある。
 砂町銀座商店街でも感じたが、買い物が楽しい。それは「安さ」を買うということだが、期待を裏切らない安さであり、それ以上の新鮮な「発見」があるからだ。あれも、これもと目移りがして、ついつい買ってしまったという、普段であればケチケチ消費がこの日だけは特別になる。忘れていた衝動買いという言葉を思い出した。
砂町銀座商店街でも感じたが、買い物が楽しい。それは「安さ」を買うということだが、期待を裏切らない安さであり、それ以上の新鮮な「発見」があるからだ。あれも、これもと目移りがして、ついつい買ってしまったという、普段であればケチケチ消費がこの日だけは特別になる。忘れていた衝動買いという言葉を思い出した。
単独激安店ならば全国至る所にある。しかし、これほどまでに「商店街」として実践できているところを知らない。それは戦後何も無いところに、周りは住宅もまばら、駅からも離れた場所。そんなゼロからのスタートという、創業の精神が今なお残っているからであろう。
買い物の楽しさ
 ところで商店街の入り口に100円ショップのダイソーが出店している。東広島に誕生したダイソーは国内2800店舗、海外840店舗、3700億円を超える売り上げという、その成長には目を見張るものがある。特に、バブル以降デフレの時代の旗手の一社であったダイソーを当時多くの顧客が支持したのは次の3つの魅力であった。
ところで商店街の入り口に100円ショップのダイソーが出店している。東広島に誕生したダイソーは国内2800店舗、海外840店舗、3700億円を超える売り上げという、その成長には目を見張るものがある。特に、バブル以降デフレの時代の旗手の一社であったダイソーを当時多くの顧客が支持したのは次の3つの魅力であった。
1.「買い物の自由」;
すべて100円、価格を気にせず買える。買い物の解放感、普段の不満解消。「ダイソーは主婦のレジャーランド」。(現在は200円やそれ以上の商品もあるが、今なお基本は100円である。)
2.「新しい発見」;
「これも100円で買えるの?!」という新鮮な驚き。月80品目新製品導入。(現在ではもっと多く導入となっている)
3.「選択の自由」;
色違い、型違い、素材違い、どれを取ってもすべて100円。
一言で言えば、”100円で「こんなものが買えるのか」という新鮮な感動”であった。このダイソーが松原商店街において見事に共振しているのはこうした買い物の楽しさにある。そして、こうした買い物の楽しさは、消費金額の差はあるが、ある意味日常化したアウトレット人気に通じるものである。
砂町銀座商店街ほど足を運ぶことが少なかったこともあって看板娘や名物オヤジに出会うことはなかった。しかし、恐らくそうした人物は間違いなくいる。楽しい買い物の主役が商品であるとすれば、看板娘は謂わば名脇役である。
必要に迫られた買い物から、楽しみをもってする買い物がここ洪福寺松原商店街にもあった。年末にはこの楽しさを求めて県内外からの買い物客が「ハマのアメ横」に押し寄せる。
1、コンセプトを共有し、磨き続ける商店街
戦後ゼロからのスタートという創業の精神が今なお生きていると書いたが、その歴史を見ていくと松原商店街にも競争という大波が押し寄せていることが分かる。商店街にはいくつかの小さな市場ビルがあった。商店街を一つの市場と位置づけるとすれば市場内市場といったものである。既に他の建物へと変わってしまった「ゴールデンマート」は変化の象徴である。入っていた飲食店を含め肉店など6店は移転あるいは閉店している。あるいは松原商店街入り口を少し入った左側にある「松原センター」内にも空き店舗はある。更に言うならば餃子専門店などの閉店もある。しかし、多くのショッピングセンターを見てきた私に取って、スクラップ&ビルトが当たり前の世界になっており、松原商店街における閉店は極めて少なく珍しい存在である。
 どんな変化が松原商店街にあったかであるが、まず魚幸水産は少し前に新しいビルにリニューアルし、その少し先にあるスーパーマーケットマルセンも新しい建物へとリニューアルしている。リニューアルできるとは成長し、更に成長するための投資である。年末には「ハマのアメ横」となって売りまくると思うが、自転車や徒歩で買いにくる周辺住民に愛されない限り、成長はない。
どんな変化が松原商店街にあったかであるが、まず魚幸水産は少し前に新しいビルにリニューアルし、その少し先にあるスーパーマーケットマルセンも新しい建物へとリニューアルしている。リニューアルできるとは成長し、更に成長するための投資である。年末には「ハマのアメ横」となって売りまくると思うが、自転車や徒歩で買いにくる周辺住民に愛されない限り、成長はない。
こうしたなかで、唯一安くはない飲食店がある。それが光家という横浜家系のラーメン専門店である。ラーメン(並)600円と他の家系のラーメンと比較し安く設定されてはいるが、商店街の総菜や弁当価格等を考えれば少し高めではある。しかし、カウンター席だけであるが、昼時にはいつも行列ができるのは商店街の買い物顧客だけでなく、光家を目的に食べにくる顧客、つまり広域集客できる特徴をもったラーメン店だからである。
こうした独自な魅力を持たない店は結果として脱落していったということだ。しかし、多くの店は工夫し、努力し、「松原安売り商店街」というコンセプトの旗を自らの経営ポリシーとしてきたということである。

ここから学ぶことは小さくとも、いや小さければ小さいほど明快なコンセプト(=選ばれる理由)を持たなければならないということである。そして、その一点にあらゆる経営資源を集中するということである。大きな商業施設はその物理的な大きさ故に集中・集積の意味が薄まってしまう。逆に、小さな商店街であればこそコンセプトを磨き続けることが必要となる。コンセプトを共有し、継続し磨きつづける珍しい商店街である。
2、小売りの原点、実感販売
過去10年、右肩下がりの流通にあって売り上げを伸ばしてきたのはどこか、それは周知のネット通販企業である。例えばその象徴であるが、若い世代にとってのショッピングは有店舗で実際の商品を見て確かめ、ネット上の一番安い通販サイトから商品を買う。そんな光景は数年前から日常となってきた。また、共稼ぎ家庭が当たり前の時代にあって食品などの日常消費商品の買い物時間は極めて少ない多忙な生活となっている。あるいは子育て中の主婦やシニア世代にとって重い買い物は身体的にもつらいものである。こうした買い物行動の解決に向かったのがネットスーパーで1回の買い物金額が5000円以上の場合は無料となっている。そして、東京の都市部においては既に当たり前のサービスとして実施されている。
しかし、それは同時に同じ商品ばかりを購入することにつながり、新たな発見やメニューの広がりに向かうことは少なくなる。結果、消費は固定的になり、売り上げも落ちていくこととなる。そして、どういうことが小売り現場で今起きているか、百貨店もスーパーもプロの実演販売や商品を熟知している仕入れ担当者を店頭に立たせる、そうした販売を再検討している。
ネット上には膨大な情報が存在し、日々新たなものとなっている。しかし、ヴァーチャルな世界であり、実感に乏しい。実演販売のように、目の前で説明され実際に使い調理し、食べてみる、これこそが買い物に必要であると、売り手も買い手も気づき始めたということである。
この買い物のリアリテイは必要に迫られた買い物にあっても、便利さと共に不可欠なものとなっている。コストを押さえるためには顧客も小売りもセルフスタイルへと否応無く向かってきた。今、そうした課題解決が、規模の大小を問わず、小売り現場に求められている。松原商店街には、実感世界、リアリティ、実、そうした新鮮な変化に溢れている。小売りの原点を踏まえていればこその「ハマのアメ横」である。
3、小売りの原点、相対コミュニケーション
ところで松原商店街の場合、そのほとんどが顧客と相対し、例えば安いわけありの訳を説明してくれる。いや説明というより、店頭を歩く顧客に向かって声をかけ、そんな声がいたる所でかわされる。これも一つの賑わい感を醸成しているのだが、興味があれば顧客は足を止め、実感納得して買うことができる。曲がった規格外のきゅうりだけれど美味しさは変わらないよ!とか、この時期のこの魚は刺身にするのが一番、あるいは明日は休みだからこの値段にしているといった会話である。実は町の商店街の最大の強みが、こうした相対してのコミュニケーション商売である。
有り余るほどの情報世界に生きているが、実は過剰情報の時代とは使える情報がいかに少ないかである。昨年、ホテルの飲食メニューの虚偽表示が大きな社会的話題となった。次から次へと一流ホテルなどの虚偽表示が発覚し記者会見が行われた。一流ホテルブランドが失墜したのだが、顧客の側にもそうした「嘘」を見抜く実感力を有していなかったという反省も生まれた。そうした体験学習を踏まえ、売る側と買う側が相対して会話する、時に世間話も含めてだが、そうした信頼関係こそが小売業の原点である。砂町銀座商店街でも感じたことだが、洪福寺松原商店街においても感じたことである。それらの延長線上に「ハマのアメ横」もあるということだ。
 写真は魚幸水産の売り場で買い求めた刺身の盛り合わせである。マグロの赤みと中トロの刺身であったが、特に中トロはうまかった。そして、買い求めた折、夏の暑い日であったこともあるのだが、奥まったところに保冷剤代わりの製氷機があり、セルフでポリ袋に氷を入れて持ち帰ることを勧めてくれた。こうしたことも相対であればこそのサービスで、更に満足度が高まるということだ。
写真は魚幸水産の売り場で買い求めた刺身の盛り合わせである。マグロの赤みと中トロの刺身であったが、特に中トロはうまかった。そして、買い求めた折、夏の暑い日であったこともあるのだが、奥まったところに保冷剤代わりの製氷機があり、セルフでポリ袋に氷を入れて持ち帰ることを勧めてくれた。こうしたことも相対であればこそのサービスで、更に満足度が高まるということだ。
町の商店街は必要なのかと流通専門家の間においてもそのように議論されている。スマホに「○○したいのだが」、あるいは「○○を買いたいのだが」と検索すれば、マップ上にいくつかの選択肢が即座に提供される。そんな便利な時代にあって、そうしたスマホ程度の便利さであれば町の商店街はいらない。もし、商店街が存在する理由、顧客に”あって欲しい”と望まれるには、そうした情報では得られない「相対」ならではのリアルな情報となる。こうした相互のコミュニケーションを無くした商店街は、勿論消滅し、シャッター通りとなる。
効率さ、便利さ、売る側も買う側もこうしたことばかりを追い求めてきた時代から、「人」が介在することによって生まれる豊かな買い物へと、そんな体験からの揺れ戻しが始まっている。
例えば、シニア世代に向けた通販ビジネスにエバーライフという企業が福岡にある。皇潤というブランドでヒアルロン酸などを販売し成長しているが、この会社の顧客窓口となるコールセンターのオペレーターは担当者制となっている。担当者制という固定的であるが故に効率からは離れたシステムであるが、顧客は担当者がいることによって安心して相談ができる。時に世間話をするなど仲のよいリアルな関係をつくることになる。通販という顔が見えない関係から相対しての会話ができるそんな小売りの原点とも言うべきシステムを実は通販企業も実践しているのだ。
豊かな時代、生活の「質」が消費のパラダイム転換のキーワードとなって久しいが、実はこうした小売りの原則は商店街にこそ求められ、そして応えることが商店街の明日を創っていく。(続く)
「商店街から学ぶ」洪福寺松原商店街(後半)を公開いたします。「ハマのアメ横」と呼ばれる安さの奥に、小売りの原点・原則がしっかりと実践されている。今、商店街にこそこの原則が求められており、松原商店街に学びます。
商店構成も顧客によって創られている

砂町銀座商店街の場合もそうであったが、年数を経ることによって、結果今日の商店構成へと至る。松原商店街の場合、結構業種的にはバランスのとれた構成となっている。生鮮三品を始め、パン、総菜、豆腐、練り製品、乾物、焼き鳥、和菓子、婦人服や用品店、ドラッグに眼鏡、生活雑貨や美容室まで一通りの商店が軒を連ねている。こうした専門店だけでなく、生鮮三品を始めとした地域スーパーもある。
恐らく、店舗としては少ないなと感じたのは飲食店である。吉祥寺や戸越銀座商店街もそうであったが、必ずあるのがラーメン専門店である。松原商店街にも光家という横浜家系の専門店があり、昼時にはいつも行列ができる人気店となっている。

商店街に飲食店が少ないのは駅から5分ほど歩き、周辺にはオフィスビルの少ない住宅地であるからで、写真のように天王町駅前商店街には多くの飲食店がある。昼時には周辺のビジネスマンやOLが利用している。光家のようにどうしても食べてみたいと広域集客できる飲食店以外は商売として成立しないということである。
また、ラーメン専門店とともに人気なのが焼き鳥である。ここ松原商店街にも露店タイプの焼き鳥店があり、なぜか市場という光景になじんだものとなっている。
そして、80店舗弱という小さな松原商店街にあって、結構目立つのが喫茶店や甘味処である。シニア世代向きではあるが、店の中を覗いてみるとファミリーで楽しんでおり、これまた特徴の一つとなっている。

行政が企画推進する商店街ツアー
砂町銀座でよく目にしたのが「食べ歩きツアー」であった。焼き鳥を食べながら、おでんをつまみながら、昭和の商店街を歩くという自然発生的に生まれたものであるが、松原商店街の場合は神奈川県が積極的に商店街を取り上げ、PRを兼ねてツアーを組んでいる。そのなかの一つが松原商店街である。そのツアーの概要であるが、大手旅行会社(近畿日本ツーリストグループ)とタイアップし、神奈川ならではの魅力ある旅行商品の開発と、全国規模での観光PRを行う初めての事業に取り組むとのことである。
 ツアー例:横浜・横須賀下町商店街&横須賀軍港めぐり!(日帰り)
ツアー例:横浜・横須賀下町商店街&横須賀軍港めぐり!(日帰り)横浜駅-洪福寺松原商店街-横浜橋通商店街-三笠公園-ヴェルニー公園-軍港めぐりクルーズ-ヴェルニー公園-どぶ板通り商店街-横浜駅
*ツアーの実施は平成26年7月23日から平成27年1月31日までとなっており、既にスタートしている。
このツアー例以外にも人気の横浜赤レンガ倉庫やカップヌードルミュージアムなどを回るいくつかツアーがある。
立地商売を超えるテーマ競争力
松原商店街周辺には他の商店街同様商業施設があり、激しい競争が行われている。相鉄線天王町駅から松原商店街に向かう道筋は商店街となっており、近くにはイオン天王町店やマルエツ天王町店もある。砂町銀座商店街も大型商業施設に囲まれたそんな市場と同じ構造を持っている。砂町銀座商店街について小さな商店街であるとブログに書いたが、松原商店街は更に小さな商店街である。しかも、駅前ではなく、徒歩5分という歩かないと行けないどちらかと言えば立地としては中途半端な商店街である。砂町銀座商店街は長さ670メートル、店舗数約180、松原商店街は東西240メートル、南北200メートル、店舗数約80弱。
 こうした小さな商店街が勝ち残るにはどうすれば良いのか、その答えの一つが松原商店街にある。どの店も「安さ」へと向かい、仕入れの工夫やアイディア、売り切る努力、ローコスト経営・・・・ほとんどの店が同じ方向を向いて商売しているということである。この「安さ」というテーマ集積力こそが競争軸となっている。この小さな商店街に平日2万人、休日2.5万人、年末には1日10万人以上という賑わいはこのテーマ集積にある。
こうした小さな商店街が勝ち残るにはどうすれば良いのか、その答えの一つが松原商店街にある。どの店も「安さ」へと向かい、仕入れの工夫やアイディア、売り切る努力、ローコスト経営・・・・ほとんどの店が同じ方向を向いて商売しているということである。この「安さ」というテーマ集積力こそが競争軸となっている。この小さな商店街に平日2万人、休日2.5万人、年末には1日10万人以上という賑わいはこのテーマ集積にある。 砂町銀座商店街でも感じたが、買い物が楽しい。それは「安さ」を買うということだが、期待を裏切らない安さであり、それ以上の新鮮な「発見」があるからだ。あれも、これもと目移りがして、ついつい買ってしまったという、普段であればケチケチ消費がこの日だけは特別になる。忘れていた衝動買いという言葉を思い出した。
砂町銀座商店街でも感じたが、買い物が楽しい。それは「安さ」を買うということだが、期待を裏切らない安さであり、それ以上の新鮮な「発見」があるからだ。あれも、これもと目移りがして、ついつい買ってしまったという、普段であればケチケチ消費がこの日だけは特別になる。忘れていた衝動買いという言葉を思い出した。単独激安店ならば全国至る所にある。しかし、これほどまでに「商店街」として実践できているところを知らない。それは戦後何も無いところに、周りは住宅もまばら、駅からも離れた場所。そんなゼロからのスタートという、創業の精神が今なお残っているからであろう。
買い物の楽しさ
 ところで商店街の入り口に100円ショップのダイソーが出店している。東広島に誕生したダイソーは国内2800店舗、海外840店舗、3700億円を超える売り上げという、その成長には目を見張るものがある。特に、バブル以降デフレの時代の旗手の一社であったダイソーを当時多くの顧客が支持したのは次の3つの魅力であった。
ところで商店街の入り口に100円ショップのダイソーが出店している。東広島に誕生したダイソーは国内2800店舗、海外840店舗、3700億円を超える売り上げという、その成長には目を見張るものがある。特に、バブル以降デフレの時代の旗手の一社であったダイソーを当時多くの顧客が支持したのは次の3つの魅力であった。1.「買い物の自由」;
すべて100円、価格を気にせず買える。買い物の解放感、普段の不満解消。「ダイソーは主婦のレジャーランド」。(現在は200円やそれ以上の商品もあるが、今なお基本は100円である。)
2.「新しい発見」;
「これも100円で買えるの?!」という新鮮な驚き。月80品目新製品導入。(現在ではもっと多く導入となっている)
3.「選択の自由」;
色違い、型違い、素材違い、どれを取ってもすべて100円。
一言で言えば、”100円で「こんなものが買えるのか」という新鮮な感動”であった。このダイソーが松原商店街において見事に共振しているのはこうした買い物の楽しさにある。そして、こうした買い物の楽しさは、消費金額の差はあるが、ある意味日常化したアウトレット人気に通じるものである。
砂町銀座商店街ほど足を運ぶことが少なかったこともあって看板娘や名物オヤジに出会うことはなかった。しかし、恐らくそうした人物は間違いなくいる。楽しい買い物の主役が商品であるとすれば、看板娘は謂わば名脇役である。
必要に迫られた買い物から、楽しみをもってする買い物がここ洪福寺松原商店街にもあった。年末にはこの楽しさを求めて県内外からの買い物客が「ハマのアメ横」に押し寄せる。
洪福寺松原商店街に学ぶ
1、コンセプトを共有し、磨き続ける商店街
戦後ゼロからのスタートという創業の精神が今なお生きていると書いたが、その歴史を見ていくと松原商店街にも競争という大波が押し寄せていることが分かる。商店街にはいくつかの小さな市場ビルがあった。商店街を一つの市場と位置づけるとすれば市場内市場といったものである。既に他の建物へと変わってしまった「ゴールデンマート」は変化の象徴である。入っていた飲食店を含め肉店など6店は移転あるいは閉店している。あるいは松原商店街入り口を少し入った左側にある「松原センター」内にも空き店舗はある。更に言うならば餃子専門店などの閉店もある。しかし、多くのショッピングセンターを見てきた私に取って、スクラップ&ビルトが当たり前の世界になっており、松原商店街における閉店は極めて少なく珍しい存在である。
 どんな変化が松原商店街にあったかであるが、まず魚幸水産は少し前に新しいビルにリニューアルし、その少し先にあるスーパーマーケットマルセンも新しい建物へとリニューアルしている。リニューアルできるとは成長し、更に成長するための投資である。年末には「ハマのアメ横」となって売りまくると思うが、自転車や徒歩で買いにくる周辺住民に愛されない限り、成長はない。
どんな変化が松原商店街にあったかであるが、まず魚幸水産は少し前に新しいビルにリニューアルし、その少し先にあるスーパーマーケットマルセンも新しい建物へとリニューアルしている。リニューアルできるとは成長し、更に成長するための投資である。年末には「ハマのアメ横」となって売りまくると思うが、自転車や徒歩で買いにくる周辺住民に愛されない限り、成長はない。こうしたなかで、唯一安くはない飲食店がある。それが光家という横浜家系のラーメン専門店である。ラーメン(並)600円と他の家系のラーメンと比較し安く設定されてはいるが、商店街の総菜や弁当価格等を考えれば少し高めではある。しかし、カウンター席だけであるが、昼時にはいつも行列ができるのは商店街の買い物顧客だけでなく、光家を目的に食べにくる顧客、つまり広域集客できる特徴をもったラーメン店だからである。
こうした独自な魅力を持たない店は結果として脱落していったということだ。しかし、多くの店は工夫し、努力し、「松原安売り商店街」というコンセプトの旗を自らの経営ポリシーとしてきたということである。

ここから学ぶことは小さくとも、いや小さければ小さいほど明快なコンセプト(=選ばれる理由)を持たなければならないということである。そして、その一点にあらゆる経営資源を集中するということである。大きな商業施設はその物理的な大きさ故に集中・集積の意味が薄まってしまう。逆に、小さな商店街であればこそコンセプトを磨き続けることが必要となる。コンセプトを共有し、継続し磨きつづける珍しい商店街である。
2、小売りの原点、実感販売
過去10年、右肩下がりの流通にあって売り上げを伸ばしてきたのはどこか、それは周知のネット通販企業である。例えばその象徴であるが、若い世代にとってのショッピングは有店舗で実際の商品を見て確かめ、ネット上の一番安い通販サイトから商品を買う。そんな光景は数年前から日常となってきた。また、共稼ぎ家庭が当たり前の時代にあって食品などの日常消費商品の買い物時間は極めて少ない多忙な生活となっている。あるいは子育て中の主婦やシニア世代にとって重い買い物は身体的にもつらいものである。こうした買い物行動の解決に向かったのがネットスーパーで1回の買い物金額が5000円以上の場合は無料となっている。そして、東京の都市部においては既に当たり前のサービスとして実施されている。
しかし、それは同時に同じ商品ばかりを購入することにつながり、新たな発見やメニューの広がりに向かうことは少なくなる。結果、消費は固定的になり、売り上げも落ちていくこととなる。そして、どういうことが小売り現場で今起きているか、百貨店もスーパーもプロの実演販売や商品を熟知している仕入れ担当者を店頭に立たせる、そうした販売を再検討している。
ネット上には膨大な情報が存在し、日々新たなものとなっている。しかし、ヴァーチャルな世界であり、実感に乏しい。実演販売のように、目の前で説明され実際に使い調理し、食べてみる、これこそが買い物に必要であると、売り手も買い手も気づき始めたということである。
この買い物のリアリテイは必要に迫られた買い物にあっても、便利さと共に不可欠なものとなっている。コストを押さえるためには顧客も小売りもセルフスタイルへと否応無く向かってきた。今、そうした課題解決が、規模の大小を問わず、小売り現場に求められている。松原商店街には、実感世界、リアリティ、実、そうした新鮮な変化に溢れている。小売りの原点を踏まえていればこその「ハマのアメ横」である。
3、小売りの原点、相対コミュニケーション
ところで松原商店街の場合、そのほとんどが顧客と相対し、例えば安いわけありの訳を説明してくれる。いや説明というより、店頭を歩く顧客に向かって声をかけ、そんな声がいたる所でかわされる。これも一つの賑わい感を醸成しているのだが、興味があれば顧客は足を止め、実感納得して買うことができる。曲がった規格外のきゅうりだけれど美味しさは変わらないよ!とか、この時期のこの魚は刺身にするのが一番、あるいは明日は休みだからこの値段にしているといった会話である。実は町の商店街の最大の強みが、こうした相対してのコミュニケーション商売である。
有り余るほどの情報世界に生きているが、実は過剰情報の時代とは使える情報がいかに少ないかである。昨年、ホテルの飲食メニューの虚偽表示が大きな社会的話題となった。次から次へと一流ホテルなどの虚偽表示が発覚し記者会見が行われた。一流ホテルブランドが失墜したのだが、顧客の側にもそうした「嘘」を見抜く実感力を有していなかったという反省も生まれた。そうした体験学習を踏まえ、売る側と買う側が相対して会話する、時に世間話も含めてだが、そうした信頼関係こそが小売業の原点である。砂町銀座商店街でも感じたことだが、洪福寺松原商店街においても感じたことである。それらの延長線上に「ハマのアメ横」もあるということだ。
 写真は魚幸水産の売り場で買い求めた刺身の盛り合わせである。マグロの赤みと中トロの刺身であったが、特に中トロはうまかった。そして、買い求めた折、夏の暑い日であったこともあるのだが、奥まったところに保冷剤代わりの製氷機があり、セルフでポリ袋に氷を入れて持ち帰ることを勧めてくれた。こうしたことも相対であればこそのサービスで、更に満足度が高まるということだ。
写真は魚幸水産の売り場で買い求めた刺身の盛り合わせである。マグロの赤みと中トロの刺身であったが、特に中トロはうまかった。そして、買い求めた折、夏の暑い日であったこともあるのだが、奥まったところに保冷剤代わりの製氷機があり、セルフでポリ袋に氷を入れて持ち帰ることを勧めてくれた。こうしたことも相対であればこそのサービスで、更に満足度が高まるということだ。町の商店街は必要なのかと流通専門家の間においてもそのように議論されている。スマホに「○○したいのだが」、あるいは「○○を買いたいのだが」と検索すれば、マップ上にいくつかの選択肢が即座に提供される。そんな便利な時代にあって、そうしたスマホ程度の便利さであれば町の商店街はいらない。もし、商店街が存在する理由、顧客に”あって欲しい”と望まれるには、そうした情報では得られない「相対」ならではのリアルな情報となる。こうした相互のコミュニケーションを無くした商店街は、勿論消滅し、シャッター通りとなる。
効率さ、便利さ、売る側も買う側もこうしたことばかりを追い求めてきた時代から、「人」が介在することによって生まれる豊かな買い物へと、そんな体験からの揺れ戻しが始まっている。
例えば、シニア世代に向けた通販ビジネスにエバーライフという企業が福岡にある。皇潤というブランドでヒアルロン酸などを販売し成長しているが、この会社の顧客窓口となるコールセンターのオペレーターは担当者制となっている。担当者制という固定的であるが故に効率からは離れたシステムであるが、顧客は担当者がいることによって安心して相談ができる。時に世間話をするなど仲のよいリアルな関係をつくることになる。通販という顔が見えない関係から相対しての会話ができるそんな小売りの原点とも言うべきシステムを実は通販企業も実践しているのだ。
豊かな時代、生活の「質」が消費のパラダイム転換のキーワードとなって久しいが、実はこうした小売りの原則は商店街にこそ求められ、そして応えることが商店街の明日を創っていく。(続く)
2014年08月26日
未来塾(9)「商店街から学ぶ」洪福寺松原商店街(前半)
ヒット商品応援団日記No590(毎週更新) 2014.8.26.
第9回の未来塾は洪福寺松原商店街から学びます。横浜の生活者にとってはなじみのある商店街ですが、東京の生活者にとってはほとんど知られていない「ハマのアメ横」と呼ばれるユニークな商店街です。上野のアメ横と同様「安さ」を売り物にした商店街ですが、その「安さ」の奥にある商店街の原点とも言うべきポリシーを学びます。

横浜には3大商店街があり、その賑わいぶりは各々異なり、そのなかでも親しみを込めて「ハマのアメ横」と呼ばれる洪福寺松原商店街がある。実は以前から友人にその賑わいぶりを聞いていたが、どんな激安ぶりなのか興味をそそられ何回か炎天下の商店街に足を運んでみた。
その実感であるが、今日の激安の原点である「わけあり商品」「ローコスト経営」「賑わいづくり」「売り切る力」「小売業はアイディア業」「人なつっこさ」「業種を超えた安さの追求と共有」・・・・・町の商店街の原点、商売の原点ともいうべき要素が至る所で体感した。
今、上野のアメ横は上野という街自体が変わりつつある。上野公園側にはおしゃれな飲食店が入る商業ビルがつくられ、アキバのAKB48に触発されて「ご当地アイドル」の発表舞台がつくられる。一方、アメ横センタービル地下の食品売り場に代表されるようにアジア系、中国系飲食が至る所にに進出している。年末の買い出し=アメ横というイメージから変わりつつある。街は常に変わっていくものであり、もしかしたら、あの懐かしい人ごみで溢れる市場感覚はここ洪福寺松原商店街にしか残らないのではと思われるぐらいである。東西250メートル、南北200メートルに約80店舗弱と規模は極めて小さいながらあの「上野のアメ横」のもつ匂いを残す商店街であった。

洪福寺松原商店街は横浜から相鉄線に乗り3つめの天王町駅から徒歩5分ほどのところにある。横浜の3大商店街の内、横浜橋通り商店街は横浜市営地下鉄阪東橋駅徒歩2分、六角橋商店街は東急東横線白楽駅の駅前にある。前回の戸越銀座商店街を始め多くの商店街が駅前という好立地にあるのだが、松原商店街は砂町銀座商店街と同様に駅から離れたところにある。
何故「ハマのアメ横」と呼ばれる名物商店街になったのか、商店街ビジネスの原点が実は松原商店街にもあった。
その松原商店街の誕生であるが、どこか上野のアメ横を思い起こさせる共通するものがある。昭和24年米軍の車両置き場として接収されていた天王町界隈や松原付近が解除返還される。住宅もまばらだった一角に昭和25年1号店とも言うべき萩原醤油店が開店する。醤油1升につき3合の景品付きで値段も安く評判を呼ぶ。その後八百屋、乾物店、魚屋など相次いで店舗を構える。
昭和27年には18店舗になるが、周辺の住宅はまだまだ少なく、ある程度広域集客することがビジネス課題となる。そこでつけたキャッチフレーズが「松原安売り商店街」であった。上野のアメ横も戦後の焼け野原からの、ゼロからの出発であった。そして、お客を呼ぶにはどうしたら良いのか、まだまだ物が不足している時代にあって、安く提供することが「上野のアメ横」も「ハマのアメ横」も同様の商売のポリシーでありその原点であった。
元祖わけあり商売

商店街創業のなかでも、今日の集客の中心的店舗である魚幸水産は当時からユニークな商法であった。三崎漁港や北海道から直接仕入れ激安で売りまくる。今日でいうところの「わけあり商売」を当時から行っていたということである。
炎天下ということもあり、店先には鮮魚は並ばれていないが、入り口の奥まったところではマグロの解体ショーと共に、ブロックになったマグロを客と相対で値段をやり取りして売っていく、そんな実演商売である。これも上野のアメ横商売を彷彿とさせる光景が日常的に繰り広げられている。

魚幸水産と共に、商店街の集客のコアとなっているのが外川商店という青果店である。年末のTV報道で取り上げられる青果店であるが、次から次へと商品が売れ、売るタイミングを逃さないために、空となった段ボール箱をテントの上に放り投げ、一時保管するといった松原商店街の一種の風物詩にもなっている青果店である。
炎天下の昼時という最も買い物時間にはふさわしくない時であったが、テントの上には段ボールの空箱がいくつも積まれていた。
この外川商店も激安商品で溢れている。季節柄果物は桃の最盛期で1個100円程度とかなり安く売られている。

また、この外川商店も魚幸水産と同様、見事なくらいの「わけあり商品」が店頭に並んでいる。写真の商品はきゅうりであるが、なんと一山100円である。そして、見ていただくとわかるが、見事なくらい曲がった規格外商品である。商店街には青果店は他にも3店ある。例えば、規格外ではないまっすぐなきゅうりを売っている青果店の場合、一山150円であった。
こうした商品が店先の路上にまで進出して売られている。実は、この商店街の南北に伸びる通りは旧東海道で10メートルほどの道幅があるのだが、これもルール違反ではあるが、道幅は半分ほどになり、結果として一つの賑わい演出につながっている。
冒頭の写真もこの外川商店の全容写真であるが、他の店もそうであるが、その多くはテントとパラソルが店先のフェースとして使われている。
テントとパラソルが商店街のアイデンティティ
テントとパラソルからイメージされるのが市場、マルシェである。洪福寺松原商店街も多くの商店街と同様振興組合があるが、その誕生と成長のコンセプトである「松原安売り商店街」が商店街全体のイメージをつくっている。そのシンボル、アイデンティティがテントであり、パラソルである。
次の写真はそうした店頭の風景写真である。

どちらかというと、上野と同様の戦後の闇市的雰囲気を醸し出している商店街であるが、このカラフルなテントとパラソルによって、他には無い独自な世界をつくり出している。
エブリデーロープライス、毎日が特売日

エブリデーロープライスをポリシーに世界No1の流通企業になったのはあのウオルマートであるが、そのウオルマートを見に行かなくとも日本にもそうした企業があり無借金経営を果たしているのがスーパーオーケーである。周知のようにスーパーにおけるわけあり商品の元祖でもあるのだが、特売というセール設定を無くしたスーパーである。結果、特売の折り込みチラシといった経費を無くすこととなり、これもローコスト経営へとつながる。ちなみにオーケーの経営の目標は「売上高総経費率を15%以下に抑える」というローコスト経営にある。
ところでオーケーのように全体システムとして実施してはいないが、基本的な考え方はこの松原商店街においても至る所で見られる。
写真の値書きの上に「本日限り」とあるが、3回ほど日を違えて見て回ったが、毎回同じ「本日限り」であった。
あるいは不二家の菓子ぺこちゃんも50円とこれも激安である。

こうした個々の商店と共に、ここ松原商店街では横水市場という業務用スーパーも出店している。周知のように量的には大袋商品が多いが、それほどでは無い商品も売られている。また、面白いことに、奥まったところにある鮮魚コーナーでは普通の刺身類なども売られており、あるいは青果や酒類も売られ、業務用ではない小さな単位の商品も安価で売られている。業務用スーパーではあるが、一般顧客への小売りを意識したMDとなっているのは、推測するに最近流行の業務用スーパーのFC店かもしれない。

更にユニークなことであるが、物販店以外の美容院についても激安サービス料金となっている。松原商店街は80店舗弱の商店街であるが、激安は魚幸水産や外川商店だけでなく、業種を超えた「安売り」、まさに「松原安売り商店街」というコンセプトに基づき、どこよりも強いパワーを創ることに成功している。エブリデーだけでなく、オールショップロープライスとなっている。
名物づくりへのチャレンジ

このようにハマのアメ横と呼ばれるように「安さ」は大きな名物となっている。その中心は前述の魚幸水産や外川商店によるわけあり商売であるが、小さな商店も個店ならではの名物づくりにチャレンジしている。例えば、ぼけた写真で申し訳ないが、サン・ペルルの半熟卵入りのカレーパン(200円)もその一つである。少し辛めのカレーに半熟卵がほど良く合ってなかなか美味しくいただいた。
また、こうした商店街巡りの楽しみの一つがこうした「買い食い」であるが、懐かしいハムカツが(1枚65円)精肉店で売られていたので、食パンに千切りキャベツと一緒にはさんで食べたが、昭和30年代にタイムスリップした。
更には、知る人ぞ知る段階であると思うが、キムチの冬伯の唐辛子みそやキムチ類もなかなか美味しく、聞くところによると近隣の焼肉店が買い求めに来店すると言う。これも一般販売だけでなく、業務用需要をもまかなっている専門店ということだ。
砂町銀座商店街にも煮卵やシュウマイ、おでんといった名物惣菜が沢山あったが、戸越銀座商店街にはなかった名物が、ここ松原商店街には存在している。(後半へ続く)
第9回の未来塾は洪福寺松原商店街から学びます。横浜の生活者にとってはなじみのある商店街ですが、東京の生活者にとってはほとんど知られていない「ハマのアメ横」と呼ばれるユニークな商店街です。上野のアメ横と同様「安さ」を売り物にした商店街ですが、その「安さ」の奥にある商店街の原点とも言うべきポリシーを学びます。

「商店街から学ぶ」
時代の観察
洪福寺松原商店街
横浜には3大商店街があり、その賑わいぶりは各々異なり、そのなかでも親しみを込めて「ハマのアメ横」と呼ばれる洪福寺松原商店街がある。実は以前から友人にその賑わいぶりを聞いていたが、どんな激安ぶりなのか興味をそそられ何回か炎天下の商店街に足を運んでみた。
その実感であるが、今日の激安の原点である「わけあり商品」「ローコスト経営」「賑わいづくり」「売り切る力」「小売業はアイディア業」「人なつっこさ」「業種を超えた安さの追求と共有」・・・・・町の商店街の原点、商売の原点ともいうべき要素が至る所で体感した。
今、上野のアメ横は上野という街自体が変わりつつある。上野公園側にはおしゃれな飲食店が入る商業ビルがつくられ、アキバのAKB48に触発されて「ご当地アイドル」の発表舞台がつくられる。一方、アメ横センタービル地下の食品売り場に代表されるようにアジア系、中国系飲食が至る所にに進出している。年末の買い出し=アメ横というイメージから変わりつつある。街は常に変わっていくものであり、もしかしたら、あの懐かしい人ごみで溢れる市場感覚はここ洪福寺松原商店街にしか残らないのではと思われるぐらいである。東西250メートル、南北200メートルに約80店舗弱と規模は極めて小さいながらあの「上野のアメ横」のもつ匂いを残す商店街であった。

洪福寺松原商店街は横浜から相鉄線に乗り3つめの天王町駅から徒歩5分ほどのところにある。横浜の3大商店街の内、横浜橋通り商店街は横浜市営地下鉄阪東橋駅徒歩2分、六角橋商店街は東急東横線白楽駅の駅前にある。前回の戸越銀座商店街を始め多くの商店街が駅前という好立地にあるのだが、松原商店街は砂町銀座商店街と同様に駅から離れたところにある。
何故「ハマのアメ横」と呼ばれる名物商店街になったのか、商店街ビジネスの原点が実は松原商店街にもあった。
その松原商店街の誕生であるが、どこか上野のアメ横を思い起こさせる共通するものがある。昭和24年米軍の車両置き場として接収されていた天王町界隈や松原付近が解除返還される。住宅もまばらだった一角に昭和25年1号店とも言うべき萩原醤油店が開店する。醤油1升につき3合の景品付きで値段も安く評判を呼ぶ。その後八百屋、乾物店、魚屋など相次いで店舗を構える。
昭和27年には18店舗になるが、周辺の住宅はまだまだ少なく、ある程度広域集客することがビジネス課題となる。そこでつけたキャッチフレーズが「松原安売り商店街」であった。上野のアメ横も戦後の焼け野原からの、ゼロからの出発であった。そして、お客を呼ぶにはどうしたら良いのか、まだまだ物が不足している時代にあって、安く提供することが「上野のアメ横」も「ハマのアメ横」も同様の商売のポリシーでありその原点であった。
元祖わけあり商売

商店街創業のなかでも、今日の集客の中心的店舗である魚幸水産は当時からユニークな商法であった。三崎漁港や北海道から直接仕入れ激安で売りまくる。今日でいうところの「わけあり商売」を当時から行っていたということである。
炎天下ということもあり、店先には鮮魚は並ばれていないが、入り口の奥まったところではマグロの解体ショーと共に、ブロックになったマグロを客と相対で値段をやり取りして売っていく、そんな実演商売である。これも上野のアメ横商売を彷彿とさせる光景が日常的に繰り広げられている。

魚幸水産と共に、商店街の集客のコアとなっているのが外川商店という青果店である。年末のTV報道で取り上げられる青果店であるが、次から次へと商品が売れ、売るタイミングを逃さないために、空となった段ボール箱をテントの上に放り投げ、一時保管するといった松原商店街の一種の風物詩にもなっている青果店である。
炎天下の昼時という最も買い物時間にはふさわしくない時であったが、テントの上には段ボールの空箱がいくつも積まれていた。
この外川商店も激安商品で溢れている。季節柄果物は桃の最盛期で1個100円程度とかなり安く売られている。

また、この外川商店も魚幸水産と同様、見事なくらいの「わけあり商品」が店頭に並んでいる。写真の商品はきゅうりであるが、なんと一山100円である。そして、見ていただくとわかるが、見事なくらい曲がった規格外商品である。商店街には青果店は他にも3店ある。例えば、規格外ではないまっすぐなきゅうりを売っている青果店の場合、一山150円であった。
こうした商品が店先の路上にまで進出して売られている。実は、この商店街の南北に伸びる通りは旧東海道で10メートルほどの道幅があるのだが、これもルール違反ではあるが、道幅は半分ほどになり、結果として一つの賑わい演出につながっている。
冒頭の写真もこの外川商店の全容写真であるが、他の店もそうであるが、その多くはテントとパラソルが店先のフェースとして使われている。
テントとパラソルが商店街のアイデンティティ
テントとパラソルからイメージされるのが市場、マルシェである。洪福寺松原商店街も多くの商店街と同様振興組合があるが、その誕生と成長のコンセプトである「松原安売り商店街」が商店街全体のイメージをつくっている。そのシンボル、アイデンティティがテントであり、パラソルである。
次の写真はそうした店頭の風景写真である。

どちらかというと、上野と同様の戦後の闇市的雰囲気を醸し出している商店街であるが、このカラフルなテントとパラソルによって、他には無い独自な世界をつくり出している。
エブリデーロープライス、毎日が特売日

エブリデーロープライスをポリシーに世界No1の流通企業になったのはあのウオルマートであるが、そのウオルマートを見に行かなくとも日本にもそうした企業があり無借金経営を果たしているのがスーパーオーケーである。周知のようにスーパーにおけるわけあり商品の元祖でもあるのだが、特売というセール設定を無くしたスーパーである。結果、特売の折り込みチラシといった経費を無くすこととなり、これもローコスト経営へとつながる。ちなみにオーケーの経営の目標は「売上高総経費率を15%以下に抑える」というローコスト経営にある。
ところでオーケーのように全体システムとして実施してはいないが、基本的な考え方はこの松原商店街においても至る所で見られる。
写真の値書きの上に「本日限り」とあるが、3回ほど日を違えて見て回ったが、毎回同じ「本日限り」であった。
あるいは不二家の菓子ぺこちゃんも50円とこれも激安である。

こうした個々の商店と共に、ここ松原商店街では横水市場という業務用スーパーも出店している。周知のように量的には大袋商品が多いが、それほどでは無い商品も売られている。また、面白いことに、奥まったところにある鮮魚コーナーでは普通の刺身類なども売られており、あるいは青果や酒類も売られ、業務用ではない小さな単位の商品も安価で売られている。業務用スーパーではあるが、一般顧客への小売りを意識したMDとなっているのは、推測するに最近流行の業務用スーパーのFC店かもしれない。

更にユニークなことであるが、物販店以外の美容院についても激安サービス料金となっている。松原商店街は80店舗弱の商店街であるが、激安は魚幸水産や外川商店だけでなく、業種を超えた「安売り」、まさに「松原安売り商店街」というコンセプトに基づき、どこよりも強いパワーを創ることに成功している。エブリデーだけでなく、オールショップロープライスとなっている。
名物づくりへのチャレンジ

このようにハマのアメ横と呼ばれるように「安さ」は大きな名物となっている。その中心は前述の魚幸水産や外川商店によるわけあり商売であるが、小さな商店も個店ならではの名物づくりにチャレンジしている。例えば、ぼけた写真で申し訳ないが、サン・ペルルの半熟卵入りのカレーパン(200円)もその一つである。少し辛めのカレーに半熟卵がほど良く合ってなかなか美味しくいただいた。
また、こうした商店街巡りの楽しみの一つがこうした「買い食い」であるが、懐かしいハムカツが(1枚65円)精肉店で売られていたので、食パンに千切りキャベツと一緒にはさんで食べたが、昭和30年代にタイムスリップした。
更には、知る人ぞ知る段階であると思うが、キムチの冬伯の唐辛子みそやキムチ類もなかなか美味しく、聞くところによると近隣の焼肉店が買い求めに来店すると言う。これも一般販売だけでなく、業務用需要をもまかなっている専門店ということだ。
砂町銀座商店街にも煮卵やシュウマイ、おでんといった名物惣菜が沢山あったが、戸越銀座商店街にはなかった名物が、ここ松原商店街には存在している。(後半へ続く)
2014年08月13日
未来塾(8)「スポーツから学ぶ」「プロ化」市場
ヒット商品応援団日記No589(毎週更新) 2014.8.13.
未来塾(8)ではスポーツという視点から新たにどんなビジネスが生まれているかを学びます。長年スポーツを取材しその変化を体験してきた元京都新聞社運動部長であった井上年央氏にお願いをしました。第一回目は「プロ化」市場、アマチュアスポーツからプロスポーツへ、その変化する市場について学びます。

日本のスポーツは今年(2014年)で103歳といえる。1911(明治44)年、現在の日本体育協会の前身である大日本体育協会が創立された。次の年にストックホルムで開かれる第5回オリンピックに初出場を目指す動きだった。中心人物は柔道の講道館創始者、嘉納治五郎で、大日本体育協会の初代会長に就任する。ストックホルム五輪の日本選手団もつとめるが、選手は男子陸上の2人だけだった。
◇
近年の日本のスポーツにいくつかの大きな変化があった。代表的なものは「プロ化」、さらに「女子(女性)スポーツの興隆」、「企業スポーツの衰退と再生」といったことだろう。ほかにも、スポーツ医学の発達で選手寿命が伸びたり、ジュニア選手の活躍などの現象もある。野球やサッカーなどで、日本のトップレベルの選手が、続々と海外に進出しているのも、一昔前には考えられなかった傾向だ。
まず、1回目では、プロ化の流れを追ってみたい。日本人のスポーツ感覚に「アマチュアは崇高であり、プロはお金儲けにすぎない」というのがあった。「あった」と書いたのは、現在では、もうその価値観から脱していると考えていいからである。後遺症というべきものもある。野球は、プロとアマの垣根が長くあり、プロの選手やコーチが、高校、大学などのアマチュア選手を指導してはいけなかった。笑い話に「長嶋茂雄が、家でご飯を食べながら、息子の一茂に野球の話をしたら、ルール違反の指導に当たるのか」というのがあった。相撲、ゴルフ、ボクシングも、アマとプロの組織は別々である。サッカーは、世界の常識を日本でも取り入れていて、日本サッカー協会という一つの団体がプロもアマも統括している。
サッカー以外の他の競技でも、オリンピック級の選手は、すべてプロ活動をしていると見て差し支えない。ただし、マスコミ露出の極めて少ないマイナー競技は別だ。スポーツのプロ化は、スポーツの各種競技の間に「貧富」の格差を確実に生む。
◇
振り返ると、日本のスポーツは当初、大学中心だった。「早慶戦」であり、帝国大学の学生が主役だった。戦後、高度経済成長とともに、強化の面では企業(実業団)チーム、選手が突出する。1964(昭和39)年東京五輪の女子バレーボール金メダル「東洋の魔女」は、「いとへん」企業のニチボー貝塚だった。
ヨーロッパ、アメリカのスポーツからみると、日本の企業スポーツは理解不能といわれた。会社の社員がビジネスの仕事ではなく、スポーツをして給料をもらうのである。賢い日本人は独特の言葉を編み出した。「ノンプロ」である。
独自の成長を遂げた?日本のスポーツは、経済のバブル崩壊とともに否応なしに姿かたちを変える。第1の変革は、企業(実業団)が本業の不振をなんとかしなくてはいけなくなり、金のかかるスポーツを一斉に切り始めた。スポーツの社員たちは本業の仕事をしていなかった。事実上の解雇に遭う。かつて、企業スポーツは「会社の知名度を上げる何よりの宣伝部隊であり、勝つことで、社員や工員の士気を高めた」のだが、バブル崩壊で企業の存続が危ぶまれ「そんなこと言っておれない」状況になった。
1993年に誕生したサッカーのJリーグは、企業の強力アな支援が背景にあり、滑り込みセーフ。当時、川淵三郎チェアマンは「Jリーグの立ち上げ時期が半年遅れていたら、実現しなかっただろう」と言っている。
◇
さて、スポーツの「プロ」の要件とはなんだろう。選手は、当然ながらアマチュアには真似のできない高度なプレーをしなければならない。技術的なことだけではなく、「スター性」が求められる。入場料を払っても見たいと思う観客が必要だ。そのスポーツ、選手のスポンサーがでてくることも不可欠だろう。ひっくるめて「興行」が成立し、プロスポーツが確立される。
もっとくだいていうなら、そのスポーツに「お金が集まる」ということだ。サッカーのJ2・愛媛は、優秀なストライカーを獲得するために、ファンドを設定した。一般のファンなどから集めたお金で有力選手と契約する。その選手が活躍してクラブ収入が増えれば、出資者に還元する仕組みだ。成功すれば、スポーツに「ファンド」を持ち込む一つの道が開かれる。注目していきたい。
現在、国内で正面からプロリーグを名乗っているのは、プロ野球以外ではサッカーのJリーグと、バスケットボールのbjリーグである。ラグビーは、海外ではプロ化の動きが定着しつつあるが、国内では「企業スポーツ」から地域の「クラブスポーツ」に切り替え中で、一気にプロリーグ化は難しいだろう。他の競技では、チームゲームであっても、プロとしての契約選手と、従来のアマ選手が混在している状況だ。
日本のスポーツ百年の歴史からみると、プロスポーツの世界は、まだまだヨチヨチ歩きなのだ。だからこそ、ビジネスチャンスがある、ともいえる。2020年東京五輪に向けて、日本のスポーツが大きく変化することだけは確かだ。

1、「プロ化」という市場
企業スポーツからプロスポーツへの進化の象徴としてJリーグが挙げられるが、そのことはビジネスとしての経済的自立を目指すことでもある。その経済的自立とは普通の企業経営と同じで、経営は顧客(フアン)によって支えられる。そして、Jリーグにおいてもやっと資金調達のひとつの方法としてファンドが実施され始めている。
ファンドという方法は既に映画製作から太陽エネルギーによる電力会社の運営や、最近では東日本大震災における産業復興のためのファンドとして、個人でも参加しやすい小額ファンドとして浸透している。ある意味、やっとスポーツビジネスにおいてもという感がするが、こうしたスポーツファンドを活用した新たなスポーツ市場の開発が期待される。
つまり、「プロ化」とは自ら顧客創造を行う企業活動のもう一つの名前としてあるということである。
そして、プロ化した市場とはその頂点にはオリンピックやサッカーであればワールドカップなど世界選手権といった活躍の舞台がある。この舞台に立つためには通らなければならないいくつものステップや段階があり、登りつめるための道具やトレーニングといった市場が世界レベルに広がっている。最近のヒット商品としては、古くはイチロー選手が愛用してきたワコールのコンディショニングウエアCW-Xがそうであるし、最近では女子フィギュアスケートの浅田真央選手が使用しているマットレスのエアーウィーヴが該当する。そして、その先に何があるかと言えば、「プロ化」とはグローバル市場につながるキーワードのことであり、既にナイキやアディダスなどが活動しているように世界市場の開拓ということになる。
周知のナイキという企業はもともとは日本のシューズ・メーカーの米国輸入販売業者として創業した企業である。日本の技術者を引き抜き次第に自社製品を開発するようになり、現在では世界170以上の国と地域で自社製品の販売、ネット通販、卸売ならびにライセ ンス契約による販売を行っており、世界中のほぼ全ての地域でスポーツ・シューズ・メーカーとしてトップクラ スのブランドを築き上げている。
この「プロ化」とはつまるところ企業活動そのものであり、プロチームが顧客による入場料収入やグッズ販売などによって経営がなされる。しかし、企業経営がそうであるように「成長」は宿命となっている。そのために野球もサッカーも選手自身を一つの「商品」とし、他チームへの移籍によって新たな収入を得るようなもう一つのビジネスモデルが活性化している。そして、Jリーグにおいても更なるグローバルビジネスメニューとして新たな試みも始まっている。その良き事例が横浜Fマリノスとタイとのサッカー交流で、タイのスター選手をリクルートし、その試合をタイにて放送し、放映権料という収入を得る。更には選手育成のノウハウを提供したり、タイ進出の日本企業をタイリーグのスポンサーとしてつないだり、つまり、スポーツを通じた互いに新たな市場の創造を行うといったビジネスモデルである。
2、「プロ化」市場の裾野は大きい
景気の好不況はあってもGDPの60%を消費が占める成熟した豊かな時代にいる。そして、グルメの時代とは飽食の時代のことでもあり、時代の最大関心事は「健康」であり、ダイエットとなった。一時期の“楽してやせる”“サプリメントを飲めばやせられる”といった間違った方法による経験を経て、健康としてのスポーツが見直され始めている。
例えば、オリンピックのマラソンのようにトレーニングを積んだアスリートの世界ではなく、全国至るところで行われる町の市民マラソンや今なおブームが去らない皇居一周ジョギングまで、広く浸透している。最近では村おこし、町おこしと連動したマラソン大会が行われ、給水所ならぬ名産品のスイカを食べる休み所といった、勝敗を競う競技よりかは一つのスポーツイベントを楽しむ方向のマラソン大会まで実施されてきた。
また、皇居のジョギングアスリートを対象とした「鹿屋アスリート食堂」が東京竹橋にオープンしたが、連日多くの人で賑わっている。面白いことにその賑わいの中心はアスリートではなく、周辺のサラリーマンやOLであるという点である。この「鹿屋アスリート食堂」の特徴は鹿屋体育大学による「スポーツ栄養学」に基づいたメニューにより「バランスのとれた豊かな食生活」を提案。 アスリートの食事のように、健康的な減量やパフォーマンスを発揮するためのメニューに関心と共に人気が集まっている理由からだ。
こうした健康をキーワードとしたスポーツ市場の広がりにあって、その頂点にあるのが「味の素ナショナルトレーニングセンター」内にある栄養管理食堂「勝ち飯食堂」であろう。このように「プロのための食事」が健康スポーツ市場を牽引し、「鹿屋アスリート食堂」といった裾野市場を誕生させているといっても過言ではない。つまり、「プロ化」による新市場の開発はやっと始まったばかりであるということである。
(続く)
未来塾(8)ではスポーツという視点から新たにどんなビジネスが生まれているかを学びます。長年スポーツを取材しその変化を体験してきた元京都新聞社運動部長であった井上年央氏にお願いをしました。第一回目は「プロ化」市場、アマチュアスポーツからプロスポーツへ、その変化する市場について学びます。

「スポーツから学ぶ」
時代の観察
「プロ化」市場
日本のスポーツは今年(2014年)で103歳といえる。1911(明治44)年、現在の日本体育協会の前身である大日本体育協会が創立された。次の年にストックホルムで開かれる第5回オリンピックに初出場を目指す動きだった。中心人物は柔道の講道館創始者、嘉納治五郎で、大日本体育協会の初代会長に就任する。ストックホルム五輪の日本選手団もつとめるが、選手は男子陸上の2人だけだった。
◇
近年の日本のスポーツにいくつかの大きな変化があった。代表的なものは「プロ化」、さらに「女子(女性)スポーツの興隆」、「企業スポーツの衰退と再生」といったことだろう。ほかにも、スポーツ医学の発達で選手寿命が伸びたり、ジュニア選手の活躍などの現象もある。野球やサッカーなどで、日本のトップレベルの選手が、続々と海外に進出しているのも、一昔前には考えられなかった傾向だ。
まず、1回目では、プロ化の流れを追ってみたい。日本人のスポーツ感覚に「アマチュアは崇高であり、プロはお金儲けにすぎない」というのがあった。「あった」と書いたのは、現在では、もうその価値観から脱していると考えていいからである。後遺症というべきものもある。野球は、プロとアマの垣根が長くあり、プロの選手やコーチが、高校、大学などのアマチュア選手を指導してはいけなかった。笑い話に「長嶋茂雄が、家でご飯を食べながら、息子の一茂に野球の話をしたら、ルール違反の指導に当たるのか」というのがあった。相撲、ゴルフ、ボクシングも、アマとプロの組織は別々である。サッカーは、世界の常識を日本でも取り入れていて、日本サッカー協会という一つの団体がプロもアマも統括している。
サッカー以外の他の競技でも、オリンピック級の選手は、すべてプロ活動をしていると見て差し支えない。ただし、マスコミ露出の極めて少ないマイナー競技は別だ。スポーツのプロ化は、スポーツの各種競技の間に「貧富」の格差を確実に生む。
◇
振り返ると、日本のスポーツは当初、大学中心だった。「早慶戦」であり、帝国大学の学生が主役だった。戦後、高度経済成長とともに、強化の面では企業(実業団)チーム、選手が突出する。1964(昭和39)年東京五輪の女子バレーボール金メダル「東洋の魔女」は、「いとへん」企業のニチボー貝塚だった。
ヨーロッパ、アメリカのスポーツからみると、日本の企業スポーツは理解不能といわれた。会社の社員がビジネスの仕事ではなく、スポーツをして給料をもらうのである。賢い日本人は独特の言葉を編み出した。「ノンプロ」である。
独自の成長を遂げた?日本のスポーツは、経済のバブル崩壊とともに否応なしに姿かたちを変える。第1の変革は、企業(実業団)が本業の不振をなんとかしなくてはいけなくなり、金のかかるスポーツを一斉に切り始めた。スポーツの社員たちは本業の仕事をしていなかった。事実上の解雇に遭う。かつて、企業スポーツは「会社の知名度を上げる何よりの宣伝部隊であり、勝つことで、社員や工員の士気を高めた」のだが、バブル崩壊で企業の存続が危ぶまれ「そんなこと言っておれない」状況になった。
1993年に誕生したサッカーのJリーグは、企業の強力アな支援が背景にあり、滑り込みセーフ。当時、川淵三郎チェアマンは「Jリーグの立ち上げ時期が半年遅れていたら、実現しなかっただろう」と言っている。
◇
さて、スポーツの「プロ」の要件とはなんだろう。選手は、当然ながらアマチュアには真似のできない高度なプレーをしなければならない。技術的なことだけではなく、「スター性」が求められる。入場料を払っても見たいと思う観客が必要だ。そのスポーツ、選手のスポンサーがでてくることも不可欠だろう。ひっくるめて「興行」が成立し、プロスポーツが確立される。
もっとくだいていうなら、そのスポーツに「お金が集まる」ということだ。サッカーのJ2・愛媛は、優秀なストライカーを獲得するために、ファンドを設定した。一般のファンなどから集めたお金で有力選手と契約する。その選手が活躍してクラブ収入が増えれば、出資者に還元する仕組みだ。成功すれば、スポーツに「ファンド」を持ち込む一つの道が開かれる。注目していきたい。
現在、国内で正面からプロリーグを名乗っているのは、プロ野球以外ではサッカーのJリーグと、バスケットボールのbjリーグである。ラグビーは、海外ではプロ化の動きが定着しつつあるが、国内では「企業スポーツ」から地域の「クラブスポーツ」に切り替え中で、一気にプロリーグ化は難しいだろう。他の競技では、チームゲームであっても、プロとしての契約選手と、従来のアマ選手が混在している状況だ。
日本のスポーツ百年の歴史からみると、プロスポーツの世界は、まだまだヨチヨチ歩きなのだ。だからこそ、ビジネスチャンスがある、ともいえる。2020年東京五輪に向けて、日本のスポーツが大きく変化することだけは確かだ。

スポーツビジネスに学ぶ
1、「プロ化」という市場
企業スポーツからプロスポーツへの進化の象徴としてJリーグが挙げられるが、そのことはビジネスとしての経済的自立を目指すことでもある。その経済的自立とは普通の企業経営と同じで、経営は顧客(フアン)によって支えられる。そして、Jリーグにおいてもやっと資金調達のひとつの方法としてファンドが実施され始めている。
ファンドという方法は既に映画製作から太陽エネルギーによる電力会社の運営や、最近では東日本大震災における産業復興のためのファンドとして、個人でも参加しやすい小額ファンドとして浸透している。ある意味、やっとスポーツビジネスにおいてもという感がするが、こうしたスポーツファンドを活用した新たなスポーツ市場の開発が期待される。
つまり、「プロ化」とは自ら顧客創造を行う企業活動のもう一つの名前としてあるということである。
そして、プロ化した市場とはその頂点にはオリンピックやサッカーであればワールドカップなど世界選手権といった活躍の舞台がある。この舞台に立つためには通らなければならないいくつものステップや段階があり、登りつめるための道具やトレーニングといった市場が世界レベルに広がっている。最近のヒット商品としては、古くはイチロー選手が愛用してきたワコールのコンディショニングウエアCW-Xがそうであるし、最近では女子フィギュアスケートの浅田真央選手が使用しているマットレスのエアーウィーヴが該当する。そして、その先に何があるかと言えば、「プロ化」とはグローバル市場につながるキーワードのことであり、既にナイキやアディダスなどが活動しているように世界市場の開拓ということになる。
周知のナイキという企業はもともとは日本のシューズ・メーカーの米国輸入販売業者として創業した企業である。日本の技術者を引き抜き次第に自社製品を開発するようになり、現在では世界170以上の国と地域で自社製品の販売、ネット通販、卸売ならびにライセ ンス契約による販売を行っており、世界中のほぼ全ての地域でスポーツ・シューズ・メーカーとしてトップクラ スのブランドを築き上げている。
この「プロ化」とはつまるところ企業活動そのものであり、プロチームが顧客による入場料収入やグッズ販売などによって経営がなされる。しかし、企業経営がそうであるように「成長」は宿命となっている。そのために野球もサッカーも選手自身を一つの「商品」とし、他チームへの移籍によって新たな収入を得るようなもう一つのビジネスモデルが活性化している。そして、Jリーグにおいても更なるグローバルビジネスメニューとして新たな試みも始まっている。その良き事例が横浜Fマリノスとタイとのサッカー交流で、タイのスター選手をリクルートし、その試合をタイにて放送し、放映権料という収入を得る。更には選手育成のノウハウを提供したり、タイ進出の日本企業をタイリーグのスポンサーとしてつないだり、つまり、スポーツを通じた互いに新たな市場の創造を行うといったビジネスモデルである。
2、「プロ化」市場の裾野は大きい
景気の好不況はあってもGDPの60%を消費が占める成熟した豊かな時代にいる。そして、グルメの時代とは飽食の時代のことでもあり、時代の最大関心事は「健康」であり、ダイエットとなった。一時期の“楽してやせる”“サプリメントを飲めばやせられる”といった間違った方法による経験を経て、健康としてのスポーツが見直され始めている。
例えば、オリンピックのマラソンのようにトレーニングを積んだアスリートの世界ではなく、全国至るところで行われる町の市民マラソンや今なおブームが去らない皇居一周ジョギングまで、広く浸透している。最近では村おこし、町おこしと連動したマラソン大会が行われ、給水所ならぬ名産品のスイカを食べる休み所といった、勝敗を競う競技よりかは一つのスポーツイベントを楽しむ方向のマラソン大会まで実施されてきた。
また、皇居のジョギングアスリートを対象とした「鹿屋アスリート食堂」が東京竹橋にオープンしたが、連日多くの人で賑わっている。面白いことにその賑わいの中心はアスリートではなく、周辺のサラリーマンやOLであるという点である。この「鹿屋アスリート食堂」の特徴は鹿屋体育大学による「スポーツ栄養学」に基づいたメニューにより「バランスのとれた豊かな食生活」を提案。 アスリートの食事のように、健康的な減量やパフォーマンスを発揮するためのメニューに関心と共に人気が集まっている理由からだ。
こうした健康をキーワードとしたスポーツ市場の広がりにあって、その頂点にあるのが「味の素ナショナルトレーニングセンター」内にある栄養管理食堂「勝ち飯食堂」であろう。このように「プロのための食事」が健康スポーツ市場を牽引し、「鹿屋アスリート食堂」といった裾野市場を誕生させているといっても過言ではない。つまり、「プロ化」による新市場の開発はやっと始まったばかりであるということである。
元京都新聞社運動部長
スポーツライター 井上年央
ヒット商品応援団 飯塚敞士
スポーツライター 井上年央
ヒット商品応援団 飯塚敞士
(続く)
2014年08月05日
暑い夏に寒い消費
ヒット商品応援団日記No588(毎週更新) 2014.8.5.
少し前の日経新聞に民間の調査機関による4-6月期の経済指標の予測一覧が掲載されていた。調査機関6社の予測中央値として、GDPの前期比▲2.0、年率▲8.0、個人消費▲4.3、設備投資▲3.1であった。リーマンショック以降最大の落ち込みで、最早駈け込み需要の反動減であるとは言えなくなった。全て消費増税によるものとは考えないが、日本が持つ構造的問題にあると思っている。そして、更に8月から乳製品やソーセージなどの値上げの発表があり、ガソリン価格は夏の最需要期を迎え高止まり状態にある。
ところで、消費増税前の3月末に「消費増税による消費変化への視点として」というタイトルで次の3つの視点が重要であるとブログに書いた。
1、消費の移動を見極める
2、新たなローコスト業態に注目
3、余暇の過ごし方への注視
そして、次のようにコメントした。
『現在は「リーマンショック前の水準」に戻ってきた。低すぎた株価を元に戻したという意味ではアベノミクスによるところが大きいと思うが、5年前と比較し、消費環境は極めて悪い。駈け込み需要の反動という意味合いではなく、周知のように、まず大手企業の賃金は上がったが、70%を占める中小企業勤労者の賃金は逆に下がっている。更には円安によるエネルギーコストのアップによる物価高が消費を萎縮させる。円安によって輸出が増えるどころか、輸入超過という赤字体質に陥ってしまった。そして、今回の増税である。現象としてではあるが、なぜかスタグフレーション的状況に向かいつつあるようで心配である。』
上記1の「消費の移動」については、昨年からの傾向として挙げられるのが、新車販売に見られる傾向である。普通車・小型車が売れず、軽自動車が売れ続け、販売台数トップ10のうち軽自動車は7つ占めている。中には軽自動車への乗り替えがかなり含まれているという傾向である。ちょうど2年半ほど前の日経MJヒット商品番付の東関脇にホンダのN BOXが入ったが燃費の良さばかりかそのデザイン性からヒットした車である。以降、こうしたコスパ型商品は車以外においても次々とヒットしている。ちなみにこの年の番付には東大関に LCC、西大関には LINEが入っている。これらは全てデフレ型商品である。
次のローコスト業態への注目であるが、日経MJの番付を引用するならば、上期のヒット商品番付の東横綱に入った格安スマホがその着目すべき傾向の象徴であろう。この格安スマホは、現在のスマホが高機能高価格であるのに対し、良く計算すれば少々動画が遅くてもこれで十分とするいわゆる低機能低価格市場商品と言える。そして、発売したイオンでは今なお売れ続けている。
ところで、TVネタとして「激安ランチ」があるが、その代表がワンコイン(500円)ランチである。最近ではそのワンコインランチを出すところが減ってきているという。飲食店にとっては宣伝費代わりに安くするということだが、その宣伝効果も当たり前であるが長続きはしない。今、注目されているのが「ランチパスポート」で、1冊ほぼ1000円で購入し、そこに掲載されている飲食店のメニューが店舗の違いはあるものの例えば1200円のメニューが500円になるといった仕掛けで、1店舗3回までで3ヶ月利用できる。ランチの選択肢が広がり、5回も使えば1000円の元は取れるということで順次エリアが拡大している。但し、魅力ある仕組みではあるが、”今日は終わりました”といった店もあり、どこまで継続利用されていくか問題もある。
ところで「余暇の過ごし方」であるが、7月上旬のJTBによる夏休みの旅行予測が発表されたが、旅行人数は過去最高となり、夏のボーナスも多かったことから消費は盛んになると予測レポートがあった。しかし、今年のGWの時の予測もそうであったが、「移動」という点ではある程度活性されていたが、その内容は円安から海外から国内へ、日数も少なく、使用金額も減って、という内容で、例えば人気なのは海外クルージングのLCC版であったり、鉄ちゃん人気といったテーマを持ったファミリーの旅である。
今年の夏は暑く、旅ではないが家族で楽しむ時間としては、例えばアイスクリーム工場の見学と食べ放題といった工場見学が人気となっている。その象徴と思うが横浜にある日清食品の「カップヌードルミュージアム」で、自分でデザインしたカップに、4種類の中からお好みのスープと、12種類の具材の中から4つのトッピングを選べるという「マイカップヌードル」作りが人気とのこと。こうした「家族との時間」を楽しむという余暇の原点回帰が強く出てきている。
景気は「気」次第とした心理市場の時代ではあるが、メーカーであれ、小売業であれ、飲食店であれ、「誰を顧客とするのか」によってその景気の考え方も異なる。2004年から2006年にかけて都心ではミニバブルが起きた。都心の不動産価格は上がり、ファンドマネジャーという職種が注目され、消費では「ヒトリッチ」や「隠れ家」といったキーワードが出現した。今、そこまではいかないが都内の億ションが即日完売し、都心のホテルや百貨店の老舗飲食店は満席状態である。全ての市場はまだら模様となっているので、「平均値」あるいは「一般的」市場はない。ただ、今回の経済指標のマイナス幅や新幹線や国内航空の予約状況を見ると、暑い夏に寒い消費と言わざるを得ない、そんな夏である。(続く)
少し前の日経新聞に民間の調査機関による4-6月期の経済指標の予測一覧が掲載されていた。調査機関6社の予測中央値として、GDPの前期比▲2.0、年率▲8.0、個人消費▲4.3、設備投資▲3.1であった。リーマンショック以降最大の落ち込みで、最早駈け込み需要の反動減であるとは言えなくなった。全て消費増税によるものとは考えないが、日本が持つ構造的問題にあると思っている。そして、更に8月から乳製品やソーセージなどの値上げの発表があり、ガソリン価格は夏の最需要期を迎え高止まり状態にある。
ところで、消費増税前の3月末に「消費増税による消費変化への視点として」というタイトルで次の3つの視点が重要であるとブログに書いた。
1、消費の移動を見極める
2、新たなローコスト業態に注目
3、余暇の過ごし方への注視
そして、次のようにコメントした。
『現在は「リーマンショック前の水準」に戻ってきた。低すぎた株価を元に戻したという意味ではアベノミクスによるところが大きいと思うが、5年前と比較し、消費環境は極めて悪い。駈け込み需要の反動という意味合いではなく、周知のように、まず大手企業の賃金は上がったが、70%を占める中小企業勤労者の賃金は逆に下がっている。更には円安によるエネルギーコストのアップによる物価高が消費を萎縮させる。円安によって輸出が増えるどころか、輸入超過という赤字体質に陥ってしまった。そして、今回の増税である。現象としてではあるが、なぜかスタグフレーション的状況に向かいつつあるようで心配である。』
上記1の「消費の移動」については、昨年からの傾向として挙げられるのが、新車販売に見られる傾向である。普通車・小型車が売れず、軽自動車が売れ続け、販売台数トップ10のうち軽自動車は7つ占めている。中には軽自動車への乗り替えがかなり含まれているという傾向である。ちょうど2年半ほど前の日経MJヒット商品番付の東関脇にホンダのN BOXが入ったが燃費の良さばかりかそのデザイン性からヒットした車である。以降、こうしたコスパ型商品は車以外においても次々とヒットしている。ちなみにこの年の番付には東大関に LCC、西大関には LINEが入っている。これらは全てデフレ型商品である。
次のローコスト業態への注目であるが、日経MJの番付を引用するならば、上期のヒット商品番付の東横綱に入った格安スマホがその着目すべき傾向の象徴であろう。この格安スマホは、現在のスマホが高機能高価格であるのに対し、良く計算すれば少々動画が遅くてもこれで十分とするいわゆる低機能低価格市場商品と言える。そして、発売したイオンでは今なお売れ続けている。
ところで、TVネタとして「激安ランチ」があるが、その代表がワンコイン(500円)ランチである。最近ではそのワンコインランチを出すところが減ってきているという。飲食店にとっては宣伝費代わりに安くするということだが、その宣伝効果も当たり前であるが長続きはしない。今、注目されているのが「ランチパスポート」で、1冊ほぼ1000円で購入し、そこに掲載されている飲食店のメニューが店舗の違いはあるものの例えば1200円のメニューが500円になるといった仕掛けで、1店舗3回までで3ヶ月利用できる。ランチの選択肢が広がり、5回も使えば1000円の元は取れるということで順次エリアが拡大している。但し、魅力ある仕組みではあるが、”今日は終わりました”といった店もあり、どこまで継続利用されていくか問題もある。
ところで「余暇の過ごし方」であるが、7月上旬のJTBによる夏休みの旅行予測が発表されたが、旅行人数は過去最高となり、夏のボーナスも多かったことから消費は盛んになると予測レポートがあった。しかし、今年のGWの時の予測もそうであったが、「移動」という点ではある程度活性されていたが、その内容は円安から海外から国内へ、日数も少なく、使用金額も減って、という内容で、例えば人気なのは海外クルージングのLCC版であったり、鉄ちゃん人気といったテーマを持ったファミリーの旅である。
今年の夏は暑く、旅ではないが家族で楽しむ時間としては、例えばアイスクリーム工場の見学と食べ放題といった工場見学が人気となっている。その象徴と思うが横浜にある日清食品の「カップヌードルミュージアム」で、自分でデザインしたカップに、4種類の中からお好みのスープと、12種類の具材の中から4つのトッピングを選べるという「マイカップヌードル」作りが人気とのこと。こうした「家族との時間」を楽しむという余暇の原点回帰が強く出てきている。
景気は「気」次第とした心理市場の時代ではあるが、メーカーであれ、小売業であれ、飲食店であれ、「誰を顧客とするのか」によってその景気の考え方も異なる。2004年から2006年にかけて都心ではミニバブルが起きた。都心の不動産価格は上がり、ファンドマネジャーという職種が注目され、消費では「ヒトリッチ」や「隠れ家」といったキーワードが出現した。今、そこまではいかないが都内の億ションが即日完売し、都心のホテルや百貨店の老舗飲食店は満席状態である。全ての市場はまだら模様となっているので、「平均値」あるいは「一般的」市場はない。ただ、今回の経済指標のマイナス幅や新幹線や国内航空の予約状況を見ると、暑い夏に寒い消費と言わざるを得ない、そんな夏である。(続く)