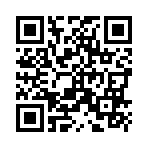2007年07月29日
視座という目
ヒット商品応援団日記No188(毎週2回更新) 2007.7.29.
ビジネスプランやマーケティングコンセプトを考える時、私が一番重要だと思っているのが「視座」についてである。例えば、視点は「どこを見るのか」であり、視野は「どの範囲を見るのか」であり、視座は「どこに立って見るのか」である。理屈っぽく言えば、視座によって、見る範囲もどこを見るかも変わってくる。視座をポリシー、志し、コンセプトと言っても間違いではない。時間という視座に立てば、伝承すべきこと、引き継ぐべきこと、といったことになり、空間という視座に立てば、俯瞰的に、あるいは地球という大きな目線で、といった「立ち位置」が重要となる。
数年前、本業回帰とか、創業回帰、あるいはコアコンピタンスといったキーワードでビジネス再生の動きがあったが、創業期には理想とするビジネスの原型、ある意味完成形に近いものがあることから立ち戻ろうという動きになったのである。ビジネスは成長と共に次第に複雑になり、視座も視野も視点もごちゃ混ぜになり、大切なことを見失ってしまう時代にいる。
私が「人力経営」を書いたテーマはこの視座についてであった。ヒット商品、売れている商品の裏側にある明確な視座、顧客に対し、社会に対する企業としてどう立つべきかその視座を明らかにしたかったからである。和菓子の叶匠寿庵もそうした視座を持つ企業である。創業者である芝田清次の講演を聞き感動した経験を持っていたのだが、その後の叶匠寿庵の視座を実感したかったのである。詳しくは「人力経営」を読んでいただきたいが、その視座は日本の風土、自然、郷土への「思い」であると言える。芝田清次は太平洋戦争に従軍し、負傷し片目を失ってふるさと大津の地に復員する。満州の地で失った目で見続けていたのは、こよなく愛した家族や郷里で、それは63000坪という広大なテーマパーク「寿長生の郷(すないのさと)」へとつながっている。1日平均700名の顧客が訪れる寿長生の郷は、日本の原風景というより、豊かな自然への感謝の「思い」が凝縮・昇華された美しい郷である。寿長生の郷は勿論のこと、商品にも、もてなし方にも、全てに視座は守られ、磨かれて今へとつながっている。
ところで牛肉偽装事件のミートホープ社はどうであろうか。20年以上も前から、牛肉ミンチに豚肉、鳥肉、羊肉などを混ぜて、加工販売してきた。誰一人見抜くことが出来ないまま20年を経て来た訳であるが、勿論悪知恵ではあるが偽装表示をしなければアイディア経営と言われて来たかもしれない。精進料理の多くは殺生しない食ということから、大豆などを巧く使ったフェイク(もどき)食品によるものである。他にも、マーガリンは戦後の一時期バターの代用であったし、魚肉ソーセージもソーセージの代用食品であった。ミートホープ社の田中社長にはミンチ肉のプロの視点はあり、食肉加工という領域では極め付きのスペシャリストであった。決定的に欠けていたのは市場、顧客への視座であった。作った商品は自己利益に立った商品であり、顧客は利益をもたらすだけの存在である。三方よしにならえば、売り手よしという自己利益だけである。もし、牛肉と鶏肉との合挽きミンチによって、カロリーが少なく、しかも価格も安く、味も食感も牛肉100%と変わらないといったフェイク食品ができれば、マーケットは小さくなるが、三方よしは成立する。顧客が社会がよしとする視座が決定的に欠けていたということだ。勿論一般的平均的な視座などない。知恵やアイディアは特定市場への視座によって生かされ、結果ビジネスとなる。(続く)
ビジネスプランやマーケティングコンセプトを考える時、私が一番重要だと思っているのが「視座」についてである。例えば、視点は「どこを見るのか」であり、視野は「どの範囲を見るのか」であり、視座は「どこに立って見るのか」である。理屈っぽく言えば、視座によって、見る範囲もどこを見るかも変わってくる。視座をポリシー、志し、コンセプトと言っても間違いではない。時間という視座に立てば、伝承すべきこと、引き継ぐべきこと、といったことになり、空間という視座に立てば、俯瞰的に、あるいは地球という大きな目線で、といった「立ち位置」が重要となる。
数年前、本業回帰とか、創業回帰、あるいはコアコンピタンスといったキーワードでビジネス再生の動きがあったが、創業期には理想とするビジネスの原型、ある意味完成形に近いものがあることから立ち戻ろうという動きになったのである。ビジネスは成長と共に次第に複雑になり、視座も視野も視点もごちゃ混ぜになり、大切なことを見失ってしまう時代にいる。
私が「人力経営」を書いたテーマはこの視座についてであった。ヒット商品、売れている商品の裏側にある明確な視座、顧客に対し、社会に対する企業としてどう立つべきかその視座を明らかにしたかったからである。和菓子の叶匠寿庵もそうした視座を持つ企業である。創業者である芝田清次の講演を聞き感動した経験を持っていたのだが、その後の叶匠寿庵の視座を実感したかったのである。詳しくは「人力経営」を読んでいただきたいが、その視座は日本の風土、自然、郷土への「思い」であると言える。芝田清次は太平洋戦争に従軍し、負傷し片目を失ってふるさと大津の地に復員する。満州の地で失った目で見続けていたのは、こよなく愛した家族や郷里で、それは63000坪という広大なテーマパーク「寿長生の郷(すないのさと)」へとつながっている。1日平均700名の顧客が訪れる寿長生の郷は、日本の原風景というより、豊かな自然への感謝の「思い」が凝縮・昇華された美しい郷である。寿長生の郷は勿論のこと、商品にも、もてなし方にも、全てに視座は守られ、磨かれて今へとつながっている。
ところで牛肉偽装事件のミートホープ社はどうであろうか。20年以上も前から、牛肉ミンチに豚肉、鳥肉、羊肉などを混ぜて、加工販売してきた。誰一人見抜くことが出来ないまま20年を経て来た訳であるが、勿論悪知恵ではあるが偽装表示をしなければアイディア経営と言われて来たかもしれない。精進料理の多くは殺生しない食ということから、大豆などを巧く使ったフェイク(もどき)食品によるものである。他にも、マーガリンは戦後の一時期バターの代用であったし、魚肉ソーセージもソーセージの代用食品であった。ミートホープ社の田中社長にはミンチ肉のプロの視点はあり、食肉加工という領域では極め付きのスペシャリストであった。決定的に欠けていたのは市場、顧客への視座であった。作った商品は自己利益に立った商品であり、顧客は利益をもたらすだけの存在である。三方よしにならえば、売り手よしという自己利益だけである。もし、牛肉と鶏肉との合挽きミンチによって、カロリーが少なく、しかも価格も安く、味も食感も牛肉100%と変わらないといったフェイク食品ができれば、マーケットは小さくなるが、三方よしは成立する。顧客が社会がよしとする視座が決定的に欠けていたということだ。勿論一般的平均的な視座などない。知恵やアイディアは特定市場への視座によって生かされ、結果ビジネスとなる。(続く)
2007年07月27日
お知らせです!
私が書いた「人力経営」の内容は人生の、ビジネスの生き方論です。経営のスキルやテクニック、ハウツーものではありません。経営者の方々に読んでいただくことも有難いですが、実は若いコトを起こそうとしている人にこそ読んでいただきたい本です。ダスキン、野の葡萄、叶匠寿庵、桑野造船、エゴイスト、ヒット企業5社の裏側にある企業の生き方を書いた本です。「人力経営」の在庫情況(7/26現在)は以下となっています。出版社にはまだ在庫がありますのでどうぞご注文ください。なお、既にお読みいただいた方は、ブログのコメント欄に感想や質問をお寄せください。ブログ上もしくはメールにてご返事いたします。
Amazon
http://www.amazon.co.jp/
セブンアンドワイ
http://www.7andy.jp/books/detail?accd=31915792
紀伊国屋書店 在庫僅少
http://bookweb.kinokuniya.co.jp/htm/443410800X.html
ジュンク堂書店 在庫3冊
http://www.junkudo.co.jp/detail2.jsp?ID=0243410800
オンライン書店 ピーケーワン
http://www.bk1.jp/product/02803610
オンライン書店 本やタウン/有鱗堂 在庫1冊
http://www.honya-town.co.jp/hst/HTdispatch?author=%94%D1%92%CB%9D%C6%8Em
Yahooブックス
http://books.yahoo.co.jp/book_detail/31915792
Livedoor BOOKS
http://books.livedoor.com/item443410800X.html
ManaHouse 在庫2冊
http://www.manah.net/book/product.jsp?sku=B443410800X
Amazon
http://www.amazon.co.jp/
セブンアンドワイ
http://www.7andy.jp/books/detail?accd=31915792
紀伊国屋書店 在庫僅少
http://bookweb.kinokuniya.co.jp/htm/443410800X.html
ジュンク堂書店 在庫3冊
http://www.junkudo.co.jp/detail2.jsp?ID=0243410800
オンライン書店 ピーケーワン
http://www.bk1.jp/product/02803610
オンライン書店 本やタウン/有鱗堂 在庫1冊
http://www.honya-town.co.jp/hst/HTdispatch?author=%94%D1%92%CB%9D%C6%8Em
Yahooブックス
http://books.yahoo.co.jp/book_detail/31915792
Livedoor BOOKS
http://books.livedoor.com/item443410800X.html
ManaHouse 在庫2冊
http://www.manah.net/book/product.jsp?sku=B443410800X
2007年07月25日
マイメディア社会
ヒット商品応援団日記No187(毎週2回更新) 2007.7.25.
世界中に発信されているブログの数は7000万以上、その内37%が日本語のブログで英語圏を抜いてNO1に戻ったと報じられた。(http://japan.cnet.com/news/media/story/0,2000056023,20346610,00.htm)私もブログを書き始めて2年近くになるが、ブログの存在を知り自分でもやってみたいと思ったのが3年ほど前で、当時のブログ数は40万程度であったと思う。そして、マーケティングのブログなど誰も見ないであろうと言われたことを覚えている。昨年秋1000万というブログ数を超え、誰もが無視できないメディアとなった。簡単に自分のメディアが持てるという快感と共に、インターネット上に膨大な知の宝物が存在していることを知り、ブログ数を加速させている。
私がインターネットの世界に興味を持ったのは、なんといってもGoogleの出現であった。日本語版のタイムでその存在を知り、友人と共に自社名を入力し検索したことを覚えている。その同じタイムに昨年12月YouTubeが大きく取り上げられた。昨年10月このYouTubeをGoogleが2000億円近くで買収した時、日本のマスメディアは著作権等の法的障害を持つメディア買収だと批判的であった。しかし、今米国の大統領選挙/民主党では、このYouTubeを使った選挙が進んでいる。文字と映像、この2つの情報をマイメディアとして、一人ひとりが持つことが可能となった。しかも、最近ではタグを自由につけることが可能となり、マイメディアは不特定多数無限大のネット空間にあって、自在に特定の世界を泳ぐことが可能となった。ブログは個人新聞社となり、YouTubeは個人放送局となった。
こうした多様で膨大なメディア・情報の中から、Googleという検索エンジンによって瞬時に特定情報の世界へとたどり着く。しかし、最終的には自ら特定の情報を選択する訳である。ある意味、選択という直感によって情報を選ぶのだが、検索エンジンが日々賢く成長していくのと同時に、私たちの側も直感力を磨いていくこととなる。
今回私は「人力経営」という本を書いたが、これもまた一つのマイメディアだと思っている。ブログと本、似ているようだが、私にとって異なるメディアとの認識だ。ブログはその時々に起こるニュースや出来事に触発されて書くメディアでフローであり、別な言葉で言うと小売業的である。一方、本は思考を一点(テーマ)に固定・凝縮させて書くメディアでストックであり、メーカー的である。
ところでネット上には2600万もの日本語ブログがひしめき合っているが、こうしたマイメディア社会の中から、新しい表現者が生まれてくる。既に若いアニメ作家がネット上を舞台に活躍し、その評価を受けてリアル世界の広告などに出現している。ネット世界は良き修行の場となり、リアル世界へのインキュベーション装置となっている。私の友人の一人である地方紙の記者は私と会う度に「これから先、新聞は存続するだろうか」と聞く。私は、既に生活者のライフスタイルとして、ネット世界(バーチャル)と現実世界(リアル)とを行ったり来たりしている。既存のメディアもその境界意識をなくし、「行ったり来たり」を仕組み化する時代に来ていると答えている。つまり、一人ひとりがアーチストになり、ジャーナリストになり、研究者になり、・・・・その技術的専門的レベルを除外すれば、全てが表現者となった時代は、既存メディアもその表現の「場」を解放していかざるを得ないであろう。(続く)
「人力経営」の一般書店でのお求めですが、紀伊国屋書店さんが力を入れていただいており全国22店で取り扱っています。http://bookweb.kinokuniya.co.jp/htm/443410800X.html
世界中に発信されているブログの数は7000万以上、その内37%が日本語のブログで英語圏を抜いてNO1に戻ったと報じられた。(http://japan.cnet.com/news/media/story/0,2000056023,20346610,00.htm)私もブログを書き始めて2年近くになるが、ブログの存在を知り自分でもやってみたいと思ったのが3年ほど前で、当時のブログ数は40万程度であったと思う。そして、マーケティングのブログなど誰も見ないであろうと言われたことを覚えている。昨年秋1000万というブログ数を超え、誰もが無視できないメディアとなった。簡単に自分のメディアが持てるという快感と共に、インターネット上に膨大な知の宝物が存在していることを知り、ブログ数を加速させている。
私がインターネットの世界に興味を持ったのは、なんといってもGoogleの出現であった。日本語版のタイムでその存在を知り、友人と共に自社名を入力し検索したことを覚えている。その同じタイムに昨年12月YouTubeが大きく取り上げられた。昨年10月このYouTubeをGoogleが2000億円近くで買収した時、日本のマスメディアは著作権等の法的障害を持つメディア買収だと批判的であった。しかし、今米国の大統領選挙/民主党では、このYouTubeを使った選挙が進んでいる。文字と映像、この2つの情報をマイメディアとして、一人ひとりが持つことが可能となった。しかも、最近ではタグを自由につけることが可能となり、マイメディアは不特定多数無限大のネット空間にあって、自在に特定の世界を泳ぐことが可能となった。ブログは個人新聞社となり、YouTubeは個人放送局となった。
こうした多様で膨大なメディア・情報の中から、Googleという検索エンジンによって瞬時に特定情報の世界へとたどり着く。しかし、最終的には自ら特定の情報を選択する訳である。ある意味、選択という直感によって情報を選ぶのだが、検索エンジンが日々賢く成長していくのと同時に、私たちの側も直感力を磨いていくこととなる。
今回私は「人力経営」という本を書いたが、これもまた一つのマイメディアだと思っている。ブログと本、似ているようだが、私にとって異なるメディアとの認識だ。ブログはその時々に起こるニュースや出来事に触発されて書くメディアでフローであり、別な言葉で言うと小売業的である。一方、本は思考を一点(テーマ)に固定・凝縮させて書くメディアでストックであり、メーカー的である。
ところでネット上には2600万もの日本語ブログがひしめき合っているが、こうしたマイメディア社会の中から、新しい表現者が生まれてくる。既に若いアニメ作家がネット上を舞台に活躍し、その評価を受けてリアル世界の広告などに出現している。ネット世界は良き修行の場となり、リアル世界へのインキュベーション装置となっている。私の友人の一人である地方紙の記者は私と会う度に「これから先、新聞は存続するだろうか」と聞く。私は、既に生活者のライフスタイルとして、ネット世界(バーチャル)と現実世界(リアル)とを行ったり来たりしている。既存のメディアもその境界意識をなくし、「行ったり来たり」を仕組み化する時代に来ていると答えている。つまり、一人ひとりがアーチストになり、ジャーナリストになり、研究者になり、・・・・その技術的専門的レベルを除外すれば、全てが表現者となった時代は、既存メディアもその表現の「場」を解放していかざるを得ないであろう。(続く)
「人力経営」の一般書店でのお求めですが、紀伊国屋書店さんが力を入れていただいており全国22店で取り扱っています。http://bookweb.kinokuniya.co.jp/htm/443410800X.html
2007年07月22日
かっわいい〜ぃ現象、その後
ヒット商品応援団日記No186(毎週2回更新) 2007.7.22.
「かっわいい〜ぃ」という言葉が社会の表舞台に登場したのは、おそらく主婦の友社が1996年に創刊したCawaiiによってだと思う。いわゆる読者参加型の高校生に向けたファッション雑誌であるが、右肩下がりの渋谷109をV字回復させるという大きな役割をエゴイストと共に果たしたメディアである。創刊当初からの読者モデルで、カリスマというキーワードを一般化させたエゴイスト初代カリスマ店長渡辺加奈さんの後を引き受けた森本容子さんもCawaiiの読者モデルの一人であった。さて、当時のCawaii読者は20代半ばから後半の世代となっている。
ところで、「かっわいい〜ぃ」という言葉は何を指して表現してきたであろうか。人によって様々な感性世界があると思う。「おもしろい」「きれい」「「いとおしい」「愛らしい」、あるいは「チョットセクシー」といった言葉で表現されるが、物語消費時代における視覚の言語化現象であると私は見ている。つまり、明確に言語化できない一種の「もどかしさ」から生まれた感情表現ということだ。複雑な文脈や知識、理屈を排除した自己表現世界である。この世界を進めて来たメディアの一つが携帯電話である。「写メール」「絵文字」といったビジュアルコミュニケーションはまさに言語の視覚化である。最近の女子高生のメールを見てもそのコミュニティ以外の人間が見ても判読不可能な秘密のコードが行き交っている。
こうした「曖昧な」気持ちや感情を語らせるにはビジュアルは最適である。「かっわいい〜ぃ」という言葉の持つ世界も、この「曖昧さ」から生まれたものだ。雑誌Cawaiiのネーミングをローマ字にしたのはこうした背景からだと思う。
1990年代後半から、この「かっわいい〜ぃ」という言葉はあらゆる世界へと浸透していく。昔はおまけであった「カプセル・トイ」や「フィギュア」へ。テディベアー等のぬいぐるみ、あるいは商品パッケージやCMにも多くの「かっわいい〜ぃ」キャラクターが登場した。こうした「かっわいい〜ぃ」という「曖昧さ」は、中間、境界、なんとなく、といった意味の世界として登場する。何がかわいいの、どこがかわいいの、といっても意味はない。女性ならば誰でもがヴィトンのバッグと共に知っている村上隆氏の活動を見ていけばよく分かる。アニメや漫画といったサブカルチャーを積極的に取り入れ、新しいポップアートの世界を創造している。村上隆氏が主宰する「カイカイキキ」(http://www.kaikaikiki.co.jp/whatskaikaikiki/)の活動も「かっわいい〜ぃ」クリエーションと言えなくはない。
「かっわいい〜ぃ」という言葉の裏側に自己愛を見る事も可能であり、また日本語理解の足りなさを指摘することも必要である。ただ、コミュニケーション、表現という視座に立つと、過剰なまでの情報の中で、「かっわいい〜ぃ」は直感的表現そのものと言える。過剰な情報の時代にあって、よく言われるデザインの時代とは直感の時代のことだ。そして、その直感はアートとサブカルチャーとの中間、狭間から生まれている。和と洋、日常と非日常、女と男、人工と自然、従来異なる分野の狭間に新しい何かが生まれてくる。「かっわいい〜ぃ現象」という視覚≒言語の表現世界はこれからも進化していくと思う。コラボレーション、協業、共創、といった方法が増々重要な時代だ。(続く)
「人力経営」の一般書店でのお求めですが、紀伊国屋書店さんが力を入れていただいており全国22店で取り扱っています。http://bookweb.kinokuniya.co.jp/htm/443410800X.html
「かっわいい〜ぃ」という言葉が社会の表舞台に登場したのは、おそらく主婦の友社が1996年に創刊したCawaiiによってだと思う。いわゆる読者参加型の高校生に向けたファッション雑誌であるが、右肩下がりの渋谷109をV字回復させるという大きな役割をエゴイストと共に果たしたメディアである。創刊当初からの読者モデルで、カリスマというキーワードを一般化させたエゴイスト初代カリスマ店長渡辺加奈さんの後を引き受けた森本容子さんもCawaiiの読者モデルの一人であった。さて、当時のCawaii読者は20代半ばから後半の世代となっている。
ところで、「かっわいい〜ぃ」という言葉は何を指して表現してきたであろうか。人によって様々な感性世界があると思う。「おもしろい」「きれい」「「いとおしい」「愛らしい」、あるいは「チョットセクシー」といった言葉で表現されるが、物語消費時代における視覚の言語化現象であると私は見ている。つまり、明確に言語化できない一種の「もどかしさ」から生まれた感情表現ということだ。複雑な文脈や知識、理屈を排除した自己表現世界である。この世界を進めて来たメディアの一つが携帯電話である。「写メール」「絵文字」といったビジュアルコミュニケーションはまさに言語の視覚化である。最近の女子高生のメールを見てもそのコミュニティ以外の人間が見ても判読不可能な秘密のコードが行き交っている。
こうした「曖昧な」気持ちや感情を語らせるにはビジュアルは最適である。「かっわいい〜ぃ」という言葉の持つ世界も、この「曖昧さ」から生まれたものだ。雑誌Cawaiiのネーミングをローマ字にしたのはこうした背景からだと思う。
1990年代後半から、この「かっわいい〜ぃ」という言葉はあらゆる世界へと浸透していく。昔はおまけであった「カプセル・トイ」や「フィギュア」へ。テディベアー等のぬいぐるみ、あるいは商品パッケージやCMにも多くの「かっわいい〜ぃ」キャラクターが登場した。こうした「かっわいい〜ぃ」という「曖昧さ」は、中間、境界、なんとなく、といった意味の世界として登場する。何がかわいいの、どこがかわいいの、といっても意味はない。女性ならば誰でもがヴィトンのバッグと共に知っている村上隆氏の活動を見ていけばよく分かる。アニメや漫画といったサブカルチャーを積極的に取り入れ、新しいポップアートの世界を創造している。村上隆氏が主宰する「カイカイキキ」(http://www.kaikaikiki.co.jp/whatskaikaikiki/)の活動も「かっわいい〜ぃ」クリエーションと言えなくはない。
「かっわいい〜ぃ」という言葉の裏側に自己愛を見る事も可能であり、また日本語理解の足りなさを指摘することも必要である。ただ、コミュニケーション、表現という視座に立つと、過剰なまでの情報の中で、「かっわいい〜ぃ」は直感的表現そのものと言える。過剰な情報の時代にあって、よく言われるデザインの時代とは直感の時代のことだ。そして、その直感はアートとサブカルチャーとの中間、狭間から生まれている。和と洋、日常と非日常、女と男、人工と自然、従来異なる分野の狭間に新しい何かが生まれてくる。「かっわいい〜ぃ現象」という視覚≒言語の表現世界はこれからも進化していくと思う。コラボレーション、協業、共創、といった方法が増々重要な時代だ。(続く)
「人力経営」の一般書店でのお求めですが、紀伊国屋書店さんが力を入れていただいており全国22店で取り扱っています。http://bookweb.kinokuniya.co.jp/htm/443410800X.html
2007年07月18日
五風十雨
ヒット商品応援団日記No185(毎週2回更新) 2007.7.18.
台風4号が過ぎて良かったと思った16日午前10時過ぎ、東京に住む私のマンションが揺れ、地震を体感した。PCに向かっていたが、TVをつけたところ今回の新潟中越沖地震のテロップが流されていた。3年前の新潟中越地震の時もそうであったが、大きな地震は地を伝い230Km先の東京にもその揺れは感じる。更に、その後京都府沖の地震が1000Kmも離れた北海道や東北の太平洋沿岸まで揺れは伝わっている。当たり前と言えばそうであるが、大きなプレートの狭間の列島に住む日本人にとって自然は畏敬すべきものだと多くの人は実感したと思う。畏怖すべき自然との生活の中で、日本人は多くのこころの在り方を歴史に残して来た。沖縄で言えば台風もそうであるが、日常においても風は強く、その風にのって悪霊等悪いものがのってやってくる、その番人にあのお土産にもなっているシーサーがある。寺社の山門等にある仁王様が悪霊を入れまいと入り口で番をしてくれているのと同じである。
五風十雨(ごふう じゅうう)という言葉の意味は、五日に一度風が吹き、十日に一度雨が降る、という農作物には良い湿潤な気候、風土を表す言葉である。豊かな自然を育み、その恵みをいただくと同時に、また恐ろしい災害となる自然の力も受けざるをえないのが日本という国だ。日本の面積は地球上の陸地面積の約0.25%、過去記録されている地球上に起こったM6.0以上の地震の約20%が日本で起きているという。そして、年に数回必ず台風はやってくる。自然を前に、人為が及ばない世界であることを数千年前から続けてきたのが日本という国だ。呆然と半壊した家を前に、思い出という人生そのものである家を捨てざるを得ないお年寄りの表情は悲しい。
どんな調査をしても、約70%以上の日本人は無宗教だと答えている。米国のメガ・チャーチについて少し前に触れた事があったが、約80%の米国人が宗教を持っていると答えているが、極めて対照的である。というより、日本人は無宗教ではなくて、自然教と言った方が正確だ。キリスト教やイスラム教といった一神教という信仰心ではなく、人為が及ばない大いなるものへの信心と言った方がわかりやすい。
今東京では新しい商業施設のオープンやリニューアルが続いているが、地方の銘店、名品が続々と登場している。地方のパイロットショップも東国原知事現象にのって売上は順調だという。つまり、いかに知らない世界が多いかということとともに、いかに伝えてこなかったかということである。災害という自然ではない、豊かな自然がもたらしてくれた産物である。それをどう都市生活者に伝えていくか、どんな地域固有の自然文化物語を伝えていくかが、都市市場の開拓のポイントとなる。以前、公開した「伝え方革命」について再度添付しますのでご活用ください。(続く)

「人力経営」の一般書店でのお求めは紀伊国屋書店さんが力を入れていただいており全国22店で取り扱っています。http://bookweb.kinokuniya.co.jp/htm/443410800X.html
台風4号が過ぎて良かったと思った16日午前10時過ぎ、東京に住む私のマンションが揺れ、地震を体感した。PCに向かっていたが、TVをつけたところ今回の新潟中越沖地震のテロップが流されていた。3年前の新潟中越地震の時もそうであったが、大きな地震は地を伝い230Km先の東京にもその揺れは感じる。更に、その後京都府沖の地震が1000Kmも離れた北海道や東北の太平洋沿岸まで揺れは伝わっている。当たり前と言えばそうであるが、大きなプレートの狭間の列島に住む日本人にとって自然は畏敬すべきものだと多くの人は実感したと思う。畏怖すべき自然との生活の中で、日本人は多くのこころの在り方を歴史に残して来た。沖縄で言えば台風もそうであるが、日常においても風は強く、その風にのって悪霊等悪いものがのってやってくる、その番人にあのお土産にもなっているシーサーがある。寺社の山門等にある仁王様が悪霊を入れまいと入り口で番をしてくれているのと同じである。
五風十雨(ごふう じゅうう)という言葉の意味は、五日に一度風が吹き、十日に一度雨が降る、という農作物には良い湿潤な気候、風土を表す言葉である。豊かな自然を育み、その恵みをいただくと同時に、また恐ろしい災害となる自然の力も受けざるをえないのが日本という国だ。日本の面積は地球上の陸地面積の約0.25%、過去記録されている地球上に起こったM6.0以上の地震の約20%が日本で起きているという。そして、年に数回必ず台風はやってくる。自然を前に、人為が及ばない世界であることを数千年前から続けてきたのが日本という国だ。呆然と半壊した家を前に、思い出という人生そのものである家を捨てざるを得ないお年寄りの表情は悲しい。
どんな調査をしても、約70%以上の日本人は無宗教だと答えている。米国のメガ・チャーチについて少し前に触れた事があったが、約80%の米国人が宗教を持っていると答えているが、極めて対照的である。というより、日本人は無宗教ではなくて、自然教と言った方が正確だ。キリスト教やイスラム教といった一神教という信仰心ではなく、人為が及ばない大いなるものへの信心と言った方がわかりやすい。
今東京では新しい商業施設のオープンやリニューアルが続いているが、地方の銘店、名品が続々と登場している。地方のパイロットショップも東国原知事現象にのって売上は順調だという。つまり、いかに知らない世界が多いかということとともに、いかに伝えてこなかったかということである。災害という自然ではない、豊かな自然がもたらしてくれた産物である。それをどう都市生活者に伝えていくか、どんな地域固有の自然文化物語を伝えていくかが、都市市場の開拓のポイントとなる。以前、公開した「伝え方革命」について再度添付しますのでご活用ください。(続く)

「人力経営」の一般書店でのお求めは紀伊国屋書店さんが力を入れていただいており全国22店で取り扱っています。http://bookweb.kinokuniya.co.jp/htm/443410800X.html
2007年07月15日
「予」の市場
ヒット商品応援団日記No184(毎週2回更新) 2007.7.15.
このブログを書きながら台風4号の動きについてTVの天気予報を見ている。好きな沖縄に先日行って来たばかりということもあるが、行けば必ず立ち寄る糸満公設市場にあるnaminamiというコミュニティカフェのメンバーはどうであったか心配である。丁度、そんな時沖縄のコミュニティブログ「ティーダ」から、台風による欠航から多くの旅行者が立ち往生しており、宿泊ボランティア要請の情報が流れてきた。台風や地震といった災害予防のための情報精度はどんどん良くなり、そのためのボランティアネットワークなどが瞬時に組まれる時代だ。少し前に、コンビニにふれて、気温が2〜3度違う事で売れる商品が変わると書いたが、予報、予知、予防、予測、予想といった一つの情報に依って、あらゆるものや出来事が動く「予」の時代になっている。
しかし、「予」という情報は過剰なまでに流されており、私のブログにも情報精度とは、あるいは情報のねつ造といったキーワード検索で多くの人が訪問している。1990年代後半、多くの経済評論家やコンサルタントの未来予測はことごとく外れたという経験を持つ。関西テレビの「発掘!あるある大辞典」の時にも書いたが、過剰な情報は生活者に多くの学習体験を促し、何が正しいのか直感的判断へと向かわせている。この学習体験はマスメディアによるものから、口コミ、最近ではSNSといったネット上のコミュニティにまで及び始めている。私のブログにも自動的にトラックバックするいわゆるトラックバックスパムが数多くつけられているが、公開している以上、面倒がらずに出来る限り問題あるものは削除している。つまり、あらゆるところに真偽混濁したコマーシャルベースの情報が浸透しているということだ。
ところでこうした情報学習を踏まえた直感力、研ぎすまされた感性人間が増加していると思う。この時代のマーケティングを、共感のマーケティングとか、感動のマーケティングと呼んでいる。もっと若い世代の言葉でいうと、センスということになる。ああ、これいいじゃん〜。かっこいいじゃん、という美的感覚、感性世界という情報を感じ取る「感」マーケティングの世界だ。
ところで、変化の時代とは次から次へと新たなモノや出来事が押し寄せる時代だ。つまり、未来はわからない、だから「予」という市場は変化に対する不安を背景に増々広がっていく。少子高齢社会で言えば、予防医療ということになる。先日、今日の快眠市場を創って来た一人である大手枕メーカーの方と会って来た。認知症や転倒予防のための快眠方法を広く進めていきたいと話されていた。眠りの質を高めるために「福寿体操」と「軽い昼寝」を組み合わせて不眠を解決し、認知症や転倒を防ぐ予防方法である。「福寿体操」は長寿県沖縄の睡眠健康教室で開発された軽い運動である。また、ビジネスマンにとっても実は良いとされている短い昼寝・シェスタ(スペインやポルトガルでは社会習慣化されている)を組み合わせた方法である。こうした眠りの質的改善からも高齢者の予防医療に役立てたいという話であった。ある意味で東洋漢方における「未病」と同じ考え方だ。
快眠以外の食の世界でもこうした試みは始まっているし、高齢者ばかりか小学校低学年の子供達への様々な「予」市場が広がっている。今は、犯罪に対するセキュリティといった商品やサービスだけであるが、健康への「予」市場は大きくなっていくと思う。旧来の考え方からすると、まだ生命力溢れる子供達には必要とされないであろう多くの「予」に関する商品やサービスがこれから生まれてくるということだ。ただ、こうした新市場は、未経験市場であり、「予」という情報が偽装、ねつ造されないことを願いたい。(続く)
「人力経営」の一般書店でのお求めは紀伊国屋書店さんが力を入れていただいており全国22店で取り扱っています。http://bookweb.kinokuniya.co.jp/htm/443410800X.html
このブログを書きながら台風4号の動きについてTVの天気予報を見ている。好きな沖縄に先日行って来たばかりということもあるが、行けば必ず立ち寄る糸満公設市場にあるnaminamiというコミュニティカフェのメンバーはどうであったか心配である。丁度、そんな時沖縄のコミュニティブログ「ティーダ」から、台風による欠航から多くの旅行者が立ち往生しており、宿泊ボランティア要請の情報が流れてきた。台風や地震といった災害予防のための情報精度はどんどん良くなり、そのためのボランティアネットワークなどが瞬時に組まれる時代だ。少し前に、コンビニにふれて、気温が2〜3度違う事で売れる商品が変わると書いたが、予報、予知、予防、予測、予想といった一つの情報に依って、あらゆるものや出来事が動く「予」の時代になっている。
しかし、「予」という情報は過剰なまでに流されており、私のブログにも情報精度とは、あるいは情報のねつ造といったキーワード検索で多くの人が訪問している。1990年代後半、多くの経済評論家やコンサルタントの未来予測はことごとく外れたという経験を持つ。関西テレビの「発掘!あるある大辞典」の時にも書いたが、過剰な情報は生活者に多くの学習体験を促し、何が正しいのか直感的判断へと向かわせている。この学習体験はマスメディアによるものから、口コミ、最近ではSNSといったネット上のコミュニティにまで及び始めている。私のブログにも自動的にトラックバックするいわゆるトラックバックスパムが数多くつけられているが、公開している以上、面倒がらずに出来る限り問題あるものは削除している。つまり、あらゆるところに真偽混濁したコマーシャルベースの情報が浸透しているということだ。
ところでこうした情報学習を踏まえた直感力、研ぎすまされた感性人間が増加していると思う。この時代のマーケティングを、共感のマーケティングとか、感動のマーケティングと呼んでいる。もっと若い世代の言葉でいうと、センスということになる。ああ、これいいじゃん〜。かっこいいじゃん、という美的感覚、感性世界という情報を感じ取る「感」マーケティングの世界だ。
ところで、変化の時代とは次から次へと新たなモノや出来事が押し寄せる時代だ。つまり、未来はわからない、だから「予」という市場は変化に対する不安を背景に増々広がっていく。少子高齢社会で言えば、予防医療ということになる。先日、今日の快眠市場を創って来た一人である大手枕メーカーの方と会って来た。認知症や転倒予防のための快眠方法を広く進めていきたいと話されていた。眠りの質を高めるために「福寿体操」と「軽い昼寝」を組み合わせて不眠を解決し、認知症や転倒を防ぐ予防方法である。「福寿体操」は長寿県沖縄の睡眠健康教室で開発された軽い運動である。また、ビジネスマンにとっても実は良いとされている短い昼寝・シェスタ(スペインやポルトガルでは社会習慣化されている)を組み合わせた方法である。こうした眠りの質的改善からも高齢者の予防医療に役立てたいという話であった。ある意味で東洋漢方における「未病」と同じ考え方だ。
快眠以外の食の世界でもこうした試みは始まっているし、高齢者ばかりか小学校低学年の子供達への様々な「予」市場が広がっている。今は、犯罪に対するセキュリティといった商品やサービスだけであるが、健康への「予」市場は大きくなっていくと思う。旧来の考え方からすると、まだ生命力溢れる子供達には必要とされないであろう多くの「予」に関する商品やサービスがこれから生まれてくるということだ。ただ、こうした新市場は、未経験市場であり、「予」という情報が偽装、ねつ造されないことを願いたい。(続く)
「人力経営」の一般書店でのお求めは紀伊国屋書店さんが力を入れていただいており全国22店で取り扱っています。http://bookweb.kinokuniya.co.jp/htm/443410800X.html
2007年07月12日
コミュニティに夢を描く
ヒット商品応援団日記No183(毎週2回更新) 2007.7.12.
以前「家族のゆくえ」というテーマであるいは折に触れて、家族の崩壊やコミュニティの崩壊についてこのブログでも書いて来た。家族という単位から個人という単位への進行、個人化社会における様々な問題点としてである。未成熟な個人によって起こされる事件は後を絶たない。昨年度の児童虐待は37,000件を優に超え、子供の虐待死は50件に及んでいる。お年寄りの孤独死も増加し、各種ボランティアや行政はその対策を実行し始めている。以前にも書いた事があるが、65歳以上の高齢者が住民の50%を超える限界集落は全国で7873カ所にも及んでいる。一方、若い世代はと言えば、以前にも書いたが様々な依存症として現れて来ている。ケータイ依存から始まり、薬物依存まで多くの依存症が若い世代を覆っている。つまり、個人化とは孤独化ということでもある。
個人化社会を先行している米国でも同様に既にコミュニティはない。このコミュニティに替わって急増しているのが、周知のメガ・チャーチである。あの共和党ブッシュ政権誕生のキーマンとなった宗教保守としてのメガ・チャーチである。2000名以上の信者を有する教会をメガ・チャーチと呼ぶそうであるが、2007年にはこのメガ・チャーチは全米で1250カ所にも及んでいると聞く。一番大きなレイクウッド教会は4万人もの信者を有し、コンサートのような礼拝は全米に放映されている。こうしたメガ・チャーチには、「米国らしさ」が現れている。その「らしさ」とは、シングルマザーの悩みやアルコール依存症といった悩みまで多くの悩み相談といった「人を助けること」をビジネスモデルにしていることだ。なんでもかんでもビジネスにしてしまう米国ならではのことと思うが約80%の人が信仰心をもつ米国ならではの世界かもしれない。
さて、日本においてはどんなコミュニティ再生が動き始めているであろうか。数年前から一斉に動き始めた町おこし、村起こしといった地域活性化センターがやっているようなことは別として、新しい試みが個人の単位で動き始めている。少し前に書いた東京杉並の和田中学の中に「地域本部」を創り、コミュニティのコアにしようとする元リクルートの藤原校長のような行動が良き例である。あるいは、ベストセラーになった「ウェッブ進化論」を書かれた梅田望夫さんによるシリコンバレー5万人移住計画なんかも当てはまる。未来へとIT技術者の聖地に集まり、その精神を共有し合うという一種のコミュニティ創造である。今回、私が取材し「人力経営」の中に取り上げた福岡県岡垣町の「野の葡萄」なんかも当てはまる。代表である小役丸さんの「どこにでもある田舎を、ここにしかない田舎にしたい」という夢を語ってくれたが、私はそんなビジネスの取り組み方を「夢経営」と呼んだ。コミュニティ再生とは理想を描くこと、その精神を明らかにすることだと思う。日本のグランドデザインという言い方もあるが、もっと小さな単位で、個人の単位で「夢」が語られ始めている。(続く)
なお、「人力経営」のお求めはAMAZON以外のセブンアンドワイや紀伊国屋などのオンラインショップでお求めいただけます。(「人力経営」とキーワード入力すれば多くのオンラインショップが出てきます)
以前「家族のゆくえ」というテーマであるいは折に触れて、家族の崩壊やコミュニティの崩壊についてこのブログでも書いて来た。家族という単位から個人という単位への進行、個人化社会における様々な問題点としてである。未成熟な個人によって起こされる事件は後を絶たない。昨年度の児童虐待は37,000件を優に超え、子供の虐待死は50件に及んでいる。お年寄りの孤独死も増加し、各種ボランティアや行政はその対策を実行し始めている。以前にも書いた事があるが、65歳以上の高齢者が住民の50%を超える限界集落は全国で7873カ所にも及んでいる。一方、若い世代はと言えば、以前にも書いたが様々な依存症として現れて来ている。ケータイ依存から始まり、薬物依存まで多くの依存症が若い世代を覆っている。つまり、個人化とは孤独化ということでもある。
個人化社会を先行している米国でも同様に既にコミュニティはない。このコミュニティに替わって急増しているのが、周知のメガ・チャーチである。あの共和党ブッシュ政権誕生のキーマンとなった宗教保守としてのメガ・チャーチである。2000名以上の信者を有する教会をメガ・チャーチと呼ぶそうであるが、2007年にはこのメガ・チャーチは全米で1250カ所にも及んでいると聞く。一番大きなレイクウッド教会は4万人もの信者を有し、コンサートのような礼拝は全米に放映されている。こうしたメガ・チャーチには、「米国らしさ」が現れている。その「らしさ」とは、シングルマザーの悩みやアルコール依存症といった悩みまで多くの悩み相談といった「人を助けること」をビジネスモデルにしていることだ。なんでもかんでもビジネスにしてしまう米国ならではのことと思うが約80%の人が信仰心をもつ米国ならではの世界かもしれない。
さて、日本においてはどんなコミュニティ再生が動き始めているであろうか。数年前から一斉に動き始めた町おこし、村起こしといった地域活性化センターがやっているようなことは別として、新しい試みが個人の単位で動き始めている。少し前に書いた東京杉並の和田中学の中に「地域本部」を創り、コミュニティのコアにしようとする元リクルートの藤原校長のような行動が良き例である。あるいは、ベストセラーになった「ウェッブ進化論」を書かれた梅田望夫さんによるシリコンバレー5万人移住計画なんかも当てはまる。未来へとIT技術者の聖地に集まり、その精神を共有し合うという一種のコミュニティ創造である。今回、私が取材し「人力経営」の中に取り上げた福岡県岡垣町の「野の葡萄」なんかも当てはまる。代表である小役丸さんの「どこにでもある田舎を、ここにしかない田舎にしたい」という夢を語ってくれたが、私はそんなビジネスの取り組み方を「夢経営」と呼んだ。コミュニティ再生とは理想を描くこと、その精神を明らかにすることだと思う。日本のグランドデザインという言い方もあるが、もっと小さな単位で、個人の単位で「夢」が語られ始めている。(続く)
なお、「人力経営」のお求めはAMAZON以外のセブンアンドワイや紀伊国屋などのオンラインショップでお求めいただけます。(「人力経営」とキーワード入力すれば多くのオンラインショップが出てきます)
2007年07月09日
変わらないこと
ヒット商品応援団日記No182(毎週2回更新) 2007.7.9.
あらゆるメディアからの情報を定点観測しているが、常に思うのがその変化スピードである。私は結構新しいもの好きなのでこの春大ヒット商品となった電子マネーPASMOを使っている。勿論、JR東日本が出したスイカも使ってはいたが、JRだけではどうも使い勝手が悪かった。途中チャージをしないまま、そのままにしていたのだが、JRも私鉄もバスまでもがこの1枚で使えると言う便利さに多くの人が殺到し、周知の通り追加発売が延期になっている。こうした動きと併行するようにヨーカ堂グループではNANACO、イオングループではWAONと相次いで電子マネーが発売された。2006年の電子マネー市場は1800億円と言われ、今年度2007年には6900億円にもなると予測されている。ヨーカ堂グループではこうして集められた顧客データを分析し、顧客が欲しい商品へとつなげて行くと、その主旨を発表している。
小売業における情報についてはそのPOSデータを駆使することで他のコンビニに追随をさせなかったセブンイレブンは単なる小売業NO1という売上規模や利益だけでなく、その顧客主義について学ぶべきことは多い。今やセブンイレブンだけでなく、西武やそごうといったミレニアムグループ全体では1日で2600万人のデータが集まっている。時間帯における顧客心理を巧みに商品化させていったのはセブンイレブンであるが、同時に気候・気温による心理変化についてはかなり精度高い物となっている。最近では一番に考えているのが市場変化である。つまり、少子高齢市場で、セブンイレブンの平均年齢はこの9年間で30歳から36歳へと6歳も上がっている。「ご用聞き」というアナログ的活動をスタートさせたのも、高齢顧客を知り、より太い関係づくりのためだ。恐らく、高齢市場が本格化する数年後にはこうした活動が生きてくると思う。
ところで、セブンイレブンという業態をつくったのは鈴木敏文さんであることは良く知られている。スタート当時は東京台東区の小さな店舗でこのような売り上げを上げるとは誰も想像していなかった。そして、当初の商品は時代と共に大きく変わってきていることも周知の通りである。実は、変わらないこともいくつかある。1つは小さなこだわりと工夫する努力である。そのこだわりとは、例えば「天候」と売り上げへの工夫である。穏やかな天候の日は想定通りの安定した売り上げを示せるが、気温が2〜3度違うだけで売れる商品が違ってくる。真冬に冷やし中華は売れるであろうか?中には変わった人間もいますからでは答えにはならない。例えば、前日8度であった気温が明日は10度以上になるという予報で仕入れ商品が決まる。気温差が2〜3度違うと冷たいものもいいかなと思う人間の心理欲求を小さなテストの繰り返しによって精度の高い仕入れと売り上げに結びつける。そうした1店ごとの丁寧なスーパーバイジングに今なおこだわっている。店頭には平均3000品目あり、1年間で約70%が入れ替わる業態である。欲しい商品が並ばないかぎり売り上げはあがらない。
もう一つの変わらないことは毎週1500名もの店舗経営相談員を東京に集めることだ。効率論から言えば、年間30億もの出張経費をかけることは問題があると見えるかもしれません。しかし、先ほどの気温が2度違うだけで売れる商品が異なる業態であることを徹底させることに経営の意味があると鈴木さんは考えていると思う。そして、もっと丁寧なお店になれば更に売り上げは上がると考えてもいる。さて、「小さな」ことの積み重ねに学ぶことも必要である。そして、小さなことは「現場」でしか分からないということも学べる。また、「何」にお金を使うべきかに学ぶこともできる。私にはもう一つ、「変わるべきこと」と「変わらないこと」を学ぶが、皆さんはどう学ぶであろうか?(続く)
なお、「人力経営」のお求めはAMAZONでは次のところでお求めいただけます。
http://www.amazon.co.jp/dp/443410800X?tag=magmagpremium-22&camp=243&creative=1615&linkCode=as1&creativeASIN=443410800X&adid=0ZK05Z269V43865QYYNN&
あらゆるメディアからの情報を定点観測しているが、常に思うのがその変化スピードである。私は結構新しいもの好きなのでこの春大ヒット商品となった電子マネーPASMOを使っている。勿論、JR東日本が出したスイカも使ってはいたが、JRだけではどうも使い勝手が悪かった。途中チャージをしないまま、そのままにしていたのだが、JRも私鉄もバスまでもがこの1枚で使えると言う便利さに多くの人が殺到し、周知の通り追加発売が延期になっている。こうした動きと併行するようにヨーカ堂グループではNANACO、イオングループではWAONと相次いで電子マネーが発売された。2006年の電子マネー市場は1800億円と言われ、今年度2007年には6900億円にもなると予測されている。ヨーカ堂グループではこうして集められた顧客データを分析し、顧客が欲しい商品へとつなげて行くと、その主旨を発表している。
小売業における情報についてはそのPOSデータを駆使することで他のコンビニに追随をさせなかったセブンイレブンは単なる小売業NO1という売上規模や利益だけでなく、その顧客主義について学ぶべきことは多い。今やセブンイレブンだけでなく、西武やそごうといったミレニアムグループ全体では1日で2600万人のデータが集まっている。時間帯における顧客心理を巧みに商品化させていったのはセブンイレブンであるが、同時に気候・気温による心理変化についてはかなり精度高い物となっている。最近では一番に考えているのが市場変化である。つまり、少子高齢市場で、セブンイレブンの平均年齢はこの9年間で30歳から36歳へと6歳も上がっている。「ご用聞き」というアナログ的活動をスタートさせたのも、高齢顧客を知り、より太い関係づくりのためだ。恐らく、高齢市場が本格化する数年後にはこうした活動が生きてくると思う。
ところで、セブンイレブンという業態をつくったのは鈴木敏文さんであることは良く知られている。スタート当時は東京台東区の小さな店舗でこのような売り上げを上げるとは誰も想像していなかった。そして、当初の商品は時代と共に大きく変わってきていることも周知の通りである。実は、変わらないこともいくつかある。1つは小さなこだわりと工夫する努力である。そのこだわりとは、例えば「天候」と売り上げへの工夫である。穏やかな天候の日は想定通りの安定した売り上げを示せるが、気温が2〜3度違うだけで売れる商品が違ってくる。真冬に冷やし中華は売れるであろうか?中には変わった人間もいますからでは答えにはならない。例えば、前日8度であった気温が明日は10度以上になるという予報で仕入れ商品が決まる。気温差が2〜3度違うと冷たいものもいいかなと思う人間の心理欲求を小さなテストの繰り返しによって精度の高い仕入れと売り上げに結びつける。そうした1店ごとの丁寧なスーパーバイジングに今なおこだわっている。店頭には平均3000品目あり、1年間で約70%が入れ替わる業態である。欲しい商品が並ばないかぎり売り上げはあがらない。
もう一つの変わらないことは毎週1500名もの店舗経営相談員を東京に集めることだ。効率論から言えば、年間30億もの出張経費をかけることは問題があると見えるかもしれません。しかし、先ほどの気温が2度違うだけで売れる商品が異なる業態であることを徹底させることに経営の意味があると鈴木さんは考えていると思う。そして、もっと丁寧なお店になれば更に売り上げは上がると考えてもいる。さて、「小さな」ことの積み重ねに学ぶことも必要である。そして、小さなことは「現場」でしか分からないということも学べる。また、「何」にお金を使うべきかに学ぶこともできる。私にはもう一つ、「変わるべきこと」と「変わらないこと」を学ぶが、皆さんはどう学ぶであろうか?(続く)
なお、「人力経営」のお求めはAMAZONでは次のところでお求めいただけます。
http://www.amazon.co.jp/dp/443410800X?tag=magmagpremium-22&camp=243&creative=1615&linkCode=as1&creativeASIN=443410800X&adid=0ZK05Z269V43865QYYNN&
2007年07月04日
損と得
ヒット商品応援団日記No181(毎週2回更新) 2007.7.4.
前回「儲ける」と「役に立つ」 、この2つのテーマについて書いてみた。今回も同じようなテーマ、損と得について考えてみたい。誰も損はしたくない、得をしたいと考え、ビジネス、商売をしている。「役に立つ」ことだけであればボランティアとなり、しかし継続していくには「儲ける」ことが必要だ。前回はこんな内容であったと思う。今回の損と得はもう少し、戦略的なテーマである。よく「損して得をとる」という言い方があるが、その場合の損は「次」「明日」のための投資の意味合いとして使われることが多い。特に、新しい市場、未知の市場においては損をしてでも市場シェアーNO1、一定のシェアーを確保することを目標とすることが多い。不正請求をしたコムソンなんかはこうした例である。つまり、24時間いつでも訪問介護するという現場の損によってシェアーNO1を目指したのだが、目指す理由の第一はNO1だけが持つ「価格リーディング」があるからだ。コムソンの場合は、価格は国によって決められているため、「不正請求」という方法が取られたと思う。
日本式経営の特質を分析した経営学者の奥田健二氏は、著書「日本型経営の未来」(TBSブリタニカ)で、自分のためではなく、他者に役に立つ受苦的な行動を、日本人特有の優れた能力として注目している。 受苦的な生き方とは、自分を二の次にして、人のために尽くすという姿勢だ。この生き方は、日本では古くから価値あるものとされてきたが、今や失ってしまったことの一つとなっている。社会生活でも、組織の中やチームワークにとって有用な役割りを果していると思う。「 私が私が」とする能動的生き方だけでなく、日本の伝統である受動的、受苦的生き方にも、もっと光をあててみる必要があると思う。損と得という言い方をするならば損の道をゆくことも必要な時代だ。
課題はどんな「損」の仕方をするかである。勿論、会社を倒産させてしまうような損ではない。顧客、市場、社会が喜んでもらう損の仕方である。最近のスーパーは取り入れて来たが、10年ほど前から個人化の進行に伴い、個食=小食という視点で利益を上げて来たスーパーがあった。そこではメロンのハーフカットからクオーターカットにし、1個1000円のメロンをクオーターカットで300円で販売していた。1/4にすれば250円であるが、300円で売り、手間はかかるがその差50円が利益というわけだ。顧客にとっては無駄にせず、買いやすい価格になり、売り手も買い手も一つの調和が成立する世界である。手間という損、時間をかけるという損、多くの損の仕方がある。大きな損は難しい。しかし、小さな損は誰でも可能である。一手間、一言、一工夫、こうしたチョットした損が顧客創造へとつながる。サービス精神という損が得をもたらす時代だ。(続く)
前回「儲ける」と「役に立つ」 、この2つのテーマについて書いてみた。今回も同じようなテーマ、損と得について考えてみたい。誰も損はしたくない、得をしたいと考え、ビジネス、商売をしている。「役に立つ」ことだけであればボランティアとなり、しかし継続していくには「儲ける」ことが必要だ。前回はこんな内容であったと思う。今回の損と得はもう少し、戦略的なテーマである。よく「損して得をとる」という言い方があるが、その場合の損は「次」「明日」のための投資の意味合いとして使われることが多い。特に、新しい市場、未知の市場においては損をしてでも市場シェアーNO1、一定のシェアーを確保することを目標とすることが多い。不正請求をしたコムソンなんかはこうした例である。つまり、24時間いつでも訪問介護するという現場の損によってシェアーNO1を目指したのだが、目指す理由の第一はNO1だけが持つ「価格リーディング」があるからだ。コムソンの場合は、価格は国によって決められているため、「不正請求」という方法が取られたと思う。
日本式経営の特質を分析した経営学者の奥田健二氏は、著書「日本型経営の未来」(TBSブリタニカ)で、自分のためではなく、他者に役に立つ受苦的な行動を、日本人特有の優れた能力として注目している。 受苦的な生き方とは、自分を二の次にして、人のために尽くすという姿勢だ。この生き方は、日本では古くから価値あるものとされてきたが、今や失ってしまったことの一つとなっている。社会生活でも、組織の中やチームワークにとって有用な役割りを果していると思う。「 私が私が」とする能動的生き方だけでなく、日本の伝統である受動的、受苦的生き方にも、もっと光をあててみる必要があると思う。損と得という言い方をするならば損の道をゆくことも必要な時代だ。
課題はどんな「損」の仕方をするかである。勿論、会社を倒産させてしまうような損ではない。顧客、市場、社会が喜んでもらう損の仕方である。最近のスーパーは取り入れて来たが、10年ほど前から個人化の進行に伴い、個食=小食という視点で利益を上げて来たスーパーがあった。そこではメロンのハーフカットからクオーターカットにし、1個1000円のメロンをクオーターカットで300円で販売していた。1/4にすれば250円であるが、300円で売り、手間はかかるがその差50円が利益というわけだ。顧客にとっては無駄にせず、買いやすい価格になり、売り手も買い手も一つの調和が成立する世界である。手間という損、時間をかけるという損、多くの損の仕方がある。大きな損は難しい。しかし、小さな損は誰でも可能である。一手間、一言、一工夫、こうしたチョットした損が顧客創造へとつながる。サービス精神という損が得をもたらす時代だ。(続く)
2007年07月01日
「儲ける」と「役に立つ」
ヒット商品応援団日記No180(毎週2回更新) 2007.7.1.
「儲ける」と「役に立つ」 、この2つのテーマは商売・ビジネスに携わる人にとって永遠のテーマである。そして、最近のミートポーク社における牛肉偽装事件や少し前の耐震偽装事件やライブドア事件といった経済事件の多くは、この2つの命題に深く関わっている。勿論、2つともビジネスには不可欠で表裏、鶏と卵のようなものであるが、この2つをもう少し分かりやすく整理すると、「儲ける」にウエイトを置くのが欧米の商慣習、「役に立つ」にウエイトを置くのが今までの日本の商慣習。数年前から言われている企業価値も簡単に言ってしまえば、「儲ける」と「役に立つ」の2つがテーマとしてある。
今回、私が「人力経営」という本を書いた理由の一つが、この2つのテーマの狭間で悩み、決断を下す経営リーダーの姿であった。例えば、ダスキンもミスタードーナツ肉まん事件を起こし社会の批判を受けたが、その背景にはデフレ下での激烈なコスト削減競争があった。他のファーストフード業界と同じように肉まんを中国で製造していたのだが、日本においては使ってはいけない添加剤を使い、その情報を隠蔽したと社会から指弾された事件である。この危機を救ったのは、「役に立とう」とする経営理念を顧客接点における現場の人の実践であった。今回のミートホープ社の不祥事においても危機管理会社のコメントが数多く報じられたが、本質としての危機管理は経営理念を現場の人がいかに生きるかにかかっている。
「役に立つ」 ことを続け、結果「儲ける」こととなれば理想である。しかし、なかなかそのようにはいかない現実がある。「役に立つ」象徴がボランティアであり、NPO法人である。しかし、継続して「役に立つ」、更にはその「役に立つ」を広げていくには「儲ける」ことが必要だ。最近では、有償ボランティアという仕組みも出て来ており、そもそも株式会社の原点はNPO法人であることを考えれば、非営利活動も「儲ける」ことを考えなければならないということだ。
沖縄南城市にある世界遺産「斎場御嶽(せ〜ふぁ うたき)」への入場が7/1から200円の入場料をとると報じられた。市の財政は厳しく、保全のためにはボランティアにおんぶにだっこでは続かないということだ。本土からの観光客は「未知」の世界を求めてやってくる。しかし、沖縄の人にとっては日常の祈りの場である。観光客からは2000円でも3000円でも徴収したら良い。しかし、沖縄に住む人達からは出来る限り徴収しないで欲しいと思う。
「役に立つ」ビジネスの代表的なものとして近江商人の心得、「三方よし」がある。「売り手よし、買い手よし、世間よし」の中に次のような教えが残されている。
利真於勤(りはつとむるにおいてしんなり)
唐の詩人韓愈の「業精於勤(業は勤において精し)」、から転用して作られた言葉であり、小倉栄一郎によれば伊藤忠兵衛の座右の銘という。商人の手にする利益は、権力と結託したり、買占めや売り惜しみをしたりせず、物資の需給を調整して世のなかに貢献するという、商人の本来の勤めを果たした結果として手にするものでなければならない。そうした利益こそ真の利益であるという意味である。(財団法人「滋賀県産業支援プラザ」より、http://www.shigaplaza.or.jp/sanpou/mini_info/ohmi_businessman.html#5)
(続く)
「儲ける」と「役に立つ」 、この2つのテーマは商売・ビジネスに携わる人にとって永遠のテーマである。そして、最近のミートポーク社における牛肉偽装事件や少し前の耐震偽装事件やライブドア事件といった経済事件の多くは、この2つの命題に深く関わっている。勿論、2つともビジネスには不可欠で表裏、鶏と卵のようなものであるが、この2つをもう少し分かりやすく整理すると、「儲ける」にウエイトを置くのが欧米の商慣習、「役に立つ」にウエイトを置くのが今までの日本の商慣習。数年前から言われている企業価値も簡単に言ってしまえば、「儲ける」と「役に立つ」の2つがテーマとしてある。
今回、私が「人力経営」という本を書いた理由の一つが、この2つのテーマの狭間で悩み、決断を下す経営リーダーの姿であった。例えば、ダスキンもミスタードーナツ肉まん事件を起こし社会の批判を受けたが、その背景にはデフレ下での激烈なコスト削減競争があった。他のファーストフード業界と同じように肉まんを中国で製造していたのだが、日本においては使ってはいけない添加剤を使い、その情報を隠蔽したと社会から指弾された事件である。この危機を救ったのは、「役に立とう」とする経営理念を顧客接点における現場の人の実践であった。今回のミートホープ社の不祥事においても危機管理会社のコメントが数多く報じられたが、本質としての危機管理は経営理念を現場の人がいかに生きるかにかかっている。
「役に立つ」 ことを続け、結果「儲ける」こととなれば理想である。しかし、なかなかそのようにはいかない現実がある。「役に立つ」象徴がボランティアであり、NPO法人である。しかし、継続して「役に立つ」、更にはその「役に立つ」を広げていくには「儲ける」ことが必要だ。最近では、有償ボランティアという仕組みも出て来ており、そもそも株式会社の原点はNPO法人であることを考えれば、非営利活動も「儲ける」ことを考えなければならないということだ。
沖縄南城市にある世界遺産「斎場御嶽(せ〜ふぁ うたき)」への入場が7/1から200円の入場料をとると報じられた。市の財政は厳しく、保全のためにはボランティアにおんぶにだっこでは続かないということだ。本土からの観光客は「未知」の世界を求めてやってくる。しかし、沖縄の人にとっては日常の祈りの場である。観光客からは2000円でも3000円でも徴収したら良い。しかし、沖縄に住む人達からは出来る限り徴収しないで欲しいと思う。
「役に立つ」ビジネスの代表的なものとして近江商人の心得、「三方よし」がある。「売り手よし、買い手よし、世間よし」の中に次のような教えが残されている。
利真於勤(りはつとむるにおいてしんなり)
唐の詩人韓愈の「業精於勤(業は勤において精し)」、から転用して作られた言葉であり、小倉栄一郎によれば伊藤忠兵衛の座右の銘という。商人の手にする利益は、権力と結託したり、買占めや売り惜しみをしたりせず、物資の需給を調整して世のなかに貢献するという、商人の本来の勤めを果たした結果として手にするものでなければならない。そうした利益こそ真の利益であるという意味である。(財団法人「滋賀県産業支援プラザ」より、http://www.shigaplaza.or.jp/sanpou/mini_info/ohmi_businessman.html#5)
(続く)