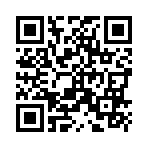2007年07月29日
視座という目
ヒット商品応援団日記No188(毎週2回更新) 2007.7.29.
ビジネスプランやマーケティングコンセプトを考える時、私が一番重要だと思っているのが「視座」についてである。例えば、視点は「どこを見るのか」であり、視野は「どの範囲を見るのか」であり、視座は「どこに立って見るのか」である。理屈っぽく言えば、視座によって、見る範囲もどこを見るかも変わってくる。視座をポリシー、志し、コンセプトと言っても間違いではない。時間という視座に立てば、伝承すべきこと、引き継ぐべきこと、といったことになり、空間という視座に立てば、俯瞰的に、あるいは地球という大きな目線で、といった「立ち位置」が重要となる。
数年前、本業回帰とか、創業回帰、あるいはコアコンピタンスといったキーワードでビジネス再生の動きがあったが、創業期には理想とするビジネスの原型、ある意味完成形に近いものがあることから立ち戻ろうという動きになったのである。ビジネスは成長と共に次第に複雑になり、視座も視野も視点もごちゃ混ぜになり、大切なことを見失ってしまう時代にいる。
私が「人力経営」を書いたテーマはこの視座についてであった。ヒット商品、売れている商品の裏側にある明確な視座、顧客に対し、社会に対する企業としてどう立つべきかその視座を明らかにしたかったからである。和菓子の叶匠寿庵もそうした視座を持つ企業である。創業者である芝田清次の講演を聞き感動した経験を持っていたのだが、その後の叶匠寿庵の視座を実感したかったのである。詳しくは「人力経営」を読んでいただきたいが、その視座は日本の風土、自然、郷土への「思い」であると言える。芝田清次は太平洋戦争に従軍し、負傷し片目を失ってふるさと大津の地に復員する。満州の地で失った目で見続けていたのは、こよなく愛した家族や郷里で、それは63000坪という広大なテーマパーク「寿長生の郷(すないのさと)」へとつながっている。1日平均700名の顧客が訪れる寿長生の郷は、日本の原風景というより、豊かな自然への感謝の「思い」が凝縮・昇華された美しい郷である。寿長生の郷は勿論のこと、商品にも、もてなし方にも、全てに視座は守られ、磨かれて今へとつながっている。
ところで牛肉偽装事件のミートホープ社はどうであろうか。20年以上も前から、牛肉ミンチに豚肉、鳥肉、羊肉などを混ぜて、加工販売してきた。誰一人見抜くことが出来ないまま20年を経て来た訳であるが、勿論悪知恵ではあるが偽装表示をしなければアイディア経営と言われて来たかもしれない。精進料理の多くは殺生しない食ということから、大豆などを巧く使ったフェイク(もどき)食品によるものである。他にも、マーガリンは戦後の一時期バターの代用であったし、魚肉ソーセージもソーセージの代用食品であった。ミートホープ社の田中社長にはミンチ肉のプロの視点はあり、食肉加工という領域では極め付きのスペシャリストであった。決定的に欠けていたのは市場、顧客への視座であった。作った商品は自己利益に立った商品であり、顧客は利益をもたらすだけの存在である。三方よしにならえば、売り手よしという自己利益だけである。もし、牛肉と鶏肉との合挽きミンチによって、カロリーが少なく、しかも価格も安く、味も食感も牛肉100%と変わらないといったフェイク食品ができれば、マーケットは小さくなるが、三方よしは成立する。顧客が社会がよしとする視座が決定的に欠けていたということだ。勿論一般的平均的な視座などない。知恵やアイディアは特定市場への視座によって生かされ、結果ビジネスとなる。(続く)
ビジネスプランやマーケティングコンセプトを考える時、私が一番重要だと思っているのが「視座」についてである。例えば、視点は「どこを見るのか」であり、視野は「どの範囲を見るのか」であり、視座は「どこに立って見るのか」である。理屈っぽく言えば、視座によって、見る範囲もどこを見るかも変わってくる。視座をポリシー、志し、コンセプトと言っても間違いではない。時間という視座に立てば、伝承すべきこと、引き継ぐべきこと、といったことになり、空間という視座に立てば、俯瞰的に、あるいは地球という大きな目線で、といった「立ち位置」が重要となる。
数年前、本業回帰とか、創業回帰、あるいはコアコンピタンスといったキーワードでビジネス再生の動きがあったが、創業期には理想とするビジネスの原型、ある意味完成形に近いものがあることから立ち戻ろうという動きになったのである。ビジネスは成長と共に次第に複雑になり、視座も視野も視点もごちゃ混ぜになり、大切なことを見失ってしまう時代にいる。
私が「人力経営」を書いたテーマはこの視座についてであった。ヒット商品、売れている商品の裏側にある明確な視座、顧客に対し、社会に対する企業としてどう立つべきかその視座を明らかにしたかったからである。和菓子の叶匠寿庵もそうした視座を持つ企業である。創業者である芝田清次の講演を聞き感動した経験を持っていたのだが、その後の叶匠寿庵の視座を実感したかったのである。詳しくは「人力経営」を読んでいただきたいが、その視座は日本の風土、自然、郷土への「思い」であると言える。芝田清次は太平洋戦争に従軍し、負傷し片目を失ってふるさと大津の地に復員する。満州の地で失った目で見続けていたのは、こよなく愛した家族や郷里で、それは63000坪という広大なテーマパーク「寿長生の郷(すないのさと)」へとつながっている。1日平均700名の顧客が訪れる寿長生の郷は、日本の原風景というより、豊かな自然への感謝の「思い」が凝縮・昇華された美しい郷である。寿長生の郷は勿論のこと、商品にも、もてなし方にも、全てに視座は守られ、磨かれて今へとつながっている。
ところで牛肉偽装事件のミートホープ社はどうであろうか。20年以上も前から、牛肉ミンチに豚肉、鳥肉、羊肉などを混ぜて、加工販売してきた。誰一人見抜くことが出来ないまま20年を経て来た訳であるが、勿論悪知恵ではあるが偽装表示をしなければアイディア経営と言われて来たかもしれない。精進料理の多くは殺生しない食ということから、大豆などを巧く使ったフェイク(もどき)食品によるものである。他にも、マーガリンは戦後の一時期バターの代用であったし、魚肉ソーセージもソーセージの代用食品であった。ミートホープ社の田中社長にはミンチ肉のプロの視点はあり、食肉加工という領域では極め付きのスペシャリストであった。決定的に欠けていたのは市場、顧客への視座であった。作った商品は自己利益に立った商品であり、顧客は利益をもたらすだけの存在である。三方よしにならえば、売り手よしという自己利益だけである。もし、牛肉と鶏肉との合挽きミンチによって、カロリーが少なく、しかも価格も安く、味も食感も牛肉100%と変わらないといったフェイク食品ができれば、マーケットは小さくなるが、三方よしは成立する。顧客が社会がよしとする視座が決定的に欠けていたということだ。勿論一般的平均的な視座などない。知恵やアイディアは特定市場への視座によって生かされ、結果ビジネスとなる。(続く)