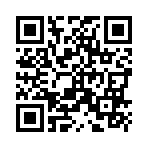2018年05月13日
ここにしかない観光地
ヒット商品応援団日記No713(毎週更新) 2018.5.13.
 前回「日本観光進化」への視座 」としてその観光コンテンツの変化について ブログに書いた。それは「西高東低」と言う観光地の変化・広がりを踏まえてだが、今後目標とすべき一つが「回数化」の促進であると。更にはその回数化と言う魅力については地方への広がりと日本固有の文化を提供する旅になると。こうした着眼を「テーマ観光」として物語化して行くことが必要であると指摘をした。何故、こうした日本観光の進化への着眼をしたかと言うと、それは「地方」の特性を生かした観光政策を実施ている国、イタリアに一つのモデルを見出したからである。
前回「日本観光進化」への視座 」としてその観光コンテンツの変化について ブログに書いた。それは「西高東低」と言う観光地の変化・広がりを踏まえてだが、今後目標とすべき一つが「回数化」の促進であると。更にはその回数化と言う魅力については地方への広がりと日本固有の文化を提供する旅になると。こうした着眼を「テーマ観光」として物語化して行くことが必要であると指摘をした。何故、こうした日本観光の進化への着眼をしたかと言うと、それは「地方」の特性を生かした観光政策を実施ている国、イタリアに一つのモデルを見出したからである。
そのイタリアであるが、日本と同じ時期に近代国家となったが、それまではいわゆる地方ごとの都市国家で、日本における江戸時代の「藩」と同じような経緯をとってきた国である。つまり、過去の歴史・文化を受け継いだ「地方」が色濃く残っていて、それが産業として確立し、輸出産業にまで発展している国である。風土としても国土は日本の5分の4ほどで、北はアルプス山脈に遮られ、地中海に囲まれたシチリア島やサルデーニャ島など約90の島々から成りたった国である。そして、国内は20の州(regione)、100以上の県(provincia)、さらには市町村にあたる約8,000のコムーネ(comune)に区分されている。日本の場合、明治になり廃藩置県となったが、それでも今なお「藩」の名残を残す日本とよく似ている。これ以上説明する必要はないと思うので省いていくが、イタリアの観光も都市国家の歴史・文化を踏まえた産業となっていることにある。ちなみにフランスがテロなどから観光客数が減少する中、イタリアは伸びており5237万人ほどとなっており、日本における目標4000万人にとって一つのお手本となる国である。話を戻すが、イタリアのコムーネには都市国家の歴史を受け継いだ地域が多く、都市ごとに見ていくと、それぞれが独自に特徴的な伝統産業を発展させてきていることがよくわかる。例えば、
・トリノ:1899年創業の自動車メーカー「フィアット」(FIAT)が、国内最大の企業グループへと急成長を遂げたことにより飛躍的に発展した都市である。周知のフィアットはフェラーリ、アルファ・ロメオなど国内自動車メーカーを次々と傘下に収め、1990年代には海外にも市場を拡大。日本でいうならば、愛知におけるトヨタ自動車のような地域である。
・ジェノバ:海洋都市国家として繁栄し、ベネチア、ピサ、アマルフィとともに四大海洋都市として地中海の覇権を争ってきた。イタリア最大の貿易港でミラノやトリノの工業製品を輸出。日本でいうと、千葉、名古屋、横浜ということになるが、貿易額では成田空港ということになる。
・ミラノ:北部イタリア最大の工業都市であるミラノはブランド創造都市である。アパレル業界が価格競争になり、ミラノもその渦に巻き込まれ低迷してはいるが、そのデザイン世界は今なおブランドとして世界に発信している。
・フィレンツェ:伝統手工芸として上質な革製品の製造都市であり、周知の「グッチ」(GUCCI)や「フェラガモ」(Salvatore Ferragamo)などが創業の地でもある。
他にもベネチアのガラス産業、観光都市ローマ、「食」の中心ナポリ、このように歴史・文化を受け継いた産業がイタリアを成長させてきている。
以上のように簡単にイタリアとの相似点を指摘して見たが、本来であれば政府観光庁が観光日本のグランドデザインを行うべきであるが、そうした構想の前に訪日外国人客が押し寄せてしまったというのが実情である。また、数年前から地方自治体にあっては外国人客を誘致するために観光部門に外国人を採用したり、誘致したい国のブロガーなどを招いて集客を行っており、それなりの成果は上がってきているかと思う。ただ、前回の結論として少し触れたが、後手後手に回ってしまった日本観光に対し、回数化を測るためには先行した観光客、日本オタクの観光客が何に興味を持ち、オタク化していくかを見極めて観光政策として全体化していくことが必要になっている。そうしたオタク客の裾野を広げるためには、観光コンテンツにおけるテーマ化、その物語化が重要になっているということである。この物語化とは観光の産業化であり、エリア全体として取り組む必要があるということである。
産業化の構図としては、以前から地域おこしによく使われるキーワードとして「6次産業化」がある。周知のように、1次産業(生産)、2次産業(加工製造)、3次産業(流通)を全体として行うことを6次産業化というが、観光産業に置き換えるならば、1次産業は観光地などの資源整備や保全であり、2次産業はそれら資源のテーマ物語化・プログラム化・メニュー化であり、3次産業はそれらをどうサービスしていくかということになる。これら全体を一つのものとして実行していくのが観光の産業化ということになる。
つまり、どこにでもある田舎・地方をどこにもない田舎・地方にする試みのことである。例えば、京都府の京丹後伊根町に小さな漁村がある。舟屋のある町として知る人ぞ知る観光地であるが、その舟屋は海辺ぎりぎりに建ち並び、1階が舟の格納庫の他に、漁具などの物置場として使われており、2階は住居となった機能的な建物である。実は旅行ガイド本「ミシュラン・グリーンガイド」日本編に、京都府から天橋立(宮津市)と伊根の舟屋(伊根町)の景観が、いずれも「二つ星」の評価で新たに掲載され、訪日外国人観光客が押し寄せてきたということである。重要伝統的建造物群保存地区に指定された街並みも素敵だが、遊覧船による海上から見る『伊根湾めぐり』も用意されていて、伊根の舟屋物語を満喫できるようになっている。最近では空き家であった舟屋をリノベーションした宿泊施設やおしゃれなカフェも出来てきているようだ。テーマという表現をするとすれば、これは伊根町観光協会のコピーにも出ているフレーズであるが、「海の京都 和の源流をめぐる旅」とある。ある意味、京都市という観光表通りから京丹後地方という路地裏のミニミニ観光地ということになる。アクセスするには少々不便ではあるが、であればこそ「ここにしかない漁村」が今尚残っており、小さな観光名所になるということである。こうした試みは飽和状態にある京都観光の分散化・広域化につながっていることは言うまでもない。
ただイタリアも京都もそうであるが、観光客が押し寄せることによる問題も生まれている。それは観光ビジネスにおける利害対立というより、地元住民と観光客との間で起こる多様な軋轢である。交通利用におけるマナーやルールから始まり、違法民泊による住民とのトラブル、更には街中の混雑・騒音・・・・・・・。実は町歩きの第一歩が上野裏の谷根千(ヤネセン)であったが、7年前既に谷根千は観光地化しており、地元商店街・住民との間で問題が指摘されていた。以前、谷根千の旅館「澤野屋」はどこよりも早く訪日外国人を受け入れ地域全体で「もてなしてきた」とブログに書いたことがあった。全体としてはこうした受け入れをしている地域であるが、例えば谷中ぎんざ商店街の中には地域住民の生活に必要なもの売る小売店もあれば、観光客相手の店もある。その象徴であるが、地元住民相手の総菜店には200円の格安弁当が売られ、観光客相手には200円の食べ歩き用のメンチカツが売られる、という状況が生まれている。誰を顧客とするのかという問題であるが、こうした状況は大阪の黒門市場にも起きている。黒門市場は寺社の境内に魚の行商が集まり鮮度もよく安いということから生まれた住民顧客向けの市場であるが、数年前から訪日外国人が押し寄せるという一大観光地へと変貌した。結果どういうことが起きているか。訪日外国人による混雑と、小売価格の上昇、こうしたことから地域住民は黒門市場から離れて行きつつある。
日本におけるインバウンドビジネス拡大の主要な背景・要因が明確になってきた。従来から言われてきたように、円安に加えて世界的なLCCやクルーズ船の旅の急拡大、つまり以前と比べて格段に行きやすくなったことによる。そして、その増加の裾野の消費傾向は日本人の生活と同じようなことをしてみたいという体験の旅となる。日本は長引くデフレ下にあり、訪日外国人にとって安く済むパラダイスのような旅を満喫できるということである。繰り返しブログにも書いてきたように、日本人の日常的なライフスタイル、ごくごく普通の生活を同じように体験してみたいということである。トリップアドバイザーのお気に入り日本レストランのランキングにも出てきているが、その多くはご近所住民が日常利用しでいる普通の飲食店である。勿論、訪日外国人向けの特別価格などではない。そんな特別なことばかりしていくと、地域住民だけでなく、その事実を知った訪日外国人はすぐさまSNSに投稿するであろう。
「ここにしかない地域」を観光地とするのであれば、ありのままの「生活文化」を提供するということだ。海に囲まれた日本には約2800ほどの漁港、後背集落は約6300、共に減少傾向にある。勿論、沿岸漁業の不振、高齢化、結果過疎化の象徴でもあるが、京丹後伊根町のような特色ある「生き方」もある。ちなみに、伊根町は922世帯、人口2135人という小さな漁村である。観光協会のHPには「ディープな伊根を旅してみよう」とある。過疎化の進む地方であるが、逆に考えれば豊かな自然が残り、歴史文化があちらこちらに残っている。伊根町の近くには浦嶋太郎伝説が残る「常世の浜」がある。舟屋だけでなく、浦島伝説という物語体験もまた面白い。(続く)
追記 冒頭の写真は伊根町観光協会の写真を掲載したことをお断りしておく。
 前回「日本観光進化」への視座 」としてその観光コンテンツの変化について ブログに書いた。それは「西高東低」と言う観光地の変化・広がりを踏まえてだが、今後目標とすべき一つが「回数化」の促進であると。更にはその回数化と言う魅力については地方への広がりと日本固有の文化を提供する旅になると。こうした着眼を「テーマ観光」として物語化して行くことが必要であると指摘をした。何故、こうした日本観光の進化への着眼をしたかと言うと、それは「地方」の特性を生かした観光政策を実施ている国、イタリアに一つのモデルを見出したからである。
前回「日本観光進化」への視座 」としてその観光コンテンツの変化について ブログに書いた。それは「西高東低」と言う観光地の変化・広がりを踏まえてだが、今後目標とすべき一つが「回数化」の促進であると。更にはその回数化と言う魅力については地方への広がりと日本固有の文化を提供する旅になると。こうした着眼を「テーマ観光」として物語化して行くことが必要であると指摘をした。何故、こうした日本観光の進化への着眼をしたかと言うと、それは「地方」の特性を生かした観光政策を実施ている国、イタリアに一つのモデルを見出したからである。そのイタリアであるが、日本と同じ時期に近代国家となったが、それまではいわゆる地方ごとの都市国家で、日本における江戸時代の「藩」と同じような経緯をとってきた国である。つまり、過去の歴史・文化を受け継いだ「地方」が色濃く残っていて、それが産業として確立し、輸出産業にまで発展している国である。風土としても国土は日本の5分の4ほどで、北はアルプス山脈に遮られ、地中海に囲まれたシチリア島やサルデーニャ島など約90の島々から成りたった国である。そして、国内は20の州(regione)、100以上の県(provincia)、さらには市町村にあたる約8,000のコムーネ(comune)に区分されている。日本の場合、明治になり廃藩置県となったが、それでも今なお「藩」の名残を残す日本とよく似ている。これ以上説明する必要はないと思うので省いていくが、イタリアの観光も都市国家の歴史・文化を踏まえた産業となっていることにある。ちなみにフランスがテロなどから観光客数が減少する中、イタリアは伸びており5237万人ほどとなっており、日本における目標4000万人にとって一つのお手本となる国である。話を戻すが、イタリアのコムーネには都市国家の歴史を受け継いだ地域が多く、都市ごとに見ていくと、それぞれが独自に特徴的な伝統産業を発展させてきていることがよくわかる。例えば、
・トリノ:1899年創業の自動車メーカー「フィアット」(FIAT)が、国内最大の企業グループへと急成長を遂げたことにより飛躍的に発展した都市である。周知のフィアットはフェラーリ、アルファ・ロメオなど国内自動車メーカーを次々と傘下に収め、1990年代には海外にも市場を拡大。日本でいうならば、愛知におけるトヨタ自動車のような地域である。
・ジェノバ:海洋都市国家として繁栄し、ベネチア、ピサ、アマルフィとともに四大海洋都市として地中海の覇権を争ってきた。イタリア最大の貿易港でミラノやトリノの工業製品を輸出。日本でいうと、千葉、名古屋、横浜ということになるが、貿易額では成田空港ということになる。
・ミラノ:北部イタリア最大の工業都市であるミラノはブランド創造都市である。アパレル業界が価格競争になり、ミラノもその渦に巻き込まれ低迷してはいるが、そのデザイン世界は今なおブランドとして世界に発信している。
・フィレンツェ:伝統手工芸として上質な革製品の製造都市であり、周知の「グッチ」(GUCCI)や「フェラガモ」(Salvatore Ferragamo)などが創業の地でもある。
他にもベネチアのガラス産業、観光都市ローマ、「食」の中心ナポリ、このように歴史・文化を受け継いた産業がイタリアを成長させてきている。
以上のように簡単にイタリアとの相似点を指摘して見たが、本来であれば政府観光庁が観光日本のグランドデザインを行うべきであるが、そうした構想の前に訪日外国人客が押し寄せてしまったというのが実情である。また、数年前から地方自治体にあっては外国人客を誘致するために観光部門に外国人を採用したり、誘致したい国のブロガーなどを招いて集客を行っており、それなりの成果は上がってきているかと思う。ただ、前回の結論として少し触れたが、後手後手に回ってしまった日本観光に対し、回数化を測るためには先行した観光客、日本オタクの観光客が何に興味を持ち、オタク化していくかを見極めて観光政策として全体化していくことが必要になっている。そうしたオタク客の裾野を広げるためには、観光コンテンツにおけるテーマ化、その物語化が重要になっているということである。この物語化とは観光の産業化であり、エリア全体として取り組む必要があるということである。
産業化の構図としては、以前から地域おこしによく使われるキーワードとして「6次産業化」がある。周知のように、1次産業(生産)、2次産業(加工製造)、3次産業(流通)を全体として行うことを6次産業化というが、観光産業に置き換えるならば、1次産業は観光地などの資源整備や保全であり、2次産業はそれら資源のテーマ物語化・プログラム化・メニュー化であり、3次産業はそれらをどうサービスしていくかということになる。これら全体を一つのものとして実行していくのが観光の産業化ということになる。
つまり、どこにでもある田舎・地方をどこにもない田舎・地方にする試みのことである。例えば、京都府の京丹後伊根町に小さな漁村がある。舟屋のある町として知る人ぞ知る観光地であるが、その舟屋は海辺ぎりぎりに建ち並び、1階が舟の格納庫の他に、漁具などの物置場として使われており、2階は住居となった機能的な建物である。実は旅行ガイド本「ミシュラン・グリーンガイド」日本編に、京都府から天橋立(宮津市)と伊根の舟屋(伊根町)の景観が、いずれも「二つ星」の評価で新たに掲載され、訪日外国人観光客が押し寄せてきたということである。重要伝統的建造物群保存地区に指定された街並みも素敵だが、遊覧船による海上から見る『伊根湾めぐり』も用意されていて、伊根の舟屋物語を満喫できるようになっている。最近では空き家であった舟屋をリノベーションした宿泊施設やおしゃれなカフェも出来てきているようだ。テーマという表現をするとすれば、これは伊根町観光協会のコピーにも出ているフレーズであるが、「海の京都 和の源流をめぐる旅」とある。ある意味、京都市という観光表通りから京丹後地方という路地裏のミニミニ観光地ということになる。アクセスするには少々不便ではあるが、であればこそ「ここにしかない漁村」が今尚残っており、小さな観光名所になるということである。こうした試みは飽和状態にある京都観光の分散化・広域化につながっていることは言うまでもない。
ただイタリアも京都もそうであるが、観光客が押し寄せることによる問題も生まれている。それは観光ビジネスにおける利害対立というより、地元住民と観光客との間で起こる多様な軋轢である。交通利用におけるマナーやルールから始まり、違法民泊による住民とのトラブル、更には街中の混雑・騒音・・・・・・・。実は町歩きの第一歩が上野裏の谷根千(ヤネセン)であったが、7年前既に谷根千は観光地化しており、地元商店街・住民との間で問題が指摘されていた。以前、谷根千の旅館「澤野屋」はどこよりも早く訪日外国人を受け入れ地域全体で「もてなしてきた」とブログに書いたことがあった。全体としてはこうした受け入れをしている地域であるが、例えば谷中ぎんざ商店街の中には地域住民の生活に必要なもの売る小売店もあれば、観光客相手の店もある。その象徴であるが、地元住民相手の総菜店には200円の格安弁当が売られ、観光客相手には200円の食べ歩き用のメンチカツが売られる、という状況が生まれている。誰を顧客とするのかという問題であるが、こうした状況は大阪の黒門市場にも起きている。黒門市場は寺社の境内に魚の行商が集まり鮮度もよく安いということから生まれた住民顧客向けの市場であるが、数年前から訪日外国人が押し寄せるという一大観光地へと変貌した。結果どういうことが起きているか。訪日外国人による混雑と、小売価格の上昇、こうしたことから地域住民は黒門市場から離れて行きつつある。
日本におけるインバウンドビジネス拡大の主要な背景・要因が明確になってきた。従来から言われてきたように、円安に加えて世界的なLCCやクルーズ船の旅の急拡大、つまり以前と比べて格段に行きやすくなったことによる。そして、その増加の裾野の消費傾向は日本人の生活と同じようなことをしてみたいという体験の旅となる。日本は長引くデフレ下にあり、訪日外国人にとって安く済むパラダイスのような旅を満喫できるということである。繰り返しブログにも書いてきたように、日本人の日常的なライフスタイル、ごくごく普通の生活を同じように体験してみたいということである。トリップアドバイザーのお気に入り日本レストランのランキングにも出てきているが、その多くはご近所住民が日常利用しでいる普通の飲食店である。勿論、訪日外国人向けの特別価格などではない。そんな特別なことばかりしていくと、地域住民だけでなく、その事実を知った訪日外国人はすぐさまSNSに投稿するであろう。
「ここにしかない地域」を観光地とするのであれば、ありのままの「生活文化」を提供するということだ。海に囲まれた日本には約2800ほどの漁港、後背集落は約6300、共に減少傾向にある。勿論、沿岸漁業の不振、高齢化、結果過疎化の象徴でもあるが、京丹後伊根町のような特色ある「生き方」もある。ちなみに、伊根町は922世帯、人口2135人という小さな漁村である。観光協会のHPには「ディープな伊根を旅してみよう」とある。過疎化の進む地方であるが、逆に考えれば豊かな自然が残り、歴史文化があちらこちらに残っている。伊根町の近くには浦嶋太郎伝説が残る「常世の浜」がある。舟屋だけでなく、浦島伝説という物語体験もまた面白い。(続く)
追記 冒頭の写真は伊根町観光協会の写真を掲載したことをお断りしておく。
2018年05月06日
日本観光「進化」への視座
ヒット商品応援団日記No712(毎週更新) 2018.5.6.
 やっと日本のインバウンドビジネスの方向がビジネスは勿論のこと社会的にも認識されてきた。これはまさに訪日外国人客の消費という「需要実績」によって、それまでのパラダイム(価値観)が変わってきたということである。
やっと日本のインバウンドビジネスの方向がビジネスは勿論のこと社会的にも認識されてきた。これはまさに訪日外国人客の消費という「需要実績」によって、それまでのパラダイム(価値観)が変わってきたということである。
昨年秋に書いたブログにそれまでのゴールデンルート(成田ー東京ー富士山ー京都)といった日本観光初心者定番の観光から、これもかなり前から書いてきたことだが「個人旅行」あるいは「リピート観光」が半数を超え、それまでの観光内容がガラッと変わってきたと。その象徴的キーワードが「西高東低」と表現されてきている。「東」とはゴールデンルートから、「西」は大阪を中心とした西日本への需要拡大という観光先が変わり広がってきたということである。私の言葉でいえば、それまでの浅草寺・富士山観光、寿司・すき焼き体験から、日本人の日常的な生活文化観光への進化である。その象徴が一昨年からの「桜観光」人気であった。ある意味東京ディズニーランド&京都といった「表通り」から、大阪を中心とした地方という「横丁路地裏」への進化でもある。
観光も回数を経てくるとより目的が深まっていく。あるいはその観光体験の中から新たな関心事も生まれる。スタート当初の団体・パック旅行から、その目的に合わせた個人単位、仲間単位、家族単位の「個人旅行」へと変化してくる。日本への滞在時間も長くなり、費用もかかることから宿泊費を抑える傾向も生まれる。面白いことに、日本旅館・露天風呂の体験が主目的の場合、相応の費用になるが、それ以外の宿泊は安価なゲストハウスで済ますといった具合である。交通についてもそれまでのタクシー利用から鉄道やバス利用へと変化してくる。食事についても宿泊ホテルや旅館の食事から、体験してみたい街場の飲食店を探し出して食べに行くこととなる。こうした観光行動を可能にしているのがスマホであり、トリップアドバイザーや各国の日本ガイドサイトを検索しながらということになる。3年ほど前の訪日外国人の要望の第一がWiFiの設置であり、スマホ片手の旅スタイルは世界標準になったということだ。こうして不思議の国日本巡りの旅に向かうということである。
さてこうしたインバウンド市場の経過を見て行くと、その目標は更なる「回数化」「リピーター化」ということになる。このことは日本人顧客のリピーター化とそれほど大きな違いはない。ただ顧客の興味関心事は常に変化して行く環境下にあることを忘れてはならない。それも世界規模においてである。こうしたインバウンドビジネスの一つの先行事例となっているのが北海道ニセコのスキー場である。今からかなり昔になるが南半球オーストラリアのスキーオタクが季節的には真反対の日本、しかも世界でも珍しい雪質、パウダースノーというスキー場を目指して通ってきたという経緯がある。当時はまだまだ一部の熱烈なフアン・オタクで、地元も含めインバウンドビジネスとしての可能性について言及されることはなかった。。ちょうど20数年前の秋葉原、アキバにアニメオタクの訪日外国人が来日していた構図と同じである。それがどう変化してきたか、2016年には標準地の地価公示値上がり率が19.7%で全国1位(国土交通省調べ)になり、その後も上昇が続いている。スキー客の増加を見込んでのホテルや別荘の開発が進んだ結果ということだ。ニセコ倶知安町役場の統計資料によると外国人が住み始めたのは2003年ごろからで、当時49世帯60人が住民登録をしている。リーマンショックで少し落ちたものの、その後回復。2017年2月時点では1400世帯が住民登録をしている。町全体の世帯数が8973世帯であることから約15%が外国人世帯という割合だ。ある意味スキーオタクがアキバと同じようにように世界中から集まったということだ。
このようにオタクが先行した「需要」が地方創生にもつながった事例である。勿論、オタクが全てこのような結果に繋がるとは限らない。そもそもオタクが誕生するのは、アキバにアニメやコミック関連の専門店が集積し、「好き」を母体に誕生したように、他に変えがたい極めて強い「特殊世界人」として振舞うことからであった。単なる「好き」を超えて、単なるマニアを超えて、そのこだわり度に違いを見つけようとした特殊性に身を置いた人のことをオタクと呼んだのである。つまり、”自分は単なるマニアじゃないよ”と差別化する必要が生まれる土壌があってオタクは誕生する。誇らしげに”ニセコの雪質と出会ったら他では滑れない”という仲間が次第に増え、結果地方創生にも繋がったということである。アキバの雑居ビルから生まれたAKB48の場合はこのオタク心理、例えば「自分は指原フアン」といった特殊性をシステム化したのがいわゆる「総選挙」である。つまり、オタク同士を競争させて「違い」「こだわり度」を創る仕組みを内在化させたということである。こうしたオタクの言説がSNSをはじめとしたメディアに載ることによって「いいね」が拡散し、更にオタク予備軍も生まれる。しかし、後に同じようなアイドルグループが生まれ、AKBは乃木坂46にその人気度が超えられたとも言われている。いつかその背景について書くこととするが、こうした「オタクマーケティング」は時代と共にまた変化して行くということだ。
20数年前までは「キラーコンテンツ」というキーワードがマーケティングの中心を占めていたことがあった。他に変えがたい固有性、オリジナリティこそが市場を創って行くという主旨であるが、今日のマーケティングはこの「キラーコンテンツ」という魅力がどこにあるかを探すこと、その隠れた小さな「芽」こそがオタクというわけである。
この2年ほどで「桜観光」はキラーコンテンツ足り得ることがわかった。その花見は美しさを愛でることと同時に、桜の下での家族や仲間との宴も楽しみの一つであることもわかってきた。そして、それまでの日本の名所との組み合わせ、例えば富士山と桜、さらにプラスαといったインスタ映えを狙った観光客も出てきた。問題なのは、桜の開花時期は限られていることから、ある時期だけ観光客が殺到することとなる。花見ならぬ、人見で終わる事態が出てきており、京都ではそのことを嫌って日本人観光客が減る傾向にあると。京都では分散化を考えているようだが、それほど簡単なことではない。
観光の回数化を前提としたその広域化、分散化という課題であるが、少し前のブログにも書いたが、青森などの試みは面白い。それまでの発想であると県内だけで観光を終えてしまいがちであるが、新幹線を利用して函館をも旅先にした試みである。県をまたぐもの、それは移動の楽しみをも組み込んだ「テーマ」ということになる。雪に触れることの少ない台湾観光客には冬の青森の雪は新しい体験であり、事前の理解と共に旅のプログラムさえきちんとすれば、これも日本ならではのキラーコンテンツ「体験旅行」になるということだ。この旅には居酒屋での民謡を楽しむことも含まれているようだが、津軽三味線も郷土芸能として他にはないものとなる。テーマは「冬の津軽の旅」ということになる。冬の津軽を満喫した観光客には、「5月には春の桜、弘前へどうぞお越しください」となる。これが回数化である。
つまり、このように間違いなくテーマ観光へと向かうことになる。先日のTV報道によれば、一昨年から大阪西成のドヤ街の再開発が盛んになり、多くのゲストハウスが出来てきた。一泊5000円未満(素泊まり)の施設が多く、支出の多くは交通費と飲食代に当てるという。そして、できる限り長期に滞在するつもりで、その日は京都に花見に行くという。スタイルとしてはバックパッカー風であるが、取材されたその訪日外国人は日本オタク予備軍とでも表現できる人物であった。そして、この西成にはトリップアドバイザーにおける人気No1レストランとしてお好み焼きちとせがあることも象徴的である。
これからこうした日本観光の進化の経過をレポートして行くが、観光資源という言い方をすれば以下の3つに整理することができる。
・日本固有の自然 例えば 冬の白川郷から庭園や盆栽まで
・日本固有の歴史・文化 例えば城から酒蔵巡りまで
・日本固有の人物 例えば武道・芸道から伝統工芸の職人まで
・更にはアニメ映画やファッションなどの聖地巡礼観光へ
勿論、恐らく世界の日本食ブームも更に進化し、寿司やすき焼きといった「食」ではなく、日本人が日常食べている「食」へと分化し、テーマ化して行くであろう。例えば、「あの博多の〇〇ラーメンを食べに」、更に進化して行くとすれば、日本人にもその傾向が見えてきている「博多の屋台食べ歩き」といったテーマなんかは面白い。言わば博多夜市ということである。また、桜観光はキラーコンテンツ足り得ることが明らかになったが、温泉、銭湯といった温浴観光もその可能性は高い。但し、SNSの問題点でもあるのだが、インスタ映え観光地、インスタ映え飲食店、インスタ映え体験といった「ひととき観光」で終わるのか、更なる進化を遂げ回数化が測れるものなのか見極めることが重要となる。そして、その時重要になるのが、やはりテーマの進化物語づくりということになる。(続く)
 やっと日本のインバウンドビジネスの方向がビジネスは勿論のこと社会的にも認識されてきた。これはまさに訪日外国人客の消費という「需要実績」によって、それまでのパラダイム(価値観)が変わってきたということである。
やっと日本のインバウンドビジネスの方向がビジネスは勿論のこと社会的にも認識されてきた。これはまさに訪日外国人客の消費という「需要実績」によって、それまでのパラダイム(価値観)が変わってきたということである。昨年秋に書いたブログにそれまでのゴールデンルート(成田ー東京ー富士山ー京都)といった日本観光初心者定番の観光から、これもかなり前から書いてきたことだが「個人旅行」あるいは「リピート観光」が半数を超え、それまでの観光内容がガラッと変わってきたと。その象徴的キーワードが「西高東低」と表現されてきている。「東」とはゴールデンルートから、「西」は大阪を中心とした西日本への需要拡大という観光先が変わり広がってきたということである。私の言葉でいえば、それまでの浅草寺・富士山観光、寿司・すき焼き体験から、日本人の日常的な生活文化観光への進化である。その象徴が一昨年からの「桜観光」人気であった。ある意味東京ディズニーランド&京都といった「表通り」から、大阪を中心とした地方という「横丁路地裏」への進化でもある。
観光も回数を経てくるとより目的が深まっていく。あるいはその観光体験の中から新たな関心事も生まれる。スタート当初の団体・パック旅行から、その目的に合わせた個人単位、仲間単位、家族単位の「個人旅行」へと変化してくる。日本への滞在時間も長くなり、費用もかかることから宿泊費を抑える傾向も生まれる。面白いことに、日本旅館・露天風呂の体験が主目的の場合、相応の費用になるが、それ以外の宿泊は安価なゲストハウスで済ますといった具合である。交通についてもそれまでのタクシー利用から鉄道やバス利用へと変化してくる。食事についても宿泊ホテルや旅館の食事から、体験してみたい街場の飲食店を探し出して食べに行くこととなる。こうした観光行動を可能にしているのがスマホであり、トリップアドバイザーや各国の日本ガイドサイトを検索しながらということになる。3年ほど前の訪日外国人の要望の第一がWiFiの設置であり、スマホ片手の旅スタイルは世界標準になったということだ。こうして不思議の国日本巡りの旅に向かうということである。
さてこうしたインバウンド市場の経過を見て行くと、その目標は更なる「回数化」「リピーター化」ということになる。このことは日本人顧客のリピーター化とそれほど大きな違いはない。ただ顧客の興味関心事は常に変化して行く環境下にあることを忘れてはならない。それも世界規模においてである。こうしたインバウンドビジネスの一つの先行事例となっているのが北海道ニセコのスキー場である。今からかなり昔になるが南半球オーストラリアのスキーオタクが季節的には真反対の日本、しかも世界でも珍しい雪質、パウダースノーというスキー場を目指して通ってきたという経緯がある。当時はまだまだ一部の熱烈なフアン・オタクで、地元も含めインバウンドビジネスとしての可能性について言及されることはなかった。。ちょうど20数年前の秋葉原、アキバにアニメオタクの訪日外国人が来日していた構図と同じである。それがどう変化してきたか、2016年には標準地の地価公示値上がり率が19.7%で全国1位(国土交通省調べ)になり、その後も上昇が続いている。スキー客の増加を見込んでのホテルや別荘の開発が進んだ結果ということだ。ニセコ倶知安町役場の統計資料によると外国人が住み始めたのは2003年ごろからで、当時49世帯60人が住民登録をしている。リーマンショックで少し落ちたものの、その後回復。2017年2月時点では1400世帯が住民登録をしている。町全体の世帯数が8973世帯であることから約15%が外国人世帯という割合だ。ある意味スキーオタクがアキバと同じようにように世界中から集まったということだ。
このようにオタクが先行した「需要」が地方創生にもつながった事例である。勿論、オタクが全てこのような結果に繋がるとは限らない。そもそもオタクが誕生するのは、アキバにアニメやコミック関連の専門店が集積し、「好き」を母体に誕生したように、他に変えがたい極めて強い「特殊世界人」として振舞うことからであった。単なる「好き」を超えて、単なるマニアを超えて、そのこだわり度に違いを見つけようとした特殊性に身を置いた人のことをオタクと呼んだのである。つまり、”自分は単なるマニアじゃないよ”と差別化する必要が生まれる土壌があってオタクは誕生する。誇らしげに”ニセコの雪質と出会ったら他では滑れない”という仲間が次第に増え、結果地方創生にも繋がったということである。アキバの雑居ビルから生まれたAKB48の場合はこのオタク心理、例えば「自分は指原フアン」といった特殊性をシステム化したのがいわゆる「総選挙」である。つまり、オタク同士を競争させて「違い」「こだわり度」を創る仕組みを内在化させたということである。こうしたオタクの言説がSNSをはじめとしたメディアに載ることによって「いいね」が拡散し、更にオタク予備軍も生まれる。しかし、後に同じようなアイドルグループが生まれ、AKBは乃木坂46にその人気度が超えられたとも言われている。いつかその背景について書くこととするが、こうした「オタクマーケティング」は時代と共にまた変化して行くということだ。
20数年前までは「キラーコンテンツ」というキーワードがマーケティングの中心を占めていたことがあった。他に変えがたい固有性、オリジナリティこそが市場を創って行くという主旨であるが、今日のマーケティングはこの「キラーコンテンツ」という魅力がどこにあるかを探すこと、その隠れた小さな「芽」こそがオタクというわけである。
この2年ほどで「桜観光」はキラーコンテンツ足り得ることがわかった。その花見は美しさを愛でることと同時に、桜の下での家族や仲間との宴も楽しみの一つであることもわかってきた。そして、それまでの日本の名所との組み合わせ、例えば富士山と桜、さらにプラスαといったインスタ映えを狙った観光客も出てきた。問題なのは、桜の開花時期は限られていることから、ある時期だけ観光客が殺到することとなる。花見ならぬ、人見で終わる事態が出てきており、京都ではそのことを嫌って日本人観光客が減る傾向にあると。京都では分散化を考えているようだが、それほど簡単なことではない。
観光の回数化を前提としたその広域化、分散化という課題であるが、少し前のブログにも書いたが、青森などの試みは面白い。それまでの発想であると県内だけで観光を終えてしまいがちであるが、新幹線を利用して函館をも旅先にした試みである。県をまたぐもの、それは移動の楽しみをも組み込んだ「テーマ」ということになる。雪に触れることの少ない台湾観光客には冬の青森の雪は新しい体験であり、事前の理解と共に旅のプログラムさえきちんとすれば、これも日本ならではのキラーコンテンツ「体験旅行」になるということだ。この旅には居酒屋での民謡を楽しむことも含まれているようだが、津軽三味線も郷土芸能として他にはないものとなる。テーマは「冬の津軽の旅」ということになる。冬の津軽を満喫した観光客には、「5月には春の桜、弘前へどうぞお越しください」となる。これが回数化である。
つまり、このように間違いなくテーマ観光へと向かうことになる。先日のTV報道によれば、一昨年から大阪西成のドヤ街の再開発が盛んになり、多くのゲストハウスが出来てきた。一泊5000円未満(素泊まり)の施設が多く、支出の多くは交通費と飲食代に当てるという。そして、できる限り長期に滞在するつもりで、その日は京都に花見に行くという。スタイルとしてはバックパッカー風であるが、取材されたその訪日外国人は日本オタク予備軍とでも表現できる人物であった。そして、この西成にはトリップアドバイザーにおける人気No1レストランとしてお好み焼きちとせがあることも象徴的である。
これからこうした日本観光の進化の経過をレポートして行くが、観光資源という言い方をすれば以下の3つに整理することができる。
・日本固有の自然 例えば 冬の白川郷から庭園や盆栽まで
・日本固有の歴史・文化 例えば城から酒蔵巡りまで
・日本固有の人物 例えば武道・芸道から伝統工芸の職人まで
・更にはアニメ映画やファッションなどの聖地巡礼観光へ
勿論、恐らく世界の日本食ブームも更に進化し、寿司やすき焼きといった「食」ではなく、日本人が日常食べている「食」へと分化し、テーマ化して行くであろう。例えば、「あの博多の〇〇ラーメンを食べに」、更に進化して行くとすれば、日本人にもその傾向が見えてきている「博多の屋台食べ歩き」といったテーマなんかは面白い。言わば博多夜市ということである。また、桜観光はキラーコンテンツ足り得ることが明らかになったが、温泉、銭湯といった温浴観光もその可能性は高い。但し、SNSの問題点でもあるのだが、インスタ映え観光地、インスタ映え飲食店、インスタ映え体験といった「ひととき観光」で終わるのか、更なる進化を遂げ回数化が測れるものなのか見極めることが重要となる。そして、その時重要になるのが、やはりテーマの進化物語づくりということになる。(続く)