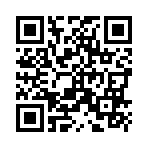2014年05月26日
消費増税の壁を超える
ヒット商品応援団日記No581(毎週更新) 2014.5.26.
新消費税導入から2ヶ月近く経過した。今回注目すべきは駈け込み需要後の落ち込みは想定内であったなどといった当たり障りの無い話ではない。1997年の消費税5%導入後の変化とは全く異なる推移となっている。この推移を見ていくと、提供する企業サイドと消費者サイドが共に良く考えて行動した結果となっていることが分かる。
その「良く考えた結果」の第一は駈け込み需要の反動が大きいと考えられていた百貨店売り上げのその内容についてである。以前のブログにも書いたが、3月の全国百貨店の売上高は既存店ベースで前年同月比25.4%増となった。伸び率は前回消費増税前の1997年3月(23.0%増)を上回り、消費税導入前の1989年3月(35.3%増)以来、25年ぶりの高い伸び率を記録した。こうした数値をベースに4月以降の売り上げの落ち込みはそれほど大きくはないと判断する専門家が多い。しかし、4月の売り上げを支えたのは「誰であるか」について言及したメディアや専門家は少ない。毎日新聞が増税影響度について以下のようにまとめていた。
大手百貨店主力店の消費増税影響度(前年同月比増減率、▲はマイナス)】
※以下、店舗名、4月売上高(%)、3月売上高(%)
(1)銀座三越、1.1、36.7 (2)大丸東京店、▲ 3.6、25.1 (3)伊勢丹新宿店、▲ 7.9、18.7 (4)西武池袋本店、▲ 9.0、24.3 (5)阪急本店、▲ 9.7、34.5 (6)新宿タカシマヤ、▲10.4、32.6 (7)そごう横浜店、▲11.1、31.6 (8)横浜タカシマヤ、▲11.4、35.6 (9)大丸心斎橋店、▲13.9、36.4 (10)日本橋三越本店、▲14.7、31.8 (11)大阪タカシマヤ、▲15.2、32.9 (12)日本橋タカシマヤ、▲15.9、40.2 (13)松坂屋名古屋店、▲18.3、57.2
まず気がつくのは銀座三越で3月の駈け込み需要売り上げも大きく、しかも4月の売り上げもマイナスではなくプラウ1,1%となっている点である。昨年秋以降のブログにも訪日外国人がビザ発給の緩和を受けて急増し、多様な消費を見せていると書いてきた。そして、その傾向は2014年に入っても続いており、観光庁によると1月から3月までの間に国内で消費した金額は推計でおよそ4300億円となり、3か月間としては過去最高額になった、と。これは前年度の同じ期間に比べて49%増。そして、4月に入り、日本を訪れた外国人旅行者は推計で123万1500人となり前の年の同じ月に比べて33.4%増えた。これは今年3月の105万人余りを大幅に上回り、1か月間の旅行者数としては最も多く、2か月連続で過去最多を更新したと。これは桜の季節であることと、羽田の発着枠の増加効果であると推測されている。
ここまで書けば皆さんも銀座三越の売り上げについてなるほどそうであったかと推測されるであろう。訪日外国人による免税品の売り上げが前年同月比93%増と大幅に増えたことが寄与したとのこと。そして、免税品の売り上げが売り上げ全体に占める割合は10%程度と、初めて2ケタ台に乗ったという。
三越伊勢丹ホールディングスは2012年から免税手続きの世界最大手グローバルブルー(スイス)と提携し、伊勢丹新宿店、日本橋三越本店、銀座三越に免税店を設け訪日外国人受け入れを強化した結果ということである。明暗という言い方をするならば、銀座三越は「明」、その他の百貨店は「暗」に近い曇りといったところであろう。
次に外食チェーンの変化である。まず牛丼大手3社についてであるが、吉野家は牛丼並盛りを20円値上げして300円とし、松屋も10円引き上げた。一方、すき家は10円値下げで対抗した。既存店の客数を見るとすき家が4.8%減、松屋が4.4%減なのに対して吉野家は9.2%減と苦戦した。値上げした吉野家は落とした客数分を値上げによって補いきれなかったという結果である。すき家も値下げをしたにも関わらずマイナスであるのは人手不足による店舗閉鎖の影響によるものである。つまり、日常利用において20円の値上げは大きく吉野家は「暗」という結果となった。確か3月のブログにも書いたことだが、新メニューである牛すき鍋膳は冬場の季節メニューであり、次のヒットメニューが求められていると。ところが新メニューも無い上に値上げをして消費増税を迎えたことは、吉野家ブランドの過信であったということである。
また、普通の企業に戻ったマクドナルドであるが、100円マックを復活させて以前の市場を呼び戻そうとしているが相変わらず低迷したままで、4月の既存店売上高は、前年比3.4%減と3カ月連続で前年実績を下回った。ここ2年ほど迷走し続けたマクドナルドであるが、明るい材料もあり、特に若い女性を狙ったアボカドを使用したハンバーガーのように明快なメニューコンセプトに戻れば復活はあり得るであろう。
また、明暗の明の一つとしてファミレスのロイヤルホストが好調で、4月度の売り上げは前年比108.1%、客数100.7%、客単価107.4%とのこと。マクドナルドが1000円バーガーによって客単価アップをはかり失敗したのに対し、ロイヤルホストは昨年ブログにも書いたが夏前からのヒット商品であるアンガスリブロースステーキは消費増税の壁を超える戦略メニューに定着したということである。
また、一昨年来低迷を続ける回転寿司チェーンであるが、大手各社揃ってラーメンや丼といった新メニュー開発に賭けているが、ロイヤルホストのアンガスリブロースステーキのようなメニューづくりには至ってはいない。
そして、明の企業としてユニクロとニトリも挙げられる。ユニクロは国内既存店は6ヶ月連続のプラスで4月は前年比103.3%、ニトリは既存店売り上げは115.1%と2014年度に入り好調さを持続させている。両社共に、一昨年から価格だけでなくデザインクオリティを高めた商品政策を取っており、こうした点が消費増税を超える顧客支持を得たということである。
日常業態である食品スーパーを始めとした流通企業は顧客継続を促す本体価格の値下げを含めた施策やプロモーションを行っており、消費増税による値上げの影響はあまり見受けられない。メーカーによってはサイズや量を減らして増税分や円安による原材料高を吸収したり、それでも難しい場合は値上げも見られるが、総じて消費者による拒否反応が見られるほどではない。
次の未来塾のテーマを「商店街から学ぶ」に設定し、2つの大型商業施設に囲まれた東京江東区にある「砂町銀座商店街」を3月から観察&調査したが、お惣菜横丁と呼ばれるような商店街においても値上げを行っている店が多く、そのことによる影響はあまり出てはいないようである。その理由についてはこのブログ上で公開するが独自な商品づくりとサービス精神旺盛な顧客関係が出来ている商店は増税の壁を超えていることが分かる。「いままでの成績表の結果」が増税後の売り上げ結果に見事に反映されるとブログにも書いたが、まさにそんな商店街であった。
数字の見方もそうであるが、「平均値」あるいは「一般的」といった認識は捨てなければならない。「明」に挙げた銀座三越を始め良い企業は訪日外国人といった新しい市場の開拓や新サービスやメニューの開発導入によって消費増税の壁を超えている。これら全て個別である。低迷を続ける回転寿司チェーンと書いたが、スシローを始めとした大手3社は現時点においては良い結果は出せていないが、業界4位のはま寿司はあのすき家を経営しているゼンショーグループ企業であるが、今出店攻勢をかけており急成長を果たしている。このように「明」の企業に共通していることは、当然ではあるが数年前からの明確な戦略の基に新しい市場づくりにチャレンジし、4月を迎えたということである。
前回1997年の時の新消費税導入と決定的に異なっているのが、企業も消費者もまだまだ「様子見」状態である。これは前回からの学習効果であると考える。例えば、GWの消費は節約程度で、旅行をやめるあるいは他の何かに変更するといった大きな消費移動は見られなかった。6月になると夏のボーナス支給が始まり、景気回復などと消費増税の影響は軽微であるかの如く論評されることが予測される。しかし、一部大手企業のベースアップは行われたが、依然として大多数の勤労者の収入は下げ続けていることを忘れてはならない。家計調査内容を始め、商業施設の売り上げ内容の分析を待たなければならないが、消費者における家計は時間経過と共にボディブローの如く効いてくると推測される。そうしたことを踏まえ企業サイドも次なる施策を考えていると思う。既に百貨店においてはお中元商戦がスタートしているが、時期を早めても売り上げ増にはならない。銀座三越のように新しいマーケット開発にトライすべきである。外食産業においても、ロイヤルホストのアンガスリブロースステーキのような新メニューの開発を急ぐということだ。(続く)
新消費税導入から2ヶ月近く経過した。今回注目すべきは駈け込み需要後の落ち込みは想定内であったなどといった当たり障りの無い話ではない。1997年の消費税5%導入後の変化とは全く異なる推移となっている。この推移を見ていくと、提供する企業サイドと消費者サイドが共に良く考えて行動した結果となっていることが分かる。
その「良く考えた結果」の第一は駈け込み需要の反動が大きいと考えられていた百貨店売り上げのその内容についてである。以前のブログにも書いたが、3月の全国百貨店の売上高は既存店ベースで前年同月比25.4%増となった。伸び率は前回消費増税前の1997年3月(23.0%増)を上回り、消費税導入前の1989年3月(35.3%増)以来、25年ぶりの高い伸び率を記録した。こうした数値をベースに4月以降の売り上げの落ち込みはそれほど大きくはないと判断する専門家が多い。しかし、4月の売り上げを支えたのは「誰であるか」について言及したメディアや専門家は少ない。毎日新聞が増税影響度について以下のようにまとめていた。
大手百貨店主力店の消費増税影響度(前年同月比増減率、▲はマイナス)】
※以下、店舗名、4月売上高(%)、3月売上高(%)
(1)銀座三越、1.1、36.7 (2)大丸東京店、▲ 3.6、25.1 (3)伊勢丹新宿店、▲ 7.9、18.7 (4)西武池袋本店、▲ 9.0、24.3 (5)阪急本店、▲ 9.7、34.5 (6)新宿タカシマヤ、▲10.4、32.6 (7)そごう横浜店、▲11.1、31.6 (8)横浜タカシマヤ、▲11.4、35.6 (9)大丸心斎橋店、▲13.9、36.4 (10)日本橋三越本店、▲14.7、31.8 (11)大阪タカシマヤ、▲15.2、32.9 (12)日本橋タカシマヤ、▲15.9、40.2 (13)松坂屋名古屋店、▲18.3、57.2
まず気がつくのは銀座三越で3月の駈け込み需要売り上げも大きく、しかも4月の売り上げもマイナスではなくプラウ1,1%となっている点である。昨年秋以降のブログにも訪日外国人がビザ発給の緩和を受けて急増し、多様な消費を見せていると書いてきた。そして、その傾向は2014年に入っても続いており、観光庁によると1月から3月までの間に国内で消費した金額は推計でおよそ4300億円となり、3か月間としては過去最高額になった、と。これは前年度の同じ期間に比べて49%増。そして、4月に入り、日本を訪れた外国人旅行者は推計で123万1500人となり前の年の同じ月に比べて33.4%増えた。これは今年3月の105万人余りを大幅に上回り、1か月間の旅行者数としては最も多く、2か月連続で過去最多を更新したと。これは桜の季節であることと、羽田の発着枠の増加効果であると推測されている。
ここまで書けば皆さんも銀座三越の売り上げについてなるほどそうであったかと推測されるであろう。訪日外国人による免税品の売り上げが前年同月比93%増と大幅に増えたことが寄与したとのこと。そして、免税品の売り上げが売り上げ全体に占める割合は10%程度と、初めて2ケタ台に乗ったという。
三越伊勢丹ホールディングスは2012年から免税手続きの世界最大手グローバルブルー(スイス)と提携し、伊勢丹新宿店、日本橋三越本店、銀座三越に免税店を設け訪日外国人受け入れを強化した結果ということである。明暗という言い方をするならば、銀座三越は「明」、その他の百貨店は「暗」に近い曇りといったところであろう。
次に外食チェーンの変化である。まず牛丼大手3社についてであるが、吉野家は牛丼並盛りを20円値上げして300円とし、松屋も10円引き上げた。一方、すき家は10円値下げで対抗した。既存店の客数を見るとすき家が4.8%減、松屋が4.4%減なのに対して吉野家は9.2%減と苦戦した。値上げした吉野家は落とした客数分を値上げによって補いきれなかったという結果である。すき家も値下げをしたにも関わらずマイナスであるのは人手不足による店舗閉鎖の影響によるものである。つまり、日常利用において20円の値上げは大きく吉野家は「暗」という結果となった。確か3月のブログにも書いたことだが、新メニューである牛すき鍋膳は冬場の季節メニューであり、次のヒットメニューが求められていると。ところが新メニューも無い上に値上げをして消費増税を迎えたことは、吉野家ブランドの過信であったということである。
また、普通の企業に戻ったマクドナルドであるが、100円マックを復活させて以前の市場を呼び戻そうとしているが相変わらず低迷したままで、4月の既存店売上高は、前年比3.4%減と3カ月連続で前年実績を下回った。ここ2年ほど迷走し続けたマクドナルドであるが、明るい材料もあり、特に若い女性を狙ったアボカドを使用したハンバーガーのように明快なメニューコンセプトに戻れば復活はあり得るであろう。
また、明暗の明の一つとしてファミレスのロイヤルホストが好調で、4月度の売り上げは前年比108.1%、客数100.7%、客単価107.4%とのこと。マクドナルドが1000円バーガーによって客単価アップをはかり失敗したのに対し、ロイヤルホストは昨年ブログにも書いたが夏前からのヒット商品であるアンガスリブロースステーキは消費増税の壁を超える戦略メニューに定着したということである。
また、一昨年来低迷を続ける回転寿司チェーンであるが、大手各社揃ってラーメンや丼といった新メニュー開発に賭けているが、ロイヤルホストのアンガスリブロースステーキのようなメニューづくりには至ってはいない。
そして、明の企業としてユニクロとニトリも挙げられる。ユニクロは国内既存店は6ヶ月連続のプラスで4月は前年比103.3%、ニトリは既存店売り上げは115.1%と2014年度に入り好調さを持続させている。両社共に、一昨年から価格だけでなくデザインクオリティを高めた商品政策を取っており、こうした点が消費増税を超える顧客支持を得たということである。
日常業態である食品スーパーを始めとした流通企業は顧客継続を促す本体価格の値下げを含めた施策やプロモーションを行っており、消費増税による値上げの影響はあまり見受けられない。メーカーによってはサイズや量を減らして増税分や円安による原材料高を吸収したり、それでも難しい場合は値上げも見られるが、総じて消費者による拒否反応が見られるほどではない。
次の未来塾のテーマを「商店街から学ぶ」に設定し、2つの大型商業施設に囲まれた東京江東区にある「砂町銀座商店街」を3月から観察&調査したが、お惣菜横丁と呼ばれるような商店街においても値上げを行っている店が多く、そのことによる影響はあまり出てはいないようである。その理由についてはこのブログ上で公開するが独自な商品づくりとサービス精神旺盛な顧客関係が出来ている商店は増税の壁を超えていることが分かる。「いままでの成績表の結果」が増税後の売り上げ結果に見事に反映されるとブログにも書いたが、まさにそんな商店街であった。
数字の見方もそうであるが、「平均値」あるいは「一般的」といった認識は捨てなければならない。「明」に挙げた銀座三越を始め良い企業は訪日外国人といった新しい市場の開拓や新サービスやメニューの開発導入によって消費増税の壁を超えている。これら全て個別である。低迷を続ける回転寿司チェーンと書いたが、スシローを始めとした大手3社は現時点においては良い結果は出せていないが、業界4位のはま寿司はあのすき家を経営しているゼンショーグループ企業であるが、今出店攻勢をかけており急成長を果たしている。このように「明」の企業に共通していることは、当然ではあるが数年前からの明確な戦略の基に新しい市場づくりにチャレンジし、4月を迎えたということである。
前回1997年の時の新消費税導入と決定的に異なっているのが、企業も消費者もまだまだ「様子見」状態である。これは前回からの学習効果であると考える。例えば、GWの消費は節約程度で、旅行をやめるあるいは他の何かに変更するといった大きな消費移動は見られなかった。6月になると夏のボーナス支給が始まり、景気回復などと消費増税の影響は軽微であるかの如く論評されることが予測される。しかし、一部大手企業のベースアップは行われたが、依然として大多数の勤労者の収入は下げ続けていることを忘れてはならない。家計調査内容を始め、商業施設の売り上げ内容の分析を待たなければならないが、消費者における家計は時間経過と共にボディブローの如く効いてくると推測される。そうしたことを踏まえ企業サイドも次なる施策を考えていると思う。既に百貨店においてはお中元商戦がスタートしているが、時期を早めても売り上げ増にはならない。銀座三越のように新しいマーケット開発にトライすべきである。外食産業においても、ロイヤルホストのアンガスリブロースステーキのような新メニューの開発を急ぐということだ。(続く)
失われた30年nの意味
マーケティングノート(2)後半
マーケティングノート(2)
2023年ヒット商品版付を読み解く
マーケティングの旅(1) 「旅の始まり」後半
マーケティングの旅(1) 「旅の始まり」前半
マーケティングノート(2)後半
マーケティングノート(2)
2023年ヒット商品版付を読み解く
マーケティングの旅(1) 「旅の始まり」後半
マーケティングの旅(1) 「旅の始まり」前半
Posted by ヒット商品応援団 at 13:50│Comments(0)
│新市場創造