2009年03月11日
自画像としての商品
ヒット商品応援団日記No348(毎週2回更新) 2009.3.11.
前回、「顧客が求めるもの」というテーマに沿って、FOODEXJAPANの感想をブログに書いた。その最後のところで、顧客が変わる、その価値観が変わるということは私たちも変わりなさいということであると。どう変わるかは、目の前の顧客と一緒に、とも書いた。ちょうど1年前何が起こっていたかを思い起こして欲しい。中国冷凍餃子事件と共に、小麦関連商品の高騰、追い討ちをかけるようにガソリンの高騰、こうした資源輸入国であることを痛切に実感したのが生活者である。そして、当たり前のことであるが、一斉に自己防衛消費へと向い根底から変わったのだ。
以降、昨年5月に私が取り上げたエブリデーロープライスのOKストアを筆頭に価格を軸にあらゆる分野の商品再編が進行した。その象徴が、最近ではユニクロのディスカウント業態であるgu.が発売する990円の激安ジーンズであり、定額給付金狙いのH.I.S.の韓国ツアー2泊3日12,000円、更には全日空のシニア割引国内全路線片道9000円。恐らく、地デジ促進に伴う薄型テレビなどこれからも続々と激安商品が市場に現れる。既に、価格維持のお手本であった飲料自販機ですら100円を割り込むものまで出てきた。何か生き残るだけが経営目標であるかのような様相を見せている。これからの体力勝負は財務力が市場に勝ち残るために重要であるとした経済専門誌のコメントがこれから盛んになると思う。が、そうではない。経営を継続させていくためには、確かに必要なことではあるが、それだけでは必要十分なことではない。
こうした低価格商品市場を成立させる背景を円高ということを除くと2つに大別できる。1つはユニクロやニトリのように戦略(SPA等)に基づいたシステムとして実行する場合と、もう一つが100円以下の飲料自販機に象徴されるような過剰在庫処分、もしくは規格外商品・賞味期限まじかな「訳あり商品」に着眼することによる低価格化である。前者と後者を併せ持ったのが、流通のOKストアやザ・プライスである。
1990年代後半、価格破壊というキーワードと共にデフレの旗を立てた企業が市場をリードした。これは推測ではあるが、第二次価格破壊が始まる。いや、既に始まっていると言った方が正確であろう。
さて、こうした第二次価格破壊が進む市場をどう考えるかであるが、こうした傾向は都市市場において顕著になる。というのもこうした低価格戦略が意味を持ち成立するのは、市場がコンパクトに一定規模存在する都市においてであろう。このブログを読まれる地方の方にとって、どれだけ価格を軸に激しい競争が繰り広げられているか実感できないかもしれない。例えば、スーパーでは集客の目玉に豆腐があるが、一丁50円以下の商品が店頭に並ぶ。ところが、ここ2年ほど急成長している豆腐屋がある。住宅街を小さなリヤカーで引き売りする築地野口屋(http://www.table-mono.co.jp/2008/shiru/teiban.html)である。濃厚な味で他の豆腐とは全く違う豆腐で一丁350円とかなり高い価格である。リヤカーを引く人にもよるが、1日20万円近くを売り上げる時もあるという。実は、こうした市場が混在しているのが、東京市場である。
この築地野口屋の代表である野口博明氏の食への思いは深い。禅宗の寺に生まれ、幼少の頃はその厳しさに疑念を抱いたという。しかし、年を重ねることを経て、その禅の考えを商品に託したという。ある意味、生きざまが商品になったということだ。引き売りというまるで昭和の時代に戻ったようなスタイルであるが、これも顧客とふれあうためだという。私が住む祖師ケ谷大蔵にも週2〜3回懐かしいラッパを吹いて回ってくる。
私が取材して書いた「人力経営」に出てくる経営リーダーも全く同じである。ユニーク、常識はずれ、前例なし、そこまでやるか、そんな形容がふさわしい経営リーダーであるが、皆創業そのものに強い思いがある。福岡県岡垣町の「野の葡萄」には、創業時に植えた葡萄の樹が今でも大切に育てられ、その40年以上の巨木を真ん中にレストランがつくられている。また、創業明治元年の桑野造船を引き継いだ古川宗寿氏はボートが好きで好きでたまらない人物である。今年の年賀状には、「今も変わらず琵琶湖を渡ってのボート通勤をしています」と書かれていた。この古川氏の持論が「ロマンだけでは飯は食えない。ロマン無しではお客に響かない」である。価格を超えるもの、それは自らの思いが映し出された商品ということだ。(続く)
前回、「顧客が求めるもの」というテーマに沿って、FOODEXJAPANの感想をブログに書いた。その最後のところで、顧客が変わる、その価値観が変わるということは私たちも変わりなさいということであると。どう変わるかは、目の前の顧客と一緒に、とも書いた。ちょうど1年前何が起こっていたかを思い起こして欲しい。中国冷凍餃子事件と共に、小麦関連商品の高騰、追い討ちをかけるようにガソリンの高騰、こうした資源輸入国であることを痛切に実感したのが生活者である。そして、当たり前のことであるが、一斉に自己防衛消費へと向い根底から変わったのだ。
以降、昨年5月に私が取り上げたエブリデーロープライスのOKストアを筆頭に価格を軸にあらゆる分野の商品再編が進行した。その象徴が、最近ではユニクロのディスカウント業態であるgu.が発売する990円の激安ジーンズであり、定額給付金狙いのH.I.S.の韓国ツアー2泊3日12,000円、更には全日空のシニア割引国内全路線片道9000円。恐らく、地デジ促進に伴う薄型テレビなどこれからも続々と激安商品が市場に現れる。既に、価格維持のお手本であった飲料自販機ですら100円を割り込むものまで出てきた。何か生き残るだけが経営目標であるかのような様相を見せている。これからの体力勝負は財務力が市場に勝ち残るために重要であるとした経済専門誌のコメントがこれから盛んになると思う。が、そうではない。経営を継続させていくためには、確かに必要なことではあるが、それだけでは必要十分なことではない。
こうした低価格商品市場を成立させる背景を円高ということを除くと2つに大別できる。1つはユニクロやニトリのように戦略(SPA等)に基づいたシステムとして実行する場合と、もう一つが100円以下の飲料自販機に象徴されるような過剰在庫処分、もしくは規格外商品・賞味期限まじかな「訳あり商品」に着眼することによる低価格化である。前者と後者を併せ持ったのが、流通のOKストアやザ・プライスである。
1990年代後半、価格破壊というキーワードと共にデフレの旗を立てた企業が市場をリードした。これは推測ではあるが、第二次価格破壊が始まる。いや、既に始まっていると言った方が正確であろう。
さて、こうした第二次価格破壊が進む市場をどう考えるかであるが、こうした傾向は都市市場において顕著になる。というのもこうした低価格戦略が意味を持ち成立するのは、市場がコンパクトに一定規模存在する都市においてであろう。このブログを読まれる地方の方にとって、どれだけ価格を軸に激しい競争が繰り広げられているか実感できないかもしれない。例えば、スーパーでは集客の目玉に豆腐があるが、一丁50円以下の商品が店頭に並ぶ。ところが、ここ2年ほど急成長している豆腐屋がある。住宅街を小さなリヤカーで引き売りする築地野口屋(http://www.table-mono.co.jp/2008/shiru/teiban.html)である。濃厚な味で他の豆腐とは全く違う豆腐で一丁350円とかなり高い価格である。リヤカーを引く人にもよるが、1日20万円近くを売り上げる時もあるという。実は、こうした市場が混在しているのが、東京市場である。
この築地野口屋の代表である野口博明氏の食への思いは深い。禅宗の寺に生まれ、幼少の頃はその厳しさに疑念を抱いたという。しかし、年を重ねることを経て、その禅の考えを商品に託したという。ある意味、生きざまが商品になったということだ。引き売りというまるで昭和の時代に戻ったようなスタイルであるが、これも顧客とふれあうためだという。私が住む祖師ケ谷大蔵にも週2〜3回懐かしいラッパを吹いて回ってくる。
私が取材して書いた「人力経営」に出てくる経営リーダーも全く同じである。ユニーク、常識はずれ、前例なし、そこまでやるか、そんな形容がふさわしい経営リーダーであるが、皆創業そのものに強い思いがある。福岡県岡垣町の「野の葡萄」には、創業時に植えた葡萄の樹が今でも大切に育てられ、その40年以上の巨木を真ん中にレストランがつくられている。また、創業明治元年の桑野造船を引き継いだ古川宗寿氏はボートが好きで好きでたまらない人物である。今年の年賀状には、「今も変わらず琵琶湖を渡ってのボート通勤をしています」と書かれていた。この古川氏の持論が「ロマンだけでは飯は食えない。ロマン無しではお客に響かない」である。価格を超えるもの、それは自らの思いが映し出された商品ということだ。(続く)
失われた30年nの意味
マーケティングノート(2)後半
マーケティングノート(2)
2023年ヒット商品版付を読み解く
マーケティングの旅(1) 「旅の始まり」後半
マーケティングの旅(1) 「旅の始まり」前半
マーケティングノート(2)後半
マーケティングノート(2)
2023年ヒット商品版付を読み解く
マーケティングの旅(1) 「旅の始まり」後半
マーケティングの旅(1) 「旅の始まり」前半
Posted by ヒット商品応援団 at 14:21│Comments(0)
│新市場創造
上の画像に書かれている文字を入力して下さい
|
|


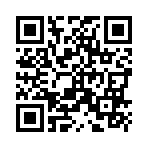






書き込まれた内容は公開され、ブログの持ち主だけが削除できます。